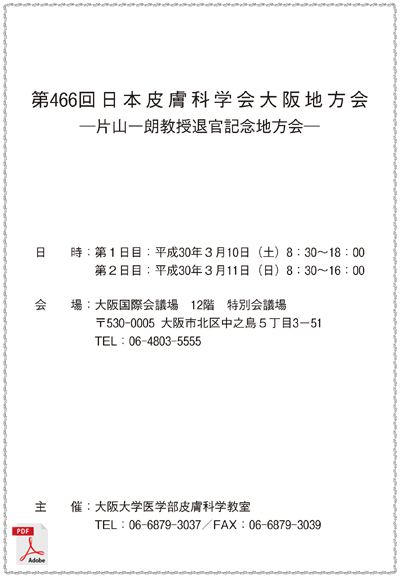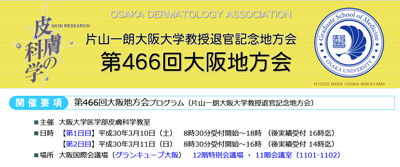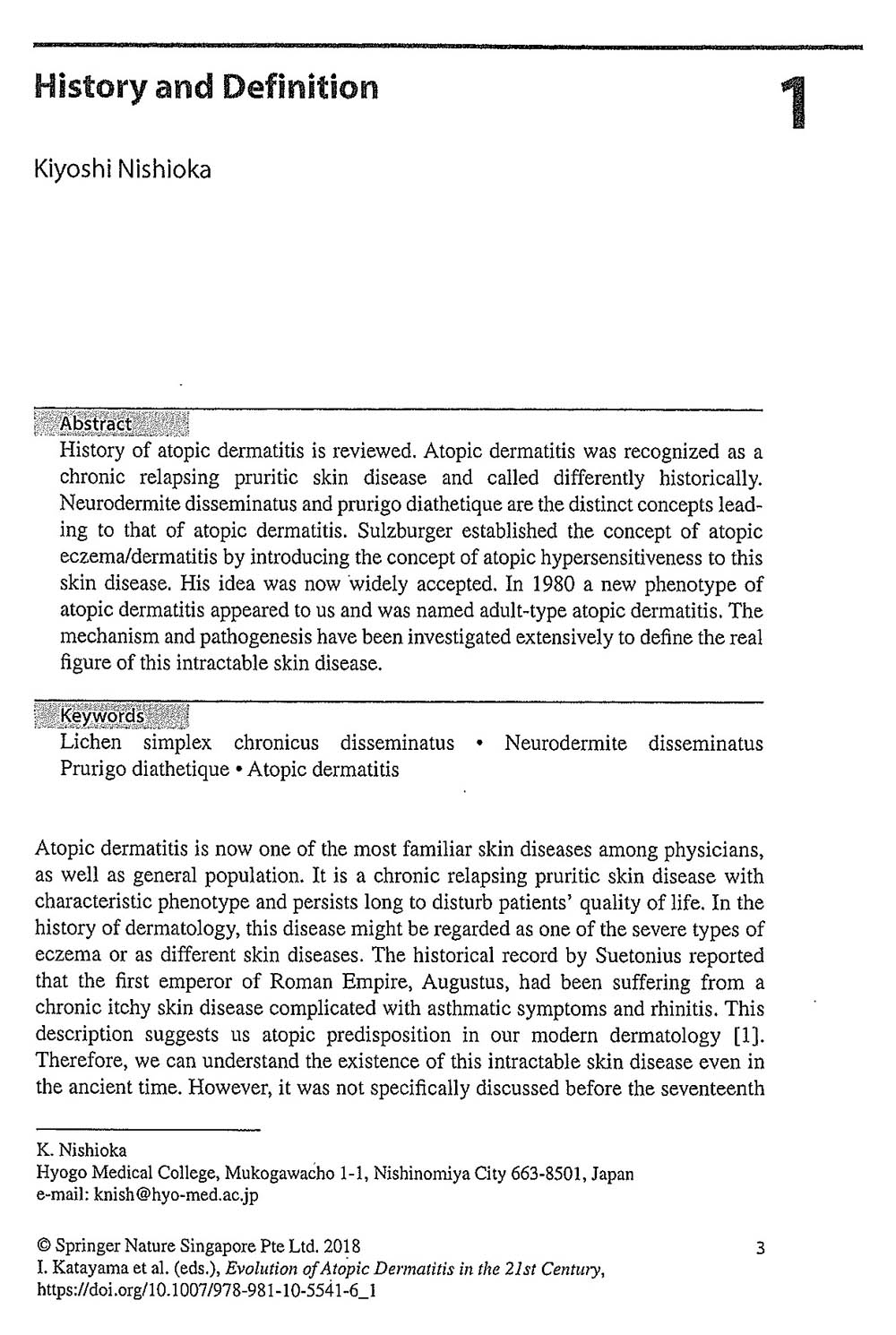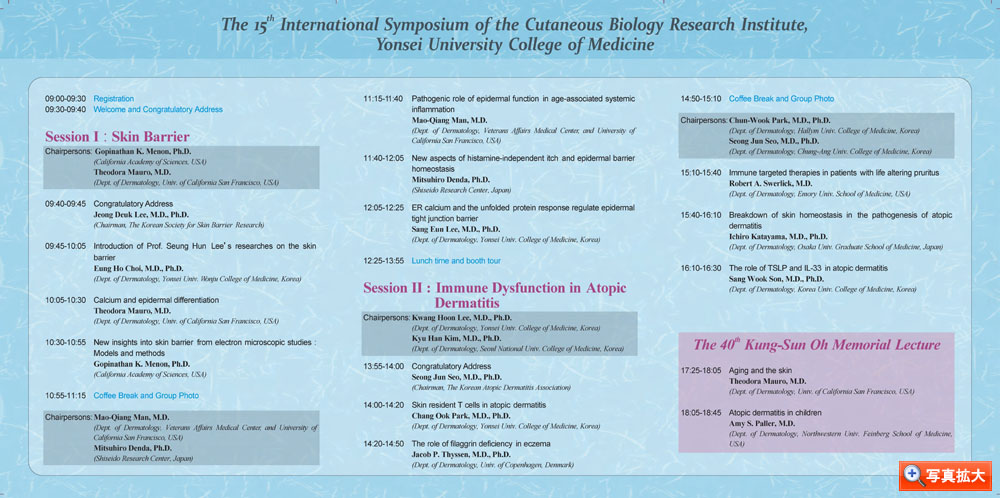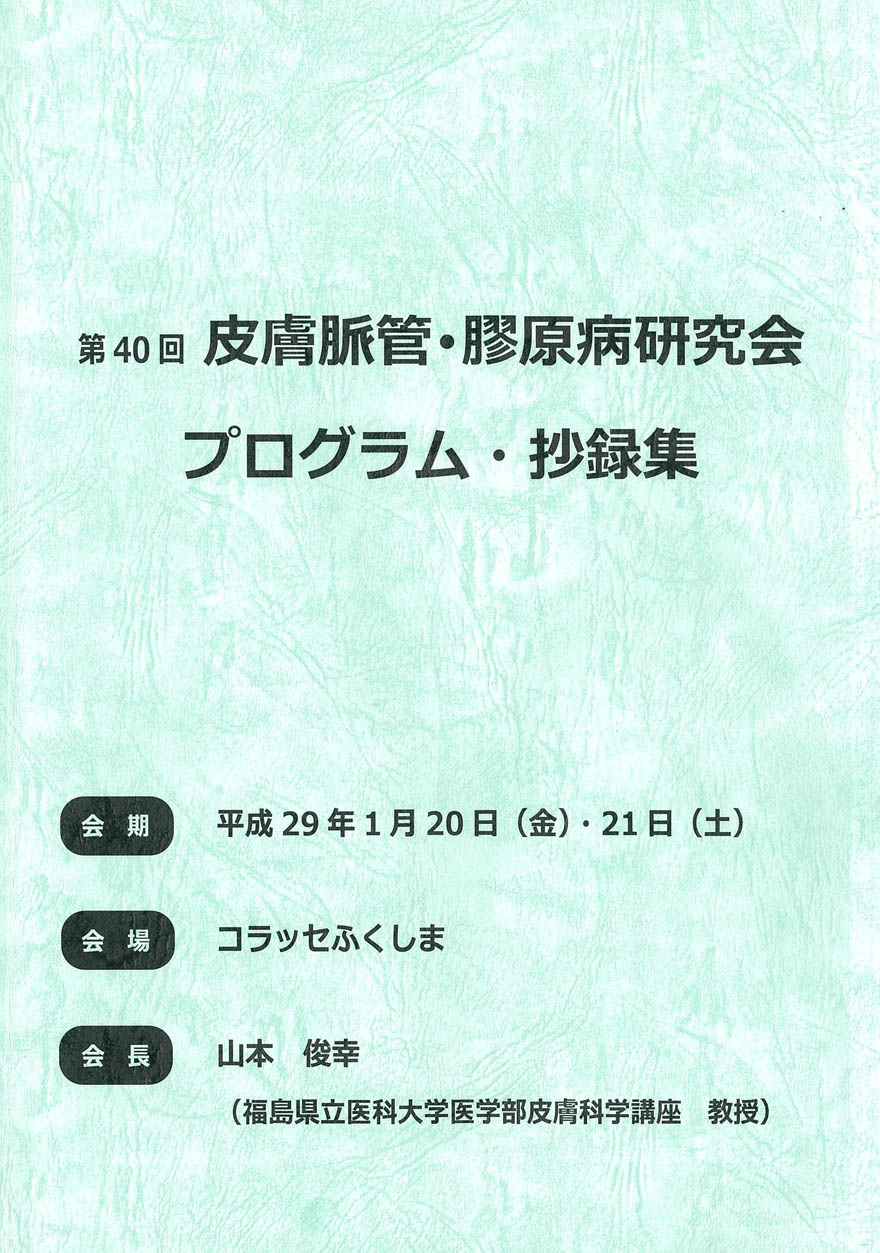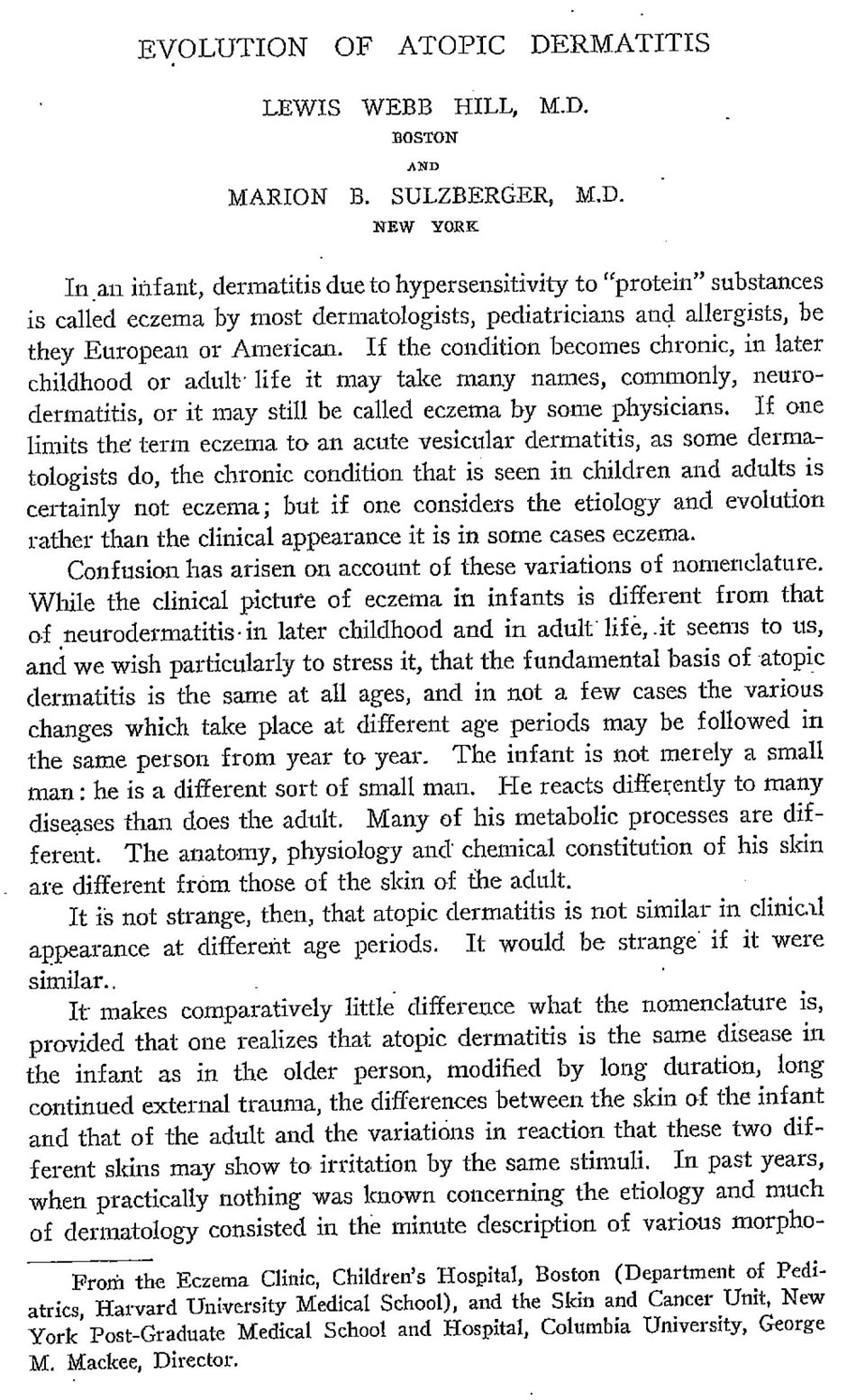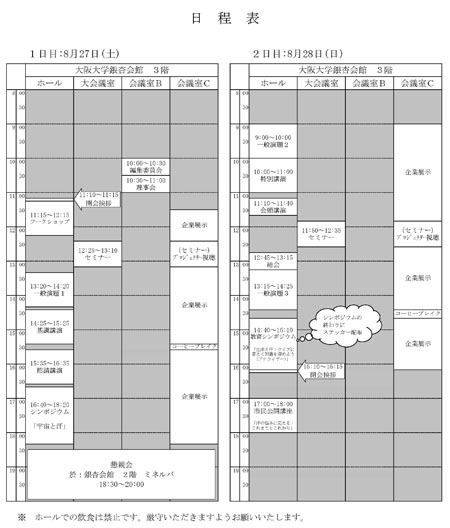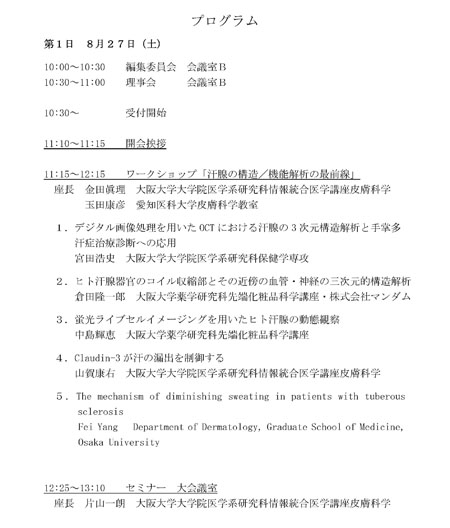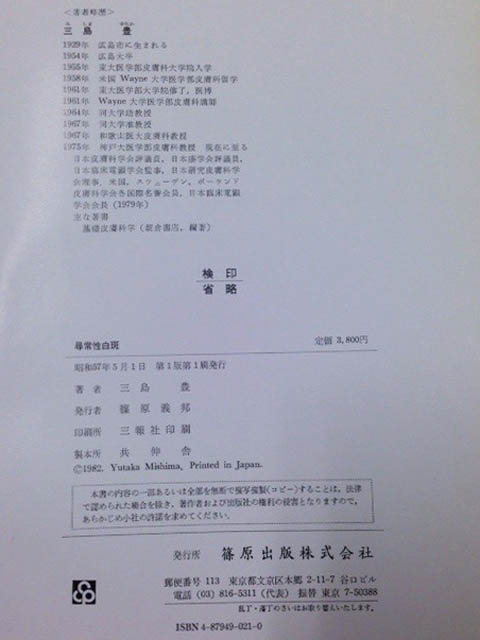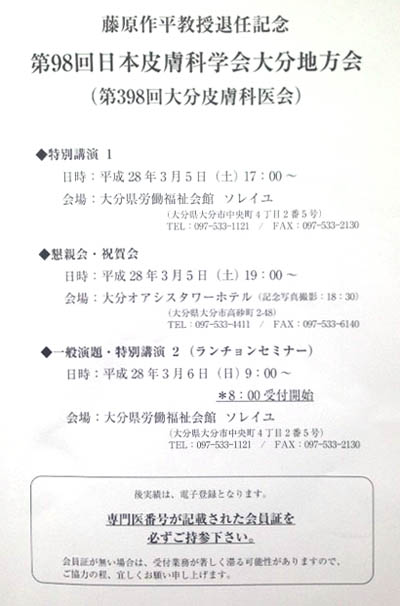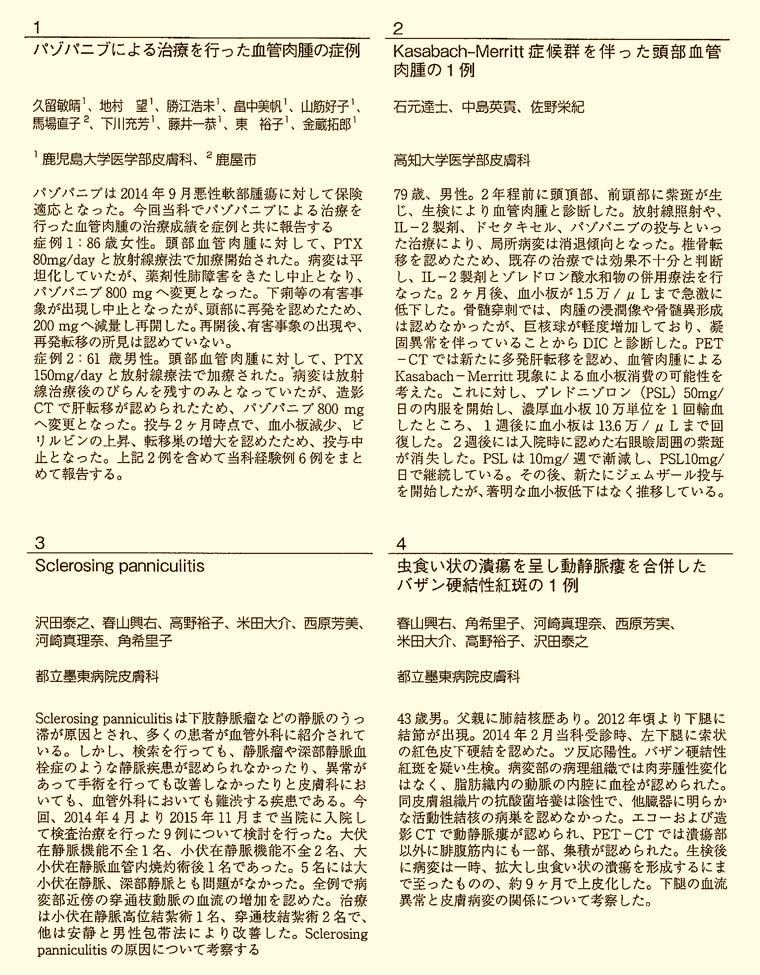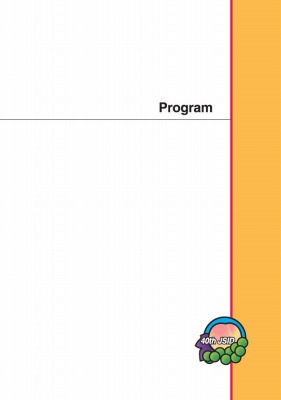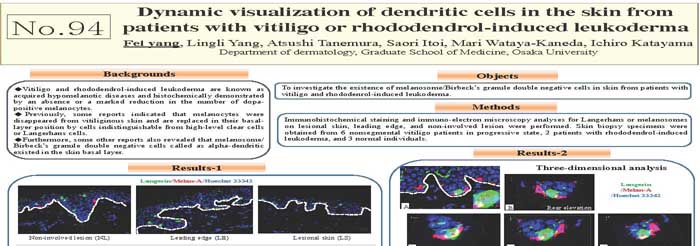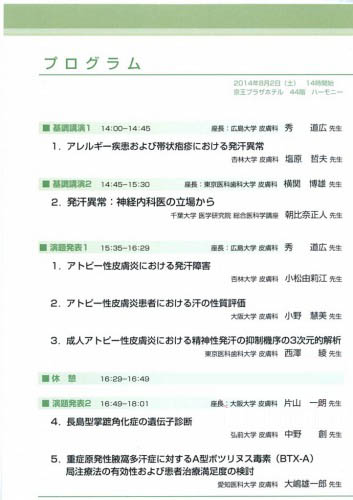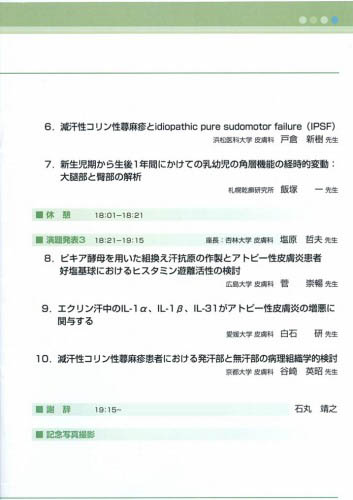大阪大学皮膚科教授退任にあたってのご挨拶
大阪大学皮膚科教授退任にあたってのご挨拶
大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学皮膚科学
教授 片山一朗
私は平成16年の3月1日付けにて伝統ある大阪大学医学部皮膚科学講座の第7代教授を担当させて頂くことになりました。
就任の挨拶では以下のような考えを述べました。「私はドイツ型の臨床を重視し、関連病院の再編と連携の強化、基礎教室との人的、学問的交流を推進し、新しい時代の大阪大皮膚科学教室の創生を目標として教室運営を行います」。着任後は日常診療で患者さんから得られる疑問点を解決する、現時点の医療知識、技術、医療機器で治せないような病態の治療法を創出するための研究を行い、患者さんに還元していく姿勢をモットーに若い医局員や関連病院の先生方と連携し、診療、教育、研究を開始しました。結果的には、スーパーローテートシステムの導入で2年間のブランクが生じましたが、認定研修施設数としては全国でも有数の規模になり、医師数も皮膚科勤務医減少の中で最低3人以上の体制を維持しています。関連病院部長と医局との密な連絡で復帰女性医師の支援や研修、皮膚科医としてのモチベーションの維持、大学院進学や国内、海外留学などある程度の成果が達成できました。研究に関しては私自身のテーマであるアトピー性皮膚炎の疫学研究や悪化因子の見直しを加味した、治療ガイドラインの策定にも関与させて頂きました。特に室田准教授と瀧原圭子循環器内科教授(保健センター所長)と開始した保健センターとの新入生のアトピー検診は大きな成果を残し、継続して研究を進めて頂く予定です。その過程で見出した悪化因子としての汗の新たなメタボロノーム解析や発汗制御の4次元解析画像は世界で初めての成果で今後のアトピー性皮膚炎の発症機序を考える上で大きな成果となりました。さらに痒みの認知機構に関しても「アーテミン」という神経成長因子がアトピー性皮膚炎の痒み過敏に大きな役割を果たしていることを室田浩之准教授が見出しました。また早期のスキンケア介入がアトピー性皮膚炎などのアレルギー疾患の発症と進展を制御するという臨床研究も生育医療センターと開始し、大きな成果を挙げました。特記すべきこととして、金田眞理講師を中心に取り組んで来たラパマイシン外用剤による結節性硬化症の治療がAMEDによる阪大発の初めての創薬として今年7月にも発売予定になります。まさに大阪大学皮膚科が世界に誇れる成果と考えます。玉井克人教授との先天性表皮水疱症の再生医療治療の確立とその臨床応用研究共々、大阪大学皮膚科が皮膚難病治療の日本、そして世界の研究拠点になることを願っております。最後になりますが、新たな専門医制度が開始され、皮膚科のような診療科では、個々の大学単独での医師教育は難しくなることが予想されます。大学間の枠を超えて、それぞれの特徴を持つ大学病院あるいは基幹病院、さらに開業の先生の施設で何年か研修、研究し、また出身医局にその成果を持ち帰って頂くことも可能になるかと思います、今後は若い先生がさらに楽しい皮膚科学を学べ、そして次の世代にその知識や技術、そして個々の皮膚科医の哲学を継承していくことの出来る環境を創って頂きたいと思います。最後になりますが14年間にわたり教室、そして私を支援していただいた全ての方にお礼を申し上げ、退任のご挨拶とさせて頂きます。
大阪大学皮膚科教授 片山一朗

なお退官記念地方会と(2018.3.10-11) と The 2nd Meeting of East Asia Vitiligo Association / The 1st Meeting of Japanese Society for Vitiligo (2018.3.9)合同学会のプログラムを掲載する。
第466回片山一朗教授退官記念大阪地方会講演 (座長:宮地良樹先生)

The 2nd Meeting of East Asia Vitiligo Association / The 1st Meeting of Japanese Society for Vitiligo

最終講義後に金田安史医学部長と教室員との集合写真

「大阪大学皮膚科教授退任にあたってのご挨拶」
大阪大学皮膚科教授 片山一朗
平成30(2018)年3月31日
2つのビッグニュース
情報統合医学皮膚科学
教授 片山一朗

彼はまた、皮膚疾患や自然現象の本質を一瞬にして捉え、それを簡潔なイラストにして残す素晴らしい才能があり、彼の紙カルテからは多くの事を勉強させて頂いた。彼が大阪にきた2004年は教授交代と、スーパーローテート開始の年で、2年間新入医局員がこない時期が続き、人事面でも大変苦労したが、彼と始めたアトピー外来と膠原病外来を中心に関連病院とも連携が強くなり、現在では大阪大学皮膚科の関連病院は部長の専門性が明確になり、ローテーターの数や研修プログラムは全国でも有数の質、量に育ってきており、今後もその維持と発展を期待する次第である。


今の時代、皮膚科が医療の中でどのように貢献できるか真剣に考える時であり、大学や国、診療科を超えて皮膚科医師、研究者が協力し、難治疾患の病態解明、創薬に向け果敢に取り組んでくれる次代の皮膚科医を育てていかないと、大学皮膚科が無くなる日が来るかもしれないと危惧する。
「明日世界が滅びるとしても、今日、君はリンゴの木を植える」。この言葉は開高健が紹介して有名になったルターの言葉とされている。私が長崎を離れる時にも医局の若い先生にこの言葉を残して来たが、今、長崎では何本かのリンゴの木が立派に育っているようである。お二人とって、これからが大事な時間の始まりであり、大きく変わる時代の中で、時間の経過は早い。たくさんのリンゴの木を育て、豊かな果実を次代に伝えてください。
平成30(2018)年3月28日
Evolution of atopic dermatitis in the 21st century
Evolution of atopic dermatitis in the 21st century
大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学皮膚科学
教授 片山一朗
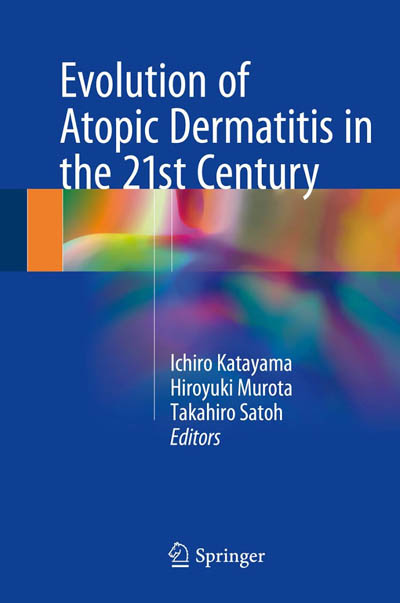
西岡清東京医科歯科大学名誉教授にはアトピー性皮膚炎の歴史と日本での概念や病態の移り変わりを巻頭に執筆頂きました。
また、お忙しい中、多くの先生にご自身のオリジナルな日本発の研究成果を執筆頂き、まさに日本でアトピー性皮膚炎の病態認識と治療がどう変化(進化)してきたかを取り纏める事ができたことは編者にとっては望外の喜びとなりました。日本のアトピー性皮膚炎の研究は東大の笹川正二先生、小嶋理一先生、京大の太藤重夫先生、上原正巳先生、田上八朗先生、名古屋大学の上田宏先生、長崎大の吉田彦太郎先生、大阪大の青木敏之先生、西岡清先生などの大先輩達が切り拓かれてきたかと思います。今回、そのお弟子さんを中心に長年に亘る研究成果として本書を発刊出来たことに改めて、関係者諸氏に感謝申し上げます。現在、アトピー性皮膚炎の病態はバリア異常とTh2アレルギー、そしてその結果として生じる痒みが大きな治療の標的となり、新しい外用剤や分子標的薬などが続々と登場していますが、Sulzberger先生がいみじくも述べられているように「正常人に対して、アトピー性の過敏性を獲得させる多様性因子が理解できるようになるまで、そしてこの多様性を直接制御できるようになるまではアトピー性皮膚炎の最善の治療は対症的ではあるが、無理のない局所ないし全身療法である」という言葉を忘れず、さらに病態研究が進み、ギリシア語でStrangeを意味する「Atopy」という名前が消える日を待っています。
Contents PDF
http://www.springer.com/gp/book/9789811055409 でも案内しています。
さらに楽しい皮膚科学を目指して
さらに楽しい皮膚科学を目指して
大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学皮膚科学
教授 片山一朗
謹賀新年
皆さま輝かしい新年を迎えておられると思います。今年は皮膚科医となり40年が経過し、退官を迎える歳になりました。ある時間と空間、そして様々な世界を共有して頂いた全ての方にお礼申し上げます。勤務医、研究者としてやりたい事は全てやり遂げたと思います。今後は、また新しい出会いを大切にし、自分の世界を広げていきたいと考えています。新たなご厚誼をお願い申し上げます。
さて昨年から、後期研修医制度が開始され、医師の地域的偏在、診療科間での偏在に加え、臨床科における研究者の減少が顕在化してきました。またトランプ現象に代表される孤立化と利権の囲い込みがアカデミアの世界にも押し寄せつつあるようです。ただ医局長の壽先生から関西圏の大学皮膚科教室間で、医局長連絡会議が持たれるようになり、学問のみでなく、医師の勤務支援や人事交流の下支えのための情報交換会を開始したとの話を聞きました。私も医学の分野の高度化と反比例するようにマンパワーの低下、運営交付金の減額が進み、最近では、競争的研究費獲得のハードルが高くなり、皮膚科のようないわゆるマイナー科と言われる診療科の医学の中での地位の相対的な低下はアメリカやお隣の韓国と似た動きをしております。これは若い皮膚科医を指導する中堅の医師が2004年のスーパーローテート以来大きく減少していることや、大学以外でのストレート研修を希望する医師が増えていること、女性医師の増加に伴う診療現場あるいは研究分野での絶対的なマンパワー不足がさらに進んでいることによるのかと思います。そのような中で先に述べた関西圏での大学を超えた連携体制の試みが医局長の先生達のご尽力で開始されたのは本当に心強い限りで、是非その流れを進めて頂きたいと思います。私も何年か前から、皮膚外科や臨床の中で必要とされる皮膚病理、また皮膚科医として膠原病などの疾患を取り扱う上で最低限の全身管理や皮膚科的な見方を勉強する機会がとみに減っていることに大きな危機感を持ってきました。その対策として、関西圏の皮膚科施設の先生が集まり皮膚腫瘍、皮膚病理を一緒に勉強するなにわ皮膚科腫瘍勉強会を種村講師の尽力で立ち上げ、参加者も増加しているようです。また以前京大と阪大で研究に特化して行っていた「天王山カンファレンス」が「関西若手皮膚医の集い」として模様替えし、先ず参加可能な大学の准教授の先生方にプログラム委員会を作って頂き、臨床、基礎両方の演題が発表されるなど、新たな展開をみせています。先日開催された会に、若手ではありませんが参加させて頂き、熱心な討論を楽しませて頂きました。若手に限らず、参加案内など出して頂ければ、より有益な会に育っていくかと思います。また大阪はびきの医療センターの片岡葉子先生が「アトピー性皮膚炎治療研究会」の組織や運営方法を大幅に変更され、若い先生が全国から集まりやすい研究会に様変わりしつつあるようです。さらに昨年から大阪国際がんセンターに爲政大幾先生が赴任され、「腫瘍皮膚科」の看板を上げられ、全国から皮膚腫瘍の治療に興味を持つ若い先生が研修できる組織作りを開始されました。これらの大学間を超えての研修、研究、討論が出来る場が増えれば、若い先生方が楽しい皮膚科学を研修できる事が可能になりますし、それぞれの特徴を持つ大学病院あるいは基幹病院、さらに開業の先生の施設で何年か研修、研究し、また出身医局にその成果を持ち帰って頂くことも可能になるかと思います。もちろんそのためには、各大学の大学教授、指導医師が参加する地方会での若い人の教育が何より大事なことは言うまでもありません。
後期専門医制度が始まる今年こそ、若い先生がさらに楽しい皮膚科学を学べ、そして次の世代にその知識や技術、そして個々の皮膚科医の哲学を継承させていくことの出来る環境を創って頂きたいと思います。

昨年12月に第3回インドシナ皮膚科学会で参加したハノイでたまたまシャッターチャンスがあった、大学病院看護師の卒業セレモニー。
次のステップに進まれる喜びが溢れている写真かと思います。
大阪大学皮膚科教授 片山一朗
平成30(2018)年1月1日
第42回日本研究皮膚科学会
第42回日本研究皮膚科学会
会頭:佐野栄紀高知大学皮膚科教授
会場:高知カルポート
会期:平成29年12月15〜17日
テーマ:「We’ve Got Science Under Your Skin」
大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学皮膚科学
教授 片山一朗
佐野先生が会頭をされた第42回日本研究皮膚科学会(JSID)に参加した。この学会が始まり41年となる。私が皮膚科医になった前年、1976年にその前身皮膚科研究会が設立され、1981年から現在の研究皮膚科学会として、正式の学会になった。私にとっては当時、日本免疫学会が最も重要な学会であったが、1985年に米国の研究皮膚科学会(SID)とJSIDがワシントンでJoint Meetingを開催し、その時にOral presentation を行った時から、参加するようになった。今回、名誉会員に選ばれ、スピーチでもそのことに触れたが、今、この学会が大きく成長し、国際英文誌を持ち、300題を超える演題が集まるようになり、また英語での発表と質疑応答が普通に行われるようになったのは歴代の理事長、事務局長、雑誌委員長などのご尽力によるところが大きく、深謝したい。特に初期の組織作りに尽力された水野信行名古屋市大名誉教授、三嶋豊神戸大学名誉教授、JDSの初代編集員長の小川秀興順天堂大学理事長の功績は大きく、本学会の発展に 大きな 貢献をされたことに新めて改めて謝意を表したい。この会期中に2023年の第8回国際研究皮膚科学会(IID)が椛島健治先生を会頭に、日本で開催されることが決定されたが、佐藤先生、森田先生、椛島先生や島田、天谷前理事長のご尽力に敬意を表したい。今回の会頭を務められた佐野先生が挨拶の中で述べられているように今回のテーマを「We’ve Got Science Under Your Skin」とされ、フランクシナトラの歌で有名なジャズの名曲「I’ve Got You Under My Skin」から取られたと述べられている。また「皮膚の科学をぎゅっと抱きしめたい、との意を込めました。」とも書かれているが、今回のプログラム内容を見ると、まさに佐野先生が抱きしめられた皮膚の科学の豊穣な世界が繰り広げられており、表紙を飾った、お父上の佐野榮春先生の「死海のほとり」と合わせ、佐野先生が考え、また楽しんでおられる「Investigative Dermatology」を若い世代の先生方に示されたのかと思う。また、招待会から懇親会、Tea time concertまで素晴らしいジャズを提供して頂いた河西さんのウッドベースの音色と講演の合間に佐野先生が選曲されたジャズの名曲が流れ、高知の風景、医局員の方の日常風景もスライドで紹介されており、学会で疲れた頭や体を癒やして頂いた。

Diploma of Dermatological Scientistを受賞された楊飛君と佐野会頭、片山
肝腎の皮膚科研究のプログラムは座長や講演、会議が重なり、免疫の三宅先生、高濱先生の講演を聞き逃したが、2日目午後の「Frontier symposium」の」5名の先生方の講演はお一人の持ち時間は少なかったが、皮膚科医にとっては毛や爪の再生や色素細胞幹細胞の最先端のお話で、普段なかなか聞けない素晴らしい講演ばかりであった(PDF参照1)。特に高橋先生のメラノソーム輸送の話は我々が現在行っている研究の参考になった。また谷奥喜平メモリアル講演で講演されたGillet教授のLL37などの抗菌ペプチドが乾癬やSLEなどの疾患の最初の引き金を引く可能性を述べられた。これは我々が現在検討している白斑の発症機序に近く、うまく白斑の動物モデルが出来れば是非検討したいと考えている。また高知大の片岡先生(p01-14, C07-3)の口演でimiquimodの外用でSLE様のモデルが誘導できるがTLR7のk/oでは発症しないこと、基剤中のisostearic acidによるInflammasome刺激皮膚炎が乾癬病変の誘導に重要であること、基剤にこの成分が含有されていないresimiquimodではSLE様の自己免疫誘導は生じるが、乾癬は誘導されないことを報告された。白斑のをモデルからはNALP1遺伝子変異による皮膚マイクロビオーム刺激の自己免疫機構の誘導に加え、酸化ストレスなどによるInflammasome刺激が白斑発症の引きがねになるのかもしれない。また浜松医大の藤山先生の演題(P04-05,C05-3)はステロイド抵抗性の乾癬の病態にMDR-1( Multi-drug resistant gene)を発現したTh17細胞が関与する可能性を人の乾癬組織から増幅したT細胞の解析で示された。このような研究は貴重で、今後の展開に期待したい。以前我々も同様の報告をしている(PDF参照2)北大の渡辺先生が口演された(P05-01,Plenary II-7)ではtype 17 コラーゲンの欠損で表皮IFEの増殖が増し、しかも極性が90度長軸方向になり見かけの表皮肥厚になることを示された。基底膜構成蛋白が表皮の形態に影響を与える可能性があり興味深い(E-lifeに発表とのこと)。また慶応大学の山上先生(P-01-17,C07-6)のバンコマイシン誘発性のLinear IgA Dermatitisは間接法陰性が多いがELISAのタイプ7コラーゲンにバンコマイシンを添加することで陽性率が大幅に増加することを綺麗に示された。接触皮膚炎のハプテンとキャリア-蛋白の関係にも近く、バンコマイシンとタイプ7コラーゲンの認識がどうなされるのか結合性も含め、興味深い。阪大の免疫フロンテア研究センターの荒瀬尚教授は自己抗体の産生にClass 2抗原に発現される、misfold proteinが重要であることをIgGのFc部分が自己抗原となるリウマチ因子の誘導機序をモデルにより解説され、抗リン脂質抗体症候群などの新たな抗原エピトープの紹介をされた。後半ではつい最近Nature(Nature. 2017 Dec 7;552(7683):101-105. Saito F et al.)に掲載されたマラリアでの感染防御に関わる B cell inhibitory receptorとマラリア感染赤血球表面に発現するRIFIN proteins の結合による免疫制御機構がPD-1/PDL1の関係に近いことを綺麗に示された。このほかにも興味深い演題が多くあったが、またPDFで確認されたい。ただ座長をして感じたがもう少し討論の時間が多く取れればと願う次第である。また日本語の討論でも良いかと思うし、若い方は先ず研究の面白さを日本語でも討論することでさらに研究の意欲が高まるかと思う。

大阪大学皮膚科教授 片山一朗
平成29(2017)年12月20日
第47回日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会総会学術大会 第41回皮膚脈管・膠原病研究会
第47回日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会総会学術大会
第41回皮膚脈管・膠原病研究会
会長:金倉拓郎 鹿児島大学教授
会場:かごしま県民交流会館
会期:2017年12月8-10日
大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学皮膚科学
教授 片山一朗
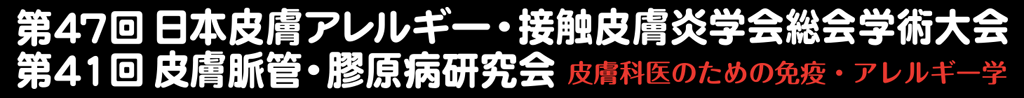

金蔵会頭の鹿児島大学学会シンボルとして有名になった薩摩ブタの可愛いイラスト、「セイブー」の名前の由来の説明から学会が開催された。今回、日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会と皮膚脈管膠原病研究会の合同化に伴い、長い学術大会の名前になったが、来年からは日本皮膚免疫アレルギー学会という、シンプルな学会名になる。また学会が2.5日になり接触皮膚炎、蕁麻疹、薬疹などのアレルギー疾患と膠原病、血管炎などが別会場で、平行して行われ、メイン会場ではシンポジウムや特別講演が、また別会場でハンズオンセミナーが時間をズラして上手くプログラム編成されていた。特に、今回は例年75題前後の演題が2日間でに亘って行われていた膠原病、血管炎関連演題が、どの程度集まるか不安だったが、最終的に40題近い演題が集まり、金蔵会頭も安堵されていたようである。ただ演題が皮膚筋炎関連が多く、本来の多様な臨床像を提呈する膠原病や血管炎の演題にやや偏りが見られ、一部議論が盛り上がらなかった点や、血管炎と膠原病関連演題が一部同じ時間帯に集まっていた点はまた来年以降検討して頂ければと考える。
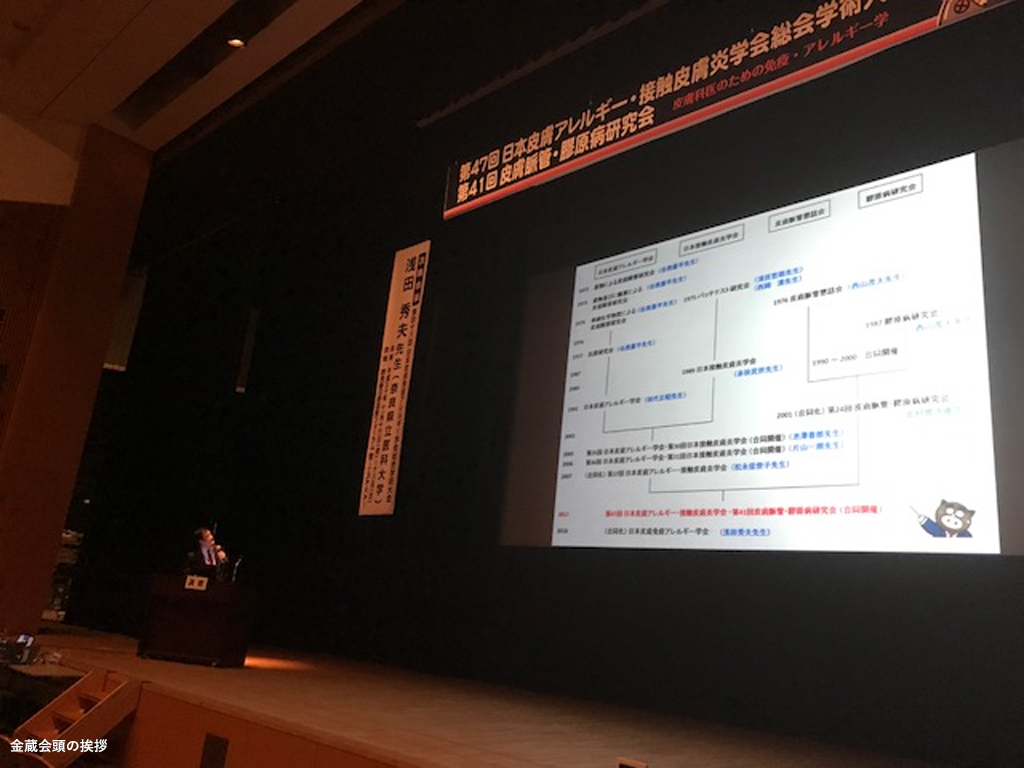
今回の企画で特筆すべきはシンポジウム「脱毛症」で、脱毛症を自己免疫疾患の観点からシンポジウムが組まれたのは恐らく、初めてかと思われる。どの発表も興味深いタイトルだったが、浜松医大の伊藤先生のReviewで円形脱毛症では毛包バルジ領域のCD200の発現がIFNγで消失することを述べられた。CD8陽性細胞による直接的な細胞傷害性で脱毛が生じると考えていたので質問したが、討論に参加された大山先生のコメントではまだ、その意義は不明とのことであった。加齢性の毛包の萎縮に、好中球エラスターゼによる17型コラーゲンの消失が毛包ステムセルの排除に関与するとの報告が西村栄美先生の研究で紹介されているが、ステムセルニッチの構成マトリックスを考える上で重要かと考える。また鹿児島大学の内田先生が円形脱毛症におけるIFNγ産生細胞がγδ細胞である可能性を報告された。彼は今回の特別講演で来日されたマンチェスター大学のRalf Paus教授の教室に留学されているが、この分野の研究が脱毛症と自己免疫の接点を考える上で重要な研究になるかと思う。一般演題では一型アレルギーの研究で有名な西宮市で開業されている原田晋先生によるゴマのアレルギーが興味深かった。日常生活でなじみの食材であるが一型アレルギーの報告は殆どないそうで、今後の解析が待たれる。大阪大学からは室田先生、中川先生、壽先生、越智先生、林先生、外村先生、田中先生、清水先生が出席、発表したがいづれの演題も興味深く、たくさんの質問があった(演題名はPDF参照)。
今回は日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会と皮膚脈管膠原病研究会の合同化に伴い、討論の盛り上がりにやや欠け、元の皮膚脈管膠原病研究会の復活を考えてはという意見も頂いた。現在、日本皮膚免疫アレルギー学会には接触皮膚炎、薬疹、アトピー性皮膚炎、蕁麻疹、職業アレルギー、あらたに加わった膠原病などのアドホック委員会があり、国際学会や皮膚科学会との窓口になっている。今後、より深い討論などが必要になるときには分科会のような形式で研究会を復活させるなどの議論がでてくるかと思う。皮膚脈管・膠原病研究会は出席者数の減少や、議論が少なくなったこと、開催校の負担増、海外との連絡、治験など色々な問題が起こり合同化となったが、逆に一時期、出席者の減少でその存続が危ぶまれたアトピー性皮膚炎治療研究会は現在、新任教授の参加が増え、また活性化していくことが期待されている。時代の変化に伴い、柔軟に対応して行くことが必要と考える。重要な点は本当にその領域の臨床や研究が好きな人が参加して、議論ができ、若い皮膚科医が積極的に演題を出し、討論に参加出来ることかと考える。新理事長には浜松医大の戸倉教授が選任され、来年の48回大会は奈良医大の浅田教授が会頭を務められる。新しく生まれ変わる日本皮膚免疫アレルギー学会が大きく発展していくことを願う次第である。

大阪大学皮膚科教授 片山一朗
平成29年12月19日
The 34th International Diploma Course in Dermatology and Dermatosurgery, Bangkok, Thailand バンコクからの新しい風 The 3rd Indochina Conference of Dermatology 第三回インドシナ皮膚科学会
The 34th International Diploma Course in
Dermatology and Dermatosurgery, Bangkok, Thailand
バンコクからの新しい風
大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学皮膚科学
教授 片山一朗

私の講義は以下の内容で1.5時間x9コマを行ったが、日本での講義に比べ、皆さん真剣に話を聞いてくれ、途中でもどんどん質問をしてくれるスタイルで、毎回結構ハードではあるが久しぶりに味合う、心地よい充実感、達成感を伴う講義であった。
| Nov. 20 (Mon) | PM | 1) Introduction himself and Allergic skin diseases: 2) Drug eruption, Contact dermatitis, Urticaria |
|---|---|---|
| Nov. 21 (Tue) | AM
PM |
3) New role of histamine in the skin, 4) Collagen Vascular Disease :Review and SLE, DM 5) Scleroderma, Sjogren’s syndrome |
| Nov. 22 (Wed) | PM | 6) Guideline of atopic dermatitis, 7) Itch and stress management, Pruritis and Prurigo |
| Nov. 23 (Thu) | AM PM |
8) Pathogenesis and guideline of vitiligo vulgaris 9) Excimer Light treatment of skin diseases |

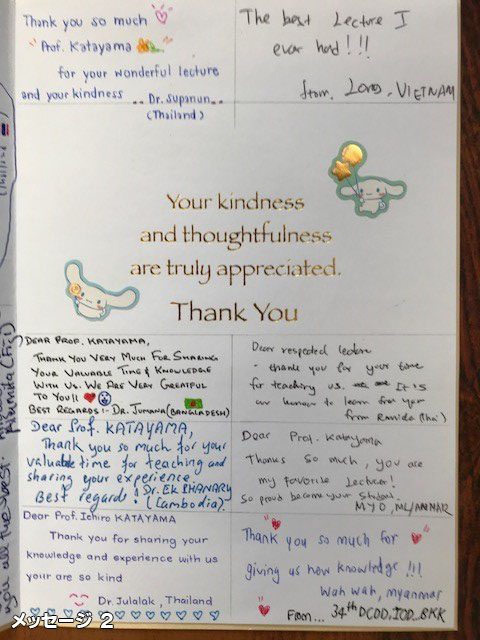
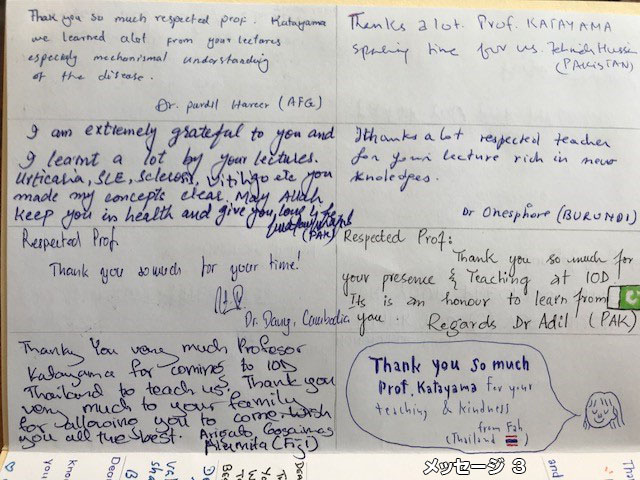


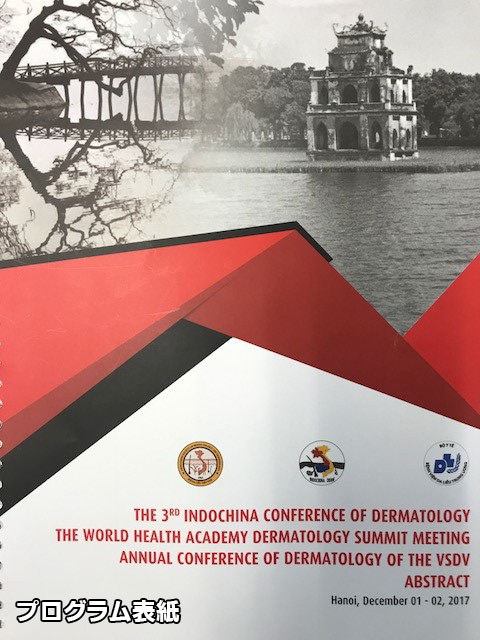
第三回インドシナ皮膚科学会
2017. December 01-02
President. Prof. Tran Hau Khang National Hospital of Dermatology and Venereology; Professor, Hanoi Medical University, Vietnam ベトナム皮膚科学会理事長
タイでの講義に引き続き、ハノイで開催された第3回インドシナ皮膚科学会に参加し、「New and old game players in vitiligo」というタイトルで講演した。この会への出席は一昨年、池田志斈順天堂大学教授を会頭として浦安で開催された日中韓皮膚科学会にて大阪市大の鶴田先生から紹介して頂いた、今回の会頭であるハノイ医科大医学教授のProf. Tran Hau Khang先生からの招待であり、白斑などがメイントピックスである学会を楽しませて頂いた。日本からは池田、鶴田教授とが参加されていたが、懇親会の席ではホーチミンを拠点としてカンボジア、ラオスなどで感染症の疫学研究をされている甲斐先生のグループや日本に留学されていた先生方とも知り合いになることが出来た。この学会が開催されたハノイは初めての訪問で、旧共産国とは思えないような活気と多くの食材で溢れた都市であり、また学会参加者の多くは若い女性医師が中心で、これからは、これら若い先生方の活躍でアジアの皮膚科学の発展が大いに期待されるかと思う。展示ブースは美容皮膚科関連が多かったが、若手の大学勤務医は優秀な方が多く、また感染症や重症皮膚疾患の病態研究や治療にも熱心であり、タイ、ミャンマーなどの大学皮膚科と良く似た傾向のようである。今後も是非インドシナ各国の皮膚科の先生方との交流が深まることを願う次第である。


高知大学皮膚科での最終講義
高知大学皮膚科での最終講義
大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学皮膚科学
教授 片山一朗

「かつて、文献情報というのは、経験的に身につけるにしても参考文献をたどるにしても、時系列的に、ある程度の歴史的経緯を伴いつつ、個人の中に蓄積されていくものであった。」… →最近はPubMedなどで限られたキーワード検索する、ダウンロード可能な文献のみしか読まない方も増えている。キーワードが限定していればそこから抜け落ちる重要な論文も多い。ただ文献主義になれと言うことではない。
「そして暗黙知が形成されていった。」…→共通の認識基盤の無い方、あるい興味の無い方との議論は不毛である。
「生命科学の研究というのは、非常に労働集約的なものであり、実験量と成果にはある程度の相関がある。手を動かしたからといってその分だけ進むというものではないが、動かさなければ全く進まない。」…→パソコンの前に座り、一日を無為に過ごしている方のなんと多いことか。
「その結果、不思議の国のアリスに出てくる赤の女王のように、自分自身がその場にとどまるため、すなわち、研究のスピードに追い越されないために、より一層のスピードで走り続けるしかないという状況が余儀なくされている。それも、あまり考えることなしに。」…→前を向いているのか後ろを向いているのかも分からなくなってしまう。そして時間の流れも分からなくなってしまう。
※以上片山引用(→コメント)
高知大学発の熱いメッセージが12月の研究皮膚科学会で若い先生方に伝わることを願いお礼とさせて頂く。

大阪大学皮膚科教授 片山一朗
平成29年11月16日
この一週間のメモランダム
この一週間のメモランダム
大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学皮膚科学
教授 片山一朗
この一週間で4つの研究会の座長を勤める機会があった。最初の会は富山大皮膚科の清水忠道教授の光老化と骨髄性ポルフィリン症に関する講演で、ここ最近はアレルギー、乾癬やざ瘡、ヘルペス、免疫チェックポイント薬など、この一年間、新規薬剤の登場で、メーカー主導の講演が多いが、清水教授のお話はスポンサー色のない学術的なお話で久しぶりに、内容の濃い講演であり、大学関連の若い先生とっても、普段、なかなか聞くことのできない有益な講演会であったかと考える。昨日の痒み国際シンポジウムも基礎から臨床迄痒み研究の最前線の研究会でこちらも、若い先生から退官された先生迄痒み研究の好きな先生方の活発な質問が飛び交う充実した研究会で、皮膚科、麻酔科、腎臓内科、神経内科、基礎生理、解剖学、企業研究者など多様な領域の先生方が有益な情報交換をされていたのが印象的だった。逆に形成外科、透析内科の先生による救肢を目指すフットケア研究会、リウマチ・膠原病医の先生による関節症性乾癬の研究会は、どちらも他科の講師による皮膚疾患に関する講演だったが、チーム医療の中での皮膚科医の存在感がゼロで、この領域の診療に関する皮膚科医の役割を再考する良い機会でもあった。前者は高齢化社会で患者の増加が予想されるが、在院日数や収益に対する介護やマンパワーの問題から積極的な治療介入が敬遠されがちな領域の疾患でありその予防、治療、長期管理をチーム医療として行う上で、皮膚科医の果たす役割は大きい。また後者は生物製剤に加え、これから続々と登場するB 細胞を標的とする膠原病治療薬の登場でその診療内容が大きく変わることが予測される中、皮膚症状に加え、生命予後に関わる全身疾患の管理や治療方針の決定に皮膚科医がどこ迄参加するべきかが大きな問題になるかと考える。生物製剤に続き、免疫チェックポイント薬を始めとして次々と高額治療薬が登場する時代となった。これらの薬剤の今後のあり方を考えると臨床的には2つの問題点があるかと考える。一つはこのような高額医療が適用される疾患、患者の選択、使用法で、その点に関しては免疫チェックポイント薬で、現在議論が進んでいるがその将来像は見えてこない。開発の多くに関わってきた欧米、特に米国ではオバマケアによる国民皆保険制度では保証されない高額の医療費を支払えない中間層の医療ローン破綻者の増加を招いていることが明らかにされている。(引用) アメリカではこれらの高額医療はまず富裕層で使用されるのは明らかでその使用法の検討が皆保健制度の整っている日本で行われているとの話も聞こえてくる。もう一つの問題点はこれらの高額医療が圧倒的な臨床的な効果を発揮することが明らかにされつつあり、普及してきたガイドラインが整備されれば、診断がつけばあとは誰でも治療が可能となることは自明であり、そこにAI診断が普及し、対面医療が緩和されれば処置が必要でない領域の専門医は不要になるかもしれない。実際米国の大病院、大学は皮膚科専門医はコンサルタントとして実際の医療現場での治療に関与しなくなりつつあるとの話を留学から帰国された先生から聞いた事がある。その先にあるのはさらに進化したAIと医療の現場で患者に診療にあたる総合医になるのかと思う。先に述べたリウマチ・アレルギー・自己免疫疾患を例に挙げると、TNFなどのProinflammatory サイトカイン、抗体産生に関わるB細胞、IL4/13を標的とする治療薬などが整備されればスーパーリウマチ専門医、スーパーアレルギー専門医、将来的にはスーパー総合医が多くの難治性皮膚疾患を治療しだすのは近いと考えるのは私だけではないと思うし、その動きは既に始まっているようである。そのような事を考えていたこの一週間であったが今朝嬉しい事があった。室田浩之先生の皮膚科臨床医としての確かな眼によるアトピー性皮膚炎患者の汗の指導に関する長い、地道な研究成果の重要さが皮膚の日の今日,天声人語(2017年11月12日)で取り上げられた。
(天声人語)アトピーという異世界 2017年11月12日朝刊掲載
汗はかくべきか、かかざるべきか――。アトピー性皮膚炎の専門医はしばしば患者から相談を受ける。医学に疎い当方など汗はかゆみの元と思い込んでいたが、実はかなりの難問。近年は汗を治療に使う試みも本格化してきた▼大阪大病院の室田浩之准教授(48)によると、アトピー患者は炎症が強くなると発汗機能が低下する。「汗を上手にかければ、皮膚の湿度を保つなど汗の主な利点をいかせると考えました」▼自転車通勤を続けて症状が緩和した患者もいる。医師に「汗は極力避けて」と指導され、長年守ってきた。思い切って汗を流し、直後にタオルでふき、保湿剤を塗るなど丹念な手入れをした。「汗は放置すると悪化につながる。でもかきたての新鮮な汗は別。皮膚を守ってくれます」▼汗の是非に限らず、アトピーには謎が多い。鼻炎やぜんそくを伴いやすい、家族に似た症状が出る、成人後に再発する……。これらはなぜなのか。そもそもアトピー自体、「奇妙さ」を意味するギリシャ語「アトピア」に由来する▼室田医師らが格闘中の課題は、汗をかいた瞬間になぜかゆみを感じるか。「難題です。でもひとつひとつ答えを見つけていけば、いつか『奇妙』な病気でなくなるはずです」▼きょうは「皮膚の日」。いい(11)皮膚(12)の語呂合わせだ。かゆみ、痛み、乾き、湿疹など症状は千差万別ながら、筆者の周囲でも悩む人は少なくない。謎が残らず解き明かされ、病名からアトピーの言葉が消える日の到来を願う。
(朝日新聞社より掲載許諾済み)<転載不可二次利用禁止>
アトピー性皮膚炎の標準的な治療にても改善しない重症患者さんの多くは今後登場する新規治療薬での改善、寛解が期待されるが、発症、進展防止における悪化因子の検討と対策は重要である。アトピー性皮膚炎の悪化因子と考えられてきた、汗の重要さを科学的に再検討することを目的として一緒に汗をかいてきて頂いた杏林大学の塩原先生、東京医科歯科大学の横関先生共々、室田浩之先生の研究成果が一般の方から評価されたことを素直に喜びたい。またこのような優れた臨床医の眼を通して初めてAIには真似の出来ない診療やあらたな研究テーマの発見、創薬開発が可能になると考える。第二、第三の室田先生が現れることを期待したい。
※引用 東洋経済Online
「オバマケア」が機能不全に陥っている理由 (2017年03月05日)
トランプが「オバマケア」を撤廃できないワケ (2016年11月15日)
大阪大学皮膚科教授 片山一朗
平成29年11月13日
9th IFSI International Federation of Society of Itch
9th IFSI International Federation of Society of Itch
President: Prof. Jacek Szepietowski. Department of Dermatology Wroclaw University
ヴロツワフ大学皮膚科教授
Venue: Novotel Hotel Wroclaw
Date:2017. Oct 15-17
大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学皮膚科学
教授 片山一朗

痒みの研究者が世界から集まるユニークな学会IFSIに参加した。基礎生理、薬理、解剖、臨床からは皮膚科、麻酔科、神経内科、腎臓内科、消化器内科など実に多様な参加者が2年に一度集まり、痒みの基礎から臨床までを幅広く発表、討論する面白い学会である。過去第5回大会の東京(高森健二順天堂大教授が会頭)、からブレスト(フランス)、ボストン、奈良(会頭を務めた)まで参加してきた。この間、痒みの研究は大きく進み、治療薬もいくつか登場してきた。今回の発表の中では先ず、IL4Rがマウス、ヒトともに脊髄後角(DRG)に存在し、慢性の痒み刺激に反応する報告が興味を引いた。今年のCell (2017, 171:1-12)に発表されたこともあり多くの聴衆の注目を集めたが、講演したワシントン大学Itch centerのZhou-Feng Chenは今売り出し中の若手の痒み研究者で、今後世界の痒み研究をリードしてくれる素晴らしい人材と期待する。前回の奈良で九大の津田先生のグループからアトピー性皮膚炎のモデルマウスで皮膚炎症部の支配領域の脊髄でSTAT3依存性のAstrocyte由来Lipocalin2がgastrin-releasing peptide(GRP)による痒み刺激を増幅するという興味深い発表があったが、今回の発表は今後のJAK 阻害薬やSTAT3,STAT6などの分子標的薬の開発に大きく貢献するかと考える。ただビタミンD誘発性のアトピー性皮膚炎モデルの痒みを慢性の痒みとしていることや、Th2サイトカインであるIL4がどのように脊髄に移行していくかは不明である。可能性としては脊髄後角でIL4が作られるのかもしれない。Dupilumab (Anti-IL4Rα)の標的がTh2細胞や肥満細胞以外、痒み認知に直接関与するDRGのIL4Rに作用し、痒みに効果を発揮すると考えられるが、IL31との優先順位やIL4がどのようにDRGに届くかなど興味深い。Johns Hopkins 大学神経科学教室のXinzhong Dong はサブスタンスPやエンドテリンなどのペプチド刺激によるマウス腹腔マスト細胞の脱顆粒にIgEを介する機序とは別にMrgprb2を介する機構があることを綺麗に証明されていた。彼はまた喉頭や気道の痒み(OASなどでの違和感に相当?)が迷走神経節の同様のMrgを介する機構が存在する可能性を報告していた。このほか順天堂大学の古宮先生は表皮ケラチノサイトがDPP4(CD26)を発現し、基質であるサブスタンスPを切断し、その分解物SP5-11が乾癬の血清中で増加すること、DPP4阻害薬がイミキモド誘発性乾癬モデルマウスの痒みを抑制する機序を発表されていた。このSP5-11はNK1受容体にAgonisticに作用するようである (JDS 2017 86 212-221)。全体的にはNK1阻害薬やPDE4阻害薬などの新規痒み治療薬に関する臨床開発試験の結果やバイオ製剤、JAK阻害薬を意識した乾癬の発表が多く、メーカ―主導の学会になりつつある危惧を感じた。また痒疹に関しても新たな治療薬の登場を意識した新たな分類や治療指針があった。阪大からは私以外に室田、松本、奥田先生が参加した。特に松本さんは室田先生指導の11βHSD1のケラチノサイト特異的ノックアウトマウスでクロロキン、ヒスタミン誘発性のAllonesis が増強することや末梢神経が表皮内に伸長すること綺麗に証明された。私はステロイドWithdrawalに長期ステロイド外用による11βHSD1のDownregulationと外用中止による表皮コーチゾールプールの急激な減少が関与する可能性を報告した。

初日の理事会の前に、Worclaw大学の皮膚科を訪問し、ムラージュなどの展示館や図書館を見学させていただいた。ヴロツワフ大学は、1702年に設立され、中央ヨーロッパ最古の高等教育機関のひとつとされる。ドイツ語ではBreslau。ポーランドもドイツ皮膚科学の流れを汲み、一つの建物に研究室、病棟があり機能的であるが、エレベーターがなく移動は結構大変だった。ムラージュはハンセン病などの感染症が多く展示してあり、ここでウイーン大学留学中に一年を過ごした土肥慶三の写真や1877〜1884年まで主任を務めたHeinrich Koebnerの写真があった。また有名な細菌学者ポール・エーリッヒもWroclaw University の卒業とのことである。
Jacek教授は、Gala dinnerをWroclaw大学病院博物館で開催された

アトラクションなどもショパンコンクールの若手入賞者やアカペラなど盛りだくさんの内容であった。後で聞くと事務局長のアダム教授からアトラクションなど室田先生に問い合わせがあったようである。
Wroclawの街はいたるところに小人の像がかくれており、小人探しツアーが人気のようだった。2002年頃に民主化の流れで作られその後、商店などが宣伝用にも作ることが認可され、広まったようで、我々もたくさんの人形に出会うことができた。
-

-

-

-


最後になるが、痒みの研究は皮膚科医にとり、大変重要な研究領域であるが、残念ながら、本学会への皮膚科医の参加は少なく、我々以外では慈恵医大の石氏先生グループ、順天堂浦安病院の高森教授グループ、九大の中原先生、東京都の江畑先生など極めて少数であった。この理由は「痒み」が皮疹を伴わない症候であること(もちろんアトピー性皮膚炎を筆頭に多数の疾患がある)、研究手法が複雑で、なじみのない用語が多いなどいくつかの理由があるかとは思うが、2017年の皮膚科領域での主な研究が製薬会社主導の場当たり的なものに変わりつつあることにその本質があるのかと考える。最近読んだ大阪大学医学部の尊敬する仲野徹教授のエッセイを読んでいると、先端基礎医学研究の現状が皮膚科のメガファーマ主導臨床研究に当てはまることがあまりに多く、驚いた。以下参考までに私が共感する、そのエッセンスを列挙するので、また内田先生の本を手に取って全文を読んで頂きたい。
出典:内田樹篇 日本の反知性主義(晶文社;2015年刊)
著者:仲野徹 大阪大学大学院医学系研究科教授
タイトル:科学の進歩にともなう「反知性主義」
仲野先生の修業時代の研究手法とは? 「思えば不親切な時代であった。経験に基づいた伝統技みたいなところも多くて、論理的に考えておかしいと思えるようなこともいろいろあった。しかし、それだけに創意工夫する余地がたくさんあって、いろいろなことを工夫しながら改善していくのがいいトレーニングになっていた。下働きという単純作業をこなしながら、ぼんやりと研究について思いをはせるというのも、ぜいたくな時間の使い方であった。そういう時に不思議といいアイデアが浮かんだものである。一方、教える側からは、そのような作業をさせてみるだけで、きちんと考えるようになる子かどうか、いい研究者になるかどうかおおよその見当がついた。」
→ 本当にそう思います。 最近の若い人の研究のトレンドは? 「しかし、標準化や定型化といった方向性が示されていれば、それにしたがって研究をおこなうことが前提になる。考える必要がないとまでは言わないが、創意工夫のはいる余地が少なくなってきてしまっている、すなわち、型が大事になって、個人の「知性」があまり必要でなくなってきているのだ。 そんな研究はあまりおもしろいとは感じられないのであるが、やらねば競争に負けてしまうので、やらざるをえない。もちろん、そのような解析には、かなりのお金がかかるし、すべてを自分のところではできないので、アウトソーシングすることもある。いわば、知性の外注だ。20〜30年前に比べると、一流雑誌に掲載するためのデータの量は、少なくとも4〜5倍、下手すれば10倍にもなっているはずだ。経験のある研究者が“常識”として言及すらしないような基本的なバックグラウンドが理解できていないこともある。」
→ 博士論文をだすにも大変な労力と資金力がいるが、Rejectが繰り返されているうちに、先をこされてしまう。 「近年、業績至上主義がどんどん厳しくなってきている。業績のある人を採用したいのは、どの組織だって同じことだし、業績はあった方がいいに決まっている。しかし、数値的に評価が可能な業績のある人材を採用することと、知性にあふれた人材を採用することとは必ずしも等価ではない。本当に偉くて尊敬すべきなのは、業績や研究費ではなくて、「なんやわからんけど知性があふれていそうで偉さを感じさせてくれる先生」のはずだ。その大きな流れに抗うには、新しい技術に振り回されすぎたり、情報検索に教えられすぎたり、目的にしばられすぎたりすることを意識的に回避しながら、自分の頭でしっかり考えるということを徹底していくしかない。同時に、一般の人が科学に対する反知性主義に陥らないように説明する必要もある」。
→ 仲野先生はつい最近も晶文社から「こわいもの知らずの病理学講義」という素晴らしい臨床講義録を上梓され、早くも六刷を超えたそうである。この本を読めば、我々臨床医にも、最近の病理学研究の流れがよくわかるし、このような素晴らしい講義を受けることのできる大阪大学医学部の学生は大変幸せである。今後、多くの優れた医師が仲野スクールから誕生することを確信する。皮膚科はまだ手作りの研究が可能な数少ない臨床科です。是非,個人の「知性」に基づいたオリジナルで夢のある研究を始めてください。
→ ※下線部(片山)
大阪大学皮膚科教授 片山一朗
平成29年10月24日
第47回ESDR
第47回ESDR
Salzburg,Congress Center, Austria
2017.9.27-30
会長 Matthias Schmuth教授(インスブルック大学)
大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学皮膚科学
教授 片山一朗

今回の学会テーマは「The Sound of Dermatology」といういかにも欧州の研究者が主宰するにふさわしい魅力的な学会であった。私自身、皮膚科研究の大きな流れの変化を感じたのは1998年のケルンでの国際皮膚学会で分子生物学的な手法が大きく取り上げられた時や、山中先生のノーベル賞受賞後開催された、2013年のエジンバラ国際皮膚科学会での再生医療研究であった。今回は皮膚組織でのTranscriptome解析やMicrobiome解析が中心で実際の生体組織で網羅的な遺伝子解析を行うことが可能な時代になり、EpigeneticsやExome解析などの発表が多くあり、またSingle cellでの遺伝子解析など次の時代の方法論の講演などがあった。ただ臨床的な観点からは乾癬、黒色腫などの皮膚がん、アトピー性皮膚炎などの新しく、かつ劇的な効果を示す薬剤の臨床研究の発表が多く取り上げられる時代になったことである。これらの治療薬はメガファーマやベンチャー企業が皮膚科の研究成果とは全く異なる次元、方法論で開発してきたものばかりで、我々皮膚科医が長年にわたり病因論を研究してきた疾患の病態が新規薬剤の標的分子の解析により次々に明らかにされ、皮膚科医の研究に関する知的な興味の持ち方やその継続性に大きな影響を与えるのではないかと参加していた何人かの先生方と議論した。

今後の研究の方向性が実用的な創薬開発に向かうのは避けられず、大規模な研究を大学レベルで行う事は難しくなる時代がくるし、AIの普及はその傾向に拍車をかけるかと思う。その中でもう一度日常診療で、患者で起こっていることを透徹した観察眼で吟味し、その未知の現象や病態を解明し、患者を治癒させたいという臨床医の熱い思いが再度要求される時代になるのかと思う。マウスばかり見ていては何も生まれてこないのは今のバイオ戦略をみれば明らかであり、その意味で「Stick to human skin diseases」、そして「Beyond Dermatology」という考え方を若い先生に伝えていくことが重要とあらためて感じ、ザルツブルグを後にした。

以下、印象に残った講演など。
Dublin大学のMartin Steinhoff教授はPre-congressのNeurobiologyにてTLR3を介する痒みの機序につき掻破などの障害でKeratinocyte由来の核酸などによる痒み誘発機構がある、また核内に存在するIL33も掻破による痒み誘発に関わるとの話であった。これは痒疹などでの痒み認知機構に関わるかもしれない。彼はPoster walkでもリーダーを務めていたが、アトピー性皮膚炎は発疹型により遺伝子発現など変わる可能性があり、Transcriptomic analysisでの病変部の選択は注意が必要とコメントしていた。
Kiel大学のHohmuth Aは、痒疹をアトピー性皮膚炎での痒疹とアトピー性素因のない痒疹の病理所見で唯一異なるのはSpongiosisと述べ、Atopic eczemaとAtopic dermatitis の病名をどう考える上で、参考になった。(P156 Hohmuth A et al. Epidermal differentiation, inflammation and serum levels of filaggrin and IgE in atopic dermatitis,classical prurigo nodularis and prurigo nodularis in AD.) 京都大学の中島先生(椛島教授が講演)の演題はブドウ球菌由来因子(LTA?)誘発皮膚炎モデルでTLR2を介して好塩基球が遊走し、末梢神経の伸長にも関わるとの内容でSteinhoffの話と同様自然型の皮膚炎でアトピー性皮膚炎より痒疹のモデルに近い印象を持った(P59 Nakashima C et al. Peripheral nerves promote basophil infiltration via TLR2 in murine atopic-dermatitis-like inflammation.) 痒疹ではアーテミンの蓄積や末梢神経の伸長がアトピー性皮膚炎とは異なり、発疹型や部位、経過、治療の差などが考えられた。
高知大学の中島喜美子先生の発表されたDorfman Chanarin 症候群に見られた魚鱗癬は夏増悪、冬軽快する、組織に脂肪滴が蓄積する、トリグリセリドの分解が寒冷刺激で亢進する、メントールの外用で症状が改善するなど、私が現在興味を持っている進化論的皮膚病論を考えるうえで大きな参考になった。(P137 Nakajima K et al. Cold sensing ameliorated ichtyosis in a patient with Dorfman Chanarin syndrome likely through reversed lipolysis under thermo-regulation in keratinocytes.)
Wien 大学のGeorge Stingl 教授は私と同世代の先生で、皮膚免疫学の世界的な研究者であるが、今回は「Unmet Needs:Neglected Niches for Dermatological Research」という魅力的なタイトルの講演をされた。潜伏性の結核菌がHematopoietic stem cellに眠っており、免疫機構の低下で結核が顕在化することをきれいなマウスとヒトの実験で証明されていた(PLoS one 2017.12(1):e16911)。彼はNiche的な要素の強い疾患、テーマにも言及していたのが印象的であった。
今回はPlenaryは10演題と少なく、記憶に残る話はなかった。
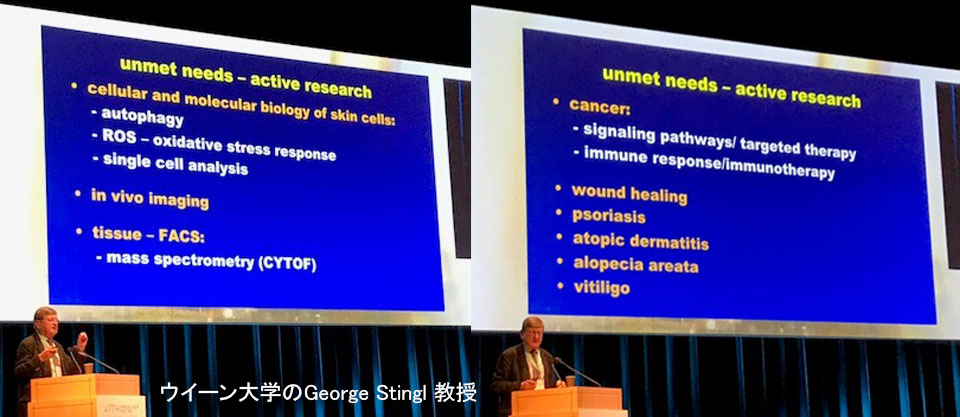

ホーエンザルツブルク城にて
大阪大学皮膚科教授 片山一朗
平成29年10月4日
第81回日本皮膚科学会東部支部学術大会
第81回日本皮膚科学会東部支部学術大会
会長:山本 俊幸(福島県立医科大学医学部皮膚科学講座 教授)
会場:ビッグパレットふくしま
会期:2017年9月23日(土)・24日(日)
大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学皮膚科学
教授 片山一朗

山本俊幸先生が会頭を務められた第81回日本皮膚科学会東部支部学術大会に出席した。今回大学のある福島ではなく、敢えて郡山にされた思い入れもあったのかと思うが、800人を超える東部支部総会としては画期的な多くの参加者があったそうである(初日の数)。昨年は東部支部と東京支部の合同開催だったが、山本先生ご自身、プロクラムの会長挨拶で以下のような決意を述べられていた。「…しかしその後、2011年に東日本大震災が起こり、当県も甚大な被害を受けました。それがあったので、これはどうしても福島県でやらなければ、と思うに至りました。震災の爪痕はまだなお過去のものではなく、5年以上たった今でも、放射線の影響を懸念して教室を去る人もいました。それはそれである意味仕方ないことで、残念としか言いようがありません」。またテーマも「自分で掴み取る皮膚科学」とされ、その理由として、「人より臨床ができるようになりたければ、人より数多くの患者さんを診る必要がありますし、人より病理ができるようになるには、人よりたくさんの標本をみなければなりません。手術にしてもそうです。自分で考え、自分で調べ、自ら実践して、時には失敗しながら少しずつ成長していくしかありません。勉強の場は提供しますので、ぜひこの学会にご参加頂き、自分で何かを学び取って帰って頂きたいと思います。」と書かれている。
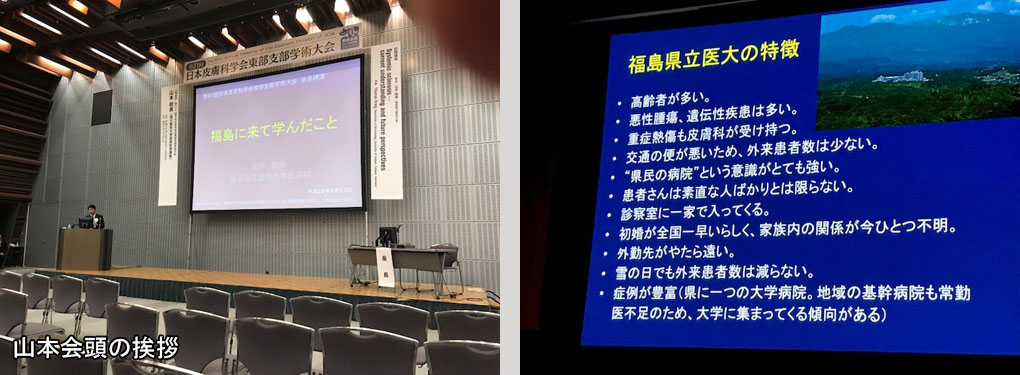
私自身は1990年から6年間、東京医科歯科大学で山本先生と一緒に皮膚科学を勉強する機会があったが、彼の一見「….男」の風貌とは異なり、病棟業務、手術の合間に多くの症例報告をされ、疲れを知らないパワーでどんどん英語論文を書かれていた。今回の会長挨拶でも、2007年に着任されてからの10年で300編以上の英語論文を発表されたそうで、震災の被害の中、本当に頭の下がる思いである。また研究に関しても、二人で良く新しいテーマを考えることが多かったが、こちらが一言、いうとすぐに行けそうな研究かやめた方が良い研究かの判断を示して頂いたことも多かった。その中で、今や世界中で強皮症の動物モデルとして広く用いられている、ブレオマイシンモデルの研究も、彼が外の病院に派遣されている時にコツコツと研究を継続された成果である。今でもハッキリ記憶に残っているが、夕方派遣病院先から戻って来た彼から、マウスの標本を見てほしいと言われた。低倍率の顕微鏡の視野にはヒトの強皮症と同様の真皮皮膚の硬化像、血管壁の肥厚と管腔の狭窄、炎症細胞の浸潤が見られ、今まで誰も成功していなかった強皮症のマウスモデルが出来たと確信し、彼と握手した思い出がある。まさに「自分で掴み取られた研究」であり、その後の世界の強皮症研究に大きな貢献をされたのは皆の知るところかと思う。 学会プログラムも最近では先ずお目にかかれないような、本当の皮膚科専門医が聞きたくなるような魅力的な5つのシンポジウムを組まれていた。私はその中で、シンポジウム 2【原著に触れる旅】「原著に触れる旅:イギリス編」シンポジウム 3【自分で掴み取る臨床皮膚科学】「他人のエビデンスより自分の経験を:臨床もサイエンス」の二つの講演をする機会を頂いた。いづれのシンポジウムも多くの先生で会場が溢れ、私自身、大変勉強になった。シンポジウム4の【皮膚病をもっと好きになるために~雑誌「皮膚病診療」とのコラボ企画~】では山本会頭が編集委員を務められる雑誌「皮膚病診療」の創刊からの歴史、過去の特集、編集方針、現状と将来に関して、過去、現在の編集委員およびアドバイザーからの提言があった。

皮膚病診療の創刊号と初代編集長の安田利顕先生を紹介される西岡清先生
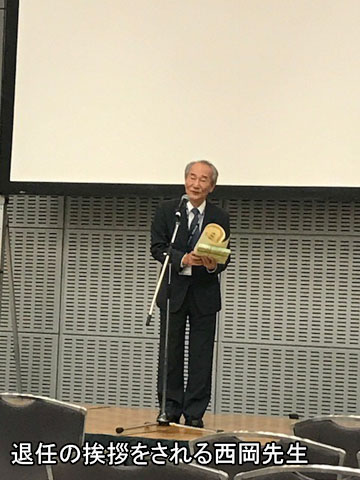
皮膚病診療の活動
●「皮膚科診療」ではなく「皮膚病診療」
●特集を組んだ臨床例の紹介
●学会報告例からのピックアップ
●良質の臨床写真による症例の紹介
●トピックス、展望による最近の知識を紹介
●治療法の特集、アンケート
●対談、鼎談、座談会
●学会ハイライト
●各臨床皮膚科医会、勉強会の訪問
●日本皮膚科学会総会時に「皮膚病診療懇親会」の開催
●Photoコンテスト表彰
●優秀論文賞表彰
●暑気払い、忘年会
他の講演では新潟大学の伊藤明子先生の「掌蹠膿疱症の治療戦略~金属アレルギーの話題を中心に~」が私の講演内容予想と逆で、掌蹠膿疱症では金属アレルギーより歯周病などの口腔内細菌の関与が大きいのではとの結論であり、これはかつて研究班で検討した粘膜苔癬と同様の結論であった。またシンポジウム5の塩原哲夫先生、村田洋三先生のそれぞれの講演(添付プログラム)はお二人の40年以上の皮膚科医としての臨床的な観察からの成果を纏められたもので、その続報を早く聞きたいと思ったのは私だけでは無いと考える。会場に若い先生が少ないように見えたが、参加された先生は改めて皮膚科学の面白さと難しさを感じ取られたのではないかと思う。
SY5-1
ケブネル現象―私はこう考える
塩原 哲夫、水川 良子(杏林大)
SY5-2
皮膚腫瘍の自然消退:良性なほもて消退す。いはんや悪性をや
村田 洋三(神戸市立医療センター中央市民病院)
大阪大学からは島田先生、田中先生、林先生が発表された。特に林先生は「ツベルクリン反応施行後急性増悪した、IL36RN 遺伝子のヘテロ変異を認めた膿疱性乾癬の1例」で会長賞を受賞され、懇親会で表彰された。

大阪大学皮膚科教授 片山一朗
平成29年9月26日
2016年 年報序文
2016年 年報序文
大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学皮膚科学
教授 片山一朗
2004年3月1日付けにて、大阪大学皮膚科学教室に着任し、来年には退官を迎えます。前任の長崎時代から毎年、年報を出していましたが、大阪に着任後も年報を出すことで、教室の目指す方向性の確認や軌道修正を行なうことができ、また若い先生の教室でのraison d’êtreの確認作業に少しは役に立ったかと思います。また2012年からは阪大皮膚科HPに教授コラムの寄稿を始めました。折々の皮膚科学を取り巻く話題への私の考えや、若い先生方へのメッセージを中心に不定期に寄稿していますが、全国の先生方や患者さん、看護師、MRさん、そして医局の先生のご家族からもコメントを頂いており、診療や教育の参考にしています。その他、HPでは教室員の学会見聞録や留学便りも楽しんで頂いているようです。来年からの年報やHPは次の時代を担って頂く方のMissionになるかと思います。教室の記録を残し、次の世代に伝えていくことは教室責任者の重要な仕事と考えます。
さて、2004年の新研修医制度の導入と大学院改革よる基礎医学講座のscrap後のbuildの成果がまだ見えてこないのが現状かと考えています。 トランプの登場で世界は二極化と孤立化が進んでいますが、少なくとも、我々の世界では新しい世代が育ちつつある事を日々実感しています。いつの時代でも、またどの世界でも輝いた眼を持つ若者は居り、次の時代を創りだしてくれると思います。私も批判精神に基づいた良き伝統の継承が第一と考え、40年近く、若い先生方と臨床、研究を楽しんできました。臨床医学も基礎医学もそうてすが、教室の歴史は、長い先人の築き上げて来られた伝統を批判的に吟味し、scrap buildを重ねて、人材を育て、研究を行ない、記録に残して行くことで初めて、次の時代に引きつがれて行くと確信しています。今、長い歴史を持つ皮膚科学という学問体系の将来がどうなるかの大きなターニングポイントの時期を迎えています。次の時代を切り拓いてくれる熱い、若い先生方の登場と活躍を期待しています。
最後に、今年三月に訪れた会津若松駅で眼にした言葉を書き留めておきたいと思います。会津を大阪大学皮膚科におきかえるとそのまま私の考えになります。
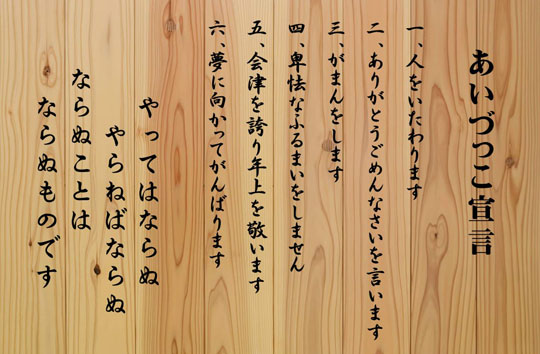
1.人をいたわります
2.ありがとう ごめんなさいを言います
3.がまんをします
4.卑怯なふるまいをしません
5.会津を誇り 年上を敬います
6.夢に向かってがんばります
やってはならぬ
やらねばならぬ
ならぬことは
ならぬものです
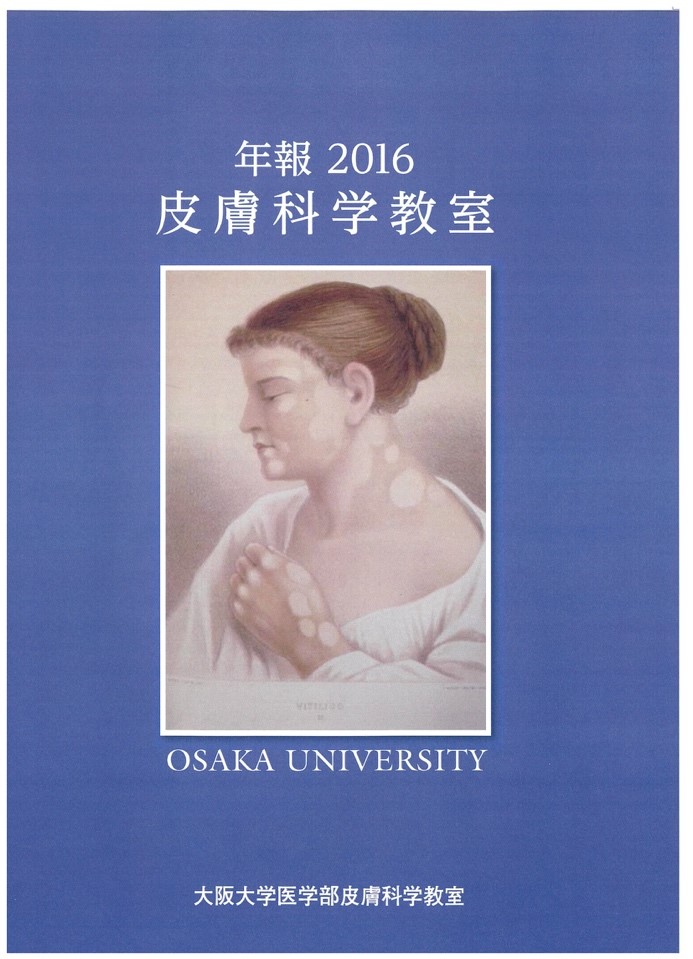
白斑の貴婦人
この図譜は、一昨年、英国オックスフォード大学名誉教授のライアン先生を訪問した折りに、偶然彼の蔵書の中から見つけた25才の白斑患者のアトラス像である。手首から発症し、次第に前腕、顔面に拡大したと記載してある。最初にこの図譜を見た時に感じたのはロドデノール白斑との類似性で、実際、Duhringはこの患者の特徴として白斑辺縁の正常皮膚の色素増強を強調している。この理由は現在、私も検討しており興味深いデータを得つつある。また白斑患者では露光部に長年病変があるにも関わらず、有棘細胞ガンなどの皮膚ガンの発生をほとんど見ないことや光老化の変化が乏しく、若々しい皮膚を維持している方が多いことが挙げられる。白斑はありふれた疾患ではあるが140年前から基本的な治療法もあまり進化していない。しかしその病因論は近年急速に進歩しており、わたしも継続して白斑の病態解明と新規治療の開発に取り組んで行きたいと、定年を前にして考えている。
「Vitiligo 」 Atlas of Skin Diseases、1876年、米国Lippincott社刊
(Aouis A Duhring, ペンシルバニア大学教授監修)
大阪大学皮膚科教授 片山一朗
平成29年9月25日
15th International Symposium of the Cutaneous Biology Research Institute
15th International Symposium of the Cutaneous Biology Research Institute
Yonsei University, Seoul
President: Kee Yang Chung, Professor and Chairman of Yonsei University
大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学皮膚科学
教授 片山一朗


そのほかはシカゴの小児科医のPallerが小児アトピー性皮膚炎の総論を話したが、アメリカでは小児科医がアトピーを見ている現状が良く理解できた。その中でAhRのリガンド外用薬がアトピーの治療に向け開発中(G社)との話があった。それ以外では臨床のレビューや留学時の仕事の話が中心であまり目新しい話はなかった。
このシンポジウムではデンバーで一緒だったSang Ho Oh先生に面倒見て頂いたが、彼もバンクーバー経由で前日に帰ソウルのことで、出国時ながいQueがあり、100人位に先に行かせてくれと頼み、ぎりぎり間に合ったそうである。我々もロスに入国時、今回初めての入国者は機械で登録ができず長い列に並ぶ必要があり、高藤先生も1時間半かかったそうである。昨年モンタナシンポジウムに行った時にはなく、トランプのおかげ?と話し、した。彼は今年までペンシルバニア大学に留学していた若手の先生で白斑の他に幹細胞が専門であり、白斑治療に応用できる再生医療を目指しているそうである。デンバーで一緒だったCatholic University のBae先生も若手の先生だが、彼は臨床面から白斑患者のビッグデータをつくりたいとのことで、お二人とも若いが目的意識がはっきりしており、本当に生き生きとした澄んだ目で、Positiveな生き方が全身から発散しており、日本では絶滅しつつある方々で、延世大学、ソウル大学をはじめ本当に羨ましい限りである。女性医師が多くを占めつつある日本に比し、韓国では6割以上が男ということで之も良い意味での競争が良い医師を育てることになるかと思う。延世大学では教授が8人おられ、その中から今のChung 教授が主任教授になられたとのことで、これはソウル大学もそうであるが任期が4年と短いためのようである。この競争原理から優れたリーダーが誕生するし、長い任期で疲れだけが残る今の日本のシステムに導入したいシステムでもあるが、長期の研究戦略からは不満が残るようである。ただ多くの指導層がいることで 若い研修医も良い指導が受けられるし、前日の歓迎会でも若いスタッフから名誉教授までが集い、海外の方とも積極的に接しておられた。今の日本の中堅から上の人材不足と全く逆である。日皮や研皮が進めている如月塾や青葉塾の参加者が早く成長してくれることを心から期待する。
最後になるが、今回、韓国白斑学会の理事長のTae-Heung Kim先生とも話する機会があり、来年大阪で開催する第2回東アジア白斑学会(EAVA)にもたくさんの参加を約束していただいた。デンバーでも山形大学の鈴木先生方等発起人の先生方と日本白斑学会の設立が確認され、来年のEAVAで合同開催することが決まった。この点は 先生とも合意した。


大阪大学皮膚科教授 片山一朗
平成29年9月7日
IPCC(International Pigment Cell Conference)2017
IPCC(International Pigment Cell Conference)2017
アメリカコロラド州デンバー
平成29年8月26日-30日
大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学皮膚科学
教授 片山一朗
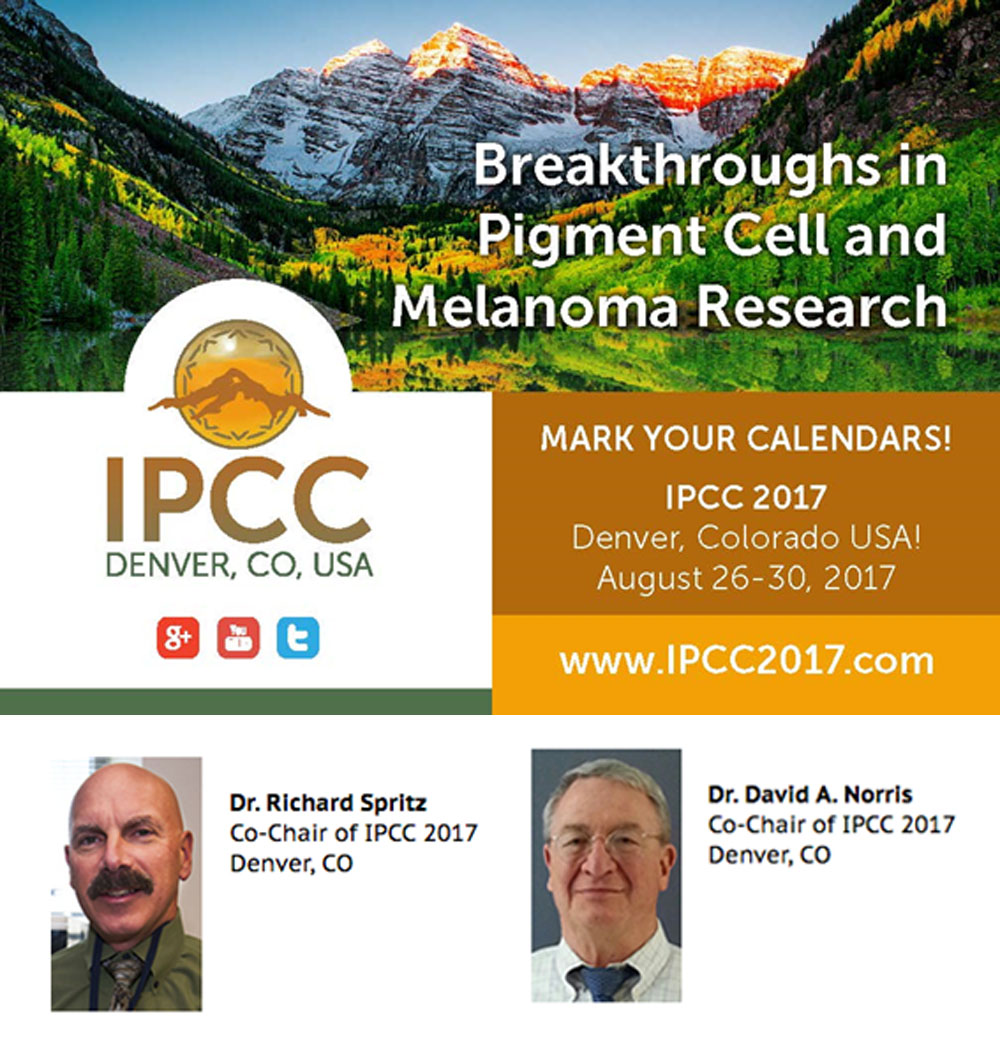
デンバーで開催された第15回のIPCCに参加した。前回のシンガポール、前々回のボルドーに引き続き、3回目の参加になる。大阪大学からは私以外に種村、壽、高藤 の3名が参加した。デンバーにはロサンゼルスからの乗り継ぎで20時間近くかかり、入国手続きも含め、かなり消耗したが、到着ホテルロビーで近大の大磯先生と会い、先に着いていた壽先生とともに近くのオープンエアのレストランに繰り出し、デンバービールとバッファローバーガーを堪能した。翌日はボルドーから続いているVitiligoの治療効果判定基準策定の委員会が開催され、参加した。今回はあまり新しい話はなかったが、韓国のBae先生を中心に韓国、中国、台湾、日本で検討している新しい白斑治療効果判定法【VESTA】の中間検討結果が紹介され、活発に議論された。日常診療での煩雑さを避け、一か所の部位の判定であり、全身の病変の評価をどうするかが今後の課題かと考える。逆にTaiebからは全身写真をとり、コンピュータで画像解析する方法が紹介されたが、外陰部の病変の評価などで議論があった。
翌々日からの学会はSpritz会頭の挨拶で始まり、学長、Norrisの挨拶と続き、患者団体の代表の方から挨拶があった。色素細胞研究のレベルは高く、動物の皮膚模様がどう作られていくかなど興味深い講演が相次いだ。岐阜大の國定教授(前日本色素細胞学会理事長)と話したおり、メラノサイトがバルジ領域からどのような分子により表皮基底層に移動し、一定の間隔で分布するかお尋ねしたところ、ゼブラフィッシュの実験で、メラノサイトが隣どうしのDendriteが接触すると、そこで遊走が止まり定着する発表があったと教えていただいた。ただ何が表皮基底層に遊走させるかや、基底層に定着する機序は不明のことであった。教室の楊先生がやっているケラチノサイトとメラノサイトとの共培養実験で、少し面白い結果がでるかもしれない。また、MicroRNA-211 Regulates Oxidative Phosphorylation and Energy Metabolism in Human Vitiligoという興味深い演題がボルドー大学のTaieb教授のラボから出されていた。miR—211の発現が白斑病変部、ヒト白斑モデルメラノサイトで低下していること、その標的遺伝子PGC1-α、RRM2, TAOK1が増幅されていることが明らかにされた。これらの細胞では酸素消費の低下と活性酸素の上昇が見られ、その理由としてミトコンドリアの機能の低下によることが示唆された。我々も同様の機序からメラノサイトの酸化ストレスの抑制に、ある生薬成分の検討を行っており、参考になった。ただmiR-211がヒト白斑モデル細胞や、白斑病変部で低下する理由やミトコンドリアの機能障害機序は不明のようである。
私自身は、白斑で肥満細胞が基底層直下で増加し、時に表皮内に浸潤していること、また辺縁部で脱顆粒が著しく、白斑部周辺での色素増強にヒスタミンが関与している可能性やトリプターゼが基底膜を傷害することで、メラノサイトのアポトーシスやFloatingに関与する可能性を報告した。





大阪大学皮膚科教授 片山一朗
平成29年9月7日
第4回汗と皮膚疾患の研究会
第4回汗と皮膚疾患の研究会(東京)
当番世話人:秀道広 広島大皮膚科教授
平成29年8月19日(土)
大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学皮膚科学
教授 片山一
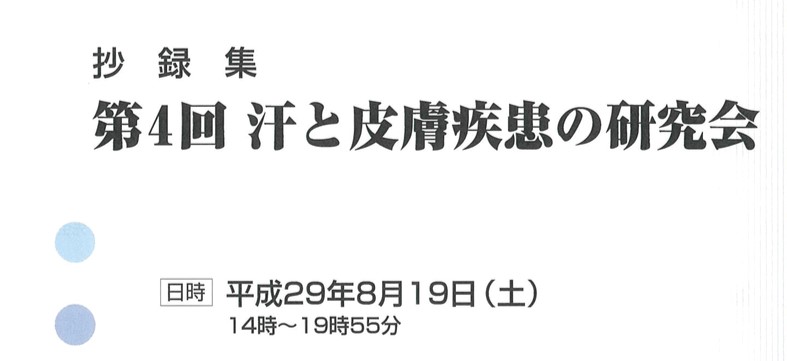
8月は昨年私が会長を務めた第25回日本発汗学会と第4回汗と皮膚疾患の研究会」が開催され、出席した。前者は神経内科、生理学の先生方がほとんどであり、皮膚科からは今年理事長に就任された東京医科歯科大学、横関博雄教授とその教室員の先生方、阪大からは私と室田先生、そして特別講演をされた浜松医大の戸倉先生くらいしか出席がなかった。来年からは横関理事長の下、臨床サイドからも出題を増やしてほしい。室田先生が報告された「血汗症の1例」は基礎の先生方も臨床の話題として興味深くとらえてくださり、議論も盛り上がり勉強になった。汗と皮膚疾患の研究会は4回目となり、若い先生方の参加が増え、活発な討論が久しぶりに楽しめた学会であった。
汗と皮膚疾患の研究会で特別講演の演者を務められた関口先生は大阪大学の蛋白質研究所の教授を長く務められ、現在はご自身が立ち上げられた寄附講座の教授として活躍されている。Stem cell nitche と BMZ〜ラミニン、幹細胞の維持機構の講演をされた(詳細はプログラム抄録参照)。前半部分では組織幹細胞の維持にはBMZを構成する蛋白、特にラミニンが重要であることを先ず紹介され、山中先生のiPS細胞の作成にもFeederとして利用されたことを話された。後半ではLabel retaining cell (分裂時間の長い幹細胞)が汗腺に多いことから、汗腺の筋上皮細胞に汗腺の幹細胞が存在することを明らかにされた。この研究では教室の室田先生が人汗腺を実体顕微鏡下で取り出すことで協力されたそうである。関口先生の作成されたラミニン関連の抗体はHPに掲載されており、必要ならアクセス可能とのことである。
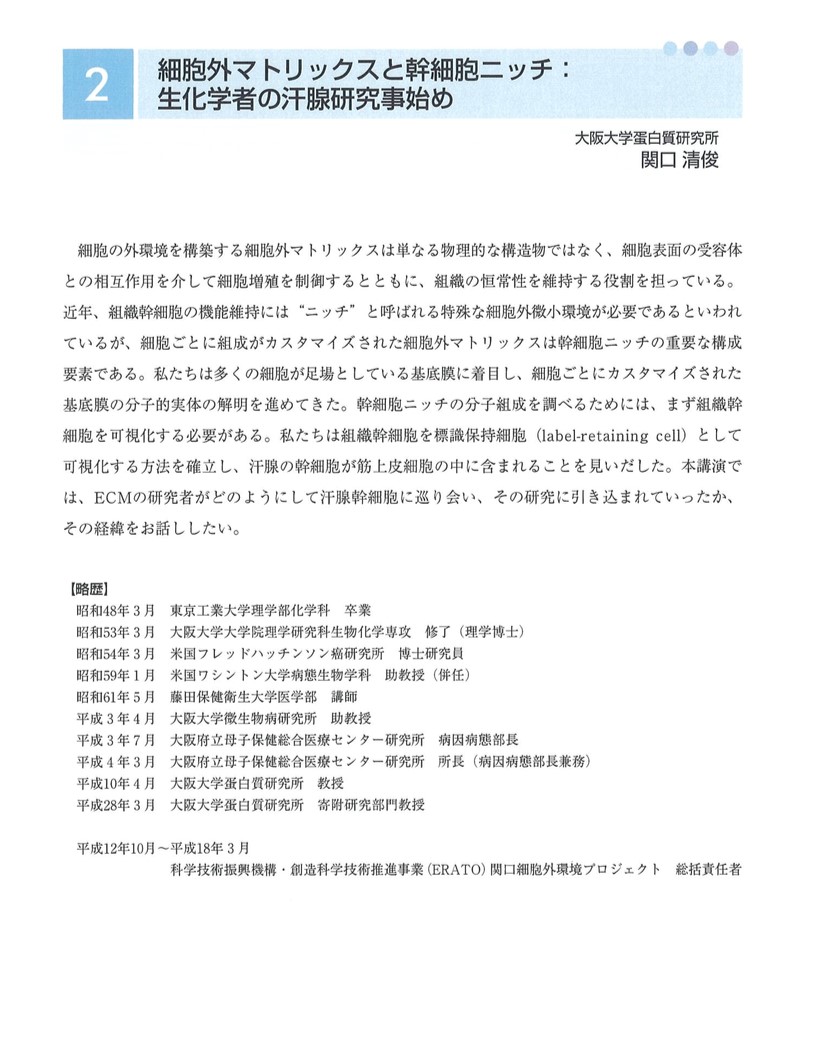
広島大学の秀先生は自己汗による蕁麻疹における汗抗原として癜風菌MMalassezia globosaが産生するMGL_1304が責任抗原として同定され、コリン性蕁麻疹、アトピー性皮膚炎患者のみでなく機械性蕁麻疹患者でも抗原になるとの興味深い結果を紹介された。フロアから「汗アレルギーとするのか癜風アレルギーとするのか」とコメントがあり、またコンタミネーションの可能性などの議論があった。汗の特定の分子量を中心とする精製汗抗原にMGL_1304が存在するのは確実かと思われるが、それ以外には細菌やダニ抗原、環境抗原の存在しないことを証明しないと癜風抗原の特異性が無くなるし、また証明出来れば汗の特異性はなくなるかとも思われる。吸収実験や阻害実験は十分されているので、個人的にはなぜ強固な細胞膜を持つ癜風菌抗原のみが汗抗原としてヒスタミン遊離を起こすかとアウトグロー患者での抗体値の変動が残された興味ある点でその解明が待たれる。
以下一般演題で議論のあった演題を纏めた。
AIGA (Acquired idiopathic generalaized anhidrosis)の治療と問題点
AIGA (Acquired idiopathic generalaized anhidrosis) は難病に指定され、治療GLの策定も横関先生のご尽力で公表されているが、ステロイドパルスをどのような症例に使用し、いつやめるかはガイドラインに明記されていない。今回発表のあったAIGAは29回ステロイドパルスを施行したが無効で、患者の希望で汗が出るまでやるとのコメントが演者からあった。ステロイドパルス療法は本来急速に進行する炎症を抑える目的で使用するが、膠原病などで使用する場合が多かったが、三回以上行なうと重篤な真菌感染症などで予後不良だった症例を何例か経験している。演者は骨粗鬆症予防や大腿骨頭壊死などの問題を考えていないようなコメントで少し唖然としたが流石に塩原先生が注意されたが、演者は施行して当然との印象であった。。塩原先生は、このような研究会で注意しないと共同正犯としてこのような危険な治療法を、容認することになると、発言された。同じことはアトピー性皮膚炎などでもあり、教訓としたい。今の研修医は20世紀末のステロイド騒動も知らなくなったと九大のF教授から聞いたことがあるが、正しい知識を継承出来ない時代が来たのかと、再認識した。逆にパルス療法が無効な症例に柴苓湯が効果を示した例が報告されたが、いくつかの漢方の有効例が報告されているとのことでその共通成分は生姜,桂皮、甘草とのことで、効果の発揮機序の検討が待たれる。我々も乾姜成分が様々な生物活性を示すことを確認しつつあるが、今後科学的な根拠に基づいた生薬の臨床研究が進展していくことを願う次第である。
AIGA患者で、ステロイドパルスにて発汗機能は改善したがチクチク感は改善しない興味深い例の報告があったが、過去の報告例でも舌疼痛症など痛覚異常の方が多く見られるとのことであった、多汗症でもepilepsyなどで活性化される大脳の部位が特定されつつあるが、発汗異常症は末梢と中枢の両者からのアプローチが必要であることを改めて認識した。
Ectodermal dysplasiaと乾皮症・アトピー性皮膚炎
Ectodermal dysplasiaは先天的に汗腺などの付属器の低形成を示すEctodysplasin A 遺伝子EDA, あるいはその受容体EDAR, EDARR遺伝子異常よる疾患で乏毛症・乏歯症・乏汗症を3徴候とする遺伝性疾患で、
ほとんどが伴性劣性遺伝形式を示す。乾燥皮膚と時にアトピー性皮膚炎様の湿疹病変を呈する疾患である。今回東京医科歯科大学から14例の報告があった。花粉症の合併が10例、湿疹が8例、うつ熱は全例で見られた。我々の報告した症例でも見られたが (Koguchi0-Yosioka h et al. Acta Derm Venereol. 2015 ;95: 476-9.)、顔面、特に下眼瞼の湿疹病変が多いようで、眼の乾燥や花粉症の影響があるようとのコメントがあった。またある程度角層皮膚の水分が維持されるのは痕跡(?)汗腺の可能性があるかとの質問があった。Ectodysplasin Aの補充療法の治験は出生後は無効で、胎児期に治療を行う必要があり、現在アメリカでのみ胎児を対象とした治験が進められているそうであるが、日本では難しいかもしれない。
痒疹に対するヘパリン類似物質外用の効果
角層内水分量が減少し、発汗低下を示す痒疹患者でステロイド外用療法に抵抗性を示す患者にヘパリン類似物質の外用が効果を示すという報告があった。特にクリーム基剤をたっぷり外用することがポイントということは杏林大学の塩原先生が、多くの講演で紹介されている。このような難治の痒疹や紅皮症患者の多くは強力なステロイド外用、時に内服を長期に受けておられる方が多いことを報告している(Katayama I,et al. Br J Dermatol. 1996 ;135:237-40.Nakano-tahara M et al. Dermatilogy. 2015;230:62-9)。よく知られているように、ステロイドは長期外用により毛包炎や細菌、真菌感染症のリスクを上げるし、皮膚萎縮やバリア障害も生じる。フロアからもピティロスポルム毛包炎や汗腺炎の混在を指摘するコメントがあったが、生検や細菌培養がなされておらず、議論は深まらなかった。私もコントロールとして密封による保湿効果やステロイド中止そのものの効果も検討すべきとコメントした。また今後、クリーム製剤から匂いの原因となっていたチモールが除去されるととのことで、より検討が進むと考える。
関連演題として、高齢者の紅皮症患者で発汗低下、掌蹠の著明な角化と真皮深層の汗の貯留の見られた例が報告された。アトピー性皮膚炎でも、全身の湿疹病変のある患者で発汗低下や掌蹠の異汗性湿疹、角化の見られるが、深層で汗がリークする理由と皮膚症状との関連性、デッキチェアサインとして健常部が残る理由を質問した。アトピー性皮膚炎でも発汗低下例で肘窩、膝窩の湿疹病変が少ないことを報告したが、デッキチェアサインも同様に保湿が保たれるためと考えている。
Takahashi A et al. Decreased sudomotor function is involved in the formation of atopic eczema in the cubital fossa. Allergol Int. 2013 ;62(4):473-8.
ヘパリン類似物質の抗炎症作用、バリア障害改善作用効果をin vitro、in vivoで検討した研究が報告された。ヘパリン類似物質を外用後テープストリッピングで角層を回収し、解析した結果では、角層内のIL1αが減少していたとのことであった。ヒトケラチノサイトがIL1αを分泌するか質問した。昔やっていた研究ではL1αはヒトケラチノサイトからmRNAは検出できるが蛋白は細胞を壊さないと検出できなかった(Horiuchi Y, Bae SJ, Katayama I. FK506 (tacrolimus) inhibition of intracellular production and enhancement of interleukin 1alpha through glucocorticoid application to chemically treated human keratinocytes. Skin Pharmacol Physiol. 2005 Sep-;18::241-6.)。また培養系でヘパリン類似物質が溶液中で作用するか? IL1αはバリア維持にも効果があり他のサイトカインの動きも検証するべきとのコメントがあった。
タイトジャンクション (TJ) 構成蛋白と皮膚の炎症性疾患
阪大からは山鹿先生が汗管でのタイトジャンクション構成蛋白であるClaudin3 k/oマウスで汗の漏出が起こることをビオチンを用いたEx vivoの綺麗な実験系で証明された。実際に生体マウスでの結果がどうなるのかが提示されず、抜去した汗管、汗腺での実験結果であり、周辺組織との関連性や組織浸透圧、抜去での刺激の影響も考慮する必要があるかとも考える。また全身の主要な外分泌腺組織では液成分の漏出は生体への深刻な影響も考えられ、TJ蛋白の異常が生じたときの代償機構の検討が必要かと質問したが、胆管では構成TJの異常は重篤な先天性の胆管炎を生じるそうである。私は以前からシェーグレン症候群に興味があり小唾液腺でリンパ球浸潤が浸潤する例を見ることも多い。この現象は診断基準にも記載されているが、山鹿先生のデータから推測すると唾液の漏出が先で口腔内の病原細菌が間質に拡散することが慢性唾液腺炎の病因になっているのかもしれない。また唾液の中には様々な抗菌ペプチドも存在し、シェーグレン症候群患者では其の産生低下も予測され、さらに病態が進展するのかもしれない。Th17 細胞がシェーグレン症候群患者の唾液腺や皮膚組織に多く浸潤していることは我々も報告している(Itoi S et al. Immunohistochemical Analysis of Interleukin-17 Producing T Helper Cells and Regulatory T Cells Infiltration in Annular Erythema Associated with Sjögren’s Syndrome. Ann Dermatol. 2014 ;26:203-8)。またTh17 細胞が塩化ナトリウムで誘導されるという興味深い論文がNature に掲載されており、汗の漏出もTh17細胞の誘導に関与しているのかもしれない。山鹿先生にはアトピー性皮膚炎のみでなく乾癬や他の自己免疫疾患などでも汗の漏出、抗菌ペプチドの動態、Th17/ Tregバランスの動態を検討して頂きたい。
Kleinewietfeld M et al. Sodium chloride drives autoimmune disease by the induction of pathogenic TH17 cells. Nature. 2013;496(7446):518-22.
Binger KJ , et al. Immun ometabolic Regulation of Interleukin-17-Producing T Helper Cells: Uncoupling New Targets for Autoimmunity. Front Immunol. 2017. 21;8:311.
Nanke Y, et al. Detection of IFN-γ+IL-17+ cells in salivary glands of patients with Sjögren’s syndrome and Mikulicz’s disease: Potential role of Th17•Th1 in the pathogenesis of autoimmune diseases. Nihon Rinsho Meneki Gakkai Kaishi. 2016;39(5):473-477
大阪大学皮膚科教授 片山一朗
平成29年8月24日
HOME V meeting CCI Nantes France
HOME V meeting
CCI Nantes France
2017.6.12-14
大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学皮膚科学
教授 片山一朗

過去のHOME 会議
アトピー性皮膚炎の疫学、EBM研究で世界をリードされているノッチンガム大学皮膚科ハイウェル・ウィリアムズ教授が主催するアトピー性皮膚炎の治療に対する国際的な評価基準を作成する第5回HOME会議に出席した。この会議は2010年から開催されており、私は第2回のアムステルダム会議以来2回目、室田先生は4回目のマルメ会議を含め。3回目の参加である。1589年のナントの勅令で有名なフランス西部、ロワーヌ河口に広がる中世都市ナントはフランス人が一番住みたい街とのことで、新しく発展する市郊外とナント城を中心とする旧市街がうまく共存する街で、ドゴール空港からTGVで到着したのは夜10時過ぎで、気温も32度と日本より暑かった。サマータイムが始まっており、まだ外は明るかったが、かろうじてレストランの閉店前に遅い夕食を摂った。前回のHOME IV
会議で評価項目として、皮膚症状、患者の症候、QOLの評価項目が策定されており、今回は長期の維持方法 (Long term control)をどうするかを決める会議で一グループ10人前後からなるグループ討論と全体討議を繰り返す進行で会議が進められた。多分この会の目的は2010年の開始の時期にすでに予測されていた、バイオ製剤を含む新しい薬剤の治療効果を世界的な評価基準で評価する目的で開始されたと考えるが、今回は企業研究が参加者の3割近くを占め、祇議論にも積極的に参加する姿を見て、新しい臨床研究の時代が始まった印象が強かった。日本ではCOIの問題で会の開催も難しいところではある。同様の白斑の世界的な研究会にも出席しているが、かなりの温度差は感じる。前回までに重症度の定義、バイオマーカー、Proactive療法などが討論されていたが、今回はLTCに関して10個の評価項目が事務局から提示され、その中から参加者が重要と思えるものを3つ挙げ、グループ討論で議論を深め、全体討論でコンセンサスを得る手法がとられた。ただ参加者の主義、主張が、そこに企業の論理なども入り、堂々巡りになった感も否めず、最後には患者代表や若い研究者からMeeting goes round in circlesという意見もで、結論らしい結論はでなかった。個人的には、全体の流れから、評価がある程度簡便で、患者が受診しなくても可能な評価項目を取り入れていくことが重要かと考える。
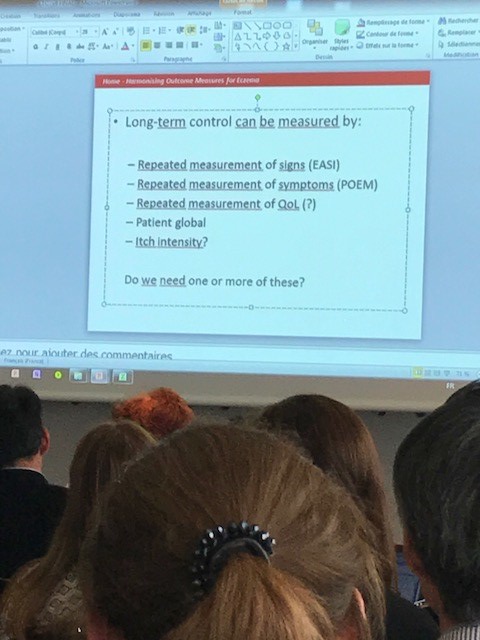
今回の結論
2015年のNottinghamでのライカシンポジウムでタール療法がAryl hydricarbon receptor を介して皮膚炎を抑えるという興味深い発表があったが、今回参加者からすでに新しいAhRリガンドが乾癬で有効な結果が出ており、アトピー性皮膚炎でも臨床治験が進んでいると聞いて、アトピー性皮膚炎の外用療法が大きく変わっていく可能性を改めて感じた。
最近、AhRのConstitutive active tgマウスがアトピー性皮膚炎様症状を呈するという報告を聞いたばかりで、この点でも驚きであった。日本からは阪大から小野、太田先生。九大の中原先生、片岡先生、大矢先生、二村先生の参加だった。
最終日はリヨンのインセルム研究所への訪問のためにあまり観光する時間がなく、念願だったベルヌ博物館は次回訪問になってしまったのが残念であった。
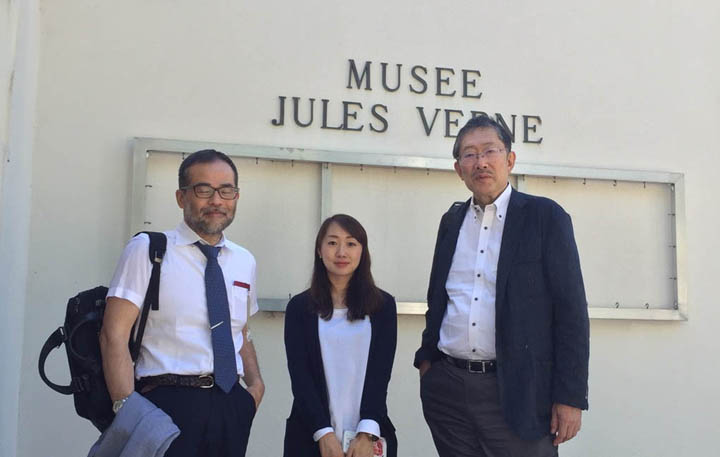
閉館で次回に持ち越しのベルヌ美術館前にて。
Inserm Meeting
ナントでのHome V会議終了後、我々はリヨンに移動し、Inserm研究所の主任部長、Jean-Franco Nicolas教授のお招きで、お互いの研究発表を行い、討論を行った。前日の夕方は21時過ぎから、Nicolas教授を囲み、教授推薦のローヌワインを地元の郷土料理とともに楽しませていただいた。彼は、岡山大学の岩月教授がリヨン大学Thivolet教授の教室に留学していた頃からの友人である。岩月教授が主催された2015年の岡山の研究皮膚科学会に来日し、帰路大阪で講演していただいて以来のお付き合いで、特に室田准教授とはオートバイが共通の趣味ということで、前回の訪問時には二人でツーリングを楽しんだそうである。その時の縁で、今年から教室の小野慧美先生が留学することが決まった。翌日は午前中みっちり研究討論を行った。小野先生は留学のテーマであるResident memory T cell の皮膚疾患での動態を綺麗な免疫染色スライドで示された。また室田先生は皮膚での活性型のコーチゾール変換酵素(11βHSD1)の動態を示され、特に彼が現在研究している痒みと本酵素の関与に関するデータを紹介された。Inserm側からはインターネット会議で小野先生の指導をしてくれているMarc先生が専門のマウス接触皮膚炎をモデルとしてFlare up現象におけるCD8b陽性のRMT細胞の動態を紹介していただいた。彼の話でハプテン特異的な末梢のRMTが存在し、感作一年後も所属リンパ節から皮膚局所に供給している可能性があるとのことであった。またPDL1による免疫抑制の実験結果など興味深いホットな話題を提供していただいた。今後、小野先生との共同研究の進展が楽しみである。
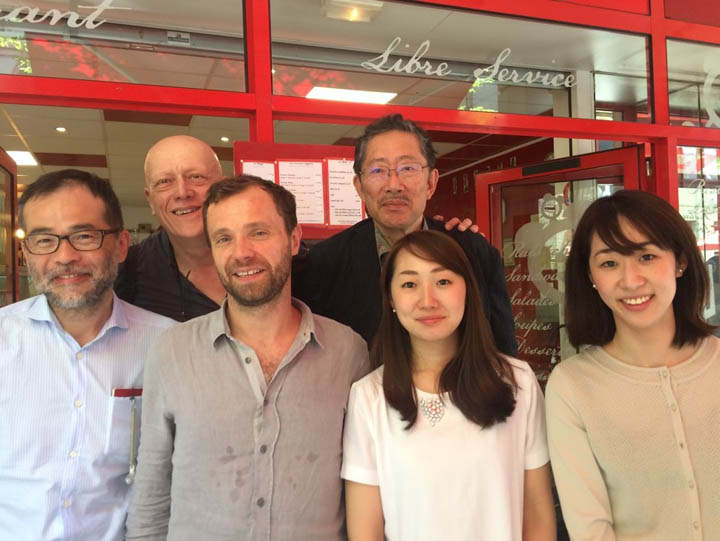
Inserm内食堂前にて。 Nicolas教授、Marc先生方と

32℃を越す夏の日差しが眩しいリヨン市
大阪大学皮膚科教授 片山一朗
平成29年6月20日
第116回日本皮膚科学会総会
第116回日本皮膚科学会総会
会場:仙台国際センター
会期:2017.6月2-4日
テーマ:Neo-dermatologyーの時代を生き抜く
大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学皮膚科学
教授 片山一朗

昨年12月の第41回日本研究皮膚科学会に引き続き、相場節也東北大学皮膚科教授を会頭として第116回日本皮膚科学会総会が仙台で開催された。今回の大会テーマは「ネオデルマトロジーの時代を生き抜く」ということで、もともとNeo-dermatologyという言葉はペンシルバニア大学のKligmann教授が20世紀から21世紀に変わる時代に提唱されたとのことを会長講演で紹介された。テーマの根幹はAI時代の到来を見据えて、次の時代の皮膚科学がどう変化し、その中で我々皮膚科医はどういう戦略を持って医学の中で自身のPresenceを発信していくかという大きな問題と、2011年の大きな自然災害から東北地方がどう復興し、東北6県が未来を見据え、どう連携していくかを2017年6月の素晴らしい回復の現状を紹介することで会員の先生への支援のお礼とされることと理解した。そのための教育講演やシンポジウムを中心にプログラムや懇親会が企画され、相場先生の意図が見事に反映された素晴らしい総会であった。

会長講演 Neo-dermatologyの時代とは
会長講演の座長は田上八朗名誉教授が務められた。先生の樹状細胞の活性化機序の素晴らしい仕事を端緒として環境と対峙する皮膚の免疫機構制御機構の解明を一貫して行ってこられた研究の成果を拝聴した。ハプテンを塗布すると、ランゲルハンス細胞が活性化し、所属リンパ節に移動するが、表皮に残るランゲルハンス細胞が大型化し、表皮下層に留まる観察所見は素晴らしい、蛍光染色所見とともに今でも鮮明に私の記憶に残っている。この後、招聘講演を務められたNIHのSteve Katz教授のラボには相場先生が東大皮膚科以外で初めて日本人留学生ということで、当時の懐かしい写真とともに相場先生の研究の一端も紹介された。Katz教授は15年前には想像できなかった5つの疾患の新しい治療の方の紹介と、次の10年に解決が予測される10の研究テーマを挙げられていたが、その5番目に痒みのメカニズムの解明を挙げられていたのが印象的であった。また相場先生は教室の病理診断を凡て一人でなされ、その数2万件以上と聞き、改めて田上先生の臨床への熱い思いが相場先生を通じて東北大学の皮膚科医局に脈々と受け継がれていることに感動したのは私だけではないと考える。一例一例の多方面からの解析結果を英文雑誌に症例報告し、新しい知見として症例集積していくことでDFSPがCD34陽性に染色されることを見出された素晴らしい研究が多くの論文で引用されているのは当然の帰結かと考える。田上先生の恩師の太藤重雄教授の研究手法も同じであり、座長席で本当に嬉しそうであった。この後は土肥記念国際交流講演ではミュンヘン大学のThomas Ruzicka教授が基底細胞癌の講演をされた。Ruzika教授の幅広い臨床の知識と経験に基づいた講演はいつ聞いても素晴らしく、ドイツ皮膚科学の歴史の奥深さを毎回感じる。
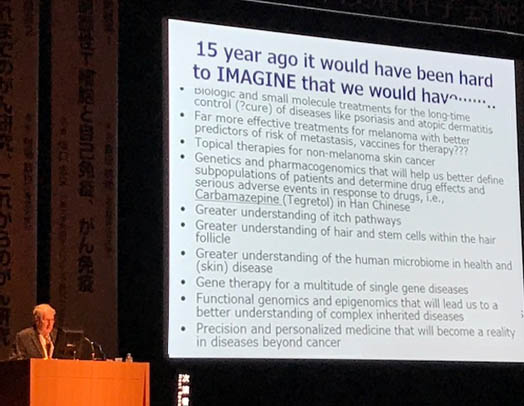
教育講演は今回58のテーマが準備され、スポンサーセミナーと合わせると会員の先生方の要求には十分すぎる内容であったかと思うが、一部でオーガナイザーの先生の専門と異なるセッションもあり、今後の検討課題としていただきたい。一般演題はすべて口頭での発表が義務付けられていたが、質疑応答がなく、残念であった。大変かとは思うが岡山大学の岩月教授が会頭を務められた113回総会で採用された、「会員に聞いていただきたい素晴らしい内容の演題」を前もって選択し、短時間でも討論を行う方法が良いかと考える。その場合も、座長の選定が最も重要であることも含め、また改善していただきたい。
特別セッションは東北復興に関する講演とNeod-ermatologyに関する講演がほぼ半分づつ企画されていた。その中で印象に残ったのは最終日の免疫に関する最新研究のセッションで、ハーバードのWinau FlorianがNatureに報告したCD1aにウルシオールが結合し、HLA非拘束性にウルシかぶれ患者のCD8細胞を活性化させるという報告は驚くような実験結果であった。また表皮由来脂質が乾癬で自己抗原として作用するという話も驚きで、座長の天谷先生が仰られたLipid immunologyの幕開けが感じられた。企業展示と懇親会はうん千万円の費用がかかったとされる特設大テントで行われ、東北6県の名物料理やお酒など、会員の先生方も十分に楽しまれたようであった。会期中は良い天気に恵まれ、杜の都仙台の名前通り、目に眩しい初夏の仙台を満喫させいただいた。事務局長の山﨑先生、実行委員長の菊池先生にもお礼を申し上げる。

理事の先生方と
大阪大学皮膚科教授 片山一朗
平成29年6月20日
「まのあたり、あるがまま目をもて視ることこそ、 いと易きに似て、げに難しからずや」(北村包彦)
「まのあたり、あるがまま目をもて視ることこそ、
いと易きに似て、げに難しからずや」(北村包彦)
大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学皮膚科学
教授 片山一朗

日本における医療制度や医学教育の大きな変換の影響は地方から顕在化し、今、大都市にも及びつつ有ります。このような中での皮膚科の将来像は私にも、明確に答えられませんが、皮膚科専門医の治療が必要な皮膚疾患はニキビや脱毛、手湿疹など生命予後には関わらないが労働生産性など経済活動の低下に大きく関わる疾患から昨今、大きな社会問題となりつつある悪性黒色腫などの皮膚癌や先天性の難治性疾患など多くの患者さんがおられます。私自身、今年の始めに以下のような考え「皮膚科のように見る、診る、視る、観る、省るなど五感、時に第六感を駆使して診断を行い、治療を考えていく分野は当分AIも及ばないと楽観視していた皮膚科医も多かったと思いますが現実は、もっと早く進むと予測するのは私一人ではないと思います。「暗黙知」で代表される皮膚病の診断もAIが人と同じ経験則を持ち、学習能力を進化させれば、今の皮膚科学が根底から覆る日も近いかと思います。」を述べましたが、もう一度私の40年近い、皮膚科医としての歴史を振り返ると、皮膚疾患の正確な診断と適切な治療の提供がいかに難しいかを再認識しています。さらに次々と新しい輸入感染症や新規薬剤アレルギーが現れる皮膚疾患の診断は容易に見えて本当に難しいかと思います。今年の新入医局員の先生への言葉として挙げた、北村包彦先生(長崎大学で教授職、その後東京大学に転任)の言葉のもとになったゲーテの言葉が有名なFitzpatrickのDermatology in General Medicineの診断学の項の最初に述べられています。臨床医学もサイエンスであり、過去に蓄積された学問を理解し、新しい成果を取り入れ、つねに自分の頭で批判的に患者の皮膚を診、最善の治療を行うこと、そして、改善しない場合、カンファレンスや学会で徹底的に論議し、批判を受け、その成果を英語の論文で記録して行く姿勢が何より大切です。最近の学生や研修医は教科書も持たずに臨床実習に来ます。その疾患に関して質問し、またレポートを見ると皆さん判で押したように同じような診断名や治療法が返ってきます。Wikipediaで得た知識は署名のない無責任なものです。専門医を目指すのであれば原著にあたり、仲間や先輩と是非熱い議論を戦わせてください。皮膚疾患は治らなければ患者自身すぐに分かり、その皮膚科医の能力が判断できます。先ずゲーテの言うように目の前にある事象をあるがままに見ることがいかに難しいかを理解することから、新しい皮膚科医としてのスタートを切って頂きたいと思います。世界はガイドラインやアルゴリズムそしてAI医療ではなく、熱い血の通った皮膚と心を持つ人による医療を待っています。

『一昨年に亡くなられた詩人の長田弘さんは,若い頃,オートバイによるヨーロッパ縦断の旅に出られ,その紀行文のなかにこんな言葉を書きとめられました。《見えてはいるが,誰も見ていないものを見えるようにするのが,詩だ》
哲学を専攻しているわたしは,ここで詩といわれているのはそのまま哲学のことだと思い,体の芯から震えました。わたしは今日まで長田弘さんの書かれる文章の「詩」のところを,いつも「哲学」に置き換え,それらの文章を哲学の研究者にも宛てられたものとして読んできました。以下略』この言葉は「詩」を「皮膚科医の眼」に置き換えて見れば、まさにその通りと思います。
“What is the most difficult of all ? It is what appears the simplest: To see with your eyes what lies in front of eyes.”
(Goethe)
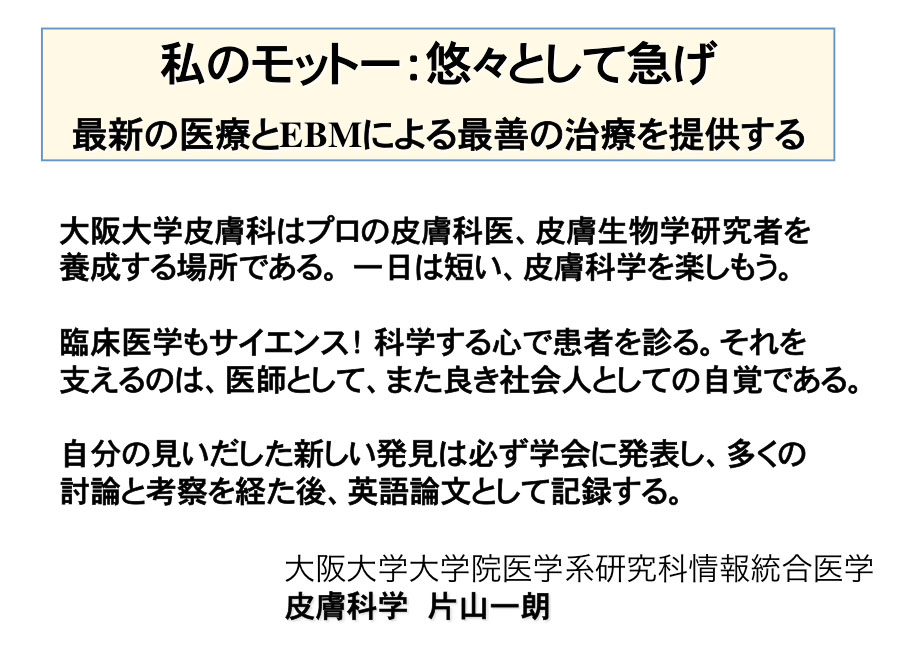
平成29年4月11日
皮膚の血管炎の考え方2017
皮膚の血管炎の考え方2017
大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学皮膚科学
教授 片山一朗
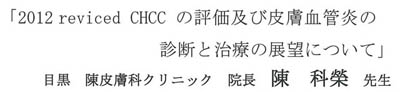
先日、3月25日に東京で開業された陳科榮先生にお越し頂き、皮膚の血管炎の考え方について上記のタイトルで講演頂いた。陳先生は私の敬愛する先生であり、多くの事を教えて頂いて来た。この数年、血管炎の分類、診断、病態、治療法などが大きく変貌しているが、この講演をお聞きし、私の中で、はっきりしなかった問題点が随分整理された。また陳先生と議論する中で私の考えている事が先生のお考えに非常に近い事でも驚いた。この機会に陳先生の講演内容と執筆された教本を整理し、記録に残しておきたい。先ず、一昨年の皮膚脈管・膠原病研究会に関するコラムでも記録しておいた2012年の改訂チャペルヒル分類についての問題点に関するお話があった。この会議では皮膚科医が一人も参加していない状況で新分類案が決められた事が大きな問題点だった。今回、日本から陳先生と川名誠司日本医大名誉教授、さらに欧米の皮膚科医、皮膚病理医が加わり、2012年のチャペルヒル分類の補遺として、いくつかの改訂点が公表されるとのお話があった。その中で重要な点として以下の1.2.の2点が述べられた。
1.チャペルヒル分類の補遺
■全身性の血管炎と異なり、皮膚の血管炎はPost capillary venuleを中心とした細静脈炎である。
■皮膚限局性血管炎の追加(下線)
IgA血管炎
クリオグロブリン血管炎
低補体蕁麻疹様血管炎(抗C1q血管炎)
ANCA血管炎
IgG/IgM免疫複合体血管炎
皮膚静脈炎・血栓性静脈炎
持久性隆起性紅斑
結節性血管 (炎Nodular vasculitis)
リべド(様)血管炎
ベーチェット病
2.免疫組織化学
IgA血管炎など、特定の医療機関でしか診断ができない点は大きな問題であり、新たな診断法の開発が必要であるという点に関しては全くその通りで、病名の再検討が必要であると考えるのも皮膚科医であれば皆さんそうである。重要な点はIgA抗体が何を認識しているかの検討であり、その解明なくして血管炎の診断をしても意味がないと考える。また皮膚の小血管炎はPost capillary venuleを中心とした細静脈炎で有り、血管壁はフィブリノイド変性を伴う壊死性血管炎であるとの指摘もその通りで、HE染色では乳頭下層から真皮中層レベルの血管炎ではフィブリンの析出や出血、好中球の浸潤、核破砕が中心と成り、血管壁はその破壊により不明瞭となる。興味ある点はなぜ皮膚の血管に限定して血管炎が生じるかで、その答えの一つとして好中球の細血管への接着とその後の炎症惹起に関わる細小動静脈の接着分子の発現の相違点の検討が挙げられると考える。この方面のエキスパートの防衛医大の佐藤貴浩教授にお聞きしたが、好中球が接着する分子は以下の通りとのことであるが、細血管側の発現パターンの詳細な検討はまだないようで、その理由としては多くの実験が内皮細胞(HUVECまたはhuman dermal endothelial cells)で行われているので細動脈と細静脈内皮細胞での違いは検討が困難とのことである。 好中球:E-セレクチン〇 P-セレクチン〇 ICAM-1〇 VCAM-1×(〇:結合する X:結合できない)。逆に皮膚を介する何らかの外的因子や循環障害により皮膚の細血管が特定の細胞接着分子を恒常的に発現している時には、一見、無関係な上気道感染症などで循環好中球側の接着分子の発現亢進がある場合、対応する血管レベルで好中球性の炎症が生じても良いかもしれない。これはアトピー性皮膚炎での非特異的なケラチノサイトの接着分子の発現と好酸球浸潤などと近い反応とも考えることも可能である。
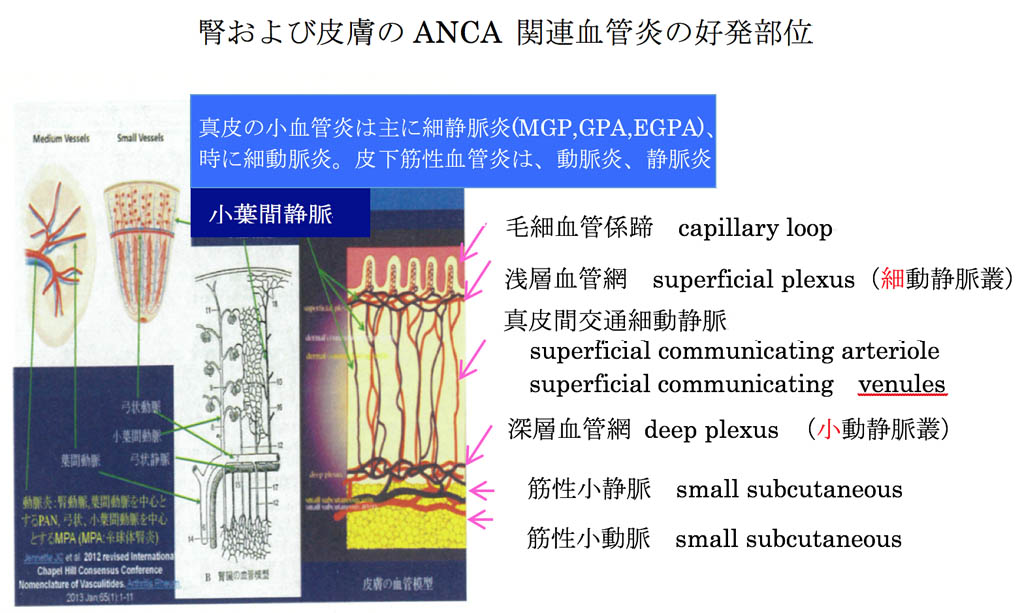
3.動脈と静脈の差は?
筋性動脈の内弾性板は均一で一層。フィブリン血栓は不整であり、内弾性板は血栓による血管の破壊を防ぐために重要で、その破綻が血管炎?血管周囲炎の原因となる。静脈の弾力線維は多層、静脈壁は厚く、血栓は同心円状で血管壁は保たれる。下腿の血栓性静脈炎はElastica van Gieson染色での弾性線維が筋型動脈の内弾性板と間違われやすく結節性多発動脈炎と誤診される例が多いとのお話であった。私もこの点は重要であり、安易な長期ステロイド投与の原因と成り、難治の原因と成ることは良く経験する。ただ炎症の強い場合、安静と2週から1月程度のステロイドの全身投与は必要であることなど、陳先生も同じ意見であった。
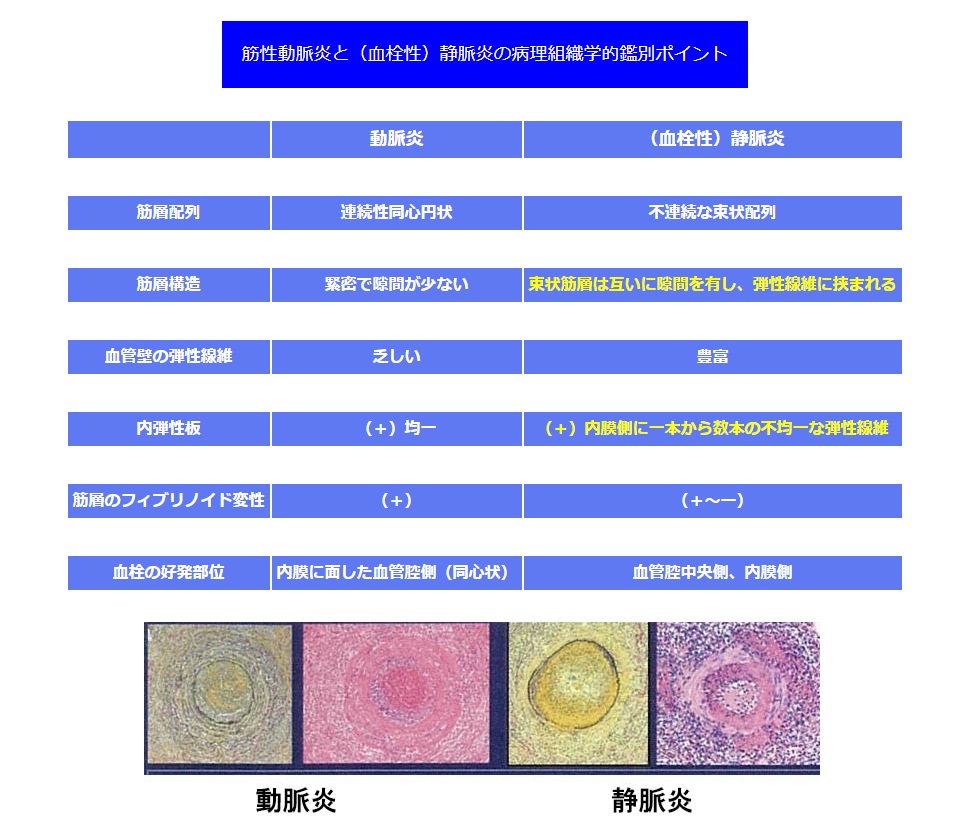
4.内臓と皮膚血管の病理組織の違いは?
結節性動脈周囲炎(PNC, CPAN)の独立性とPNへの移行、そして皮膚型と全身型PNの相違点に興味があり、コメンテーターの三浦圭子先生にもお尋ねした。陳先生も比較検討した事は無いが、当然異なるのではないかとの返事であった。今後、是非検討して頂きたい点である。
5.リベド病変への圧迫包帯、弾力靴下の使用とその考え方
リベド血管炎や皮膚型結節性動脈周囲炎でも細小血管レベルの血栓や時にフィブリノイド血栓形成と脂肪織レベルの細静脈炎がみられることから、DDSやNSAIDs、抗血小板薬などの薬物療法に加え、弾力靴下の使用が効果的であるとの解説があった。潰瘍の形成や炎症の強い時期の使用は控えるのは当然であるが、安定期の使用は私も同感である。作用機序が圧迫による血流改善やiNOSなどの誘導を指摘されていたが、内皮細胞機能の改善が大きいのではと考える。市販のものはキツすぎるとの意見もあり、改良が必要とのコメントもあった。ステロイドは血管壁の脆弱化、血液粘稠度の亢進、血小板の凝集などへ影響するとされており、一度導入すると中止が困難になることより、全身症状を欠く例では使用しない治療を心がけることが重要と私は考えている。漢方茶(ビデンスローサ)も試みる価値はあると考える。Winkelman等の提唱したSegmental hyalinized vasculitisはAtrophie blancheと同義で、今迄、どちらかというと細動脈の血管障害とフィブリン血栓が主体と考えていたが、陳先生のお話では細静脈の血栓と脂肪織レベルの静脈炎が特徴で、Livedo vasculitisもSegmental hyalinized vasculitisに近いDermal plexusレベルの静脈炎の組織反応が主体と解説されていた。ただリベドの場合、動脈側の循環障害と結果としてのHypoxiaも問題ではないかと質問したが、肯定はされたが、それ以上のコメントは無く、また議論を深めたい。最後に陳先生は今後の喫緊の課題として、血管炎を研究し、新しい治療を創出する次の世代の教育と育成が何より重要と強調された。私もその通りと考えるが、現状は中々厳しく、指導医が先陣を切って難しい血管炎の治療を行い、その面白さと重要さを若い世代に伝えて行くしかないと考える。その意味で、指導医は若い先生にドンドン演題を発表させ、活発な議論を展開し、論文として結果を記録して頂きたいし、若い先生方には陳先生と川名先生のテキストを購入し、先ず治療を開始することから血管炎を勉強して頂きたい。そこから皮膚の血管炎診療の重要さがまた、見直されていくと考える。なおこのコラムの図は陳先生の講演で使用された資料を元に作成した。
最後にチャペルヒルコンセンサス会議2012の分類を添付する(pdf)
血管炎症候群の分類|大阪大学 免疫アレルギー内科(大学院医学系研究科)
www.med.osaka-u.ac.jp/pub/imed3/lab_2/page4/vasculitis.html
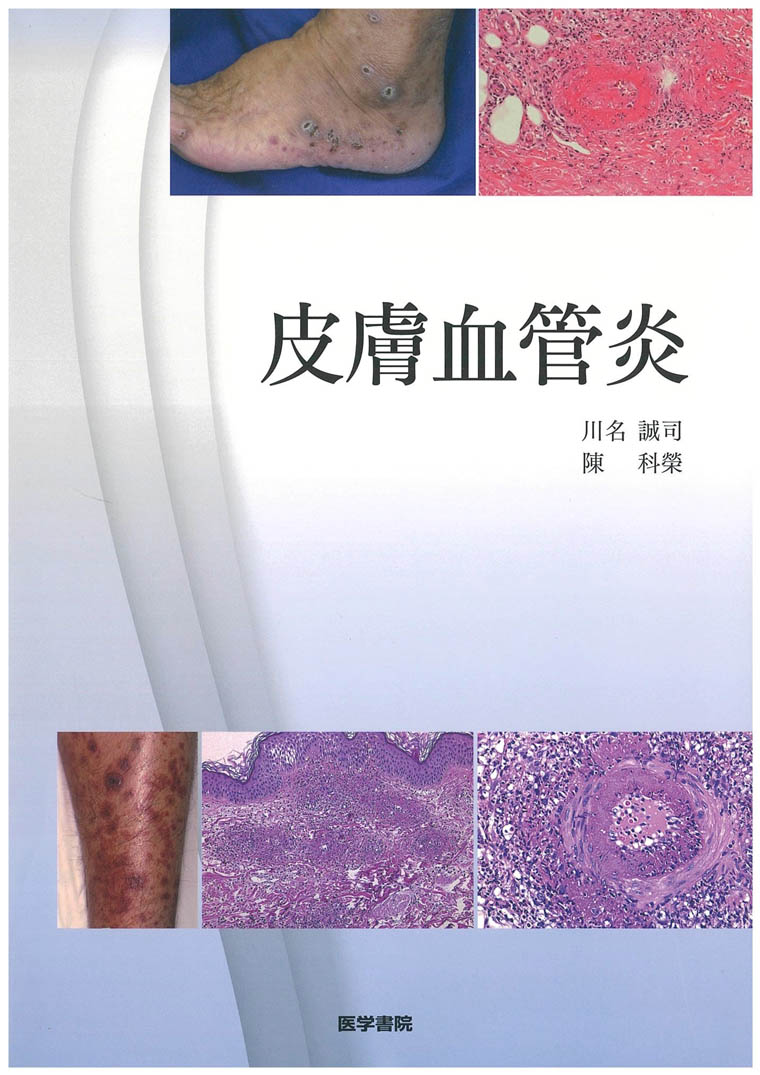
平成29年3月31日
第460回日本皮膚科学会大阪地方会 和歌山県立医科大学古川福実皮膚科教授退職記念地方会
Derma Dream 2018
第460回 日本皮膚科学会大阪地方会
和歌山県立医科大学 古川福実 皮膚科教授退職記念地方会
日時:
平成29年3月11日(土)和歌山県立医科大学講堂
平成29年3月11日(日)ホテルグランビア和歌山
大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学皮膚科学
教授 片山一朗

古川福実先生の定年退職記念地方会が開催され、出席した。初日の土曜日、午後2番目が大阪大学の林先生の発表であり、開始前には到着していたが、和歌山医大病院の敷地は広く、実際の会場に着いたのは開始5分前であった。会期の土、日2日間、水谷仁、三重大教授の退任東海地方会や静岡地方会が重なり、出席者など心配していたが、天候にも恵まれ、全国から多くの先生が出席、講演された。古川先生の長年の功績を振り返りながら、膠原病、皮膚外科、美容皮膚科、自然免疫など和歌山医大皮膚科がテーマとされる演題が発表された。私自身は、初日は今月25日に病院名の変更、新規開院する大阪国際ガンセンター、腫瘍皮膚科部長の為政大畿先生の「メラノーマに対する新規薬物療法の実際」の講演座長を務めさせて頂いた。大阪国際ガンセンターは大阪府立成人病センターからの名称変更で、今後海外からの患者の増加を見据え、ガン診療に特化して行く方針で、合わせて重粒子センターを併設し、大阪、関西地域の包括的なガン治療の拠点となる。皮膚科でも近年、重症のガン患者を診療する施設が減っており、専門医指導にも支障を来しつつある。為政先生のご指導で関西一円から腫瘍皮膚科医を目指す若い先生が集い、皮膚腫瘍診療を担う人材が育つことを期待する。3月4日に行われた開院式典でも左近病院長が、腫瘍皮膚科として西日本の皮膚腫瘍の診療拠点と紹介頂き、今回古川先生にも配慮頂いた事、この場を借りて、お礼を申し上げる。引き続き、NPO法人のオールアバウトサイエンスジャパン代表の西川伸一先生が「21世紀医学の課題」ということで講演された。西川先生は古川先生の京都大学の先輩で、我々の業界ではメラノサイトの幹細胞研究で有名な方であるが、今回は、進化医学をテーマにお話をされた。特につい最近、Nature誌に発表されたネアンデルタール人が抗生物質の素になる青カビや鎮痛作用のある薬草を歯の治療に使用していた事や、進化の過程で獲得した遺伝子変異が現代人の疾病の発症にどう影響しているか、個々の患者でexome解析することの重要性を強調された。西川先生はスライドに示すような情報提供サイトをお持ちで、興味の有る方は是非アクセスして頂きたいと述べられた。


懇親会はアバローム紀の国で開催され、大阪地方会の運営委員長として長年のご貢献にお礼を述べた。翌日も大原國明先生のモーニングセミナーから学会が開始され、午前中の一般演題が終了後、古川先生の記念講演が宮地先生を座長として、開始された。
「変貌する自己:左右(とにかく)なんとかすごしてはきた。」のタイトルは恩師の山田瑞穂浜松医大名誉教授の残された言葉とのことで、京大の病理時代、浜松医大時代、和歌山医大時代の事を多くのメモリアルフォトを使いながら述べられた。特に最近は若い先生や学生教育に力を入れてこられたとの事で、教授としていかに自分の思いを伝えるか、そして言葉として記録に残す事の重要性を恩師の濱島義博先生や古武彌四郎和歌山医大名誉教授の言葉を引用して述べられた。これらは和歌山医大皮膚科のHPで拝見できる。私も和歌山医大皮膚科同門会長の宮崎先生の座長で「膠原病の寒冷過敏」を発表した。

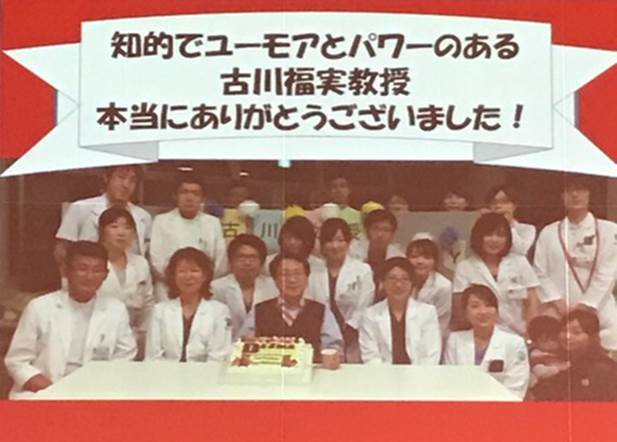
祝賀会で披露されたエピソードやたくさんの写真は古川先生が如何に多くの教室員から愛されておられたか、また先生が教室を去られる寂しさが教室員皆さんのコメントから感じられた。四月からは新しい勤務地で、祝賀会中に授かられた初孫の近くに住まれるとのことで、本当におめでとうございます。

第260回日本皮膚科学会大阪地方会プログラム
(和歌山県立医科大学 古川福実 皮膚科教授退職記念地方会) PDF
症例報告を書く
和歌山医大皮膚科教授として最後の挨拶文 PDF
平成29年3月14日
第40回皮膚脈管・膠原病研究会
第40回皮膚脈管・膠原病研究会
会長:山本俊幸(福島県立医科大学医学部皮膚科学講座 教授)
大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学皮膚科学
教授 片山一朗



(写真は坂本邦樹先生と西山茂夫先生)
1987年からは、西岡清北里大学助教授(当時、現;東京医科歯科大学名誉教授)のお考えを取り入れられ「皮膚科で膠原病を考える会」を設立され、以後2日間の同時開催として運営されるようになり、暫くは毎年六本木の国際文化会館で開催されたことは2012年、2016年のコラムにも書いた。2001年に2つの研究会が合同化し、現在の「皮膚脈管・膠原病研究会」と名称が改められた。本会は学会ではなく、研究会という自由な雰囲気の中で、毎回個々の発表演題について西山茂夫先生を中心に診断の根拠、病理組織の見方、そして解決されるべき問題点が時間の経つのを忘れて討論されたものである。西岡先生からは、最近は、あまり病態研究や治療開発の討論が無くなりつつあることや、海外の分類の紹介や検査成績の討論が中心になり、ミニ学会化しているとの指摘があった。また神崎先生からは今回、いくつかの理由から、本研究会が日本皮膚免疫・アレルギー学会(2018年1月から日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会の名称変更)に合同化すること、現在の形式での会が今回で最後になることに対する改善、再建策として、参加費が安すぎるので、現在の3倍にする、記録集は不要、演題数を減らし、討論を充実するなどの意見を頂いた。「この会が無くなれば、私はどうしたら良いのだろうか」とのコメントには、本当に申し訳ないと感じた。
今年の日本皮膚免疫・アレルギー学会(日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会から名称変更)が金蔵教授を会頭とし、(12月8日~10日、鹿児島)、合同開催とし、膠原病、血管炎のセッションを増やし、会期を3日間にするとの会の運営方針も了解を得ており、来年の奈良での浅田先生の大会でもう一度合同化の是非を考慮し、一本化する予定である。この3年位参加者が減少し、討論もほとんど無くなり、また会場や運営費の確保が先細りということで、合同化に踏み切った次第であるが、今回200名以上の参加があり、かつての会を彷彿させるような活発な討論もあり、閉会時間が大幅に遅れたが、皆さん、久し振りに満足のいく会で、大阪大学から出席した若い先生方も、大変勉強になったとのコメントを頂いた。合同化に関しては金蔵、浅田両教授の会を移行期という事で合同開催にして頂くが、血管炎や血管腫の演題発表が可能で、かつ十分討論できる専門家の出席する会がないという現実や研究会という縛りのない会で十分討論できる会をもう一度という声が上がればまた新規の会を設立する選択肢も残して置きたい。ただ今後、後期専門医制度の中でアレルギー学会やリウマチ学会の位置づけが必ずしもはっきりしないことから、皮膚アレルギー、リウマチ、自己免疫疾患を3日間で学べ、討論できる会はこの学会くらいしかないのも現実で、その兼ね合いをどう考えていくのか、悩ましい。来年、もう一度討論すべきかもしれない。
以下一般演題で気の付いた点や今後の課題を記録しておく。血管炎 のセッションでは皮膚型の結節性多発動脈炎と分枝状皮斑、結節性多発動脈炎の異同や移行が論議された。本研究会で過去、多くの論議がなされた動脈炎(静脈炎?)を炎症と取るか循環障害と取るかの問題がまた繰り返された。 私が診療してきた方で全身型のPNに移行した方は記憶がなく、多くはLivedo with noduleの方が主体で、時に潰瘍、Atrophie Blancheが見られる方が多かった。また壊疽性膿皮症に近い病変が軽快、増悪を繰り返す方も経験したが、このような方はPSL5mg位の少量ステロイド剤で維持されているがPSL減量、中止が難しく、感染症や運動負荷で悪化するが全身的な血管炎には進展しない。潰瘍が悪化時にはケブネル的な小潰瘍が多発、新生し、静脈還流の悪い方が、上気道感染症などで悪化することが多い印象を持っている。演題5の墨東病院からの症例はPSL60mgで改善せず、胆管炎の治療で速やかに改善した壊疽性膿皮症に近い病変であり、リベド、静脈血栓、プロテインSの低下を認めた症例でやはり感染症の検討が必要とあらためて感じた。またAPSにワーファリンが使用されることが多いが演題15ではリベド疾患にノアックの使用例が報告された。クロピドグレルも含め皮膚のリベドに使用する例が今後増加すると考えられるが、PNなどの部分症状としてリベドの見られる場合もあり、血管炎が生じた場合のリスクなど常に念頭に置いておく必要がある。また皮膚IgA血管炎の単独例とIgA腎症単独例のIgA免疫複合体の対応抗原や沈着血管の異同などの検討が必要と考えられる。紫斑性腎炎という診断名もあり、チャペルヒル分類だとIgA陰性の紫斑性腎炎をどうするかの問題が解決されない。また従来アナフィラクトイド紫斑(Henoch- Schoenlein purpura)と診断されてきた紫斑病の罹患血管は毛細血管レベルでPost capillary venuleを中心に炎症が生じ、罹患血管は破壊と新生を繰り返し、血管壁の炎症を病理学的に認める事は難しいとされているが、もう少し深い静脈炎が見られるとのコメントがあり、質問した。これはLE profundus (Lupus panniculitis)やLE tumidusにも共通するが、SLEに生じる血管炎は最小血管から筋型動脈まであらゆる太さの血管が障害されることが知られており、その評価が難しい。病理学的にSLEに典型的な表皮・付属器の変化や特異抗体を認めず、臓器病変が見られない場合、特にその評価は困難で、治療法も簡単に決める事ができない。演題55のLupus panniculitisに脂肪移植を施行した症例の発表は興味深く、我々の施設でも形成外科に依頼して数例施行中で、ある程度患者さんの満足度の改善に貢献している。頭部のモルフェアの遊離皮弁など形成外科的治療を施行する場合、組織および検査上の活動性の評価が重要で、鑑別疾患と合わせ、質問したが、3年間病勢が変わらない症例に施行されたとのコメントがあった。またフロアから費用などの質問があったが、脂肪移植は美容外科領域で施行される場合、高額な医療費が派生するが、あくまで自由診療の中で難治疾患の治療という観点で施行頂いている。顔面の陥凹局面を呈する疾患ではLE profundus, Lupus panniculitis以外、モルフェアやロンバーグ病などの鑑別が必要であるが、さらにEBウイルス関連リンパ腫などの慎重な除外が必要である。今回、多くの症例提示があったヒドロキシクロロキンがリンパ球や好中球性炎症が主体のSLEの皮膚症状のみに効くのか、血管の炎症に伴う病変や臓器病変にも効くのかは今後検討して行く必要がある。

プログラムをクリックするとpdfが開きます
平成29年1月24日
65th Annual Montagna Symposium on the biology of skin
65th Annual Montagna Symposium on the biology of skin
「The skin: Our sensory organ for itch, pain touch, and pleasure 」
Gleneden Beach, Oregon Coast
大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学皮膚科学
教授 片山一朗

Program chair: Gil Yosipovitch;
Professor of Miller School of Medicine, University of Miami
プログラム委員会
Diana Bautista、Ph.D.
カリフォルニア大学バークレー校細胞発達生物学科
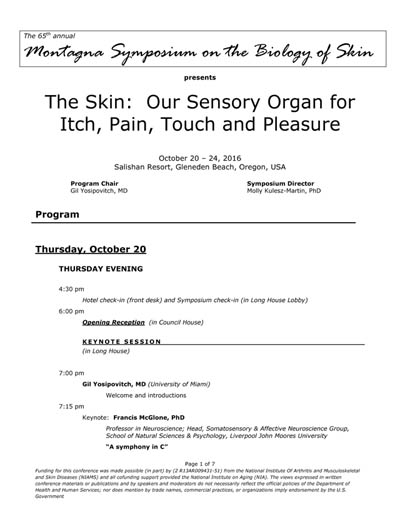
ハーバード大学医学部/マサチューセッツ総合病院皮膚科
Ellen Lumpkin、Ph.D.
コロンビア大学皮膚科・生理学・細胞生物物理学科
Francis McGlone、Ph.D.
ジョン・ムーアズ大学リバプール認知神経科学科
2016年のMontagna symposium, the biology of the skinに参加した。少し遅れたがその報告をしておきたい。テーマは大変意味深いタイトル「The skin: Our sensory organ for itch, pain touch, and pleasure 」で、ぜひ演題を出せと、プログラム委員長のGilから頼まれており、大阪大学から、片山、室田、中川、清原、高田の5名が出席した。Montagna symposiumはオレゴン州と縁の深いWilliam MontagnaやAlbert Kligmanなどの研究皮膚科学の発展に貢献して来られた先生のメモリアルとして2年に一回開催されている、セミクローズドの研究会である。有名なゴードンカンファレンスやキーストンシンポジウムと同様、シーズンオフ?の保養地に4日間ほど泊り込みで討論し、朝、昼、夜は食事やソーシャルエベントを通して、お互いが親しくなり、より、テーマの深い理解をサポートするもので、私も中枢の痒みや痛みの認知機構など全く門外漢であったが4日間のシンポジウムを通して、皮膚科医がやるべきことが少し見えてきた。残念ながら阪大以外の皮膚科からは東京医科歯科大の端本先生が参加されていたのみで、あとは神戸理研の藤原裕展先生が、「自分の研究に対する中枢神経の研究者の意見を聞きたい」との、若い先生方に聞かせてあげたい動機から参加されており,素晴らしい発表をされた。「Hair follicle stem cells define a niche for tactile sensation via secretion of a specialized ECM」(専門は毛包幹細胞ニッチ構成分子群の同定、毛包幹細胞ニッチによる幹細胞制御機構の解明、細胞外マトリックスが異種組織を繋ぐ機構の理解)。(右のプログラムをクリックするとpdfが開きます)

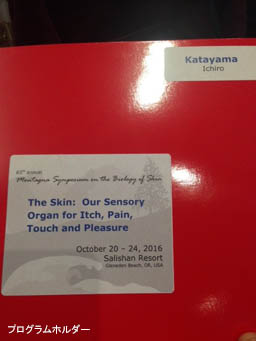



に陣取り、赤ら顔の柔和な表情で講演を楽しまれ、時に臨床家としての鋭い視点から質問をされていた。

The Skin: Our Sensory Organ for Itch, Pain, Touch and Pleasure
A primary objective of this meeting will be to bring together research expertise from the domains of the skin, brain, and cognitive sciences, to focus in depth upon the roles of the skin in inter-relationships between somatic sensation, perception, and behavior in health and disease. We will present topics from varied disciplines in the skin and brain/mind sciences to address itch, pain, touch and pleasure, focusing on the peripheral nervous system in the skin and in particular the C-fiber system. Speakers and participants will be drawn from a number of fields, including dermatology, neuroanatomy, neurobiology, molecular biology, genetics/epigenetics, cognition and emotion, social and affective neuroscience, and cognitive neuroscience in order to examine current knowledge and forge future strategies to understand the structural-functional basis of itch, pain, touch and pleasure. We will address issues of differences in nerve types and nerve functions in the skin, including how nerves in the skin affect skin function and other skin cells, adnexal structures, and processes such as normal homeostasis, wound healing and inflammatory disease. The neurosciences and skin biology are inherently inter- and intra-disciplinary. This symposium will provide an opportunity for researchers to learn, discuss, and debate topics in fields outside but related to their own, new insights and directions will be identified and new therapeutic strategies – pharmacological and behavioral – will be explored.
Program Chair
Gil Yosipovitch, M.D.
Department of Dermatology, Miller School of Medicine-University of Miami
History of Montagna symposium, the biology of the skin

In 1965, the Symposium moved to Oregon Health & Science University with Dr. Montagna when he became Director of the Oregon Regional Primate Research Center. The meetings were held at Salishan Lodge on the Oregon coast for nearly 20 years. From 1979 to 1992, the Symposium was directed by Kirk D. Wuepper of Oregon Health & Science University. Dr. David Norris and Dr. Wuepper co-directed the Symposium in 1991 and 1992 at Snowmass Village, Colorado. Dr. Norris assumed directorship of the Symposium for the 1993 meeting.
The 2003 Symposium brought a closer affiliation of the Montagna Symposium with the Society for Investigative Dermatology and a celebration of the leadership of Dr. Norris, who currently serves as Director Emeritus and member of the Symposium’s Advisory Committee. In 2004, Molly Kulesz-Martin and Jackie Bickenbach assumed directorship of the Symposium and oversaw a move back to Oregon. Dr. Bickenbach became Director Emeritus in 2011.
Now in its seventh decade, the Montagna Symposium continues to fulfill its mission to bring together basic scientists, clinicians, and young investigators to explore the frontiers of dermatology.
December 2002 article by Albert M. Kligman in the Journal of Investigative Dermatology
October 2005 address by Walter C. Lobitz, Jr. at 54th annual Montagna Symposium

今年のSID(4.26-29)が開催されるポートランドはオレゴンワインと並んでたくさんの素晴らしい地ビールでも有名です。多くの方が参加されますようにとの学会本部からの依頼です。
平成29年1月13日
2017年を迎えて: 「Fluctuat nec mergitur」
2017年を迎えて: 「Fluctuat nec mergitur」
大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学皮膚科学
教授 片山一朗
皆さん輝かしい新年を迎えられ、一年の夢に満ちた計画や皮膚病診療に関する新たな抱負を考えておられることと思います。
私も2018年度の退官を控え、最後の主催学会となる退任地方会や、第2回東アジア白斑学会などの準備を始めました。また臨床、基礎研究もやりたかったことに目処がつき、皮膚科医になった頃考えていた事、そしてそれぞれの時代の勤務先で生じた疑問に対する解答 が自分なりに達成、あるいは解決できたかと考えています。これからも体力、知力の続く限り未知への好奇心を大切にして行きたいと年頭にあたり考えを新たにしています。
そのような中、昨年の英国のEU離脱やISのテロが拍車をかけた反グローバリズムの大きなうねりは、次期45代アメリカ大統領にその象徴ともいえる ドナルド・ジョン・トランプ氏が選ばれた事で、さらに大きくなり、トランプ現象が2017年の世界を飲み込もうとしているようです。今の日本そして欧州、アジアと旅をしても、旅行者に見せる街の顔は平穏で、行き交う人々も楽しそうな語らいの中でいつもと変わらない毎日を過ごしているように見えてきます。しかし、マスコミなどの報道を見る限り、大きな歴史の変革の波が自由な世界を変えつつあるのは確かなようで、その先に何が待ち構えているのかは誰にも分からない、あるいは分からない振りをせざるを得ない状況になりつつあるのかと思います。
医学の分野においても昨年、我々皮膚科医の将来に直接関わる三つの大きな問題点が出てきました。一つは皮膚科医が取り扱うメラノーマの治療で最初に保険適応となった免疫チェックポイント阻害薬の薬価が決定後、その高額さ、有効例の選定と中止時期の問題、適応拡大からの流れから、一気に薬価の大幅な切り下げと毎年の薬価の見直し案などが厚労省を飛び越し、閣議決定されたことです。これは、今後の創薬開発への企業や研究者の意欲を削ぐ可能性、政府がメガファーマの圧力とどこ迄対決できるか、そして国がどこまで高額医療を保証するのかという大きな問題点を白日の下に晒してしまいました。二点目は人工知能(AI)が大きな進歩を遂げ、今まで勝てなかった棋士をもやぶる時代となり、Scienceの今年の科学の発見トップ10に挙げられたことです。皮膚科のように見る、診る、視る、観る、省るなど五感、時に第六感を駆使して診断を行い、治療を考えていく分野は当分AIも及ばないと楽観視していた皮膚科医も多かったと思いますが現実は、もっと早く進むと予測するのは私一人ではないと思います。「暗黙知」で代表される皮膚病の診断もAIが人と同じ経験則を持ち、学習能力を進化させれば、今の皮膚科学が根底から覆る日も近いかと思います。

2017年元旦
平成29年1月1日
Vitiigo International Symposium
Vitiigo International Symposium
Rome November 30~December 3, 2016
Presidents: Mauro Picard Alain Taieb
大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学皮膚科学
教授 片山一朗

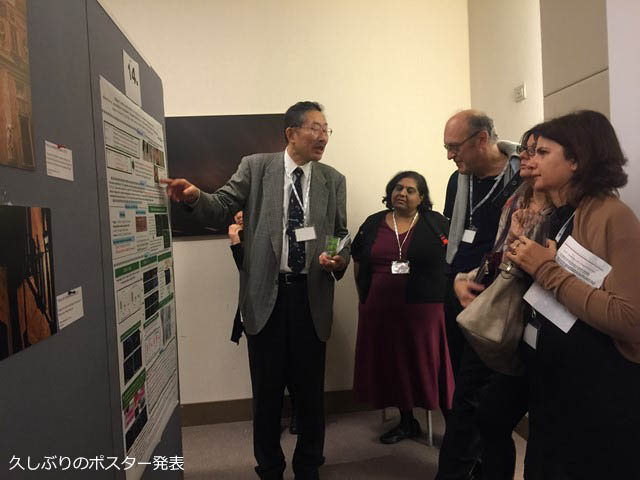
今回の学会には韓国のLee教授、Kim、Hang台湾ノLan、中国のFloraなどが参加されており。2018年に私が会頭を務める第2回東アジア白斑会議の運営や4か国で白斑の定量的な解析を共同研究として進めること、今回の白斑シンポジウムを国際的な学会へと発展させる議論などもあり大変有益な会であった。会期の4日間、朝から深夜の懇親会まで毎日学会場に缶詰状態で、英国留学時以来37年ぶりのローマだったが、帰国当日朝、国立博物館とカピトリーノ美術館を訪れることができ、ガリアのローマを楽しむことができた。来年8月にはデンバーで国際色素細胞学会もあり、より多くの日本人研究者が参加されることを期待する次第である。

懇親会にて。イタリア語しか話さないシシリー島からの先生、韓国の若手の先生方と。

唯一観光できたカピトリーノ美術館にて

講演する壽先生
平成28年12月8日
年報序文
年報序文
大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学皮膚科学
教授 片山一朗
今年も、新しく皮膚科学を生涯の職業とされる先生方を迎える季節となり、ましたが、今年は例年になく早く年報序文を書いております。2004年にスーパーローテートシステムが導入され、来年からは先行きは不透明ですが、後期研修医制度の開始にともなう研修プログラム作成が基盤18学会で進行しており、学会以外の組織から専門医が認定・授与されることが言われており、その是非が今も論議されています。 さて今、ウェッブ上でヒフミル君と」いう、アプリが広まっているようで、「皮膚の写真と患者情報、あらかじめ決まっ」いる項目を入力して送信すると、12時間以内に皮膚科専門医(どのような専門医か不明)から無料で診断のアドバイスを得られるということのようです。同じような「メミル君」という眼科サイトもあるらしく、このような画像診断の精度の向上にともない、診断のみでなく、対面診療によらない治療の可能性に関しても、国の政策として進められる事が予測されています。
私が皮膚科を選択した理由はいくつかありますが、将来はコンピューター技術やロボット医療がいくら進歩しても皮膚科はその疾患の多様性、4次元的な病因論などによる診断の困難さ、そして診療医の工夫による独自の外用治療が主体である事から医師の対面診療が無くならないと考えた事があります。その対極として星新一のショートショートにありそうな、機械に簡単な問診表を挿入し、腕をさしいれるだけで心電図や血液検査が行われ、ボタンを押すと薬がでてくる機械が、近い将来、実用化されるのではと考えた事もあります。
今後の皮膚科専門医の位置づけがどうなるかは全く予測ができませんが、「ヒフミル君」の今後の進化を考えると、将棋のようにAI(人工知能)が認定機構の認定専門医よりも診断能力や治療コンサルテーションの情報量の多さで勝ち、皮膚科医に取って代わる可能性も否定はできない時代が近づいている事を感じます。どう対応していくか、次の時代の指導者に引き継がれるべき大きな問題です。さて、このたび名誉ある「2015年度、第6回小川・清寺記念賞」 を受賞し、小川 秀興理事長より賞状と記念のグラス盾を頂きました。清寺眞先生は私が学生時代に勉強した教科書にもすでにメラニンの合成経路として生化学、電顕による研究成果が記載されていた世界的な研究者で、私が在籍した東京医科歯科大學皮膚科学教室の第2代教授として、その素晴らしい肖像写真が医局図書館に飾られていました。私自身メラノサイトの研究はこの10年あまり行ってきただけで、今やっとその研究が面白くなってきたところであり、受賞資格などとてもないのですが、今回の受賞理由に「アレルギー疾患、膠原病の病態解析と治療法の開発及び皮膚免疫研究に関する実績は国際的にも高い評価を受けておられます。また、痒みの研究や汗の分野にも国際的な業績の積上げに貢献されました。」とあり、畏れ多くも受賞の栄誉を頂く事になりました。また授賞式では恩師の西岡清東京医科歯科大学名誉教授が駆けつけてくださり、私の研究歴を紹介して頂き、身に余るお言葉を頂きました。私の研究は大阪大学、北里大学、東京医科歯科大學、長崎大学、そして再び大阪大学と異動するそれぞれの大學で直面した臨床での疑問を解決したいという動機から開始し、それを自分の中で有機的に結びつけながら継続性を持って行ってきました。その中で多くの若い先生方と一緒に研究を開始し、試行錯誤しながら他の研究施設の素晴らしい先生方とも知り合うことで世界を広げる事ができたと考えております。泥臭い日々の臨床の中から、生まれる疑問を見いだし、新しい世界を創り出して行く事は、AIには決してできない事で、その努力を放棄しない限り皮膚科医はその「皮膚科医の眼」で皮膚疾患を的確に診断し、AIにはできない最良の医療を提供できると考えています。
熊野大花火と太陽伝説

熊野は古来、徐福伝説に由来する不老不死の国への出発口であり、太陽信仰の聖地でもある。熊野の大花火は大輪の花を夜空に描き、消えて行く大花火と異なり、次の時代に時を超えて繋がる扇型の光の芸術である。上に見える赤い光の玉は北欧の夏の太陽を重ね合わせ、時空を超えて繋がる熊野からの未来をイメージした。
平成28年10月7日
「原著に学ぶ英米皮膚科学の古典」刊行に当たり
「原著に学ぶ英米皮膚科学の古典」刊行に当たり
2016.9.12
大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学皮膚科学
教授 片山一朗
このたび西岡清先生総監修で片山、岩月、横関が編集に協力させて頂いた
「原著に学ぶ英米皮膚科学の古典」が刊行された。この本の刊行の意義は序文にも書かせて頂いたが昨今の若い先生方の「英語論文離れ」、やPubMedでの論文検索でよしとする風潮への警鐘の意味もあるが、もっと大きな目的は皮膚科の膨大な歴史とそこに残された先人の叡智を訪ねる事であると考える。そのことで、本当に皮膚科の好きな若い先生が一人でも多く育っていただくこと、そしてかつての我々がそうであったように、このような皮膚疾患の原著を読む事が端緒となって世代を超えた先生方と議論、討論が可能になることであり、それが本来のアカデミアの復活になればと願う次第である。
ドイツ語版はまもなく出来の予定で、時期を見て岩月先生のフランス語版と合本販売予定である。皆さんのコンセンサスが得られれば、今回、ページ数の関係で省略せざるを得なかった、臨床経過、組織所見などの詳細や英、独、仏以外の原著も追加して、合本化できればと考える。参考として西岡清先生、片山、Ryan先生の刊行の挨拶、序文、寄稿と先生方からの書評を貼付する。
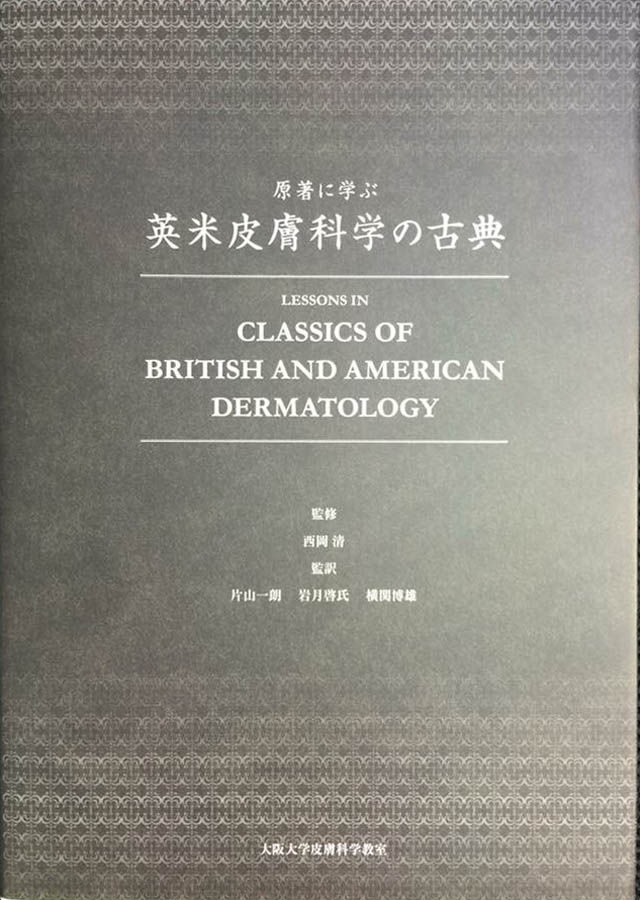
先生方よりの書評(順次アップ予定、寄稿者のお名前は省かせて頂き、一部本文から削除させて頂いている)。
●素晴らしい本をお送り下さり誠に有り難うございます。誰かがやらなければならなかった仕事ですが、お忙しい先生方がそれをしてくださったことに対して、心からの敬意を表します。この本は、これからの若い人だけでなく、我々のように現役を退いた人にも大変に役立つ本だと思います。出来うれば非売品ではなく、多くの人に読まれるような形で出版されれば、もっと価値が出るように思います。思わず読みふけってしましました・
●昨日「原著に学ぶ 英米皮膚科学の古典」が届きました。
先生とは、遊ぶだけのお付き合いの私(笑)に対して、このような立派な御本を頂戴し、恐縮の限りです。大変興味深い内容ですので、楽しみながら読ませて頂きます。
●「原著に学ぶ英米皮膚科学の古典」をご贈呈下さいましてありがとうございました。まさに、これは全皮膚科医必読のバイブルと思いました。必ず、抄読会で取り入れたいと思いました。貴重な書籍を下さいまして誠にありがとうございました。
●すごい本
「原著に学ぶ英米皮膚科学の古典」が届きました。本著の発行を考えた人、それを受け継ぎ、翻訳を担当した方々の努力に感服しています。ありがとうございました。
●西岡 清先生監修で、先生、岩月先生、横関先生の監訳の「原著に学ぶ英米皮膚科学の古典」(大阪大学皮膚科教室発行)を拝受致しました。
若い人達に皮膚科学の歴史を見直してもらうべきという目的で造られた本のようですが、近来見ない立派な装丁の書籍であり、 私もお贈りいただき、恐縮するとともに、感謝の申しようがありません。
開いてみると 私自身も知らなかった英米の皮膚科学の系列をゆったりと学ばせていただけるように、と作製されており、十三年前に大学を引退してから、先日は先生主宰の発汗学会で話をさせていただきましたが、段々と、学問から遠ざかる立場に置かれた感じがしていたところでもあり、毎日、楽しみにして読ませていただきます。先生のもとで、新たな皮膚科学が益々、発展することを祈念致しております。
●最近の若い先生は学会発表でもすぐにレビューを探し、原著など読んでいないようである。
●様々な疾患の原著です。臨床像の記載や経過がやはり秀逸であり、翻訳も一流の方がなさるとこうなるのかと、唸りました。最近のネットだけ調べてガイドラインに沿った治療だけを発表するだけのくだらない他人行儀な(失礼)一部の論文や学会発表は原著を読んでないのかもしれませんね(生意気ですみません)。
僕らは予々、常に原著を読むように西岡清先生に指導されたのでますますそんな思いが最近します。
●臨床像の経過の記載が楽しいよね。まるでその場にいるような記載!訳者も一流だからこそ、かつて読んだ事があるものでも新鮮ですね(⌒▽⌒)✨
●医療の先人たちの不便な時代だからこそ、しっかりモノをみようとする「ココロの目」はとても勉強になります。
●大阪大学 片山先生から、いただきました。今から、時間ができそうなのでタイムリーです。ありがとうございました。まず、profundusから読みます。
●昔、京大皮膚科では、新入局者に皮膚疾患発見ないし命名の逸話をまとめた英語の本の輪読を課していました。残念ながら著者の名前が出てきません(トホホ)。
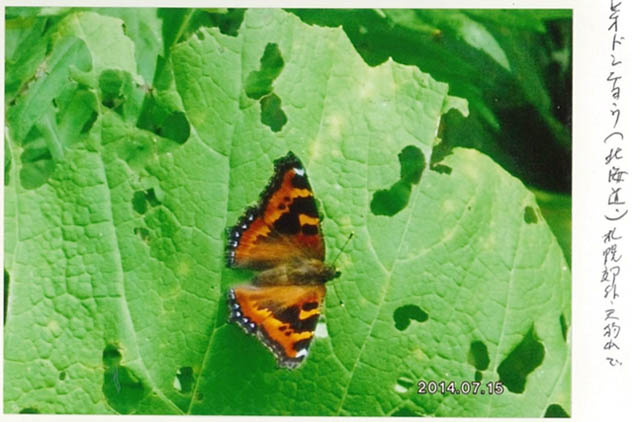
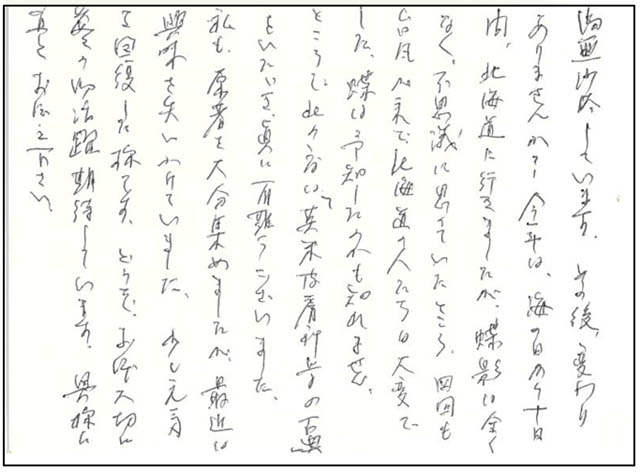
●先日は「原著に学ぶ 英米皮膚科学の古典」をお送りいただき誠にありがとうございました。驚嘆すべき力作で、並々ならぬ年月をかけられたものと思います。 私共の分野もこのような形で次世代に残さねばならないことが、多々ございますが何せ浅学非才でままなりません。
本当に、ありがとうございました。
●
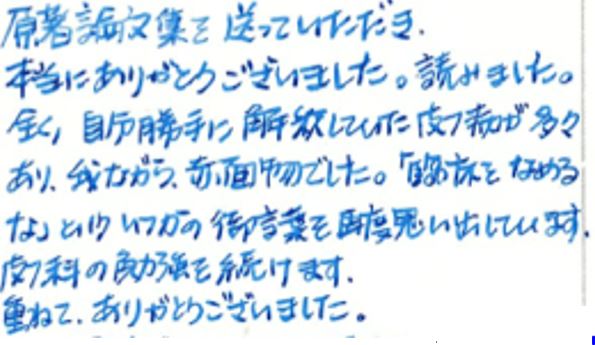
●今日はとても素晴らしい本をお送りいただきありがとうございます。もう、面白くて一気に読みました。写真ではなくイラストとムラージュで先人の先生方の偉大さに改めて敬意を表し、さらに皮膚科学に興味を持てる本だと思いました。刊行になれば周りの先生方に勧めさせていただきます。
本当にありがとうございます。
●「英米皮膚科学の古典」、拝受いたしました。
この年齢になると尚更、心を打つ企画だと感銘いたしました。
皮膚科医人生を振り返りながら拝読させていただきます。
周りにも勧めます。ありがとうございました。
●
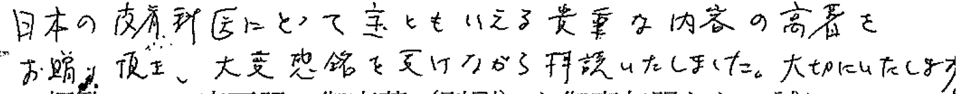
●
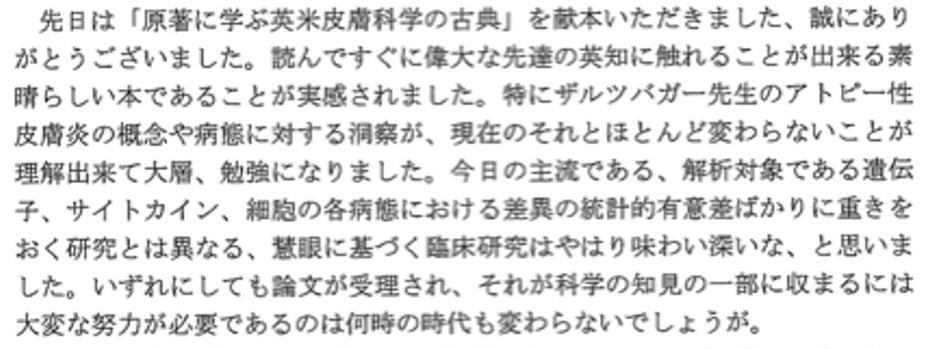
●
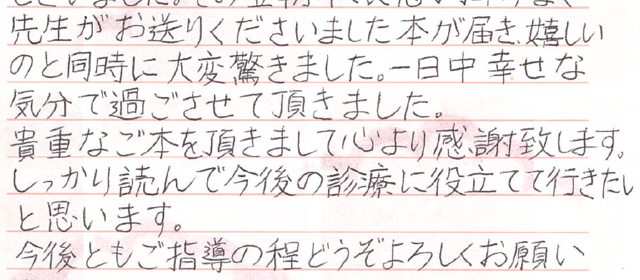
●
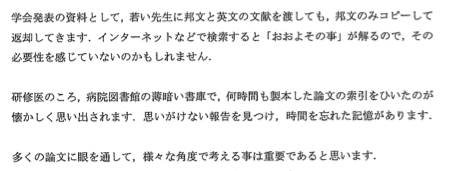
9月30日追加
●この度は「原著に学ぶ 英米皮膚科学の古典」をお送りいただ き誠にありがとうございました。 ゲッケルマンやスティーブンス・ジョンソンなど、もはや固有 名詞であったことを忘れるような方々の論文を眼にすることができるとは思ってもおりませんでした。私も、チャーク・ストラウス症候群の論 文を書いた際、原著にあたりましたが、その際、その頁だけが手垢で汚れており、自然とその頁が開いたという経験が思い出されました。この 度、この書籍をいただき、改めて原著に触れること、そして自分がその原著を読むまでに多くの医師達がその論文を読んで学んだという歴史を 実感することの大切さを認識した次第です。 ただ、先生が巻頭で書かれていますように、私も最近ではイン ターネットで引ける文献のみ読むということが多くなっております。病院図書館では、定期購読されている皮膚科書籍がなかったため、私が着 任してから「皮膚病診療」のみ購読するようになりました。それでも、昔のArchivesやBritishは少しは図書館にありますので、病院の図書館 にある文献は自分でチェックするようにしておりました。ただ身近の若い先生の言動からは、論文の原著にあたるというこ とは無駄と思っているような気がします。購読している「皮膚病診療」も目にしたことはないと思います。(ミーティングなどの際、私は 皮膚病診療を持ち歩いて、読んでいる姿をアピールしていますがあまり響いていないように思われます)。日本語文献も目にしないように なると、例えば「そうよう」をワープロで変換すると、やまいだれの「そう」は候補に出てきませんので、「掻痒」と当たり前のように電 子カルテに入力してそれに違和感を感じなくなってしまうようなことも危惧されます。このようなことは一部の医師にしか当てはまらないことかと 思っていましたが、先生の巻頭を読ませていただくと、多くの医師にそのような傾向が見られていることが認識されました。もちろん自分自身 を含めて、文献に当たる、雑誌を触る、ということを実践するべきだと改めて感じた次第です。いただいた書籍をゆっくりと拝読させていただきます。
●この度は、「英米皮膚科学の古典」を賜り、ありがとうございました。疾患の概念を最初に提唱された先人の慧眼に触れ、衝撃を受けました。普段、入手しやすい文献や孫引きに頼り、分かった様な気分になっていたことに気付かされました。オリジナリティーを重んじる世界に身を置きながら、ともすると安易な方法で得た偽物の知識で済ませてしまっていたことを恥ずかしく感じています。教室員にもぜひ読んでもらいたいと思っています。
●この度は「原著に学ぶ英米皮膚科学の古典」をご贈呈下さいましてどうもありがとうございます。恐縮の限りでございます。まず乾癬の治療の部分から拝読させて戴きましたが、今ではほとんど行われていないゲッケルマン療法の原法についてゲッケルマン本人が記述された原著の日本語訳でたいへん興味深く、また現在の乾癬の治療について改めて再考させられました。刊行になりましたら周りの先生に勧めさせていただきます。 学生さんからの嬉しいメール (^^)膚科の話の他には、特に医学における古典的教養ということを教授にお伺いしたいと考えています。最新の研究には少なからず心惹かれるものがないわけではないのですが、むしろnatureを読むよりも例えばウイリアムオスラーの著作を読む方が医学生として正しいのではないかと考えています。
●
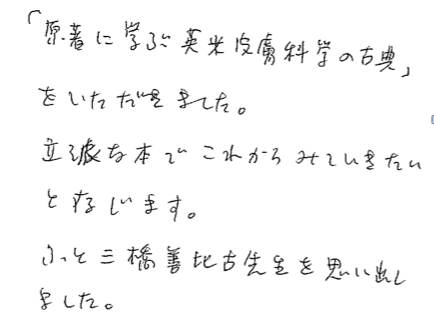
●
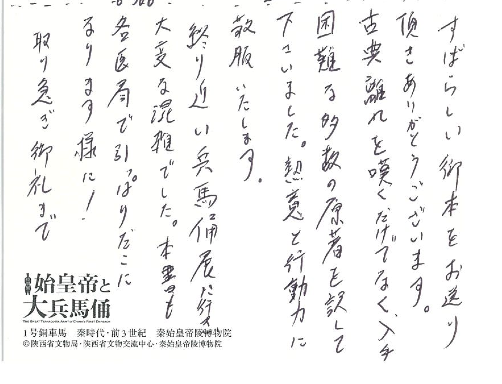
●
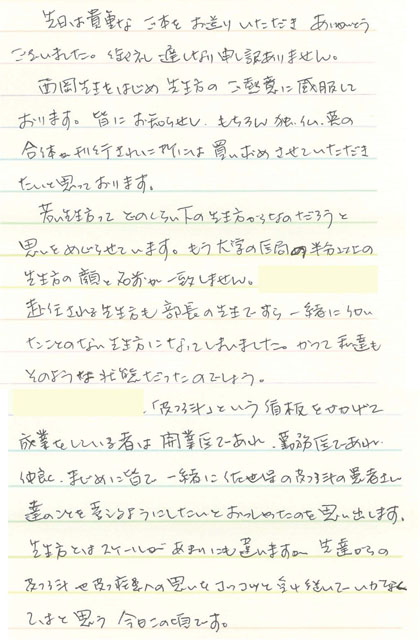
●
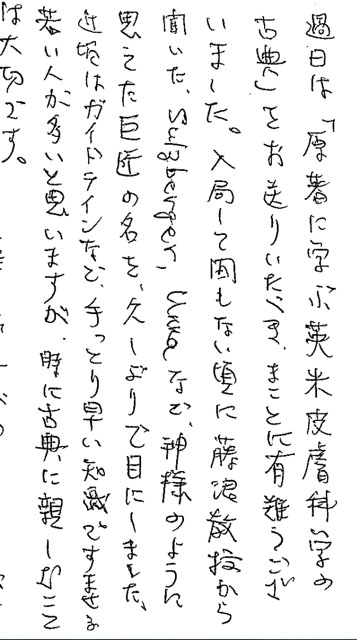
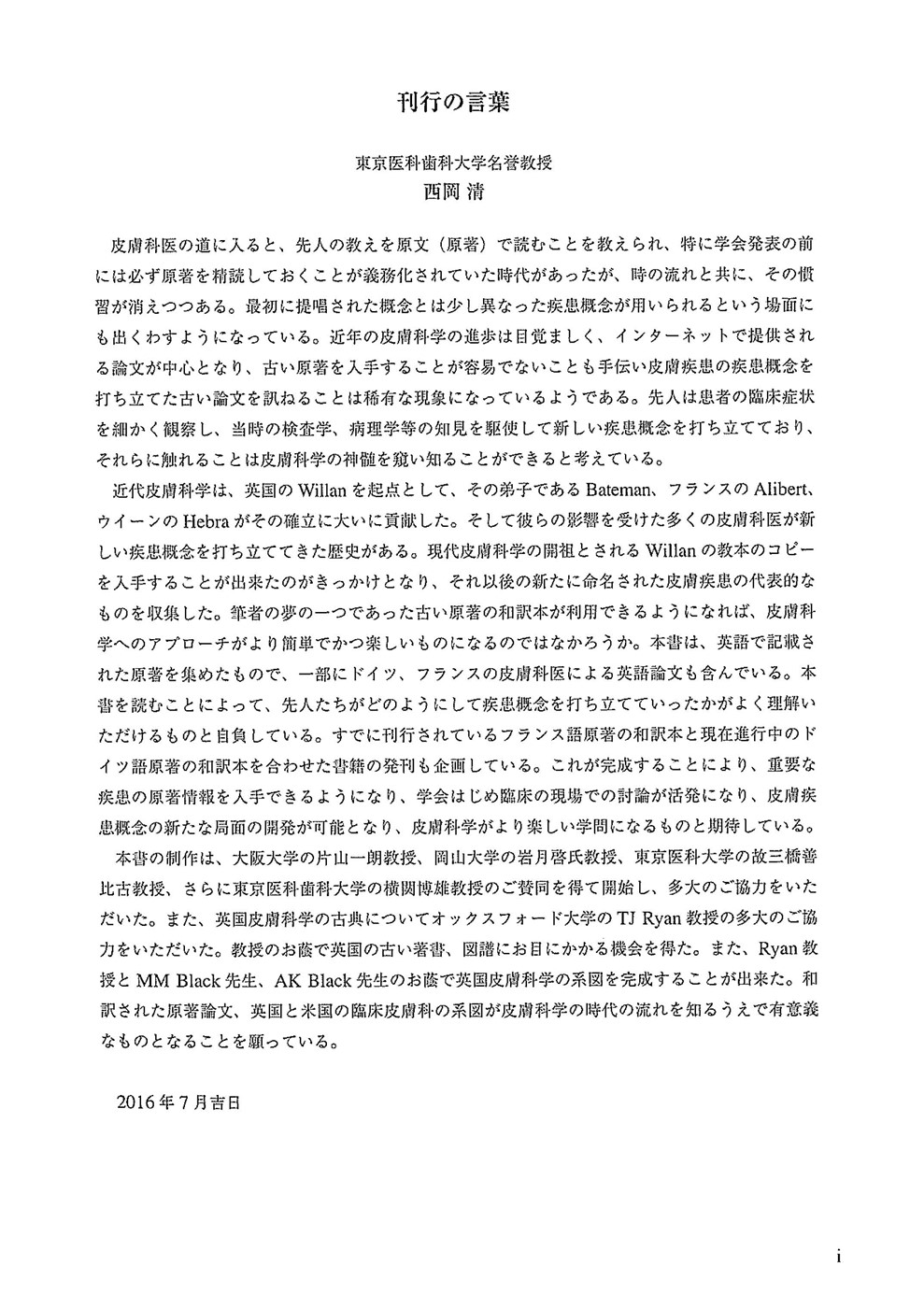
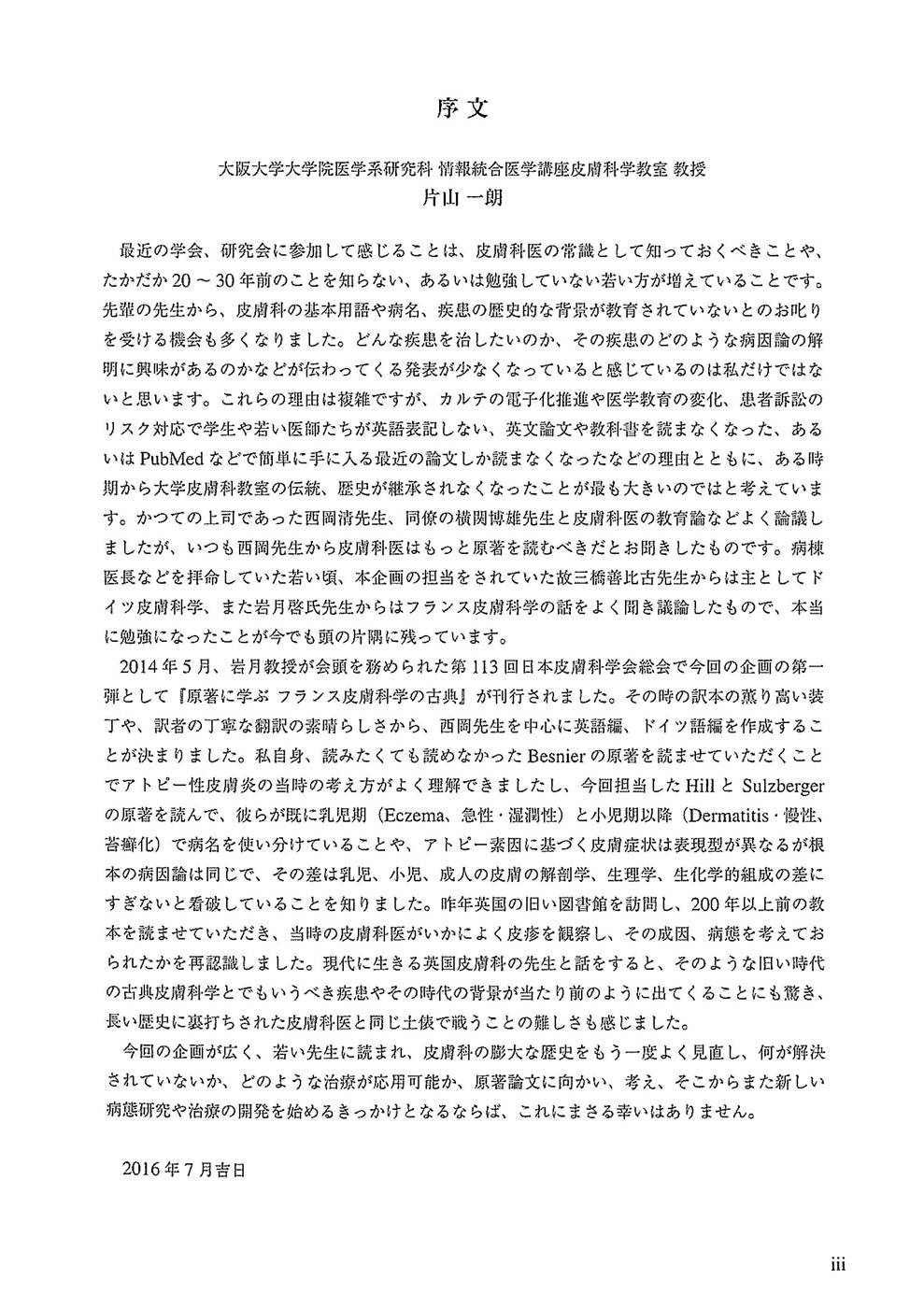
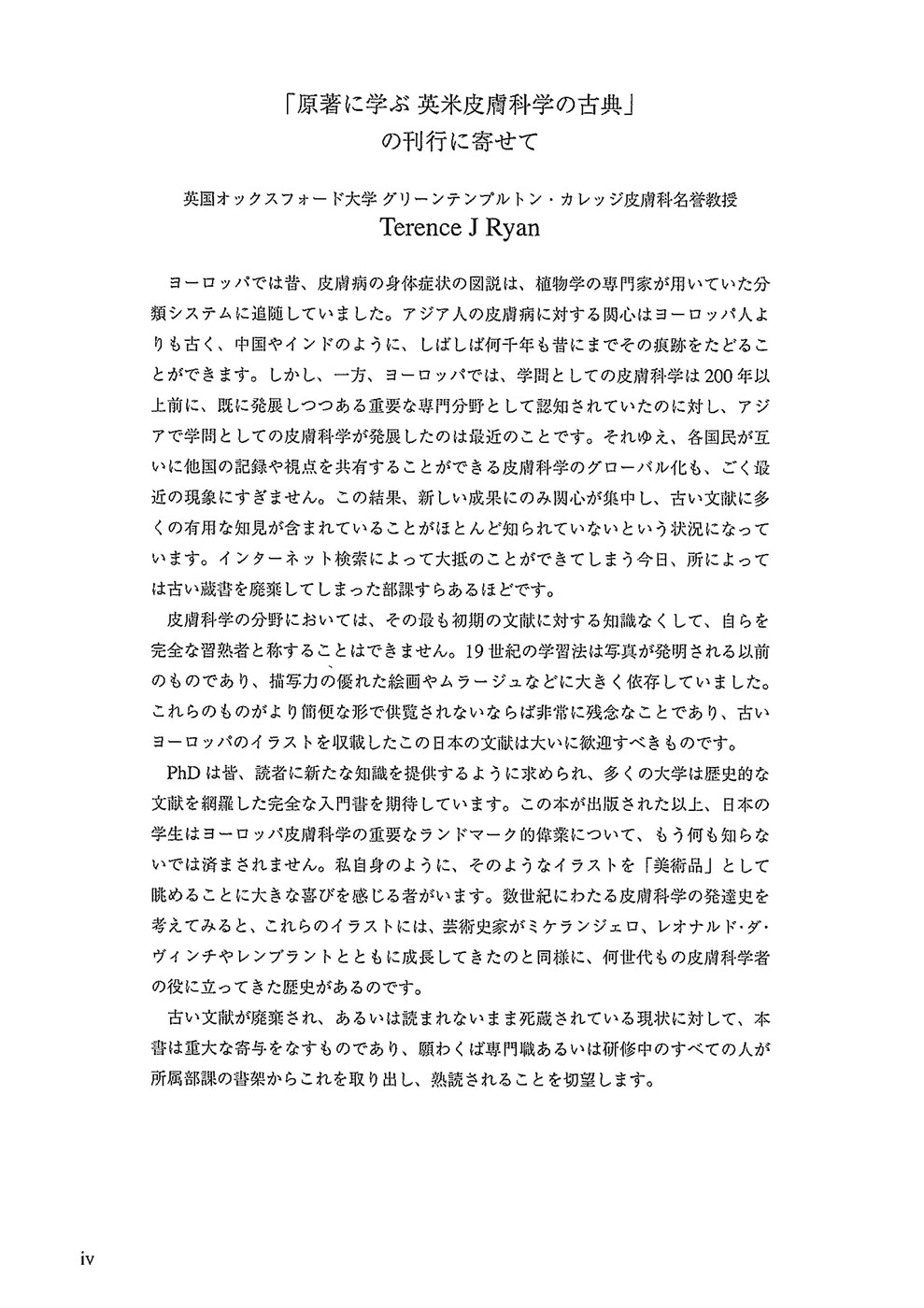
平成28年9月13日
第24回日本発汗学会
第24回日本発汗学会
会長:片山一朗 大阪大学皮膚科教授
会場:大阪大学銀杏会館
会期:2016年8月27日−28
大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学皮膚科学
教授 片山一朗

第24回日本発汗学会を2016年8月27日(土)~28日(日)の2日間、大阪大学銀杏会館にて開催させて頂いた。この学会は基礎・臨床・企業研究者が集い、汗に関する最新の研究成果や症例報告を発表し、活発な討論が飛び交うユニークな学会で多くの事務局長の室田先生を中心に教室関係者のサポートで準備を進め、無事に終了した。ご協力頂いた方には心よりお礼を申し上げたい。
我が国における、汗の研究は日本の発汗研究の創始者である名古屋大学の 久野寧先生とその門下生の方々、皮膚科では東京医科歯科大学皮膚科の横関博雄先生が留学されていたアイオワ大学の故佐藤賢三先生の単一汗腺の単離に基づく膨大な仕事を中心に発展してきた。私自身は30年程前からシェーグレン症候群、そしてアトピー性皮膚炎での発汗異常に興味を持ち、研究を継続してきたが会頭講演では、その一部を紹介させて頂いた。シェーグレン症候群は外分泌腺が障害される自己免疫疾患で、涙腺、唾液腺、尿細管などに加え、汗腺も障害されるが、発汗機能異常は診断基準には無く、今後、発汗機能検査も是非、診断に用いられるような努力が必要と考える。昨年1月から指定難病にもなり、またSEKIKENという会社から簡易型の発汗測定器も販売され、発汗機能検査が自律期神経機能検査として保険収載されており、あとは他の外分機能検査との比較や測定感度、重症度との相関などの検討を公表して行く必要があるかと考える。またアトピー性皮膚炎と合併することもあり、その場合、湿疹病変に加え、乾燥肌や皮膚のアミロイドーシスなどがより強く現れることを報告している。室田先生が中心となり進めているアトピー性皮膚炎の発汗機能やカユミの研究はOCTや2光子顕微鏡、マウスなどのMRI解析など驚くほど研究ツールが進んでいる。やれば驚くような、面白いデータが次々とでてくるようで、皮膚、そしてまた汗腺というメインストリームからはやや外れた研究対象ではあるが、逆にそこからの発見が今後,他の分野にも応用されて行く可能性があると私は考えており、若い先生にはどんどんこの古くて新しい研究領域に参入して頂きたい。20年ほど前に長崎大学に教授として赴任したおり、当時熱帯学研究所の所長をされていた久野先生門下の小坂光男先生からは恒温室の使用と当時としては画期的なQSART法を教えて頂いた。初めてアトピー性皮膚炎の発汗異常を定量的に解析することができ、論文として報告し、大阪大学に異動後も研究を継続している。学会中に久しぶりにお会いした保健学科の近江教授にはOCTのマウスへの応用で、ずいぶんとお世話になり、汗腺の4次元的な解析への道を拓いて頂いた。このように機器の進歩や新しい研究技術の開発は驚くべきスピードで進んでおり、本当に心からわくわくする、面白い時代に研究生活を送れることに改めて感謝する。特別講演でお話頂いた大阪大学の蛋白研の関口教授の細胞外真トリックスの研究でもラミニン511E8フィラグメントなどがiPS細胞の培養の進歩に貢献しているという話や、汗腺にいることが明らかになった幹細胞からの汗腺再生など夢のある話を伺うことができた。さらにJAXAの古川飛行士をゲストスピーカーとしてお招きしたシンポジウム「宇宙と汗」は普段あまり聞けないような宇宙空間での日常生活や汗の処理、そして、下着の開発の話など今後皮膚科の医者も参入できそうな話題が印象に残った。仙台から参加頂いた東北大学名誉教授の田上八朗先生は、皮膚の角層機能の定量的な測定機器の開発とその応用で大変有名な方で、以前からご指導頂いている。今回も先生ご自身の大藤真京大名誉教授との研究史秘話、Kligman教授との研究裏話を聞かせて頂いた。また高齢者の皮膚は予想以上にバリアがしっかりしていること、発汗障害のみでは皮膚の乾燥肌は生じず、同時に皮脂の分泌低下や加齢に伴うフィラグリンなどの産生低下が複合的に関与するという,マウスモデルで明らかになってきたことを、先生がご自身で人の皮膚を用いて証明されてきた結果を示された。大阪大学からは、室田先生が2光子顕微解析による新しい発汗機能解析の成果を中心に講演された。また山賀君は汗腺、汗管のタイトジャンクション蛋白の発現様式を検討され、アトピー性皮膚炎で真皮内導管のClaudin 3の発現低下が見られ、汗の漏出が観察されること、そのノックアウトで同様の現象が見られることを綺麗に証明された。今後このような現象が他の外分泌腺でも後天的に生じうるのか、もし生じるとしたら、どのような症状が出現するのかなど興味深い。小野先生は汗のメタボローム解析を核磁気共鳴法で解析され、発汗低下の見られるアトピー性皮膚炎患者では汗中にグルコースが排泄されていること,糖輸送に関わるSGLUT2の発現、分布異常があることを報告された。これは発汗に要するエネルギー消費の問題と関わるほかに、皮表常在菌成分の汗への混入など消化管や上気道など、外界と繋がる線組織での微生物との共存を考えるときに重要な問題になることが予想され、さらなる研究の展開を願いたい。楊飛先生は結節性硬化症白班部で見られる発汗低下に汗腺筋上皮細胞でのある物質の沈着が原因ではとの電顕的な観察結果を患者,およびTSC1,2のノックダウンマウスで証明し、報告された。mTORの発現亢進により結節性硬化症では血管線維腫やLAMなどの腫瘍性病変や,白班などが見られ、それらにラパマイシンが効果を示すことを報告されているが、逆に掌蹠多汗症にラパマイシン外用が効果を示すとうい結果を得ており、その結果が期待される。後天性全身性無汗症AIGAで血中CEAの上昇が見られることが最近旭川医大皮膚科から報告され,注目されているが、信州大、埼玉医大から同様の報告があり,分泌部の暗細胞の減少が関与している可能性が報告された。その他、スポーツ医学での発汗機能解析、新しいスポーツウェアへの応用、発汗機能の性差、年齢差、人種差など興味深い演題が多く、久しぶりに頭がリフレッシュされた。日本発汗学会は 会員が180名くらいの比較的小規模な学会で、その分、基礎、臨床のエキスパートの先生が参加される非常に密度の濃い学会である。ただここ数年、臨床、基礎また研究分野を問わず若手の研究者の減少や海外留学を希望する方の数が下降線を辿っており、先に述べたように今後、非常にユニークでかつ未来の生活に直結するような研究の進展が予測され、かつての久野先生や佐藤先生がそうであったように、若い先生にはその柔軟な発想で新しい世界を切り開いて頂きたい。下の教本は9月末にKarger社から出版予定の皮膚科の研究者を中心に横関先生、室田先生等とともに編集したもので、
現時点での発汗研究と臨床でのトピックスを取り纏めている。一度また手にとってご覧になればと思い佐藤賢三先生の一番輝いておられた頃の写真ともに紹介する。
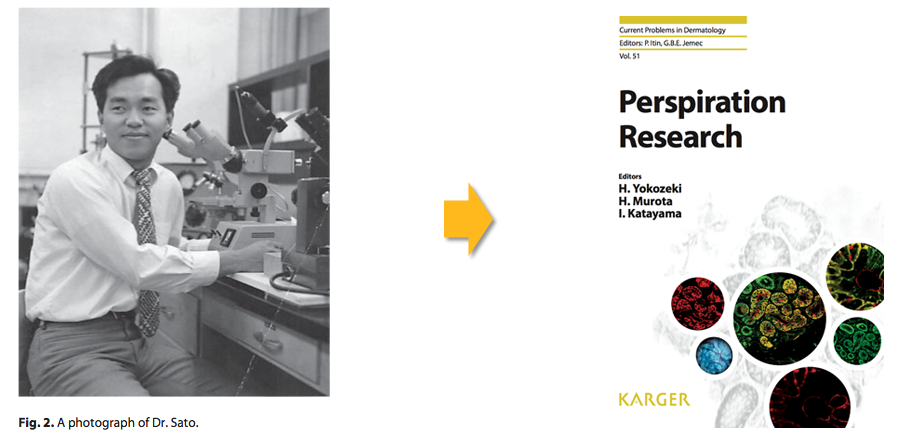
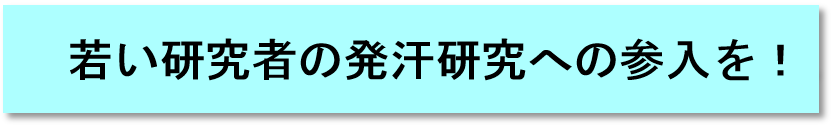
平成28年9月3日
三嶋豊先生と白斑研究
三嶋豊先生と白斑研究
大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学皮膚科学
教授 片山一朗
本年8月3日、日本色素細胞学会の初代会長で神戸大学皮膚科名誉教授三嶋豊先生がご逝去された。三嶋先生は、日本色素細胞学会の基礎を作り上げられたお一人として日本における色素細胞研究の発展に多大な貢献をされ、国際色素細胞学会でも活躍された。下記に示すような多くの国際的な賞を受賞されている。
○ 1960 デトロイト皮膚科学会賞
○ 1962 シカゴ皮膚科学会賞
○ 1964 アメリカ皮膚科学会第1位賞
○ 1973 三越学会賞
○ 1984 ヘルマン・ピンカス記念講演者賞
○ 1985 清寺真教授記念賞
○ 1985 日本臨床電子顕微鏡学会安澄記念賞
○ 1990 兵庫県科学賞
○ 1990 国際色素細胞学会 Myron Gordon Award
研修医の頃、地方会の最前列に座られ、その当時は多分許されていたパイプの似合う、オーラに包まれた教授として、また発表される皮膚腫瘍などの病理所見の解釈で徹底的に発表者を教育される姿が強い印象に残っており、佐野榮春大阪大学教授、坂本邦樹奈良医大教授、相模成一郎兵庫医大教授などの先生共々当時の大阪地方会の名物教授でもあった。三嶋先生は黒色腫に関して多くの研究成果を公表され、常に臨床的な観察と研究をフィードバックされながら退官後も研究を継続されたことは多くの黒色腫研究者が知る所で、ボロンを用いた熱中性子補足療法は今も臨床研究が継続されている。ここ数年の免疫チェックポイント阻害薬による黒色腫に対する劇的な治療効果は是非ご自身の眼で確かめられたかったと思う。私は皮膚の免疫アレルギーの研究がテーマであり、親しくお話頂く機会は無かったが、遺伝子治療学の金田安史教授の開発されたHVJによる黒色腫治療の研究にも興味を持って頂いた事や、厚労省の班研究で白斑の治療ガイドラインを作成する過程で、白斑の病態研究を開始したことがキッカケで三嶋先生からご指導を受ける事になった。私自身、白斑には研修医の頃から興味があり、三嶋先生の記載されたαデンドリテック細胞(メラノーソム、バーベック顆粒を持たない樹状細胞)が白斑の基底層で増加しているとの知見を三嶋先生執筆の尋常性白斑という教本で知っていたが、その本態が何であるかを知りたいと考えていた。班研究の過程で、CD1a陽性のランゲルハンス細胞が白斑の病変部基底層で増加、活性化していることを見いだし、報告したことや結節硬化症での白斑の病因論などを教室主催のセミナーで講演頂き、色々な事を教えて頂いた。

αデンドリテック細胞とは逆にメラノーソム、バーベック顆粒両方を持つ樹状細胞の存在も他の研究者からの報告がある。60年代の大阪大学の堀木などが報告したランゲルハンス細胞メラノサイト由来説は玉置らのランゲルハンス細胞が骨髄に由来するというNatureの論文で否定はされたが、逆にメラノサイトの前駆細胞が骨髄に存在する可能性やランゲルハンス細胞自体がメラノソームを貪食する可能性も考えられており、我々の研究室でも白斑の病因論におけるランゲルハンス細胞あるいはαデンドリテック細胞の役割の再検討を行っている。教室の大先輩の堀木学先生の美しい電顕写真からの仮説を下に、大学院生の揚飛先生が2抗体の免疫電顕や3カラーの免疫染色の解析、さらに培養系の研究で面白い現象を見いだされている。HE染色では一見、組織学的な特徴の見えない白斑ではあるが、そこに新たな画像解析法や3種、4種の色素標識蛍光抗体を用いた解析で白斑部を観察すると、驚くような細胞間あるいは組織間のクロストーク像が現れ、新たな白斑の病因論が見えてくる。私自身、皮膚科の研究のトレンドの移り変わりには興味があるが、1950年代から60年代の初頭は清寺先生や三嶋先生、Ken Hashimotoなど電子顕微鏡を用いた形態学とDOPA反応などの生化学的な手法を用いて皮膚の細胞機能の研究や皮膚疾患での動態研究が大きく発展した。70年代の免疫学、分子生物学が爆発的に発展した頃は多くの若い研究者が新しい発見を求めて米国に留学した時期でもある。21世紀の現在、研究のトレンドはiPS細胞の臨床応用や次世代シークエンサーによる疾患発症責任遺伝子の同定、2光子顕微鏡などによる4次元組織解析、Optogenetics、Gene editionなどであるが、研究のための研究になりつつあり、高額な治療薬の後追い実験などが主になり、臨床発のオリジナルな研究が激減している現状を危ぶむ声もある。新しい解析技術や方法論を創り出す事が究極のサイエンスであり、それが研究のモチベーションとなるが、臨床の教室で可能な研究をどう進めて行くかは、やはり疾患を診断し、治療していく現場の医師が解決したい問題点を明らかにし、より良い治療を難治性の患者に提供していくことが最も重要と考える。その意味で三嶋先生は生涯を白斑と黒色腫の治療開発にかけられた先生であり、我々もまた最新の解析技術を用い、創薬に繋がるオリジナルな日本発の研究を創り出して行きたい。
合掌
平成28年8月9日
植木宏明先生の思い出
植木宏明先生の思い出
大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学皮膚科学
教授 片山一朗
川崎医大元学長、名誉教授であった植木宏明先生が平成28年5月11日ご逝去された。また7月16日には植木先生を偲ぶ会が倉敷市で執り行われた。岡山大学の岩月啓氏先生からのご連絡では、生前植木先生と親交の深かった、皮膚科の先生方も参列されていたそうである。私自身は植木先生とは北里大学に赴任後から西山先生の紹介を頂き、皮膚脈管膠原病研究会で長年に亘りご指導を頂いた。植木先生との思い出はたくさんあるが、やはり日独皮膚科医学会でドレスデン、マールブルク、日本では横浜、奈良、長崎でご一緒させ頂き、いろいろなことを教えていただいたことが記憶に残っている。
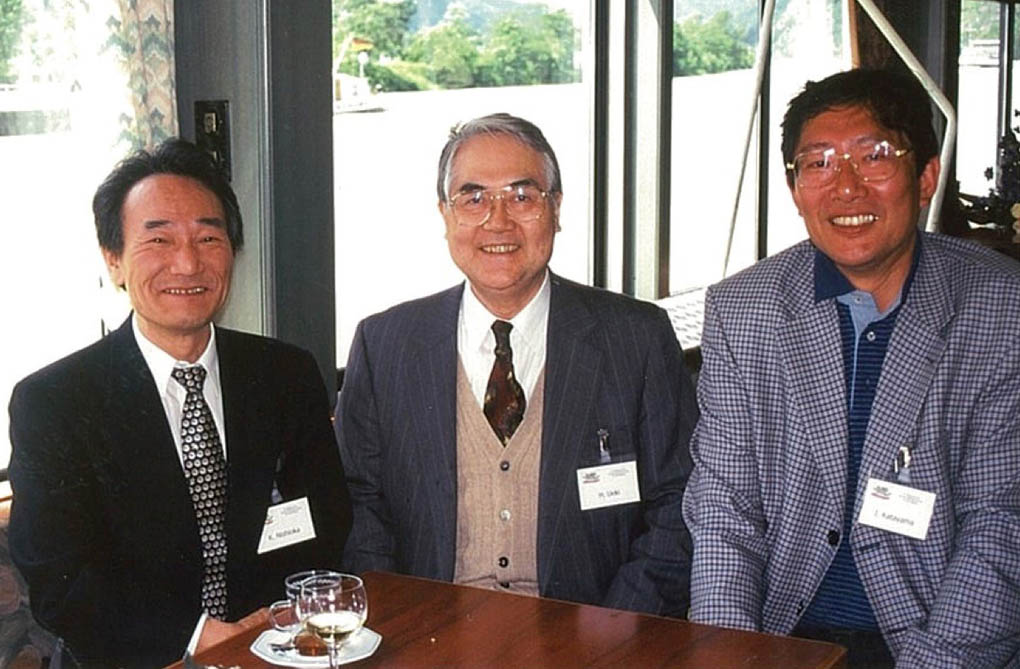
1999年Happle教授が開催されたマールブルクでのライン川下り時のスナップ
(左から西岡清東京医科歯科大名誉教授、植木先生、片山
マールブルクでHapple教授が会頭を務められた時のライン川下りの船中で開催されたセミナーで、ドイツ語で講演された時にはその流暢なドイツ語に驚かされた。特に私が北里大学でシェーグレン症候群の皮膚症状に興味を持ち、紅斑、紫斑や口唇小唾液腺生検などで、LEとの違いや血管炎、乾燥症状の評価などよく議論させていただいた。その当時、環状紅斑はSCLEとしてLEの皮膚症状と考えられており、ドイツでもシェーグレン症候群は全く考慮されていなかったが植木先生はあきらかにLEとは異なる病態であるとして、Hautarztにも、総説を発表され、私の考えを支持していただいた。その後ドイツのミュンヘン大学からもビルマ人のシェーグレン症候群患者に生じた環状紅斑の報告がヨーロッパ圏から初めて発表された時は植木先生のお力と感謝した記憶がある。その縁で皮膚病診療のシェーグレン症候群の特集号を作っていただき(貼付1)
、総説を執筆させて頂いたのも私の皮膚科医人生の中では大きな出来事であった(貼付2)
植木先生は皮膚における免疫複合体の研究のパイオニアでSLEや血管炎、自己免疫水疱症の研究で大きな業績を上げられたが、お人柄通り非常に気さくでわけ隔てのない先生でいつも若い人との議論を楽しんでおられた。川崎医大の学長になられてからもよく声をかけて頂いた。特に皮膚脈管膠原病研究会では、西山茂夫先生、西岡清先生、西川武二先生、神崎保先生などとともに最前列に陣取られ、厳しい質問やコメントを頂いたもので、今、思い返しても、考えられないような豊饒な時間を共有させていただいたことに深く感謝したい。
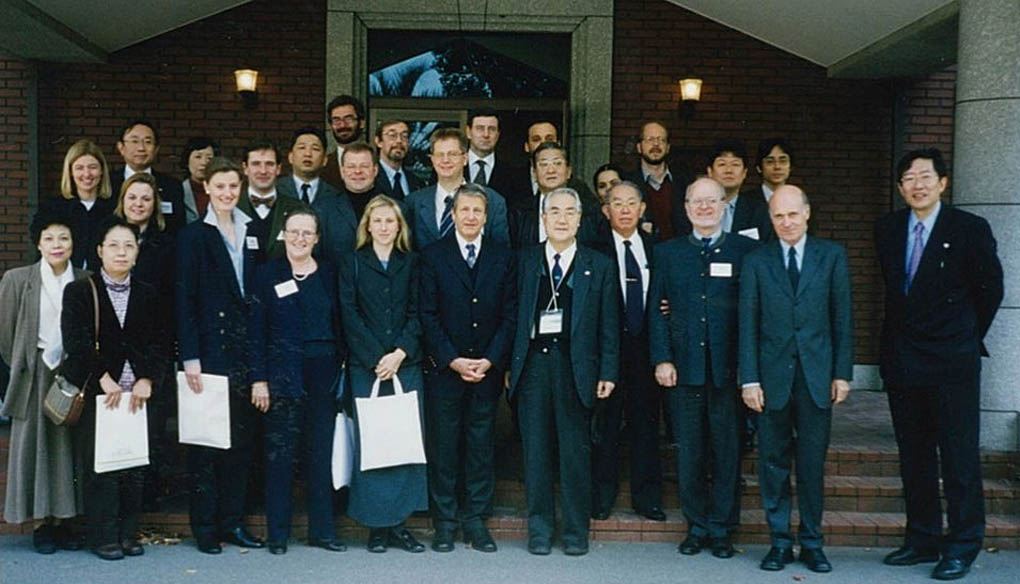
2002年長崎で片山がポストコングレス学会を開催した時のスナップ
-長崎大学ポンペ会館にて-

2002年長崎で片山がポストコングレス学会を開催した時のスナップ
(左から植木先生、二人おいてドレスデン大学Moeurer教授、マールブルク大学Happle 教授)
-長崎グラーバー園にて-
最後にご一緒の仕事をさせていただいたのはVisual Dermatologyでケブネル現象の特集を組まれた時で、私にも声をかけて頂き、ヒトアジュバント病を書かせていただいた。昨年、佐野榮春先生がご逝去されたが、植木先生も佐野先生同様大人の風格の漂う本当に教授と呼ぶにふさわしい方で、サイエンスと臨床のバランスが取れ、またユーモアに溢れた私の理想とする先生でした。長い間のご指導、本当にありがとうございました。
合掌
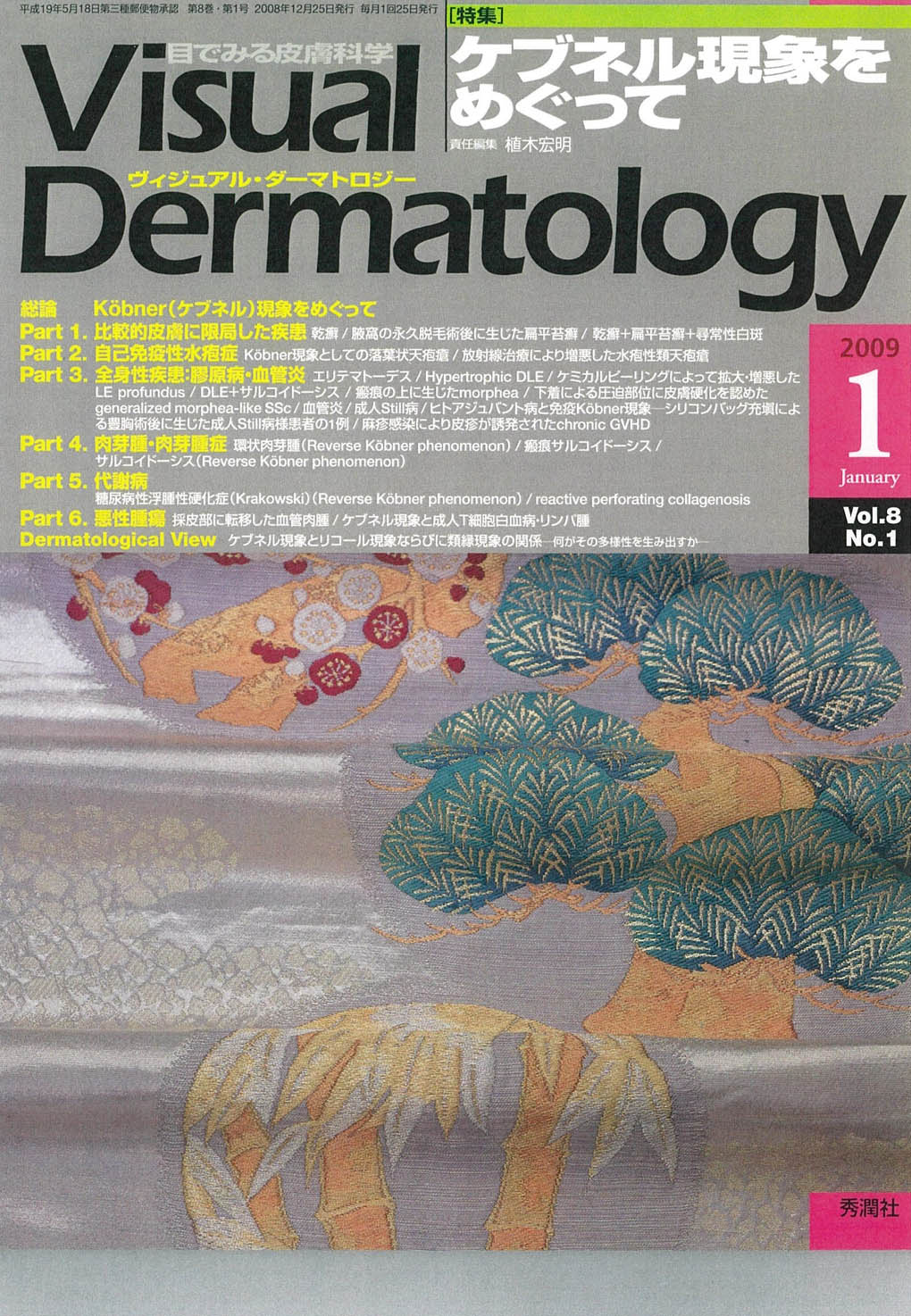
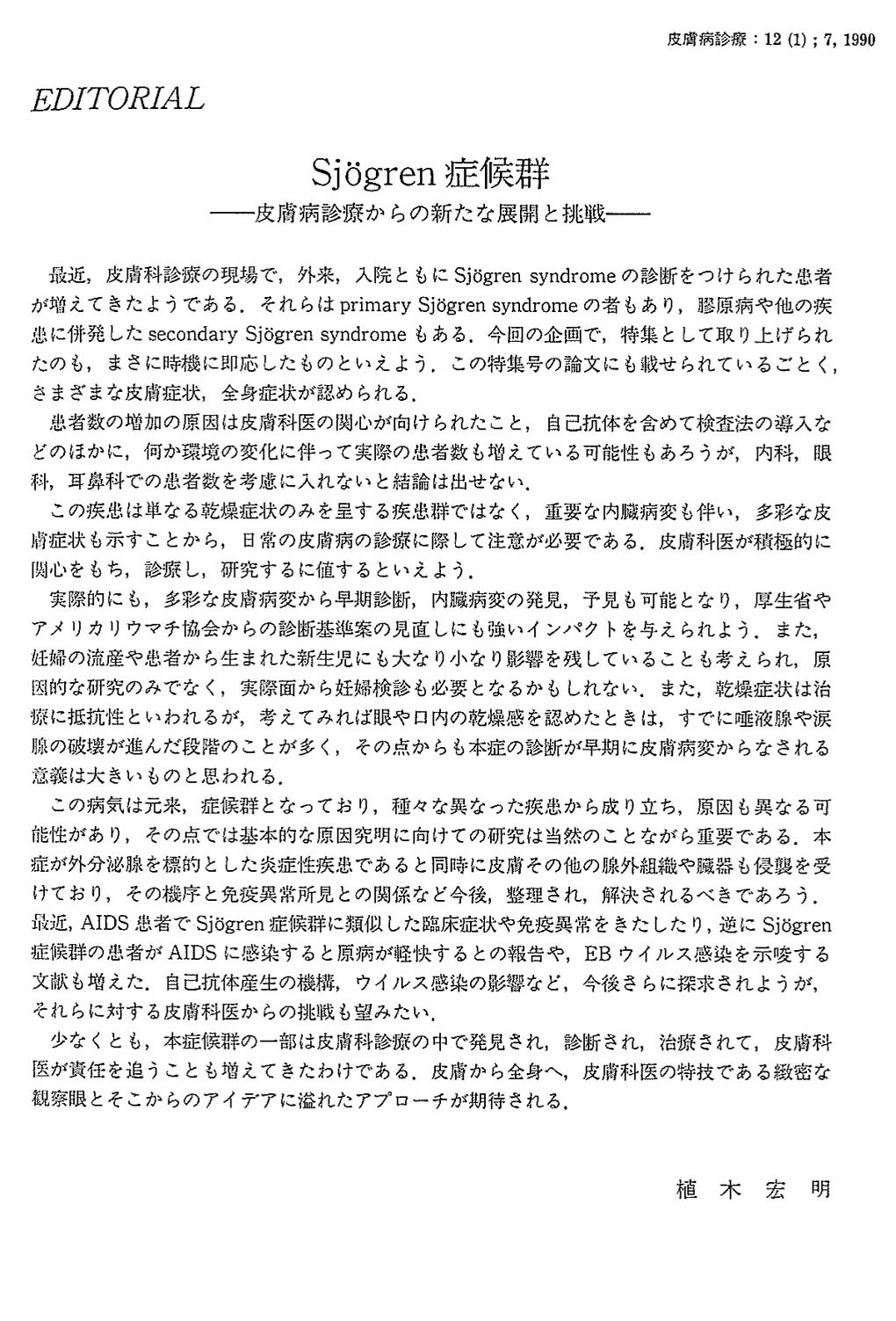
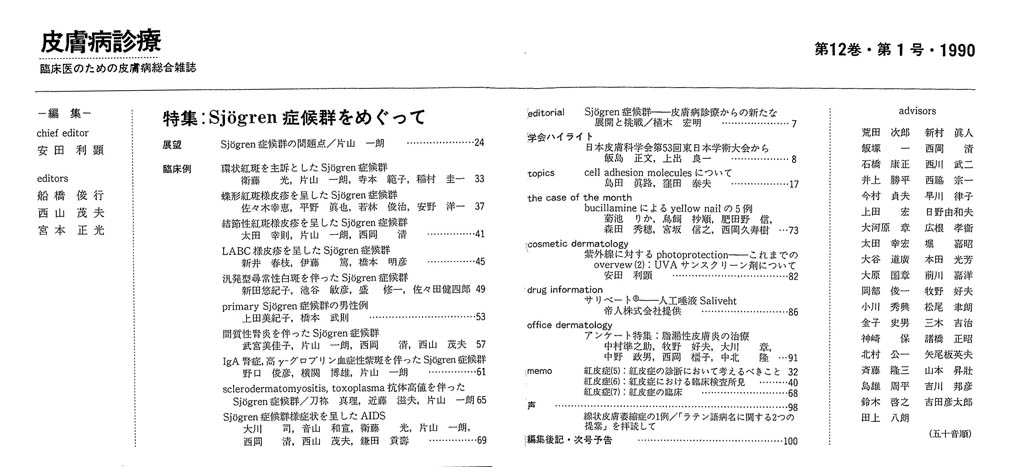

平成28年8月1日
私の一冊 立花隆「宇宙からの帰還」
私の一冊
立花隆「宇宙からの帰還」
日本医事新報 2016.No 4806 pp77
大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学皮膚科学
教授 片山一朗


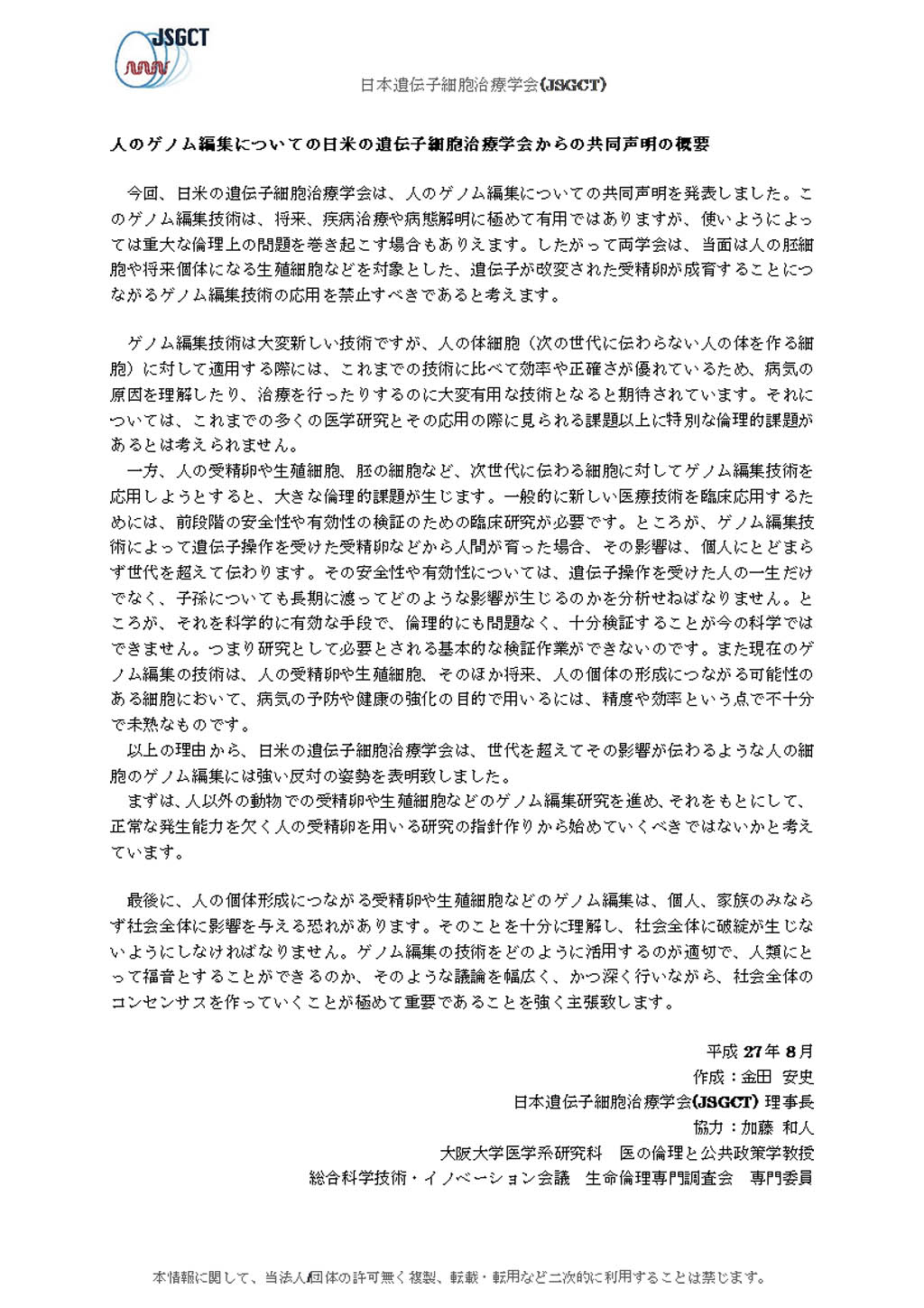
デジタル皮膚科医とアナログ皮膚科学
デジタル皮膚科医とアナログ皮膚科学
大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学皮膚科学
教授 片山一朗
私が教授を務めていた長崎大学の皮膚科の同門会誌は、今年で34号の発刊となるが、第一号よりその編集方針は変わらず、当初より編集に当たられた野北通夫名誉教授の手作りの匂いが今でも残っており、最近は宇谷教授の巻頭言を読むことを楽しみにしている。
今年届いた、最新号のページを捲っていると、タイトルのデジタル皮膚科医に関するN先生の随筆が眼に留まった。K大学のK教授が書かれた記事からの引用という事で、最近の皮膚科学はアナログ的な形態学よりは数値化されたデータに基づくデジタル的な診断が主流になりつつあり、それが先生のご専門領域の縮小化に繋がっているのではという考察である。これは先に、コラムにも書いたAI皮膚科医の話にも繋がるが、将来的にはAIは皮膚科医の形態学的診断能力を軽く超えるようになると予測されている。またN先生の領域に関わらず、皮膚の病理診断学や基礎医学研究などの手法が今アナログからデジタルの世界に大きく変貌しつあり、結果として、アナログ時代の教育を受けた皮膚科医とデジタルしか知らない若い皮膚科医の間に大きな診断的な基盤のずれが生じつつあると考える。こういったことは皮膚科の臨床ではEBMやGLの普及と治療アルゴリズムという形で専門医でなくても診断や治療が可能になりつつある現状を反映しているし、生物製剤、免疫チェックポイント阻害薬の登場による画期的な治療効果はその傾向に拍車をかけているが、診断基準にあてはまらない病態をどう診断し、どう治療して行くかの答えはない。また皮膚疾患はその臨床的な表現が非常に類似しているが、病態、病因は全く事なる「似た者同士の疾患」も多い。重要な事はマクロ、ミクロに関わらず、その疾患がその患者でなぜ、そしてどのような機序で生じたかを考え、鑑別をしっかり考え、最も適切な治療をしていく(あるいは治療しない)決断を下せるか否かであると考える。(AI皮膚科医が治療をしないという選択肢を下せるようになるかは興味があるが、、、、)。基礎においてもアナログ的な解析研究から、高額のデジタル分析器機、試薬の使用や短時間でのマス解析が可能な時代になりつつあり、其の負の部分がSTAP細胞などの問題となって現れている。また先日K大学のA教授と話をしたおり、今後、入院患者を診療できない女性皮膚科医が診療の中心になる時代、どう皮膚科学を継承して行くかの議論になった。先行する米国などの現状を仄聞する限り、皮膚科の重症患者は少数の優秀な皮膚科コンサルタント医が内科、外科に入院した患者の治療方針を決めて行くそうである。そこではEBMと診断アルゴリズムに基づいた医療が行われ、治療は保険会社が加入している保険の種類で決めるそうで、それ以外の高価な治療は自由診療になるそうである。診断がつかない場合、病理や腫瘍医、あるいはリウマチ医など専門医が参加して治療方針を決めて行く。しかしそこから漏れていく、本当に解決すべき重要な問題点が積み残されていくことが危惧されるし、EBMに乏しい最新医療が大手を振って行われるリスクも日々報道されている。

平成28年7月掲載
第48回日本結合織学会
第48回日本結合織学会
平成28年6月24日-25日
会頭:宇谷厚志(長崎大学皮膚科教授)
会場:良順会館(長崎)
大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学皮膚科学
教授 片山一朗


昨年の第67回日本皮膚科学会西部支部総会を会頭として無事終えられた、宇谷厚志長崎大学皮膚科教授が開催された第48回日本結合織学会に参加した。本学会は私が人間的にも、皮膚科医としても心より尊敬する佐野榮春大阪大学皮膚科名誉教授や新海浤千葉大皮膚科名誉教授が関与された学会で、昨年からはマトリックス研究会と発展的統合化されたそうである。(Japanese society for matrix biology and medicine)。私も日本結合織学会の評議員だが、ここ数年以上参加をしていない。ただ、昨年ソウルで開催されたSister society?の9th International Conference on Proteoglycans and 10th Pan-Pacific Connective Tissue Societies Symposiumに招待され、教室の先生方と参加したが、いづれも学会の合同化と皮膚科医の参加が非常に少なくなっているのが印象に残った。私が理事、世話人を務める日本色素細胞学会や日本発汗学会、痒み研究会でも皮膚科の参加者、特に若い研究者が減少し、学会の維持、生き残りに皆さん尽力されているが、なかなか難しい現状である。今回の学会では若い先生方を惹き付けるためのOne minute presentationや若手フォーラム、マイスターレクチャーなどが企画されており、長崎大学皮膚科の若手の頑張りが眼についた。宇谷先生自身、会頭挨拶で以下のように述べられている。
「私は1984年頃大学院時代にマトリックス研究会(コラーゲン研究会)の阿蘇山での会に参加させて頂いたのが初めてでした。その後は、臨床病院に勤務し そのまま留学したため、10年近くブランクが出来てしまいました。帰国後千葉大学皮膚科(新海先生)に就職した1990年代後半からは、毎年結合組織学会 に参加させて頂いていますが、基礎の先生に恥ずかしくない内容を発表したい気持ちで参加してきました。私には専門科の先生と同じレベルで discussionができることは楽しさに、また全く思いつかない側面からの指摘は心地よい良い刺激となっています。このような臨床と基礎の研究者が集うハイブリッド型学会は皮膚科でも数えるほどになりましたが、その意義は非常に大きいです。日頃の解けない疑問を専門科の先生、実験に詳しそうな大学院生に聞く良い機会と思います。以下省略」。是非皮膚科の若い先生方も、宇谷先生の考えられるコンセプトをもう一度考え、研究を行って頂きたいと思う。教室からは院生の小紫先生がモデルマウスを用いた間葉系骨髄幹細胞による強皮症の治療の試みを発表した。あとでF教授から、臨床応用が期待できる研究で、その成果が楽しみとのコメントを頂いた。小紫先生のさらなる頑張りを期待している。

口演する小紫先生

最後に過去の日本結合織学会の会頭(pdf)を記録しておく。
第115回日本皮膚科学会総会
第115回日本皮膚科学会総会
会頭 中川秀巳 東京慈恵会医科大学皮膚科教授
会場 京都国際会議場
会期 2016年6月3日〜6月5日
テーマ —Never Ending Dermatology〜発展し続ける皮膚科学〜
大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学皮膚科学
教授 片山一朗
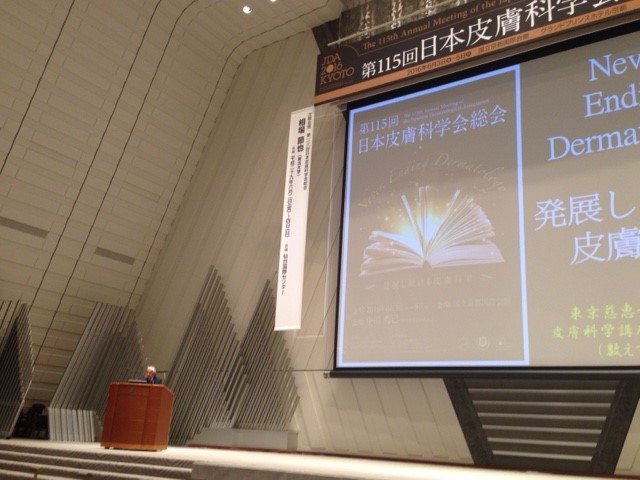
(画像:会頭講演とテーマ)

講演、演題については、私自身、今回委員会、会議、座長が多く、聞きたい演題がフォローできず残念であった。教育講演では、「発汗異常と皮膚疾患-知らないと冷汗かきますよー」での、川崎医大川崎病院の青山裕美先生の「痒疹に対するヘパリン類似物質外用の効果」を興味深く拝聴した。軟膏よりクリームが効果のあること、たっぷり外用することで、ストロンゲストクラスのステロイドが無効であった多数の改善例を紹介された。ラップなどの保湿作用だけでは改善せず、またフロアからの質問で軟膏よりクリームが有効の理由じゃ現時点では不明との答えであったが、クリーム中に含まれる成分のチモールなどの効果なども考える必要があるかと聞きながら考えた。またこれも驚いた報告で、アミロイド苔癬に効果があった例を紹介された。座長の塩原先生のコメントでは外用開始後1W位で組織学的な炎症反応を認め、その後アミロイド沈着も消失するようである。我々も以前トコレチナート軟膏がアミロイド苔癬に効く例を報告したが、同様に一過性の炎症反応を認めた。 (Terao M1, Nishida K, Murota H, Katayama I. Clinical effect of tocoretinate on lichen and macular amyloidosis. J Dermatol. 2011 .38(2):179-84.、昨今、スポンサードシンポやセミナーはメーカの意向が強く反映されるようになり、興味を引く発表が減ったが、今回は若手の登用が多く、好評であった。また従来無かった学際的なシンポも私が担当した「痛みと痒みを解き明かす」やノーベル賞受賞者の大村智先生の講演など7つの特別企画が組まれ、来年以降の総会でも同様の企画の継続を御願いしたくなるような興味深い講演が目白押しであった。
またポスター賞の中でWilliam Epstein賞を教室の加藤健一先生が受賞された。この賞はUCSFの教授で日本とも親交の深かったEpstein教授のご寄附によるもので、過去以下の4人が受賞されている。
第111回総会 江崎仁一先生 (九州大学)
第112回総会 平郡真記子先生(広島大学)
第113回総会 稲葉豊先生 (和歌山医科大学)
第114回総会 三宅智子先生 (岡山大学)
第115回総会 加藤健一先生 (大阪大学)
(島田理事長から賞状を授与される加藤先生)

← 片山 フィギュア
第1回東アジア白斑会議East Asia Vitiligo Society, EAVA
The 7th Annual Meeting of Korean Society of Vitiligo
The 1st Meeting of East Asia Vitiligo Association
Venue: Severance Hospital YUHS, Seoul
President: Seung Chul Lee
Prof. & Chairman Department of Dermatology
Chonnam National University,Gwangju, Korea
大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学皮膚科学
教授 片山一朗
第1回東アジア白斑会議 (East Asia Vitiligo Society, EAVA)が全南大学皮膚科の李承哲教授を会頭としてソウル市で開催され、大阪大学からは片山および壽、楊怜悧、楊飛先生が参加した。

全南大学Lee教授のOpening remarks
私は招待され、「Breakdown of skin homeostasis in the pathogenesis of autoimmune vitiligo」というタイトルで講演した。今、我々が検討している、自然免疫系のNALP1遺伝子の多型による自己免疫性の白斑の発症機序に関し、IL17Aを介するPro inflammatory cytokineの関与、樹状細胞の活性化、そしてロドデノール白斑患者で見られるAutophagyの機能異常の関連性を講演した。
同行した3人の先生方の仕事を現時点で纏めたが、さらに発展した形で論文にできればと考えている。日本からはコロラド大学のSpritz教授のラボに留学され、自己免疫性白斑とClass 1, Class 2 遺伝子のSNP解析で自然免疫系と白斑の発症リスクに関する素晴らしい研究をされた山形大学の林昌浩先生、鈴木民夫教授、そして開業の立場ながら白斑治療に命をかけておられる大阪市の芝田孝一先生が参加されていた。この会は2014年に済州島で開催された第3回東アジア皮膚科学会時に、今回の会頭の全南大学皮膚科教授の李先生、釜山の東亜大学皮膚科教授の金先生などから韓国、日本、台湾、中国の4カ国で東アジア白斑会議を設立しようとの提案があり、第一回のKickoff meetingの開催に至った。アジアからは台湾高雄大学の藍教授、上海復旦大学の Leihong Flora Xiang教授が招待講演を、またソウルで開業されている韓先生、東国大学の李教授が講演された。また合わせて第7回韓国白斑学会が開催された。韓国では白斑学会の会員は200名以上おられるとのことで、特に光線療法の中でエキシマレーザーが盛んとのことであった。一般演題はなく、教育講演が主体で、先ずこの一年間の基礎、臨床のトピックスをそれぞれ一名の先生が国際誌から取り上げ、丁寧に解説された。白斑研究の進歩を短時間で理解することができ、日本でも是非取り入れたい企画プログラムである。それ以外の6つの教育講演は全て、臨床が主体の講演であり、白斑診療に力を入れている韓国の開業の先生からの質問があいつでいた。日本で近年、施行件数が増えているエキシマライトは韓国では保険がエキシマレーザーのみ認可されており、その器機管理や高額な値段が日本では受け入れにくいようで、台湾では、エキシマランプ治療が国立大学しか認められておらず、また施行回数が10回までと決められており、各国での事情があり、またConsensusを得る必要があると感じた。

ソウルで開業されている前々韓国白斑学会会長の韓先生の挨拶
手前は前会長の東国大学の李教授
いづれにせよ、白斑の研究、臨床、美容ともに東アジ諸国の韓国、台湾、中国は大変Activeで若い医師の参加も多く、日本でも活発な活動を展開していく必要性を感じた。次回の第2回大会は2018年に私が会頭を務めることになり、大阪で開催する予定である。今後EAVAのHPが立ちあがるまでは、日本色素細胞学会のHPに最新情報をアップさせて頂く予定である。


設立メンバーの先生方と
平成28年4月掲載
第32回日本臨床皮膚科医会・臨床学術大会
第32回日本臨床皮膚科医会・臨床学術大会
2016年4月23日〜24日
会頭: 佐藤 淳
会場: 岡山コンベンションセンター
大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学皮膚科学
教授 片山一朗


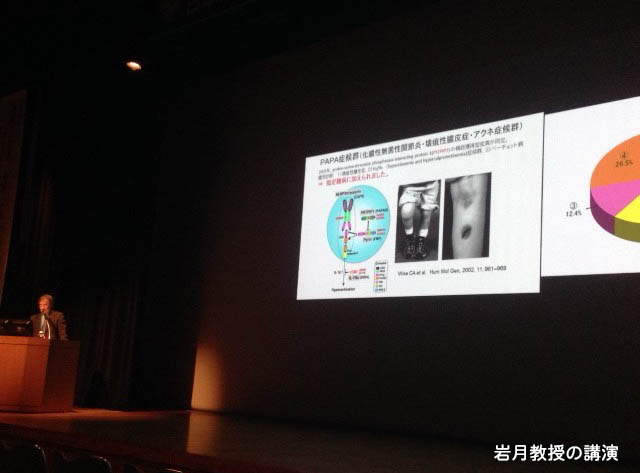
私が担当したDerma Live 2「皮膚科医の眼の値段2016年:見逃しやすい皮膚腫瘍」は共同座長の和歌山医大の山本有紀先生にイントロダクションを担当して頂き、次いで福島医大の山本俊幸先生に「赤い結節、黄色い結節」、大阪市の谷守先生に「リンパ腫」、大阪大学の種村篤先生に「黒い結節」を講演して頂いた。特に谷先生は長年大阪大学医学部皮膚科学教室で担当された悪性リンパ腫患者の臨床を騙し絵を例にとり、一面的な見方の危険性を強調された。近年アトピー性皮膚炎や乾癬の治療経過中に悪性腫瘍やリンパ腫が出現する例が報告されているが、谷先生は慢性の患者さんでは必ず全身の皮疹を観察し、異常な皮膚表現のさらに異常な皮疹が見られる場合には必ず生検をすることの重要性を指摘された。
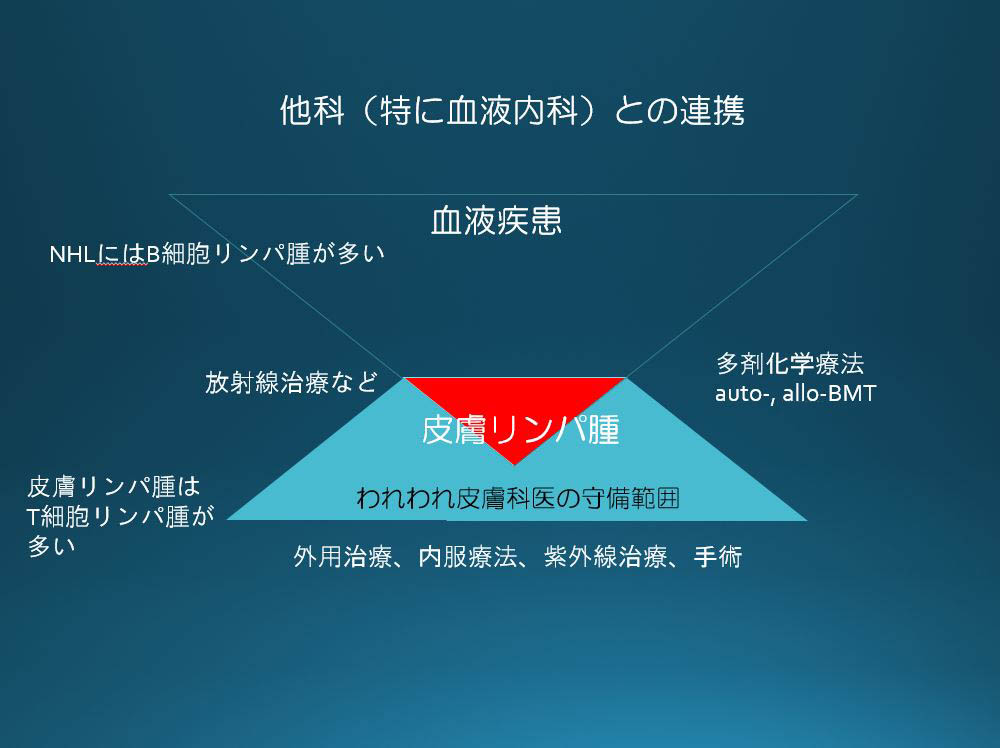
リンパ腫診療における他科との連携 (谷先生)
翌日は「そうだったのか!!この皮膚病変〜以外な原因、病理、合併症」(座長:浅井俊也、山本俊幸先生)で日本医大の安斎眞一先生の「〜以外な皮膚病理」を拝聴した。二種以上の腫瘍が一つの切片に現れるCollision tumorは参考になった。また臨床的には定型的な結節性痒疹で組織学的にEosinophilic spongiosisやVacuolar degenerationがあり、通常の痒疹反応とは異なった像を呈した症例を提示された。その時は主治医がDIFをオーダーしており最終的にPemphigoid nodulariisと診断されたそうである。このタイプはBP180抗体価が比較的低いそうである。私自身痒疹は興味がある疾患で、このタイプではIgEクラスのBP180抗体がでやすいのか、また発症に好塩基球(防衛医大佐藤教授 Hashimoto T et al. J Immunol 2015)が関与しているのか質問したが、今後検討したいとのことであった。Listen to neighbors 4「今知っておきたい感染症の最新の話題」で、岡山大学の山崎修先生は最近、市中感染型MRSA感染症でPanton Valentine 型のロイコシジン産生菌が増加し、基礎疾患のない健常者間で深部の皮膚感染症を繰り返す事が問題になっていることを講演された。我々はMSSAが証明され、両親、患児、妹の家族内で癤症を繰り返す症例を経験しており、その対策をお聞きしたが、なかなか有効なものはないとのことであった。
本学会は企画が大変すぐれ、ユニークな構成であり、参加された先生方も 十分満足されたことと考える。なおポスター賞に林美沙先生の「爪乾癬と関節症性乾癬に対する超音波検査の有用性」が選ばれ、懇親会の席で表彰された。特に乾癬の爪病変の病因を関節エコー所見で分類され、光線療法、外用療法さらに今後の生物製剤の適応を考える上で大変有益な臨床研究であり、高い評価を得られると考える。

林先生、江藤先生(東京逓信病院皮膚科部長)と懇親会にて
2016年、新人歓迎会。「考え、想い、創造する」
2016年、新人歓迎会。「考え、想い、創造する」
大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学皮膚科学
教授 片山一朗
今年も、新しく皮膚科学を生涯の職業とされる先生方を迎える季節となりました。2004年にスーパーローテートシステムが導入され、来年からは先行きは不透明ですが、後期研修医制度の開始にともなう研修プログラム作成が基盤18学会で進行しています。今年は7名の方が大阪大学皮膚科と、その関連施設で研修を開始されることになっており、4月6日、歓迎会を銀杏会館で開きました。教室、関連施設に、新しい活力をもたらして頂けるかと期待しています。

先に述べた最近の大きなニュースとして人工知能(Artificial intelligence)が絶対勝てないと考えられてきたプロの棋士を敗ったという記事がありました。クローン人間、宇宙エレベーター、ロボットなど次々とSFの世界が現実化しつつあり、その中で日本では手塚治虫、星新一、海外ではフランス、ナント市で生まれたジュール・ベルヌが彼の作品の中で予測した事の多くが実現しています。特にベルヌは「人間が想像できることは、人間が必ず実現できる」という有名な言葉を残し、世界中の少年少女に夢と希望を与えました。同様に、元大阪大学総長の山村雄一先生が残された、「-夢みて行い,考えて祈る-」は多くの若い医学者に研究する事の厳しさと、面白さを伝えています。
今年、新たに皮膚科医の道を選ばれた先生は、大きく制度の変わる時期の中での選択でもあり、時代の流れを肌で感じ、皮膚科医として生涯をかけられる病態、疾患を見つけ、楽しい皮膚医生活を送って欲しいと心から思います。難治性の皮膚疾患はまだまだ多く残されており、立体画像の送信などの進歩が予想される人工知能医に負けない、人にしかできない技量を持つ皮膚科医として、臨床であれ、研究であれ、考え、想い、そして何かを創り出して頂く事を願って、歓迎の言葉とします。

新人と大学スタッフ 2016.4.6
人工知能(AI)と皮膚病診断
人工知能(AI)と皮膚病診断
大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学皮膚科学
教授 片山一朗
先日「ヒフミル君」という、ウェッブ上で皮膚疾患の診断を行うアプリが広まっていることを聞く機会があった。その時の議論で、このような画像診断やウエッブ治療の可能性に関しては今後、国の政策医療として進められる事も予測されており、その裏付けとして人工知能(AI)が今まで不可能と考えられていたプロの棋士に勝ったという報道がさらに拍車をかけるのではと思うのは私だけではないと考える。実際、「メミル君」という眼科用アプリも利用が増えているようで、いづれも開業医への影響を懸念する声を聞く。他方、学会などが中心になり、本当の皮膚科専門医が対応すれば、皮膚科医不在の離島やマンパワーの不足する地域への強力なサポート体制を構築できるという意見もある。実際、今のネット通信技術の進歩は立体画像や匂い、香りなども送受信可能な日が近い事を予測させる。また病理画像やダーモスコピーなどもその解析ソフトの進歩と合わせ、ある程度の皮膚疾患の診断や治療に応用が可能になるかと考える。このような技術の進展に呼応するように、診断ガイドラインとアルゴリズムが多くの皮膚疾患でも作成され、患者情報の入力により診断が可能になりつつある。特に乾癬のバイオ治療や黒色腫の免疫チェックポイント阻害薬が極めて有効であるエビデンスが集積しつつある現在、診断さえつけば、後はウエッブ上で指示を出す事も可能になりそうな時代になった。チャペルヒル分類を下に作成されている皮膚の血管炎の診断アルゴリズムを例に取ると、先ず抗体や免疫グロブリン、クリオグロブリンなどの検査結果から診断プロセスが進み、それらに合致しない場合、炎症の深さで皮膚白血球破砕性血管炎と皮膚動脈炎の2つに分けられるらしい。うまく機能すれば
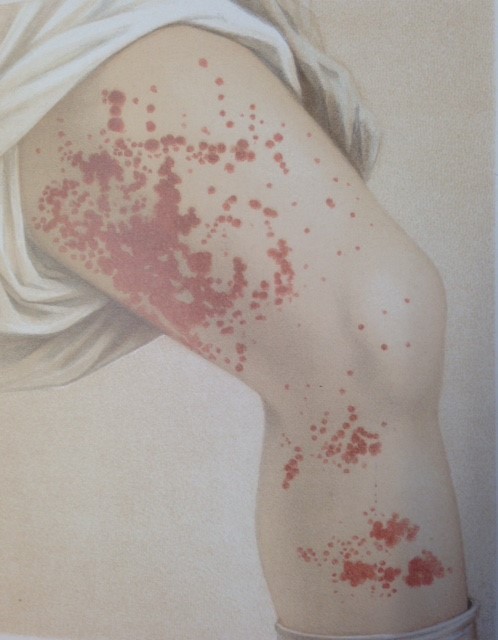
Purpura simplex
Duhringのカラー図譜 (1876年版より)
第98回日本皮膚科学会大分地方会藤原作平大分大学皮膚科教授退任記念地方会
第98回日本皮膚科学会大分地方会
藤原作平大分大学皮膚科教授退任記念地方会
「生涯一研修医」
日時:平成28年3月5日(土)~6日(日)
於: 大分県労働福祉会館
大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学皮膚科学
教授 片山一朗
藤原作平教授の退官記念地方会に出席した。前日に祝賀会が開催され、その席で多くの先生から、「無事退官」を労う多くのスピーチがあり、いかに藤原先生が多くの方から愛されておられたか良く理解できた。また先生にとっても教授生活を終えられる時間を多くの方と共有できる喜びが会場に溢れる良い会であった。その中で藤原先生を表す3つのキーワード「生涯一研修医」、「入浴は月1度」、「禁!!!、整理整頓教授室」にまつわるエピソードが多くの先生から紹介された。先生の臨床、研究に対する真摯な姿勢や厚いレンズの眼鏡を通して物事を直視されるその風貌と、実際の日常生活での物事にこだわられない行動の乖離が極端で、真面目であれば、あるほど、微笑ましい思い出として大分大学皮膚科の歴史となって残されてきたことが随所で披露された。実際、守山正胤医学部長からは藤原先生が多くの学生さんの人気を集め、また患者さんの女性フアンも多かったことが述べられた。
藤原先生は1980年に大阪大学から初代皮膚科教授として赴任された高安進先生の後任として2001年に第2代教授に就任された。高安先生と同時に助教授として着任された新海浤千葉大名誉教授を慕われ(細胞外マトリックス研究の子弟関係)、東京医科歯科大学難治疾患研究所、神戸大学内科を経て昭和61年に大分医大皮膚科に着任されたそうである。

1980高安進大分医大皮膚科教授就任壮行会
右から佐野栄春大阪大学教授、高安進助教授(当時)、新海浤先生、中村俊孝先生、板見智先生

今回の退官記念地方会でも全ての演題にコメントをされており、今や絶滅危惧種といっても良い、教育熱心な教授である。また藤原先生が大分医大教授に着任後より開始された皮膚がん検診は、今年3月26、27日にも実施されるが、その中で藤原先生が見いだされた家族性のElastofibroma(弾性線維腫)は稀な腫瘍であるが、その特異な組織像と肩甲骨の下床に発症しやすいこと、などが特徴とされ、この腫瘍が沖縄のある地域に好発することから、千葉大予防医学センター教授の関根章博先生と疫学研究を開始されている。その成果はこの退官地方会でも「弾性線維腫の大家系パラメトリック連鎖解析による原因遺伝子の探索」として関根教授から紹介された。ただもう少し母集団が必要なことや正確な診断が要求されるそうで、遺伝子の特定には至っていないそうである。

、そして岡山大学を中心とする中国地方でのメラノーマ診療ネットワークシステム構築の進行状況を話された。免疫チェックポイント阻害薬は肺の非小細胞性肺がんにも適応が拡大され、有効例がふえているそうで、今後いつまで治療を継続するか、高額な医療費をどう賄って行くが大きな問題となってくるかと思われる。
藤原先生には、あらためて30年間の単身赴任生活にご苦労様と申し上げるとともに、大阪に戻られた時にはまた皮膚科学を一緒に楽しませて頂きたいと心より思う。
第21回アトピー性皮膚炎治療研究会プログラム
第21回アトピー性皮膚炎治療研究会
テーマ:「治せないアトピー性皮膚炎」
平成28年2月27日-28日
会頭:片桐一元(独協医科大学越谷病院皮膚科教授)
会場:ソニックシテイ(大宮)
大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学皮膚科学
教授 片山一朗
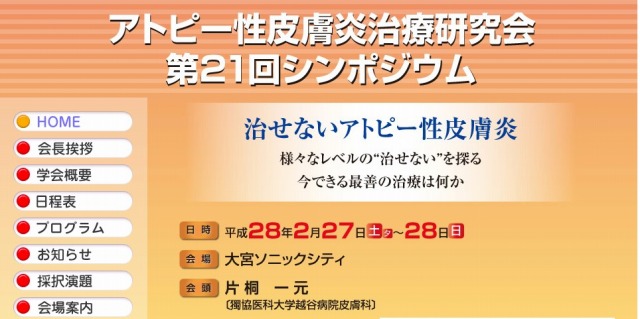
長年、代表世話人を務めてこられた青木敏之先生が退任され、最後の会となる21回のアトピー性皮膚炎治療研究会に参加した。昨年の鳥羽の会までは指定演題が中心で一般演題は殆ど公募されなかったが、今年はスポンサードセミナー以外、34題が口演され、お一人の持ち時間8分(予備時間は取られていた)で活発な討論が繰り広げられた、
開会の挨拶で片桐先生が、「他の学会でも昔の学会と同じ事が解決されないで、論議されており、この研究会でもアトピー性皮膚炎の何が解決され、今出来る最善の治療が何かを討論したい」との考えから、テーマを「治せないアトピー性皮膚炎」とし、「どこが問題なのかを浮き彫りに出来れば」と考えられたそうである。もちろん、初日は「治すぞ、アトピー性皮膚炎」という魅力的なテーマで16題の意欲的な口演があった。
今まで多くの会で治せないアトピー性皮膚炎の病態を聞いて来たが、大体10〜15%位の患者さんはどのような治療をしても治らない、あるいはすぐに再燃するようであり、その病態解明が望まれてきた。その中で医療の現場に来ない、あるいは引きこもりの方がどの程度おられるか不明であり、その中に西洋医学やステロイド忌避の方が難治例として多くおられることが予想されてきたが、最近は少しその数が減少してきているのではと考えている。会を通じて治せない症例として提示された多くの症例は紅皮症に近い方で、多くは粃糠様の鱗屑と乾燥が目立つようで、ステロイドやシクロスポリンの十分な治療でコントロールが可能となるが、減量や中止で容易に再燃するようである。外用できない何らかの理由(実際は外用していない例もある)がある方やペットなど悪化因子の回避が不可能な患者さんも難治となることが報告されていた。そのような難治例の背景に発汗低下が大きな要因となっている可能性を塩原先生が指摘された。レプリカ法による詳細な発汗機能の検討で、角質の水分保持には皮溝への発汗、体温調節には皮丘性の発汗が重要であり、アトピー性皮膚炎で慢性期の発汗低下が皮膚乾燥の大きな要因となり、汗孔の閉塞や汗管からの汗の漏出がその大きな原因であること、保湿剤の適切な外用で改善することを明確に示された。代償性に発汗過剰が見られる場合もあり、その場合は汗そのものの刺激で悪化する可能性もあるとの事である。ただアトピー性皮膚炎の真皮深層から脂肪織には目立った炎症がないのは事実で、汗孔の閉塞を一義的に考えると持続性の汗の漏出がどのような皮膚の組織反応を起こすかの検討が必要とは考える。また角層水分量測定装置が患者指導に有用であること、皮膚乾燥を的確に是正する皮膚科医としての眼が何より重要であることを強調され、バイオマーカーやGLのような他科の医者が容易に利用できるツールのみに依存する治療の危険性を指摘された。私も難治例の方は発汗低下が主体で全身の潮紅、乾燥、時にデッキチェアサインなどが見られる事、その治療に発汗指導や適切な外用が有益ななことは報告している。また今回の症例報告を聞いて汗を含めてまだまだ悪化因子の検討が不十分である事も感じた。これは塩原教授も指摘されていたが、診察医が毎回変わるような大學や基幹病院では原因アレルゲン、悪化因子の吟味はなかなか難しいことが多く、むしろアトピー性皮膚炎を熱心に診療され、長期に患者指導されている開業の先生こそが明らかに出来るのではと考える。接触皮膚炎、ペット、食物、汗、入浴法、不適切なスキンケア、外用法などの是正で驚く程改善する例があるのは良く経験する事である。ステロイド外用薬の適切な使用法や副作用の回避などは今まで多くの議論が重ねられてきたが、やはり今回の発表でもその長期使用で効果が減弱する例や不規則な使用とその中止、内服ステロイドの併用で一時的な悪化やコントロール困難になる例が発表されていた。AAD(米国皮膚科学会)からも最近のGLでは内服ステロイドの副作用が強調され、外用に関してはしてはあまり触れられていない。Hanifin, SimpsonらによるJAADの論文ではSteroid withdrawalのsystematic review
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/25592622/) が報告されており、Evidenceには欠けるが、外用ステロイドの不適切な使用による重要な副作用であり、その発症には十分な注意が必要と記載されている。ネオーラルに関しても従来の治療に反応しない重症の成人例(使用は16歳以上で最大12週で中止あるいは休薬期間を設ける)とGLに書かれているが、実際には中止できない、あるいは継続使用により副作用が見られる症例も経験している。GLには書かれているが遵守されていない事例やその逆も見られ、今後の検討が必要かと考える。現在、乾癬、メラノーマの分子標的薬が皮膚科の中で一般的に使用されるようになり、ネオーラル同様、今後登場してくる高価な分子標的薬の恩恵を受けられる患者と受けられない患者が重症のアトピー性皮膚炎治療でも起こるかと考える。本治療研究会での議論を基盤として本当に治癒できない、あるいは治癒しない患者の病態把握が何より重要であり、その意味で塩原先生の提示された、悪化因子としての汗対策や難治例での血液検査、GLにとらわれない診療、そして発疹を見てその病理像、病因、検査異常が思い浮かべられる皮膚科医としての眼の重要性と教育の必要性を再確認した。大阪大学からは室田先生が「汗対策による改善効果」、林先生が「アトピー性皮膚炎とリンパ腫の問題」、片山が「ステロイドの問題」、村上先生が「最重症の双子の患者さんの10年に亘る治療経過」を報告された。村上先生のお母さんとの協力や学校との度重なる交渉には本当に頭の下がる思いで発表を聞かせて頂いた。座長の片桐先生のこのような最重症の患者さんの長期の診療で、「折れそうになる心」をどう維持されてこられたのかという村上先生に対するコメントは、心から共感した。あわせて不可能とも思われる、このような患者さんの悪化因子を一つづつ解決していくことで、副作用を生じない治療が可能になることをあらためて認識した。早期に強力な治療を行えばこのようにならなかったという座長の片岡先生のコメントは、先生ご自身が似たような症例をたくさん経験されてきたからこその励ましのコメントと受け止めさせて頂いた。最後になるがこの会の代表世話人として我々を指導して頂いた青木先生には会員を代表して心よりお礼を申し上げる。

演者:波多野先生(大分医大)、座長:片桐、片岡先生
→アトピー性皮膚炎治療研究会プログラム第21回シンポジウム(pdf)
2016年2月
第79回日本皮膚科学会東京・東部支部合同学術大会
第79回日本皮膚科学会東京・東部支部合同学術大会
会頭 鈴木民夫山形大学教授 坪井良治東京医科大学教授
会場 京王プラザホテル
会期 2016年2月20〜21日
テーマ —皮膚科学いろいろ—
大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学皮膚科学
教授 片山一朗

-

坪井良治東京医大教授
-

鈴木民夫教授とSpritz先生
第79回日本皮膚科学会東京・東部支部合同学術大会に参加した。元々東部支部学術大会は東部支部(東日本)と東京支部が回り持ちで開催されていたが、
1990年の54回大会(杏林大学・長島正治会頭)を最後に発展的に解消し、翌年からは東京支部総会と東部支部学術大会、別個に開催されることとなった。今回25年振りに合同大会が開催される運びとなったが、その理由として大会長の鈴木民夫教授は会頭挨拶の中で以下のように述べられている。
①東部支部は地理的に広大であり、地方から地方への移動は想像を絶するほど時間がかかること。例えば、山形市から隣県の秋田市、新潟市にはそれぞれ4時間半、3時間半かかること。一方で、東京は日本中どこからも最も近い都市であること。②東部支部は会員数が最も少なく、財政面で不安があること。③近年、金 太郎飴の様な同じような内容の学会が多いことから、学会や研究会の数を減らして独自性の高い学術大会にした方が良いでのではないかと考えたこと等の理由に より東京支部に対して共同開催をお願いしました。
実際今回参加して、驚いたのは一般演題が4会場に分かれ、2日間に亘り発表されたことで、討論時間も充分にあり、久しぶりに学会らしい質疑応答を楽しむ事ができた。座長も開業医の先生も含め、東部、東京支部からその分野の若手、ベテランの先生をうまく組み合わせておられ、有益な討論を誘導されていた。昨今、地方会もふくめ、専門外の先生が役職指定で座長をされる学会も多く、討論が噛み合ない事も多いが、プログラム委員の先生方のご尽力と両支部の人材の豊富さが良く反映されていた。また意表をつくプログラムとして一番広いA会場で「皮膚科医が必要な他科の知識」として2日間、教育講演が行われた事で、しかも講演ビデオが今後暫く学会HPで閲覧できるとの事である。これは坪井会頭の発案とのことで、今後、他の学会でも取り入れて頂きたいと思う企画である。またもう一つの企画は鈴木民夫会頭の専門である色素異常症のシンポジウムがこれも2日間に亘り開催されたことで、大会のテーマ通り「いろいろ」な意見があるかとは考えるが、大会長の個性が出せなくなりつつある今の総会のあり方とは180度異なるプログラム運営で、私自身、考えさせられることが多かった。
招待講演は国際交流講演2でコロラド大学のRA Spritz先生が自己免疫性白斑のGWAS解析の最新のデータを紹介された。Spritz先生は鈴木民夫会頭が留学された時のボスで今回は鈴木先生のお弟子さんで、つい先頃Spritz研から帰国された山形大学の林昌浩先生のデータも紹介された。研究に関するシンポジウムは「微生物と上皮の相互作用、Microorganism V.S. Barrier」として資生堂の日比野さんやNIHの永尾さんの最新の成果を聞く事ができ、また臨床に置いても診断に手こずる皮膚疾患などがシンポジウムとして組まれ、参加されたそれぞれの先生が本大会を心から楽しまれた事と思う。大阪大学医学部皮膚科学教室からは亀井利沙先生が「難治性偽性腸閉、嚥下障害に対して免疫グロブリン大量療法(IVIG)が奏功した強皮症、多発性筋炎オーバーラップ症候群の一例」、楊伶俐先生が「ロドデノールの表皮ケラチノサイトへの作用」を発表された。お二人とも良く勉強されており、質疑応答も重要な問題点を適格に討論され、多いに感心した。

懇親会では鈴木民夫会頭の顔で集められたという山形の[十四代]を始めとする銘酒や米沢牛、芋煮、山形蕎麦など山形の特産品がふるまわれ、学生さんによる花笠音頭などアトラクションも素晴らしかった。例年この時期は雪による交通マヒが多く、一昨年の大会が思い起こされたが、3,000人を超す参加者が全国から集まられ、無事、大成功の内に大会を終えられた両会頭の先生にお礼を申し上げたい。
最後に、手元にあった最後の合同地方会となった54回大会時に杏林大学の長島正治先生が発刊された「東日本学術大会 半世紀の歩み」に当時のプログラムが掲載されており、私の名前を見つけたので記録に残した。
第39回皮膚・脈管膠原病研究会
第39回皮膚・脈管膠原病研究会
会場:高知市文化プラザかるぽーと小ホール
会長:佐野栄紀 高知大学皮膚科教授
会期:2016/1.22-1.23
大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学皮膚科学
教授 片山一
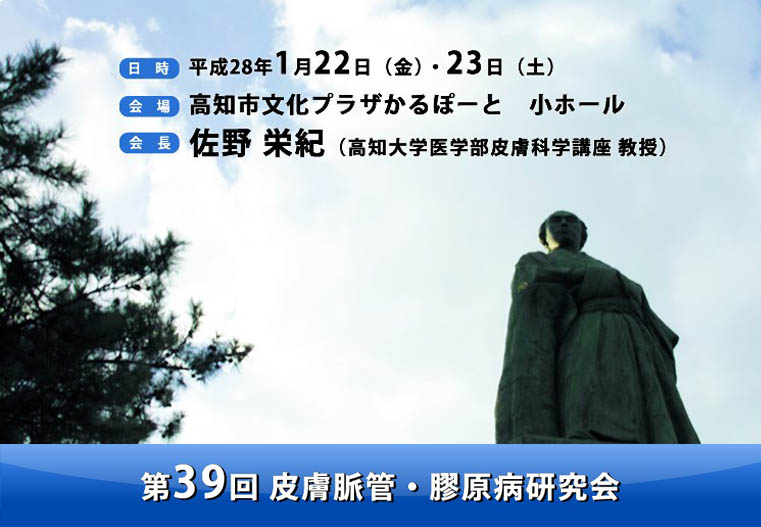

佐野栄紀教授 中島英貴事務局長
今年の第39回皮膚・脈管膠原病研究会は小玉肇高知医大(現高知大)名誉教授が平成12年に高知城を会場に開催されて以来16年ぶりの四国、高知開催であった。この会の前身はもともと故安田利顕東邦大名誉教授(元日本皮膚科学会理事長)が西山茂夫北里大学名誉教授を中心に当時、膠原病や血管炎、血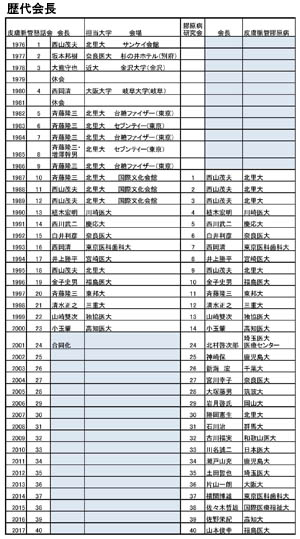
2016年1月
2016年を迎えて:Dermatology Classics
2016年を迎えて:Dermatology Classics
大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学皮膚科学
教授 片山一朗
皆さん輝かしい新年を迎えられ、今年、一年の夢に満ちた計画や皮膚科診療に関する新たな抱負を考えておられることと思います。
私も、2004年に大阪大学に着任した時の定年が今年3月末の予定でしたが、さらに2年間、今の仕事を継続できることになりました.年頭にあたり、私なりに次の2年間をどのように過ごしていくかを考え始めました。
それとは別に最近の臨床や基礎の学会、研究会に参加して感じることは、皮膚科あるいは専門分野である基礎研究で本来、常識として知っておくべきことやたかだか、20〜30年前のことを知らない、あるいは勉強していない方が増えていることです。ある先輩の先生の嘆きで、SyphilisはもちろんLuesといっても話が通じない、あるいはpapuleとnoduleの使い分けができていないなどの話は良く聞きます。また自分自身どんな疾患を治したいのか、その疾患のどのような病因論の解明に興味があるのかなどが伝わってくる発表が少なくなっていると感じているのは私だけではないと思います。これらの理由は複雑ですが、結論としてはある時期から個々の皮膚科教室の伝統、歴史が継承されなくなったことが最も大きいのではと考えています。
そのような中、新春を迎え、卒後20数年経過した今、リハビリ科の後期研修医に転科したという、ある先生から賀状を頂きました。褥創治療のために栄養学を一から勉強したいという強い思いからの決断だったようです。また尊敬する岸本忠三先生のリレーエッセイの中に、ある学生から「先生、、、、われわれは、もうすることないんと違いますか。何をしたら、ええんやろうか……」と聞かれ、「そやけど、考えてみると、まだ治ってない病気がいっぱいある。何で起きるのか、分からん病気もいっぱいある。それを研究し、治療法を見付けていくことを考えたら、いくらでもやることはあるで」と答えられ、さらに「せっかく医学部に来たのだから、ちゃんと30歳まで医者をやれ」一生懸命に医学を勉強し、医師の仕事をやれば、必ず疑問が出てくる。治療法がない病気を目の前にし、それを治したいと思うことから研究は始まる」とも言われたそうです。私も、皮膚科を志望した理由の一つが当時全く、原因も不明で、治療もない白斑という疾患を治したいということでした(皮膚科医になり32年目頃ようやく白斑の病態研究を開始する事が出来るようになりました)。また卒後7年目位で出向した病院の指導医の先生が膠原病の専門家で患者さんの皮膚症状から始まり、全ての臓器障害の診断と治療を一人でやっておられ、本当に凄い先生と思いました。その後、恩師の西岡先生の研究テーマの強皮症の班研究をお手伝いし、また北里大学で西山茂夫先生のもとで膠原病を一から勉強する過程で、私なりの膠原病診療の基礎を作れたと思います。若い先生も是非、新しい出会いを大切にし、自分のやりたい事を見つけ、興味ある疾患に関しては誰よりも自分が一番良く知っている、必ず治す位の気持ちを持って診療、研究をして頂きたいと思います。そこからが本当の皮膚科医のスタートになると考えます。
話は急に変わりますが、数年前から、入手が困難な昔の皮膚科領域の原著論文を訳し、”Dermatology classics”として若い先生に読んで頂こうというプロジェクトを西岡先生、岡山大学の岩月教授、東京医科歯科大の横関教授、故三橋善比古東京医大教授とで始めました。残念ながら三橋先生が他界され、ドイツ語版が少し遅れていますが、英語版がようやく発刊の目処がつきました。フランス語版はすでに岩月先生が一昨年の日本皮膚科学会の記念事業として刊行されました。(ちなみにこの本により私も、Prurigo Besnierに関するベニエの原著を初めて読ませて頂きました)。その過程でプロジェクトの中心となる西岡先生と入手が困難な教本を求めてOxford大学やRoyal college of Surgeons, St Bartholomew’s, Hospital, Royal College of Physicians などの図書館を訪問し、旧い貴重な資料を目にする機会を得ました。そして150年〜300年前の原著や教本を読まして頂き、当時の先生がいかに良く皮疹を観察し、その成因、病態を考えておられたか再認識しましたし、現代に生きるイギリスの皮膚科の先生方と話をすると、そのような旧い時代の古典皮膚科学とでも言うべき疾患やその時代の背景が当たり前のようにでてくる事にも驚き、長い歴史に裏打ちされた皮膚科医と同じ土俵で戦う事の難しさも感じました。免疫学の分野でも2000年代に入り、抗体療法や免疫チェックポイント薬、シグナル伝達阻害薬などが次々登場し、一昔前までは治せなかった疾患や悪性腫瘍も治す事の出来る時代になりました。その背景には1960年台から70年代に大きな研究テーマであったSuppressor cellやDendritic cell、Macrophage、Basophilの基礎的研究が再びヒトで再検討されるようになりRegulatory T cellやInnate immunityの治療への応用が進んだ事も大きいと考えます。
皮膚科の臨床でもその膨大な歴史をもう一度良く見直し、何が解決されていないか、どのような治療が応用可能か考え、そこからまた新しい病態研究や治療の開発を始めて行きたいと考えます。

John Hunter像(Lincoln’s Inn Fields, Royal College of Surgeons)
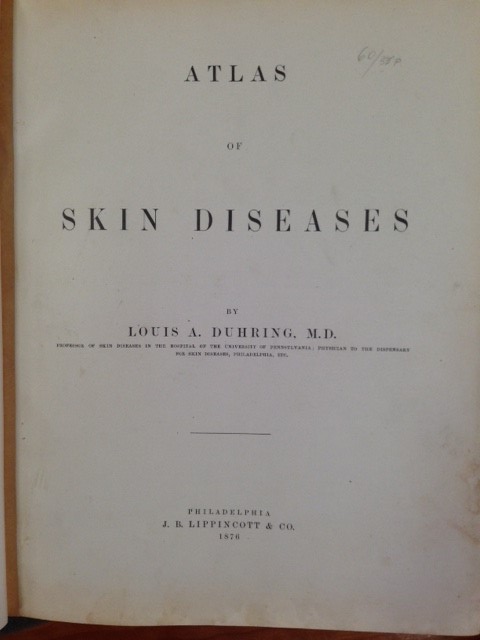
Duhringのカラー図譜 (1876年版、ライアン博士個人蔵)
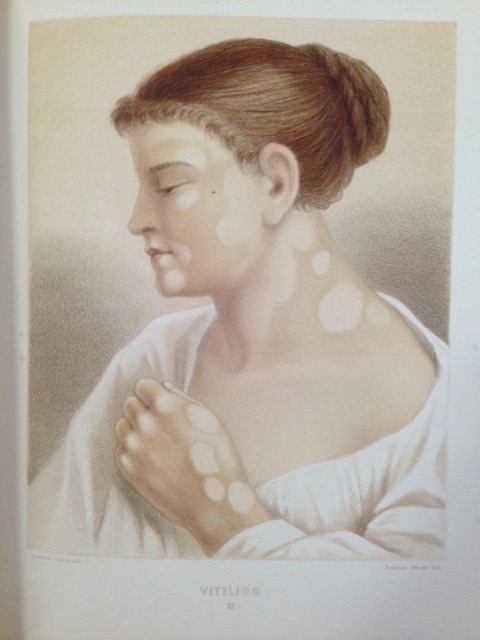
白斑患者図(Duhring の図譜より、ライアン博士個人蔵)
2016年1月
第40回日本研究皮膚科学会(JSID)
第40回日本研究皮膚科学会(JSID)
会長:岩月啓氏岡山大学皮膚科教授
会場:岡山コンベンションセンター
会期:2015年12月11日−13日v
大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学皮膚科学
教授 片山一朗
第40回日本研究皮膚科学会(JSID)が岩月啓氏岡山大学教授を会頭として開催された。大会テーマは「Advance Dermatology through Science」とされ、1 minute presentationなど新しい試みがなされ、若い先生が発表できる機会を与えられた。この形式の発表は大変評判が良く来年以降も継続されるそうである。
また海外からの多くのゲストが参加されていたが、最終日のIntractable skin diseasesの国際シンポジウムや汎太平洋皮膚バリア研究会(6th PAPSBRS)などうまく共催されたことの成果で岩月教授のアイデアがそこかしこに見られ、大成功の学会となった。私は11日朝にロンドン出張から帰国し、そのまま参加した関係でJSIDのセレモニー関連の講演は聞けなかったが、Kisaragi Awardを受賞された神戸大学皮膚科の福元先生のお仕事は多いに評価されていた。Tanioku Memorial LectureはIIDでSID理事長を務められたハーバード大学のThomas Kupper 教授が「T cells in barrier Tissue:new insights」というタイトルで講演された。皮膚に常在するメモリーT細胞TRMの講演だったそうで、皮膚というバリアの最前線に存在するメモリーT細胞による効率定な皮膚などバリア臓器での免疫システムのお話で感染症、腫瘍免疫、自己免疫疾患の発症など今後大きなブレークスルーの期待される分野で、我々の研究している皮膚細胞のステロイド産生と対をなす研究かと考える。
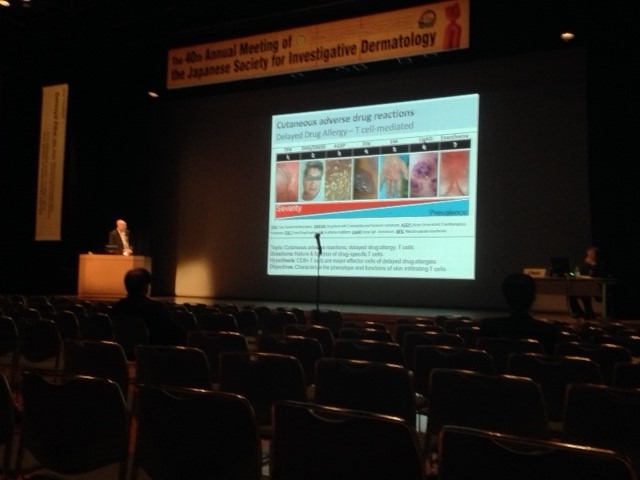
リヨン大学Jean-Francois Nicholas教授と座長の岩月教授。
大阪大学医学部皮膚科学教室からは金田、室田、荒瀬、楊怜悧、越智、小野、加藤、楊飛、松村の各先生が演題を発表され、そのうち室田先生は「Artemin-administered mice develop thermohyperesthesia of skin via central sensitization to heat」、楊怜悧先生は「Disruption of the autophagy-lysosome pathway is involved in hypopigmented macules in patients with tuberoussclerosis complex」の演題でPlenaryに選ばれ、質疑応答も活発であった。
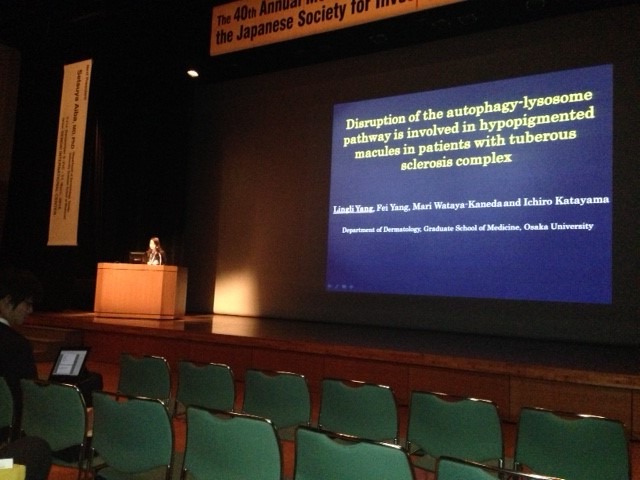
楊怜悧先生のあらたな領域の展開が期待された講演。海外の方からの質問などにも明確に答えられていた。

質問者が列を並べた室田先生の講演。
越智先生、松村さんが発表されたサンダルウッドに関する研究は資生堂RCの伝田さんから、これから大いに発展が期待される素晴らしい研究とのコメントを頂いた。お二人の今後の研究の進展に期待したい。また楊飛先生の「Diminishing sweating in patients with tuberous sclerosis and the relationship to mTOR signaling pathway」は学会終了後、大阪大学でセミナーを行って頂いたリヨン大学皮膚科のJean-Francois Nicholas教授から大変面白い発展が期待される研究との評価を頂いた。荒瀬先生のP04-05 [C12-04] 「Presence of anti-β2GP1/HLA-DR complex autoantibodies in the non-APS patients with recurrent limb ulcerations」は自己抗体の新たな産生機序に関する研究で、多くの質問を受けられていたようである。また加藤先生が発表の機会を貰ったL-14 「 B-1 B cell progenitors transiently and partially express keratin 5 during differentiation in bone marrow」は小豆澤先生、花房先生とこの5〜6年検討されてきた研究であり、今東京医科歯科大学の講師として暫くの単身赴任で活躍中の花房先生が帰阪時の休日返上の実験でようやく納得できるデータが得られ、発表となった研究であり、指導された小豆澤宏明先生の地道な研究がさらに発展することを願う。今回は発表された先生方皆さん、それぞれの分野で大きな評価を得られたようで、引き続き大阪大学のパワーを発揮して頂きたい。ただ全体としては、私の理解不足が大きな要因ではあるが、今回口述講演を聞いた範囲では、次の研究をリードするようなInnovativeで胸がワクワクするようなブレークスルー研究は残念ながらあまりなかった。iPS細胞研究も皮膚科領域からは目立った研究はなかったが、研究全般が企業主体になり、特許などのからみで発表しにくい状況になりつつある現状を反映しているのかもしれない。実際我々の研究もそのような傾向になりつつあり、今後の課題かと考える。またFBなど見ると、きさらぎ塾の卒業生のパワーが感じられるようになってきたし、Kisaragi Awardの受賞研究のレベルは世界水準を超えるようになってきているかと考えるし、口述発表に選ばれる機会も多いようである。ただ口述発表に選ばれなかった研究にも素晴らしいものが多く見られ、理事や査読される先生の負担は増えるかとは思うが、是非ポスター賞などを学会中に発表し、きさらぎ塾生以外の方のMotivationをあげる努力もお願いしたい。
懇親会は岩月先生のアイデアでライトアップされた岡山城に移動し、行われた。
海外の方も含め、お城で食事を楽しむ経験は初めてで、鎧、兜での写真撮影など皆さん、おおいに楽しんでおられた。
第41回大会は仙台にて相場節也東北大学教授を会頭として開催される予定である。学会終了後は岩月教授の親友のリヨン大学のNicholas教授をお迎えし、講演を頂いた。

懇親会場(岡山城)でのスナップ)。右からUCSFの内田先生、大分医大の波多野先生、リヨン大学のHaftek先生、資生堂RCの傳田先生、片山、T社の石田さん。アロマと皮膚機能の話で盛り上がりました。
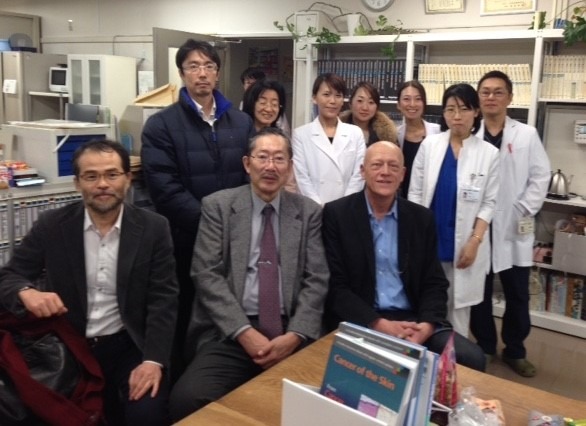
Jean-Francois Nicholas教授によるセミナー(Pathopysiology of eczema (atopic and contact dermatitis)後のスナップ。
http://jsid40-okayama.jp/3_program/151201_JSID_program.pdf
2015年12月
第45回日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎総会学術大会
第45回日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎総会学術大会
会長:森田栄伸 島根大学教授
会場:島根県民会館
会期:2015年11月20-22日
大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学皮膚科学
教授 片山一朗


元祖皮膚科医である大国主命がおられる島根での第45回日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎総会学術大会に参加した、丁度日本中から神様が出雲に来られる神在月が重なり、そこここから神様の話し声が聞こえた〜ような、気がした。昨年の仙台の理事会からの懸案であった従来の任意団体から一般社団法人への移行が10月1日付けで認められた。本45回大会はその第一回で、来年度からは公益性、社会への貢献がより重視され、予算案や、代議員の選挙方法、代議員会など大きく変わり.学会の運営方針も理事会での関与がより強くなる。現在日本アレルギー学会では学術委員会と大会長が大きなプログラム枠を作成し、一般演題もアブストラクトによりワークショップを組んだり、プレナリーセッションを設ける試みも開始されており、本学会でも今後検討して行く必要がある。
第45回大会のテーマは「みんなが主役の皮膚アレルギー」で、会長の森田栄伸先生の会頭講演もなく、懇親会もVogel Parkで行われ、お神楽、八岐大蛇を鑑賞したあとは、日本海の冬の味覚が会場いっぱいに提供され、会員一同、多いに議論に花が咲いた。


日大の照井正先生FBより
今回、森田先生が力を入れられたのはアナライザーを利用したパネルデスカッションで蕁麻疹、アトピー性皮膚炎、膠原病、接触皮膚炎、重症薬疹の5つが取り上げられ、それぞれの領域でのHot topicsが取り上げられた。ただアトピー性皮膚炎のバリア、外用など、難しい問題も多く、アナライザーで大きく意見が分かれた話題も結構見られた。また演者も大御所ばかりで、もう少し若手の臨床の最前線で頑張っておられる方も参加されればより論点がはっきりしたかと考える。その他、膠原病が本学会で大きく取り上げられた事はあまりなく、今回の演題でも自己免疫疾患関連とならび、合わせて10題前後で、近年とみに発表が減少しているアトピー性皮膚炎とならび、来年以降はより多くの演題発表を望みたいし、そういう企画を考えて頂ければと思う。日本皮膚科学会が教育中心、研究皮膚科学会が基礎研究を主に取り扱う現状で、豊富な症例報告と活発な討論が特徴の本学会の意義は大きい。会員数も1,700名を超え、皮膚アレルギーの専門家を育てる上で、森田会頭の言われる「みんなが主役の皮膚アレルギー」の立場で次の世代のプロが育つ、学会としての環境作りが益々重要になるかと考える。演題は興味深い報告が多かったが、特に地方の大学以外の先生が頑張っておられるのが印象的だった。演者から話を聞くと、皆さん大学でアレルギー専門の先生に指導を受けておられた経験があるようで、初期教育の重要性を再認識するとともに、アレルギーの発症機序の解析、新たな治療の開発、予防・啓蒙活動などに興味を持ち続け、あらたな発見をこのような学会で発表し、論文化して行くMotivationを若い先生方にどう与え、育てるか学会でも考える必要がある。
多くの素晴らしい演題の中でも、最近、我々の教室で検討しているOAS関連の発表で、雄勝中央病院からのセリ科スパイスのFDEIAはその責任アレルゲンの同定まで非常に苦労して突きとめられていた報告であり、その努力に頭が下がる思いで拝聴した。このような症例は日常診療でも多いと思われるが、放置されていると考えられ、アトピー性皮膚炎の合併する例などではOAS発症の低年齢化と重症化が増えている印象をもっている。結果として、果物などが食べられなくなることでQOLが障害され、場合により生命予後にも影響する。現在オマリズマブの蕁麻疹への治験が進行しているが、その先に是非このようなOAS治療への適応拡大を学会として進めて行きたいと考えているもう一つの話題として岐阜大学からの発表で、多種の植物アレルゲンに対して、RAST陽性、スクラッチテスト陰性患者が実は全てFalse positive でその理由として植物、花粉、昆虫などの交差抗原としてCross reactive Carbohydrate Determinant (CCD)に陽性であるとのことで、これは牛肉、豚肉などのほ乳類にある程度共通するα—Galと同様の糖鎖抗原との事であった。この患者ではα—Gal抗体陽性で牛肉、豚肉のRASTも4+で牛肉摂取による消化器症状があったそうである。日常診療でこのような多種のアレルゲンが陽性であるにも関わらず、症状がでない場合、このような機序がある事を知っておくことは重要である。この患者ではBet V1,Bet V2陰性、CCDであるMUXF3,Horse radish peroxidaseが陽性であった。

フォーゲルパークの懇親会にて
今回は全員がポスター発表ではなく、口演のみの演題も多かった。聞きたかった演題が座長など、あるいは平行して他の会場で行われていたこともあり、聞き逃した演題の情報を電子ポスターなどで確認できる、あるいは全員ポスター発表と簡潔な口演形式にするなどの検討が必要と考える。専門医の先生や、地方から遠路学会に参加される先生は皆、そのような熱い討論を聞く事を最大の学会参加の目的にされている事を忘れてはならないし、貴重な時間をレベルの低い討論で奪うようなこともしては行けないと思う。最後に、毎回同じ事の繰り返しになるが、発表された貴重な報告は是非、日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会雑誌に、さらに、議論を深めて、英文で海外の雑誌に投稿していただきたい。

2015年11月
この1週間:嬉しい知らせ、出来事など
この1週間:嬉しい知らせ、出来事など
平成27年11月8日
大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学皮膚科学
教授 片山一朗
日々、様々な出来事が私を通り過ぎていく。多くは頭を悩ますことがほとんどだが、この一週間は珍しく、嬉しい知らせや出来事が相次いだ。
最も嬉しかったのは、熊本大学の神人先生が脈管肉腫でHybrid遺伝子を見つけられたことで、まだ論文を読めておらず、以下のプレスリリースの情報しか知り得ないが、本当に大きな発見かと思う。「患者25人を調査。うち9人は「NUP160」と「SLC43A3」という本来は別々の遺伝子が異常に融合していることを確認した。この9人は、融合のない患者と比べると、がんの進行も早かった。融合のない16人は、別の要因が考えられるという。異常融合の遺伝子を導入した細胞をマウスの皮膚に注射するとがん化し、逆に融合遺伝子を取り除くと血管肉腫の細胞が減ることも判明。神人准教授は「今回の研究で皮膚がん全体の制圧にも光が差した」。DFSPで類似したCOL1A1-PDGFB融合遺伝子が検出されるが、今回の発見との異同や今後の治療戦略に与える影響など多くの議論が必要とは考える。今から30年ほど前に北里大学に赴任してすぐに初診を担当したAngiosarcomaの患者さんに対し、当時脈管肉腫の研究をされていた増澤幹男先生がIL2投与で見られるVascular leakage syndrome(Extravasation of intravascular fluid mediated by the systemic administration of recombinant interleukin 2. Rosenstein M, Ettinghausen SE, Rosenberg SA. J Immunol. 1986 Sep 1;137(5):1735-42.) を参考にIL2の投与を世界で初めて行われ、劇的な効果を認めた。この患者さんを端緒として、増澤先生は現在に至るまで本当にライフワークとして脈管肉腫の病態研究に取り組んでこられ、人の脈管肉腫の細胞株をマウスに移植すると人型の遺伝子がマウス型に変わるという驚くべき現象を発見された。多くの雑誌に投稿されたが、なかなかAccept されず最終的にJ Dermatol Sci. 1998 Jan;16(2):91-8. Establishment of a new murine-phenotypic angiosarcoma cell line (ISOS-1).Masuzawa M et al. として発表された。人型の遺伝子を持つ腫瘍がマウスに移植することで、マウス型の遺伝子に変異することで拒絶されにくくなることは、この腫瘍の持つしたたかさを反映しているが、今回の神人先生の発見がこの謎を解く端緒となることを願うとともに、乾癬などの病態発見につながるのではないかと個人的には考えている、増澤先生、本当におめでとうございました。

(写真:長崎大学皮膚科開講100周年にて)

大仁田先生の記事
済生会川口総合病院の高山かおる先生には先日大阪で講演頂き、接触皮膚炎のGL作成に加え、フットケアhttps://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/4837612636#immersive-view_1446946218312、フラダンスとドンドン御自身の領域を楽しみながら広げておられ、若い先生のよいRole modelになっておられる姿を見て嬉しく思った。今の時代、女性医師が圧倒的に増え、彼等がどのような皮膚科医になるかで皮膚科の将来が決まると言っても過言ではない。個々の女性医師が生涯をかけて取り組めるようなテーマを女性医師のライフスタイルに合わせて、考え、与えていくのが指導医の責任であることは言う迄もないが、現状は厳しいようで、第2、第3の高山先生が現れるのを期待する。

講演される高山かおる先生
同じ講演会で順天堂大学形成外科の金澤成行先生には皮膚潰瘍をいかにして早く治すか?というタイトルで、講演頂いた。彼が大阪大学の大学院生の時から研究面で情報交換していたが、今回はご専門の創傷治癒の基礎的な話と形成外科的な視点からの潰瘍治療で、講演していただいたが、嬉しい誤算で、皮膚科医以上に足が地に着いた、難しい皮膚潰瘍を自分の力で治すという意気込みが強く感じられる内容で、しかも患者さんの目線で何の気負いもなく淡々と語られる姿は若い皮膚科医にも強い感銘を与えていただいた。彼自身,皮膚潰瘍治療用の軟膏を開発、自作されているそうで、私も今、自分が日常診療で使用したい軟膏を開発しているが、彼には皮膚科医としての感性を感じた。研究面では小保方さんの事件より前から、遺伝子導入をせずに細胞をリプログラミングする研究を継続しておられ、その成果をこっそり教えて頂いた。STAP細胞は科学史から消えさったが、ひょっとしたら、彼が何気なく復活させるのでないかと思った(南方熊楠とSTAP細胞)。
http://www.dermatologyosaka-u.jp/column/katayama/2014_7.htm

2015年11月
第66回日本皮膚科学会中部支部学術大会
第66回日本皮膚科学会中部支部学術大会
会頭:錦織千佳子 神戸大学教授
会期:平成27年10月31日ー11月1日
会場:神戸国際会議場
テーマ:輝く皮膚科学
大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学皮膚科学
教授 片山一朗


神戸大学教授、錦織千佳子先生が昨日まで神戸国際会議場で開催された中部支部学術大会に出席した。先日ご逝去された佐野榮春先生(1963年)、三島豊先生(1991年)、市橋正光先生(1998年)がそれぞれ会頭を務められ17年ぶりの神戸での開催とのことであった。テーマは錦織教授の専門である光生物学から「輝く皮膚科学」とされたそうである。私自身錦織先生は米国に留学時代、Margaret L Kripke 教授と素晴らしい仕事をされていた記憶が強く、光免疫学が専門と思っていたが、神戸大学に着任後すぐに色素性乾皮症の診断システを立ち上げられ、現在、全国の医療施設からの依頼で遺伝子診断などの高度先端医療を行われ、厚労省の研究班では「色素性乾皮症のiPS細胞を用いた病態解明と治療法の開発」研究を行われ、全国でも有数の皮膚科学教室として多くのお弟子さんをに育てられている。また錦織教授は日本色素細胞学会理事長を務めておられ、私が2010年から班長を務めた厚労省の班研究による「尋常性白斑の治療ガイドライン」の作成では大変お世話になり、さらに2年前からは美白化粧品による白斑の疫学研究を御一緒させて頂いている。
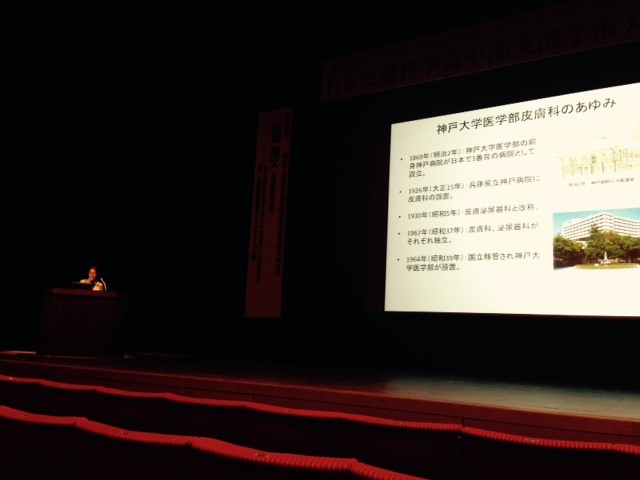
錦織先生は会頭の挨拶の中で「皮膚科学はここ数年で、多くの皮膚疾患についての原因・病態の解明や新しい治療法の応用が進み、めざましい進歩がみられています。こうした現在の状況を踏まえ、且つ、これからも学問的に輝き続けてほしいという願いもこめて、今年の学会テーマを”輝く皮膚科学”としました。」と述べられているが、会頭講演ではさらに皮膚科医が本来診療すべき様々な境界領域の疾患を手放しつつある現状を危惧され、「皮膚から全身を診る”心意気を持てば今まで以上に皮膚科医が深く関わっていける領域はたくさん有ると思います」と述べられた。その意味からも今回企画された13の教育講演では境界領域に関わるテーマのセミナーが企画され、私が座長を務めた墨東病院の澤田泰之先生の「皮膚科救急にある危険なトラップ(罠)の見つけ方」は早朝から、立ち見の方で溢れるくらいの先生方が参加されていた。私の教室、関連病院の先生も結構目についたが、このようなセミナーを聞く事でさらに皮膚科の面白さを学んで頂ければと思う。特にご自身が経験された症例を丁寧に記録され、分かりやすく話をされた澤田先生の講演からは参加された先生方は多くの事を学ばれたことと思う。昨今目につく多くの情報や文献を羅列したスライドやコピーペーストのスライドばかりの一方通行の講演より遥かに得る事が多いかと思う。
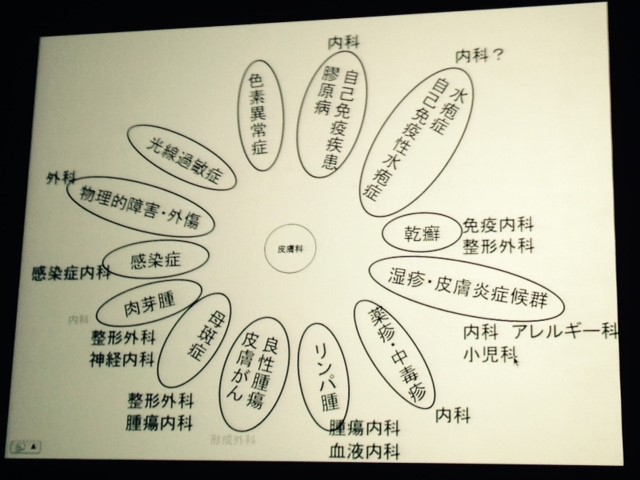
“皮膚から全身を診る” 、現状は残念ながら皮膚科の存在が小さくなりつつある。

今山先生からは空胞変成から液状変成にいたるダイナミックなプロセスを示して頂いた。Interfaceに好酸性に染まる物質は変成した基底細胞である事、そこに沈着してくるムコ多糖などはあまり大きな意味を持たないことなどを述べられた。また免疫操作電顕の手技を用いた、Interface側からの炎症細胞の表皮内への浸潤像など驚くような所見をたくさん供覧して頂いた。一般演題は チオ硫酸ナトリウムにより改善した皮膚石灰沈着症の1例(順天堂練馬病院)四肢、腹部の皮膚潰瘍を契機に診断したCalciphylaxisの1例(東邦大大森)と日常診療で苦労する皮膚石灰沈着症の治療でいづれもチオ硫酸ナトリウムを使用されていた。前者はデブリ後25%のチオ硫酸ナトリウムと酸化亜鉛軟膏を使用する事で著明に改善していた。コハク酸メチルプレドニゾロンナトリウムによる即時型アレルギーの1例(京都府立医大)、プレドニゾロンによる薬疹の1例(岩手医大)はいづれもステロイドによる稀なアナフィラキシーで特にコハク酸メチルプレドニゾロンナトリウムによる症例はアスピリン不耐症とは異なり、救急外来などでも注意が必要と考える。大阪大学からは高橋 綾先生が西部支部大会に引き続き「蕁麻疹様の紅斑を契機に発症した後天性皮膚弛緩症の一例」を、生長久仁子先生が「 大細胞転化した菌状息肉症に対しブレンツキシマブベドチンを投与した一例」を発表された。医工連携シンポジウムは残念ながら座長で聞く事が出来なかったが、天野浩教授の特別講演同様、今後皮膚科領域でもLEDなど新しい線源の光線を使った医療が発展して行くと考える。今大会は、錦織先生のお人柄どおり静かで整然と進み、基礎研究と臨床がサイエンスをベースにうまくMixし、聞き応えのある講演、発表が多かった。唯一、懇親会で同門の原田晋先生が企画されたギターの橋本祐の演奏は奥様の橋本有津子さんがオルガンのカルテットでCool Struttin’から始まるおしゃれな神戸元町にぴったりの演奏が続き、最前列で聴かせて頂いた。

2015年11月2日掲載
第67回日本皮膚科学会西部支部学術大会
第67回日本皮膚科学会西部支部学術大会
会頭:宇谷厚志 長崎大学教授
会期:平成27年10月17日ー18日
会場:長崎ブリックホールおよび長崎新聞文化ホール
大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学皮膚科学
教授 片山一朗


秋晴れの下、第67回日本皮膚科学会西部支部学術大会に出席した。韓国で開催されていた、第24回世界アレルギー学会(World Allergy Conference)での講演終了後、仁川空港から長崎入りした。私は2001年に第53回大会の会頭を務めさせて頂いたが、直前に9.11が起こり、海外からの招待者のキャンセルなど心配したが、皆さん無事来日して頂き、素晴らしい講演が聞けたことを懐かしく思い出した。
学会は宇谷先生の教室紹介と学会の聞き所などの話、そして今回の学会テーマである『本質を見抜く』ことの重要性をお話になられた。(以下、会頭挨拶より一部引用する)。『 日常診療の中で「こう言われてるけど,本当かな?」と思うようなことに出くわすことがあります。今回の学会では『本質を見抜く』 See through the Essence behind Common Knowledge をテーマに掲げ、講演では出来るだけタイトルに簡単な疑問を挙げていただくようにお願いしております。中略、 今回は、西部支部の大学から臨床・基礎を問わず研究成果を報告していただく企画を作りました。「大学は研究する場」と認知されてはいますが、最近では研究は専門医の”次のレベル”という考え方が多くなってきているようです。時間的、物理的な制約を乗り越え、大学皮膚科教室で現在行われている研究活動を発表していただき、本質は何かを考える「好奇心」があふれる皮膚科医師の育成の契機になれば嬉しく思います。』
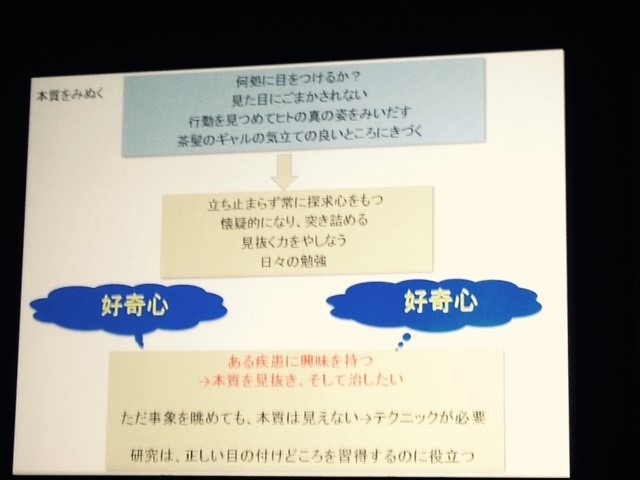
学会は引き続き、宇谷先生のご専門のマトリックスに関するシンポジウムが開始された。強皮症を除き、全て遺伝性の疾患中心の内容であったが、特に長崎大学からは宇谷先生が厚労省研究班長を務められているPXE(弾力線維性仮性黄色腫)の新規病型発見とリードスルー法という新たな遺伝性疾患治療法の開発に関する講演を長崎大学皮膚科の若手のお二人が話された。宇谷先生は長崎大学に着任されてまだ5年とお聞きしているが、元気な若手が育ってきているのが良くわかり何よりである。シンポジウムはマトリックスのほか悪性腫瘍の新規治療薬、感染症、皮膚病理学が企画されていた。私は皮膚病理学にも参加した。MM in situと色素性母斑の講演で玉田先生の鑑別が困難な場合、臨床写真がないと最終診断を下すのは難しいという結論は、6月の網走の日本臨床皮膚科医学会の教育講演で熊切正信先生が仰った「最後はそのプレパラート全体から悪性と感じ取る事が出来る感性である」という話と重なる部分があった。また陳先生の動脈炎と静脈炎の鑑別にEVG染色が有用で、血管壁の弾力線維が静脈でよりはっきりしていること、内弾性板の染色所見は結構難しい事をお話されていた。
一般演題はシクロスポリン内服が有効であった小児剣創状強皮症の1例(徳島大)、ケミカルピーリングでの治療を試みたパニツムマブによる痤瘡様皮膚炎の1例(東北大)、ミノマイシン内服とドボベット軟膏外用が奏功した融合性細網状乳頭腫症(大阪市大)など治療に関して有益な報告が多かった。大阪大学からは、高橋 綾先生が難治性ロドデノール誘発性脱色素斑患者7例の臨床的検討、山岡先生がIgG 型抗PS/PT 抗体が陽性であった皮膚型結節性多発動脈炎の3例、神谷香先生がアフィニトールの副作用としての皮疹の検討を発表された。特に神谷先生は今回が学会初デビューであったが、難しい課題を短期間で良く纏められ、発表前も全く緊張されなかったようで、皆さん感心しておられた。是非この発表を契機に結節性硬化症の治療や研究にも取り組んで頂きたい。

発表前の笑顔の神谷先生

展示ポスター
また一般演題の前に1〜2題ワークショップとして各大学の若手による研究発表があり、越智先生がInnate lymphoid cell 由来サイトカインによる表皮角化細胞・真皮線維芽細胞でのコルチゾール再活性化酵素発現の検討を発表された。
懇親会は世界遺産に登録されたグラバー園で開催された。私も53回の会頭を務めた時にグラバー園での懇親会を考えたが、雨の多い長崎ということで諦めた経緯があり、また当時BSE問題で提供できる料理にも苦労した事が思いだされたが、皆さん素晴らしい長崎の夜景そして長崎港からの花火を楽しまれた。

普賢岳遠望
2015年10月20日掲載
年報序文
年報序文
「スクラップ アンド ビルド」は何をもたらすのか?
大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学皮膚科学
教授 片山一朗
スーパーローテートが開始され、私の大阪大学教授としての在職期間と同様、はや10年以上が経過した。研修医の大学離れ、医局離れ、そして大学院への進学者や海外留学希望者の減少が毎年この時期、基礎、臨床、地域を問わず、教授の間で話題になる。その中でスーパーローテートシステム開始と平行して行われた大学院制度改革にともない多くの基礎、臨床の教室が講座名称を変更し、特に基礎では何をやっている教室かが全く分からなくなった。確かにアメリカのように大統領がかわるとホワイトハウスのスタッフがすべて入れ替わるのと同様、大学でも教授がかわると、場合により開学以来蓄積されてきた多くの知的財産や貴重な医学資料、機器がすべて処分され、その時点で、その教室の歴史に幕が下ろされる。「スクラップ アンド ビルド」により新たな研究分野を創出するのは短期の結果が要求される科学の分野では重要かもしれないが、知的財産、歴史・文化を継承して行く場合、大学の不毛化を加速させる危惧が常にある。大阪大学総長である平野俊夫先生が医学部長の頃、「大阪大学医学部の基礎教室がシャッター通り化している」との危惧を述べられ、大きく研究改革の方向に舵を切られ、最近は以前よりは活気が戻りつつあるが、新たな専門医制度の開始により、大学院への進学がさらに減少する事が予測される。ヨーロッパではどこに行っても新市街と旧市街が混在し、アメリカ型の量販店と伝統を引き継いだ職人が集まる商店街がうまく共存し、大切なその国の歴史、文化を後世に伝えている。翻って今の日本では日本の伝統ある職人芸が滅び、つい最近まで、そこ、ここにあった、地域の商店街が次々と消えていきつつある。
2014年は大阪大学皮膚科の皆さん、本当に自身の皮膚科学を追求され、臨床、研究に大きな成果を挙げられた。特に金田眞理先生は長年、診療されてきた結節性硬化症の症例を取り纏められ、素晴らしい臨床研究として2013年にPLoS Oneに発表され、その後も厚労科研で結節性硬化症の皮膚病変に対するラパマイシンの医師主導治験で大型の研究費を獲得され、今年も多汗症や神経線維腫への応用で、引き続き研究費を獲得されている。このようなご自身の臨床的な視点からの応用研究は私が目指す究極の目標であり、世界に誇れる成果である。また中国から日本に来られ、大阪大学の皮膚科大学院に進まれた楊伶俐先生は強皮症やアトピー性皮膚炎の真皮結合織のリモデリングにかかわる新たな分子機構を、寺尾美香先生は皮膚のステロイドホンルモン産生機構に関わる研究をあいついで報告され、この分野で世界をリードされている。2010年から私も厚労研究班班長として白斑のガイドライン策定、病因論の研究、新規治療法の確立などに取り組んできたが一昨年からは化粧品による白斑の病態研究にも取り組み、皆さんの協力である程度の成果が挙げられ、今年からの厚生労働省の研究へとつなげる事ができた。スタッフと若い先生の連携とその成果を見ると、大阪大学皮膚科に脈々と受け継がれてきた歴史、伝統に根ざした教室の財産を基盤としてそこに新しい視点からの研究手法が導入され、次の時代を切り開いて行く大きな成果が得られつつある。先に述べたように、一度途絶えた伝統を復興させるのは至難の業である。大学というアカデミアでもその危機感を共有し、次の世代を育てていくことが我々の大きな役割である。
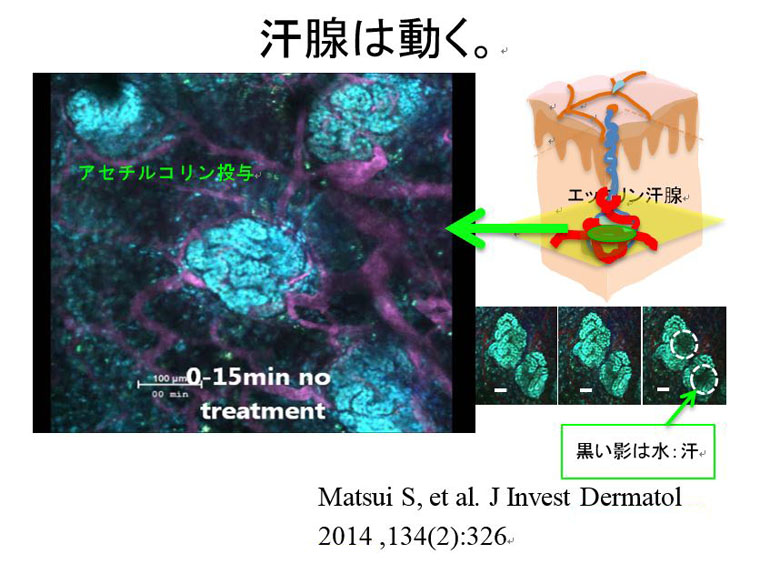
「松井佐起先生、室田浩之先生等による世界で初めてのエクリン汗腺の3次元 (4次元画像)。大阪大学菊田順一先生、石井優教授との共同研究。初めてライブビデオを見た時には感動しました」

「ユカタン半島のセノーテ」
「メキシコ、ユカタン半島には地下水が長い年月をかけ、石灰層の土壌を浸蝕して、出来た数千キロに及ぶセノーテと呼ばれる地底湖が広がっている。その巨大な地底湖から光を求めて多くの植物がしっかり根を伸ばし、若葉を広げる姿は神々しい。」
昨年12月に千里で開催した第39回日本研究皮膚科学会はメインテーマを「Global tuning of innovative dermatology」とし、大きな成功をおさめた。協力頂いた教室員、同門の先生には心よりお礼を申し上げるとともに、ここ千里が丘から伝統に根ざした次の時代の扉を拓き、あらたな歴史を創り出す研究が生まれる事を願い、2015年の年報の序とさせていただく。
2015年初夏 片山一朗
8th World Congress of Itch (WCI) 25回国際痒みシンポジウム
8th World Congress of Itch (WCI)
Nara Kasugano International Forum
September 27-29
President: Ichiro KATAYAMA (Osaka University)
25回国際痒みシンポジウム
September 27
会頭 稲垣直樹 (岐阜薬科大学教授)
奈良春日野国際フォーラム甍
大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学皮膚科学
教授 片山一朗

学会場に行く途中、興福寺の遠景を望む。気持ちのよい初日の朝。

(International Federation of Society of Itch)が設立され、今年は10年目の記念の会となり、招待会では10th Anniversary Cake が室田事務局長のお世話で皆さんに振る舞われた。

開会挨拶

IFSI 10周年記念ケーキ
国内大会の痒みシンポジウムはダブリン大学のPAR2研究で有名なMartin Steinhoff先生の特別講演をはさんで計5題の指定演題の発表があった。特にSteinhoffは痒みの新しいメデイエーターを標的とする次世代の治療戦略を述べたが、その中でIL31は痒みの伝達だけではなく、NGFとは別個に末梢神経の増生に関与するという新しい知見を発表した。また富山大学名誉教授で本学会の設立者でもある倉石泰先生は東京医科歯科大学に移られたが、相変わらずお元気で、新しい痒み研究の成果を発表された。特に上行性の痛み感覚は脊髄後角のGRP(Gastrin releasing peptide)が痒み、サブスタンスPが痛み感覚の伝達に関与することを示された。興味ある点として下行性セロトニン神経系は痛みの抑制と痒みの増強、ノルアドレナリン経路は痒みと痛みを抑制するとのことであった。これは痛みにおける筋肉の逃避行動や痒みの掻破行動を制御すると考えることができるが、逆に温熱や物理刺激による痛みや痒み知覚に対する血管反射や発汗機能に下行経路どう影響するのか興味が持たれる。同様の脊髄レベルでの知覚の制御や増幅機構に関して、九大薬剤学の津田先生はマウスの掻破行動モデルにおいてTRPV1陽性のC- fiberにより伝わる痒み感覚が脊髄後角AstrocyteのSTAT3を活性化し、Lipocalin 2の誘導を介して、GRP依存性の痒み感覚を増幅するという非常に綺麗な報告をされた。また皮膚炎の発症した領域の支配神経に一致した脊髄でよりその発現が見られたが、乾癬などのモデルで同様の変化が見られるかはまだ未検討との事であった。この成果はNature Medに報告され、その著者である林先生は今回から新設された Hermann O Handwerker賞(副賞2,000ドル)を受賞された。この他,今回のトピックスとして胆汁欝滞などで見られる痒みにAutaxinであるLysophosphatidic acid(LPA)が関与することが話題になったが、その痒みにH1Rアンタゴニストが効果を示すことを防衛医大の橋本先生が報告された。カリフォルニア大Davis校のCarstens教授は味覚におけるTRPチャンネルの世界的な研究家であるが、TRPV1、TRPA1陽性末梢神経が掻破や温熱刺激で活性化することでヒスタミンあるいはMRGPA3誘発性の痒みを抑制することを報告した。

お茶の先生(木原宗郁さん)、片山、Jacek 理事長

左よりHandwerker先生,Carsten先生(次期理事長),片山
Ethan Lerner教授はサブスタンスPがヒスタミン非依存性の痒みを誘導すること、ヒトMRGPRX2のリガンドとして作用すること、その拮抗薬がヒスタミン非依存性の掻破行動を抑制すること報告し、サブスタンスP阻害薬の新しい可能性を示された。また乾癬のモデルマウスでの痒みの増幅機序や抗IL17A抗体の効果などの話も話題になっていた。ただネズミの話がどこまでヒトの疾患に適用可能かはむずかしい。むしろヒトでの新しい脳機能解析機器を応用して行く方が早いかとも思うが、いずれにしてもこの数年の痒み研究の勢いは素晴らしく、若い皮膚科医にも是非参入してもらいたい。
今大会は初日から期間中を通じて、大変天候に恵まれ、皆さん学会のあい間に世界遺産の寺院、神社、仏像を楽しまれ、夜のガーデンパーティでは中秋の名月を愛でながらの活発な討論が繰りひろげられた。当初は奈良の知名度の低さから、参加者の数など心配していたが、最終的には230人を超す参加者があり、初日の金春流の能「高砂」で皆さん一気に奈良が気にいったようである。第9回は2017年10月にポーランドWroclawでJacek Szepietowski Wroclaw Medical College教授により開催される。

理事の方と最後の会議後の写真
最後になるが、今回、普段よく会う皮膚科の先生、特にアレルギーを専門とする先生の姿を会場、討論などで見る機会がすくなかった。皮膚科医はまず皮疹を見ることから臨床医としてのスタートを切る。臨床経験を重ねる過程で患者の全身的な背景因子を加味して皮疹を視、そして、観る。さらに患者の全てを考慮しながら、皮疹を診て治療を考え、時に看とり、その結果をサイエンスとして記録していく。痒みは皮膚科医にとりその実体が捉えにくいかと普段から思っているが、そのことがアトピーを専門とする皮膚科医の参加が少なかった理由と考えると、その点は多いに反省すべきであり、今後は是非、臨床、基礎の若い先生の力で皮膚科医のこの分野への参入を考えて頂ければと願う。


ガーデンパーティ会場からの中秋の名月
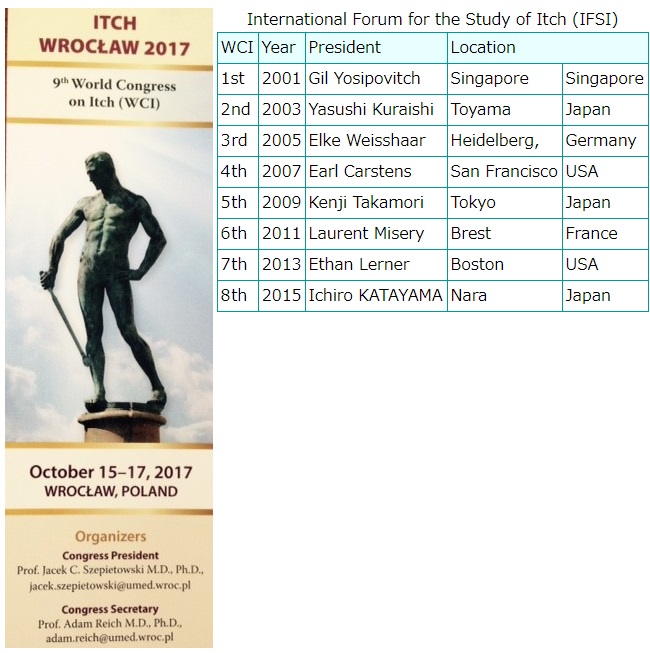
大阪大学大学院医学系研究科教授 片山一朗
平成27(2015)年10月1日
最近考えること、「天からの手紙」
最近考えること、「天からの手紙」
大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学皮膚科学
教授 片山一朗
今年の夏は猛暑続きでぐったりし、また世界経済や日本の政治も不透明感がまし、落ち着かない毎日でした。9月に入り、朝夕過ごしやすくなり、少し風向きが変わることを願いつつ、このコラム記事を書いております。9月末の奈良での第8回国際痒み学会(World Congress of Itch 2015)を控え、ようやくエンジンがかかってきました。
昨年も書きましたが専門医制度認定機構による新たな専門医制度が2017年度からスタートする予定で、日本皮膚科学会でも、最終研修プログラムが策定され、研修施設の認定基準なども決まりつつあります。研修の要件として入院患者の担当や手術件数なども重視されています。このような流れのなかで、出産後、復職して頂く先生が増えてきています。ただ全国的には皮膚科女性医師の復帰をいかにサポートするか(現実には男性医師を次の世代の皮膚科指導医としてどう教育して行くかの方にシフトしつつあります)が大きな問題として残りますし、今後の皮膚科診療が入院治療主体になって行く中で、どう病棟を維持して行くか、基礎研究を担う皮膚科医をどう育てるかなど、日本だけでなくドイツなどの欧米諸国でも問題になりつつあるようです。聞いた話では、アメリカで皮膚科医になるにはトップテン位の優秀な成績が必要で、多くは収入の良い美容皮膚科医を目指すそうです。結果的には大学内や基幹病院でも皮膚科の入院主治医とならず、コンサルタントとして内科、外科などに入院した患者の治療方針を少人数で決めるだけで、治療は全く行わないそうです。これはメラノーマなどの治療で顕著で、皮膚科医はダーモスコピーで良性、悪性の鑑別などの臨床診断のみ行う。生検、切除、リンパ節廓清などは外科、再建は形成外科が行い、再発、長期管理は臨床腫瘍医が行うそうです。これは訴訟を恐れ、専門以外手を出さないアメリカの医療の縮図ですが、そのような中で、入院治療を行わない、皮膚科の収入は激減し、以前書いたように、DepartmentからDivisionに格下げされる大学皮膚科が益々増え、近い将来皮膚科という臨床科が消滅し、Skin Biologyなど基礎研究部門が残るだけになる可能性も考えられます。先に述べた2017年の専門医改革は皮膚科医の専門性がどう担保されるか、アトピー性皮膚炎などのアレルギー疾患の治療を誰が担うか、ニキビや水虫などのCommon skin diseaseは総合診療医でも治療するなどの大きな論点が残されています。最近のOTCやジェネリックの推進やサプリの効能表記が認められた事はこのような流れの中で進められていますし、TPPの協定成立
の先にはアメリカの保険会社の参入などや外国人医師や看護師の雇用解禁の動きも見え隠れします。

大阪大学大学院医学系研究科教授 片山一朗
平成27(2015)年9月16日
第30回日本乾癬学会
第30回日本乾癬学会
会頭:森田明理 名古屋市大教授
会場:ウェスチンキャッスル名古屋ホテル
会期:2015,9.4-5
テーマ:グローバルトップの乾癬治療を目めざして
大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学皮膚科学
教授 片山一朗

今回で30回となる節目を迎える乾癬学会に参加した。演題数が150題ちょうどでプログラム誌も以前に比べ格段と厚くなっていた。ただ昨年の高知の学会でも感じたが、多くが生物製剤と関節症性乾癬に関する演題で、基礎研究の少なさや討論の内容が気にはなった。初日の会長講演は名古屋市大の映画研究会(?)製作の教室紹介ビデオが取って代わり、次代の乾癬治療を予感させるインパクトのある大胆な画像で学会が開始された。私自身、今回は3つの用務が重なり、すべてを聞くことができなかったが、昨年ノーベル物理賞を受賞された天野浩先生の講演は素人向きの話ではあったが大変興味深く拝聴した。森田先生は90年代から天野先生とは知己を得られていたそうで、後から聞いた話ではUVA1の強皮症治療から共同研究を開始されたそうで、今はLEDを用いた新しい光線治療法を開発中のようであった。LEDは青色や赤色ダイオードで創傷治癒や培養細胞からのサイトカイン産生が異なるようで、これからの治療への応用が期待される。別のグループの研究紹介でマウスの脳に青色LEDを照射すると興奮し、橙色LEDを照射すると鎮静化し、入眠するそうで、脳細胞がLEDの波長をどう認識し、脳機能がどう調節されているか大変に興味深かった。そのあとの招待講演の高島明トレド大学教授は乾癬における好中球の役割に関する最近の知見を紹介いただいた。乾癬で病態形成にかかわるIL17A産生細胞が好中球である可能性や、乾癬モデルで人為的に好中球を除去すると皮疹が形成されないなど興味深い研究の紹介があった。またLy6、CD11bなど好中球マーカーを持つ細胞をGMCSF,IL4などを含む培養液で飼うと、CD11c陽性の樹状細胞が出現すること、炎症性の疾患でこのような2つの細胞の表面マーカーを持つ細胞が増加することを示された。実際の乾癬で増加しているかはまだ明らかではなさそうで、今後の検討が期待される。
Emergence, origin, and function of neutrophil-dendritic cell hybrids in experimentally induced inflammatory lesions in mice.
Geng S, , Takashima A. Blood. 2013 7;121(10):1690-700
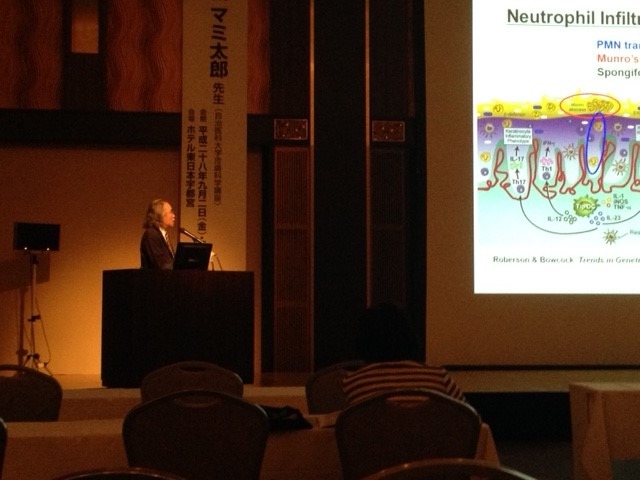
高島明先生の講演
一般演題、最初のセッションで教室の越智先生が、生物製剤導入を契機に見つかったHIV感染症の2例を報告された。現在HIVは生物製剤使用時の感染症のチェック項目には、含まれておらず、一例目はHIV感染時増悪することが知られている、脂漏性皮膚炎様のSebopsoriasisに近い臨床像、2例目は牡蠣殻状乾癬Rupioid psoriasisという非定型的な臨床像から検査を依頼されたようである。一般的にはHIVは重症の皮膚粘膜の真菌症や日和見感染で見いだされることが多いが、2例ともそのような感染症は見いだされず、その理由として乾癬上皮細胞から大量に産生される抗菌ペプチドが関与しているのかと考えている。またこの2例はHART療法にもよく反応しており、可能性として抗菌ペプチドがHIVウイルスにもある程度の効果を示していたと考えることも可能かもしれない。

講演される越智先生
今回は5会場が並列で行われ、聞きたい演題が重なったが、その中でも特記すべきこととして、一番広いA会場が人で溢れた2日目の本音トークは座長の関係で一部しか聞けなかったが、座長の佐野先生、大槻先生の本音が飛び出し、大変有益なセッションであった。来年も同様の企画をもたれるようである。特に乾癬に安易にStrongestのステロイドを処方すると離脱が困難になり皮膚の副作用が強くでることから座長のお二人ともその使用に警鐘をならされた。また高齢化社会での在宅乾癬治療、シングルマザー(ファーザー)の社会復帰支援に向けた優先順位を加味した治療、など今後継続して検討して頂きたい話題が提供された。その他、私が座長をした生物製剤使用時の肝炎ウイルスの再活性化の問題に関しては、HBsAg(-)でも既感染パターンであれば、造血幹細胞移植患者や悪性リンパ腫患者で再活性化のリスクが高くなることからウイルスDNAのモニターが重要であること、DNA(+)になってもエンテカビルの使用でコントロールが可能になったことを述べられた。また今後使用が予測される制御性T細胞を標的とする抗体製剤、免疫チェクッポイント薬でも再活性化例が報告されており、注意が必要とのことであった。教室関係からは林先生が掌蹠膿疱症と好酸球性膿疱性毛包炎合併した興味ある症例を、東山先生がアダリマブ投与前後でのメタボリックシンドローム関連のRisk factorの変動結果の中間報告を発表された。特に動脈硬化の進展阻止に生物製剤の効果がある可能性を報告された。今大会は昨年以上にバイオ製剤に関する話題で溢れた学会であったが、いみじくも大槻先生がPASI-100を達成するバイオ治療がさらに広がれば乾癬治療の主役がリウマチ内科に移るリスクを危惧する発言をされた。森田教授の主導で作成された光線療法ガイドラインの理解や本音トークで討論された原点にもどる外用療法、あらたな内服療法の登場など皮膚科医が主体で乾癬治療を行う必要性を改めて感じた乾癬学会であった。

2日目、快晴の青空をバックに部屋からの名古屋城。
大阪大学大学院医学系研究科教授 片山一朗
平成27(2015)年9月6日
9th ICP&PPCTSS2015(Seoul Korea)
9th International Conference on Proteoglycans
and 10th Pan-PacificConnective Tissue Societies Symposium
President::Eok-Soo Oh: Prof.
Department of Life Science Ewha Womans University Seoul Korea
Congres Venue: Ewha Womans University Seoul Korea
Date.:Aug. 23-27,2015
大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学皮膚科学
教授 片山一朗
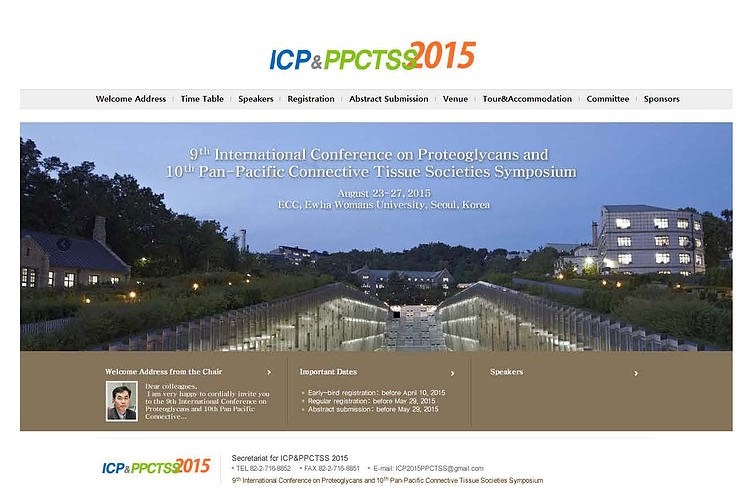

大阪大学からの参加メンバーと、Ewha Womans University にて
第9回国際プロテオグリカン学会、第10回汎太平洋結合織学会が韓国ソウルで開催された。今年6月17日に逝去された故佐野榮春大阪大学皮膚科名誉教授のご専門が強皮症などの結合織疾患であり、その研究対象がコラーゲンやムコ多糖などの結合織代謝であった関係で私も日本結合織学会の会員である。今回は学会の運営にあたられたソウル大学皮膚科のJin Ho Chung 教授から講演を依頼され、山岡、林、楊、生長の先生方と参加した。
私は[Periostin facilitates skin sclerosis via PI3K/Akt dependent mechanism in a mouse model of scleroderma]というタイトルで講演をおこなった。現在,皮膚科で結合織研究,特にプロテオグリカンの研究を行っているラボは世界的にも減少しているようである。ドイツから表皮水疱症、基底膜の研究で有名なフライブルクのBruckner-Tuderman教授と私が参加していた以外は地元韓国ソウル大学皮膚科のChung教授のラボと大阪大学、そしてEndostatinアナログの強皮症治療への応用を講演された横浜市大皮膚科の山口由衣先生くらいでやや寂しい印象は拭えなかった。ただ招待会では、永井祐先生(東京医科歯科大名誉教授)や木幡先生(東大名誉教授) 鈴木 旺 先生(名古屋大学名誉教授)など佐野榮春先生と同時代に活躍された日本の結合織研究の黄金時代を築かれた先生方の名前をお聞きし、懐かしい思いがした。我々は新しい細胞外マトリックスであるペリオスチンがコラーゲンAssemblyに関わるデコリンというプロテオグリカン発現を抑制することでブレオマイシン誘導性強皮症モデルを増幅させる可能性を報告したが、同じデルマタン硫酸を2分子GAGとして持つバイグリカンにはそのような作用を持たないことをChung教授が報告され、討論が進んだ。デコリンは36 kDaのコア蛋白質にコンドロイチンまたはデルマタン硫酸鎖を側鎖に一本持つ。コンドロイチン4硫酸を持つデコリンは成長軟骨より単離され、関節軟骨や腱 からは、デルマタン硫酸鎖をもつデコリンが単離された。デコリンは、骨、腱、鞏膜、皮膚、大動脈、角膜に多く存在している。スモールプロテオグリカン II, PG-S2, PG-40またはDS/CS-PGIIとも呼ばれる。in vitroの実験で、I型及びII型のコラーゲンと結合し、コラーゲン線維の形態の制御作用の役割が示唆されている。強皮症などではコラーゲン腺維束がうまく束ねられず、細い線維束の幼弱なコラーゲンが増加している。また横浜市大の山口先生はXVIII型コラーゲンのC末フィラグメントであるEndostatin 由来ペプチドがブレオマイシンモデルの皮膚硬化を抑制する事を報告され、臨床応用の可能性が検討されているとのことであった。糖鎖修飾はEpigenetic新たな蛋白合成においても重要であり、今後も研究を継続して行きたいと考える。
楊先生の発表はペリオスチンによるデコリンの制御調節で口述講演に選ばれ、トラベルグラントも獲得された。
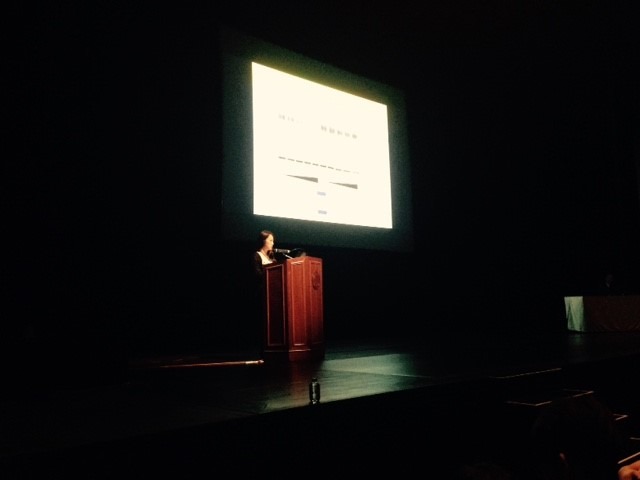
私はInvitation Dinnerに招かれて参加できなかったが、山岡、林、楊。生長の若手の先生方は韓国グルメを楽しまれたようである。会場となったEHWA女子大は世界で最も大きい女子大ということで、キャンパスも美しく、また学食やノベルテイグッズも充実していた。

Bruckner-Tudermanご夫妻(向かって右前二人)山口先生、Granville 先生、Chung先生、Fisher 先生)
大阪大学大学院医学系研究科教授 片山一朗
平成27(2015)年8月31日
第2回汗と皮膚疾患の研究会
第2回汗と皮膚疾患の研究会
平成27年8月8日
東京
大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学皮膚科学
教授 片山一朗
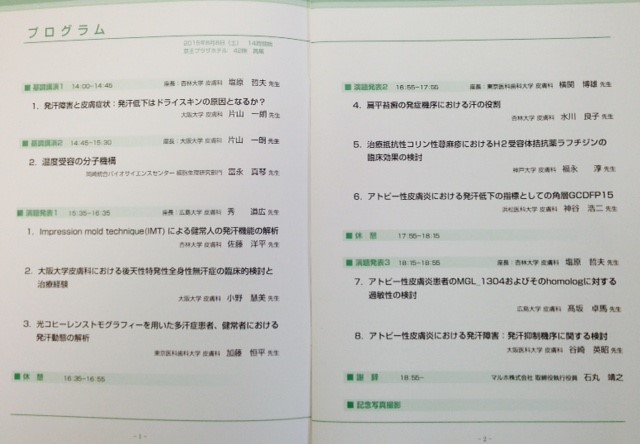
「汗と皮膚疾患の研究会」の第2回研究会が昨年に引き続き開催された。開会の挨拶で、杏林大学の塩原先生が、今年開催された汗に関する日本皮膚科学会、日本アレルギー学会での教育セミナー、シンポジウムが大変盛況であった事に触れられ、皮膚疾患における汗の重要性が少しづつ認知されるようになってきているとコメントされた。実際アレルギー学会で汗のシンポジウムが組まれたのは初めてであり、特にガイドラインの普及により、アトピー性皮膚炎における汗の指導の重要性が一般の先生にも理解されるようになってきたのではと考える。本会でも今年は出席者が39名と過去2番目に多く、若い男性医師の参加が目立ち、活発な質疑応答が繰り広げられた。
今年は世話人として私が基調講演1を担当させて頂いた。抄録とタイトルで塩原先生から先ずカウンターパンチを頂いた後、私自身の個人的汗の研究史として、3つの話題を提供させて頂いた。
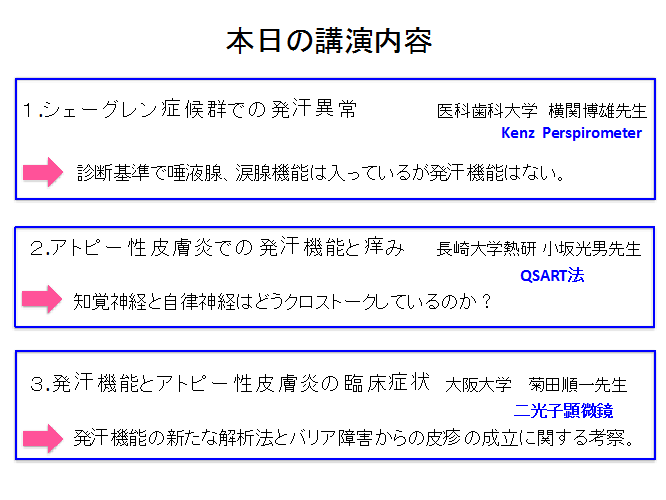
シェーグレン症候群は私のライフワークの一つであり、今年から国の特定疾患に指定され、若い先生にも興味を持って頂いたようである。塩原先生からもシェーグレン症候群で汗腺周囲の細胞浸潤と発汗低下は関連するのかと質問されたが、我々の提示した症例(図2)や過去の唾液腺障害でのリンパ球の関与に関する研究からは唾液腺、涙腺、腎などと同様の変化が生じていると考えられる。また最近の研究ではTh17あるいはIL17A産生細胞が腺障害に関与しているとの報告が増加している。(Itoi S, Katayama I.et al.Immunohistochemical Analysis of Interleukin-17 Producing T Helper Cells and Regulatory T Cells Infiltration in Annular Erythema Associated with Sjogren’s Syndrome. Ann Dermatol. 2014 Apr;26(2):203-8.)。ただムスカリンM3受容体への自己抗体が関与するとの報告はある。またアトピー性皮膚炎でのアセチルコリン受容体の発現は調べていないが、アセチルコリンエステラーゼ活性が不安の強いアトピー性皮膚炎患者で低下しており、受容体のDownregulation生じる可能性はあるかもしれない。
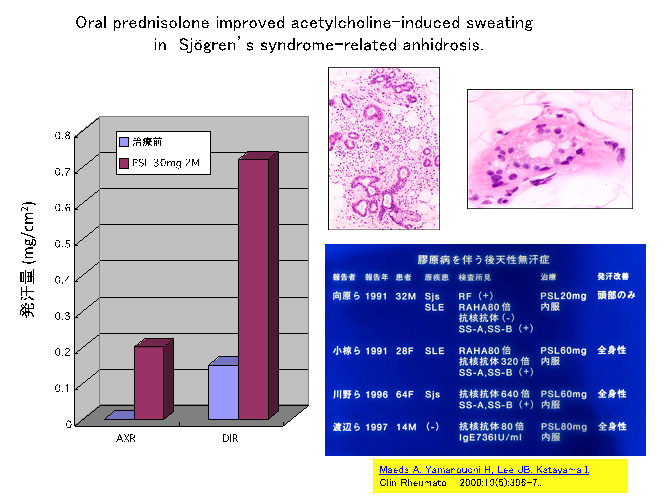
またPapuloerythroderma Ofujiで見られるDeck chair sign や成人アトピー性皮膚炎で肘窩など間擦部の病変を欠く症例は発汗低下例が多い事を合わせて提示した。(Takahashi A. et al. Decreased sudomotor function is involved in the formation of atopic eczema in the cubital fossa. Allergol Int. 2013 Dec;62(4):473-8. )
発汗の生理学的な意義として精神性発汗と温熱性発汗があるが、掌蹠、腋窩、前額などは緊張すると手に汗を握り、脂汗がしたたり、腋窩はじっとりと汗をかく。また過度の交感神経の緊張で血管は収縮し、皮膚は蒼白になる。逆に温熱性発汗は体幹からの大量の発汗が主体で、精神性発汗が生じる部位にも発汗が見られる。温熱性発汗は視床下部にある温熱中枢で深部温度が知覚される事で交感神経が逆行性にアセチルコリン誘導性の発汗を惹起する。血管反射はノルアドレナリン性の収縮反応となる筈であるが、事実は熱放散として拡張の方向に作用する。このParadoxicalな反応に対する答えはないが、発汗のみで体温調節がうまく行かない時に副交感神経系が作動するのか、あるいはサブスタンスPなど血管拡張性物質が遊離するのか興味が持たれる。
基調講演のもうお一人は、熱センサーとしてのTRP研究で御高名な岡崎統合バイオサイエンスセンター教授富永真琴先生のお話であった。私自身、温度センサーが17度、28度、43度など、なぜ、どのように、これほど精密に規定されているのか、あるいはプロトンなどのイオンと植物由来物質がどうイオンチャンネルの活性化を使い分けているのか、未だに良く理解できず、情けない限りである。後から聞いた話ではTRPは進化論的には昆虫から見られるようで、遥か昔、太古の時代、彼らが、有害な物質としてワサビ、カンフル、カプサイシンなどをセンシングする受容体として獲得し、それが人類にまで引き継がれたとしたら、我々は何をセンシングしているのか興味が持たれる。またTRPは末梢神経で発現しているものとしていないものがありその違いが何か、中枢でも温度をセンシングしているのかなど不明の点が多いようである。富永先生は皮膚科との共同研究を多いに希望されており、興味のある方は是非コンタクトを取って頂ければと思う。一般演題では若手の臨床に結びつく素晴らしい研究が8題発表された。ただアトピー性皮膚炎でのバリア機能異常と発汗障害や、汗孔の閉塞と汗の漏出など、過去繰り返されてきた「鶏が先かタマゴが先か」という論議に戻るようであり、コリン性蕁麻疹のアセチルコリン受容体の発現低下、AIGAの位置づけなども未解決であり、来年も引き続き、議論が深まることを願っている。最初に述べたように、医学研究は未知の自然現象を知り、それを患者の治療に還元したいという、知的な興味とそれを解決するための機器の進歩や人との出会いが必須である。また何がどこまで分かっているか、先人の研究を謙虚に振り返る事も重要な事である。塩原先生は世話人として最後の会であり、生涯で初めて乾杯の音頭を取られ、発汗研究への熱い思いを我々に託された。来年からは名誉顧問として、引き続き、汗の研究を押しすすめる原動力となって頂きたいと願う次第である。なお来年8月27日~28日、大阪大学銀杏会館で第24回発汗学会を開催させて頂きます。本研究会と合わせ、奮ってご参加下さい。

大阪大学大学院医学系研究科教授 片山一朗
平成27(2015)年8月11日
佐野榮春先生の遺されたもの
佐野榮春先生の遺されたもの
大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学皮膚科学
教授 片山一朗

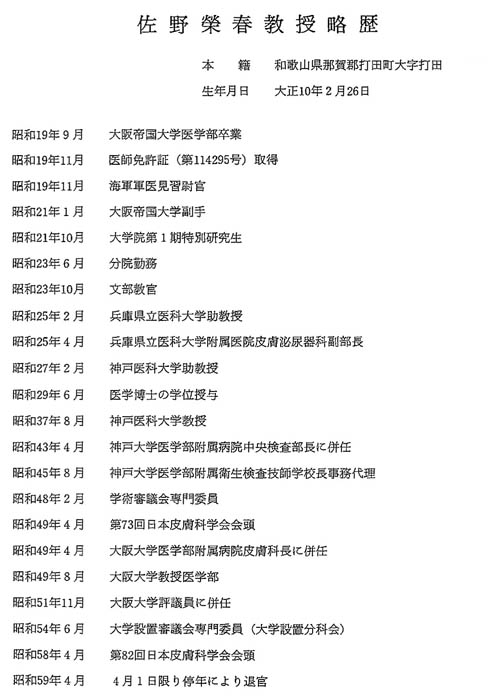
私どもの恩師である佐野榮春名誉教授は平成27年6月17日夕刻、逝去されました。ご子息の佐野栄紀高知大学教授と奥様の前で、静かに逝かれたそうです。心よりの御冥福を祈り、哀悼の念を表します。
先生は大正十年のお生まれで、生家は代々、和歌山で医家を営まれており、お名前の榮春は空海の灌頂歴名の中にある僧の名前からとられたとお聞きしました。
昭和一六年に大阪大学医学部に御入学され、昭和十九年御卒業後、海軍軍医見習尉官となられ、朝鮮半島に赴任されました。終戦後昭和二十一年一月に大阪帝国大学副手として谷村忠保教授が主宰されていた皮膚科学教室に戻られ、その後兵庫県立医科大学(現神戸大学)の助教授として転出され、昭和三十七年に神戸医科大学教授に就任されました。神戸大学の頃の話は佐野先生ご自身だけでなく多くの弟子の先生からも良くお聞きしましたが、本当に楽しく、充実した日々を送られたようです。昭和四十九年に大阪大学教授として母校に戻られております。この間多くの弟子を育てられ、日本皮膚科学会も、全国の大学教授の中で、唯お一人、神戸(昭和四十九年)、大阪(昭和五十八年)と二回会頭を務めておられます。先生のご専門は皮膚の結合織の代謝と研究でコラーゲンやムコ多糖の研究では世界的に御高名で、厚生省の研究班長も長く務められました。ワルシャワ大学のヤブロンスカ教授やコペンハーゲン大学のアスボー・ハンゼン教授などとも親交をもたれ、何度か日本にもお招きになっておられます。大阪大学に戻られた頃は、激しかった学生運動の火も衰えつつあった頃ですが、教室運営には非常に苦労されたとの話を後日良くお聞きしました。私は昭和五十二年の入局で、同期は男二人、女二人でしたが久々の新卒医局員ということで、良く学び、良く遊びにも連れて行って頂きました。佐野先生は関西でも有名なオーディオマニアで、先生のご自宅でも良く自慢のセットでクラシック、時に持参したジャズのレコードを聞かせて頂き、美味しいお酒を頂きながら、音楽や研究、臨床の話に時間の経つのを忘れた事が何度もあったことも懐かしい思い出です。先生は今の時代には存在しないような大人の風格があり、哲学者、芸術家、謹厳な研究者、優しい臨床医などいくつもの顔を持っておられましたが、我々にはいつも気さくに声をかけて頂きました。特に通称「二研」と呼ばれた、旧大阪大学付属病院八階にあった皮膚科研究室のActivityは高く、夕方5時位になると佐野先生が顔をだされ、良く議論されていた姿を思いだします。この研究室からは皮膚科、形成、基礎をあわせ10人の教授が誕生したことからも佐野先生の素晴らしいリーダーシップや先見性が推し量られるかと思います。退官後は大阪船員保険病院の院長を務められ、退職後は好きな絵画や音楽を楽しむ毎日で、私が大阪大学に戻ってきてからは良く教授室に寄って頂き、赴任当時の苦労話や国内・海外の友人、知人の研究や人物評など色々なお話を伺う機会があった事も懐かしい思い出です。晩年は高知でお孫さん達と楽しく暮らされ、ここ数年は看護師、介護士の女性達にも愛され、幸せな最晩年だったそうです。私か研修医の時に先生から受けた皮膚疾患の見方、捉え方、科学的な考え方は、今も私の皮膚科学の基礎になっております。先生の描かれた「死海のほとりで-乾癬-」や「鏡の中-血管母斑症候群-」など皮膚疾患をモチーフにした油彩は皮膚科教室に展示し、日々これらの難治疾患の病態を解明し、根本的な原理により癒せる日の来る事を願い、精進の糧にしております。先生の残された大きな遺産は必らず、次の世代に引き継がせて頂きます。今は、安らかにお休み下さい。
合掌
大阪大学大学院医学系研究科教授 片山一朗
平成27(2015)年6月25日

「鏡の中-血管性母斑症」(佐野榮春1995)

「死海のほとりで」(佐野榮春1995)
第31回日本臨床皮膚科医会総会・臨床学術大会
第31回日本臨床皮膚科医会総会・臨床学術大会
2015年6月20日〜21日
会頭 川嶋利端
会場 オホーツク文化交流センター
大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学皮膚科学
教授 片山一朗

(写真:網走湖の遠景)


大会は旭川医大名誉教授の飯塚一先生の教育講演1「飯塚一コレクション」から始まり、土曜日朝早くから多くの先生が出席された。 シンポジウム5:「学校保健〜学校現場に役立つ皮膚科をアピールするために。興味深いアナフィラキシー症例小ネタ集」は原田晋先生がタコ焼に使う小麦粉中で増殖したstorage mite (実際にはホコリダニなども)によるアナフィラキシーを紹介された。南米からの報告が多いようでpancake syndromeと呼ばれており、アスビリン不耐症の合併が多いそうである。アスビリン不耐症例に関しては感受性HLA遺伝子の解析が進んでおり、花粉症と食物アレルギーが関連する口腔アレルギー症候群やFDEIAなど特定のHLAハプロタイプを持つ人が発症しやすいのかもしれない。この他、ハムスター咬傷での抗原が上皮由来とlipocalinとよばれる唾液由来たんばくの二種あること、何れも検査可能なとのお話であった。原田先生の発表はいつ聞いても勉強になる。 教育講演3 熊切正信 「ホクロ(色素系母斑)を診断する。」は当初,良性の色素性母斑が切除8年後に色素斑として再発、最終的にメラノーマを発症した例を紹介された。結局、最終的にはブレパラートからガンと感じられる感性が重要との話が印象的であった。 シンポジウム8 膠原病の診断と最新治療 川口鎮司 東京女子医大リウマチ科教授「全身性強皮症の早期診断と治療」はエンドキサンバルスが肺線維症に有効だか、内服の長期使用は発ガンのリスクを高めること、RNA polymelase I/III抗体陽性例では強皮症腎の発症リスクが高く、ステロイドの使用は禁忌などの有益なお話をいただいた。MDA5抗体、TIF1γ抗体など皮膚筋炎などでの重要な新規抗体はもうすぐ、保険収載とのことである。ただ最近の診断基準ではレイノー現象、capillaroscopy所見を満たせば皮膚硬化がなくても診断可能と言われたことには抗セントロメア抗体陽性のシェーグレン症候群が入る可能性を質問した。

(写真:原生花園から望む斜里岳)
関係者の皆さんありがとうございました。

熊切先生と能取岬にて
大阪大学大学院医学系研究科教授 片山一朗
平成27(2015)年6月22日
第23回世界皮膚科学会
第23回世界皮膚科学会(World Congress of Dermatology)
学会長 Jerry Shapiro
バンクーバー国際学会場パンパシフィックホテル
2015.6月8-13日
大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学皮膚科学
教授 片山一朗



会場からパンパシフィックホテルに向かう通路に掲げられていたカナダ人画家の絵画。
この大会はオリンピック同様に4年に一回開催され大体、欧州圏とそれ以外の国で交互に開催されている、私は1983年に故安田利顕先生を会長に東京で開催された時に初めて、講演し、その後2007年のベノスアイレス、2011年のソウルに引き続き、今回で4回目の参加になる。他の学会に比べて参加する機会の少ない学会であるが、世界中から1万人を超える参加者があり、多くの知人と再会できることや4年間における皮膚科に進歩や今後の方向を示す講演、発表があり大変勉強になる学会である。 昨今、日本からの海外留学生の減少や国際化の遅れが危惧されているが、このような大きな学会に参加し、多くの人と知り合い交流することが重要と考える。その意味で今回、中国や韓国、そしてインドの活躍が目立ったことで皮膚科においても日本の後退を感じた学会でもあった。ただ日本の皮膚科学が基礎研究を中心に進歩してきたこと、この世界皮膚科学会が感染症、皮膚外科、美容皮膚科などを中心にプログラムが構成されており、日本から発表する意義がやや欠けるのはやむを得ないかもしれない。そんな中、プログラム委員として参画された宮地良樹ILD事務局長のご尽力で50人の日本人スピーカーが講演の機会をもたれたことは何よりであった。ただ個人的にはもっと若手教授がどんどん座長として選ばれ、講演していただきたいと願う次第である。また今回8年?の長きにわたりILD の理事として貢献された宮地教授が退任され、その後任として椛島教授が接戦を制して理事に就任されたことは日本の皮膚科学にとり大きな収穫であり、宮地教授にご尽力に心から敬意を表する次第である。 さてバンクーバーは人口240万人を有するカナダ第3の都市であり、2010年に冬季オリンピックを開催したくらいの予備知識しかなかったが、夏の日差しと爽やかな大気が我々を迎えてくれ、札幌に似たビールの美味しい街であった。街並も機能的に整備され、参加者の先生も学会の合間にバンクーバーを楽しまれたようであった。私自身、今回は白斑、痒みを中心に参加したが、特に白斑の病因論の進歩と今後の治療の可能性に関する発表は得ることが大いにあった。また今まであまり興味がなかったざ瘡も、分子標的薬の副作用としてのざ瘡様発疹症や酒さ様皮膚炎、さらに自然免疫と関連のありそうな口囲皮膚炎など多くの発表があり、私が今研究している11βHSD1/2と関連しそうで、これから新たな視点で治療薬の開発をしていきたいと考えた次第である。教室からは室田准教授、楊伶俐、楊飛、小野大学院生が出席、発表した。

大阪大学大学院医学系研究科教授 片山一朗
平成27(2015)年6月20日
第114回日本皮膚科学会総会
114回日本皮膚科学会
学会会頭 古川福実和歌山医大教授
パシフィコ横浜
2015.5月29-31日
テーマ:デルマドリーム
大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学皮膚科学
教授 片山一朗

古川福実先生が掲げられた学会テーマ「デルマドリーム」どおり皮膚科の夢を俯瞰させるプログラムで構成された学会であった。会頭講演では古川先生が病理医としてのルーツをもたれ、大学院で今の研究の礎となったループスマウスの研究の紹介をされた。和歌山医大皮膚科ホームページにも掲載されている古武弥四郎先生の有名な言葉(写真)を古川流のウイットの聞いた解釈で紹介され、素晴らしいシンボルマーク誕生秘話や古川先生の皮膚科学そして自然科学に対する夢が短時間で語りつくされた講演であった。

学会後、古川先生から会長講演や基礎関連講演は金曜の平日にしたと聞いた。その心は大学院時代?古川先生がある学会の事務局を担当された時、京大時代の恩師濱島義博先生が「自分の専門領域は例え聴衆の数が最低でも一番大きな部屋でやれ」と言われたからとのこと。濱島先生は今や絶滅した古武士の風格のある教授であったが、その考え方は和歌山医大皮膚科のホームページの濱島語録として読む事が出来る。今回古川先生の承諾(事後)を得てPDFを添付した。特に若い先生には一読、十読,百読を勧める。
アレルギー学会同様、皮膚科学会でも今専門医制度改革を見据えた教育プログラムの見直しが行われているが本学会でもその問題点を論議するシンポジウムが組まれ、島田理事長がその現状を総括された。ただ地方皮膚科教室の疲弊の状況や皮膚悪性腫瘍や膠原病などの重症疾患への若い皮膚科医が参入しない現状を討論する場がもっとあってもよかったのではないかと思う。女性医師をいくら支援しても現状が改善すると私自身は思わない。むしろ重要なのは難治な疾患、重症の患者、病因論の不明な疾患の治療、研究に先陣を切って取組み、若い皮膚科医を参加させる熱い気概を持った指導医を一人でも作りだすほうがはるかに重要と最近は考えるようになった。この問題は引き続き開催された世界皮膚科学会でますます感じた。若い皮膚科医よ!!! もっともっと 患者さんの発疹を観察し、皮膚科学を勉強し、生命生物学を研究し、世界と繋がり、皮膚科の発展と患者さんへの新たな治療の創出に貢献してください。
参考に濱島語録を読んでください。
濱島語録 (和歌山医科大学皮膚科教室ホームページより抜粋)

●研究の自由はもっとも尊重されなければらならない。しかしその自由の代償としてそれに対する責任はすべて自分が取らなくてはならない。これが自由の原則である。
●研究室では相互の和、チームワークがもっとも大切であるし、また絶対必要な場合が多い。一切のエゴは許されない。
●研究人生で最も大切な年齢は26~34才まで。この期間にノーベル賞を目標とした猛烈な研究をやって人生生き甲斐のある青春を送って欲しい。人生自分が選んだ道にすべてをかけて純粋に打ち込むことが出来るとは、これ程幸福なことはないであろう。
●研究室で最も大切なことは、どんな簡単なことでも実際にやってみて、いかに自分は不器用であるか何事も実際にやってみると非常に難しいものであるということを思い知ることである。そして何よりも先ず卓越した技術を身につけるべく努力すべきである。
●自己の研究成果は他人によって認められるものであって、自分自らで認めるものではない。自分自身は、得たデータを正直に示すだけでよい。しかし他人というものは悪口こそ云えなかなか認めようとはしないものである。それを認めさせようというのであるから、そこにプロの厳しさがある。
●その顕微鏡写真は一枚一枚真心をこめてとること。これまでの研究の苦労の最終の総まとめがその写真であるし、また最高の写真を撮るためにはそこに到るすべてのテクニックが最高でなければならない。
●濱島研究室で研究を共にしてきた者は、必ず世界の檜舞台で大活躍しなければならない。
●大学院、助手は一年間に2つ以上の英文の原著論文を教授の許に提出しなければならない。発表者は直接研究に携わった者のみにして、たとえ教授であってもその研究を直接に行っていない場合にはその名前を列記することは許されない。
論文を書かない者は研究者としての義務を怠ったものとして破門されるであろう。
論文一つ書けない者は以後の一切の発言が認められなくなるだろう。
●研究室での生活は、どんな些細なことでも綿密にかつマメにノートすることである。
●いかなる場合でも遅刻を許さない。
●すでに他で公表されたものと同じ研究は一切してはならない。他人のやったことは絶対に真似するな。
●研究室貴族を追放する。研究室貴族とは他人の洗った硝子器具を平気で使い、使いっ放しにして洗いもせず跡始末も出来ず、また自分の部屋の清掃すら出来ない先天的不能者を研究室貴族という。お互い共同使用の礼儀を心得、助け合いかつ他人のために尽くすことにつねに心懸けること。
●格調高い人間となれ。人の悪口を絶対云うな。うそをつくな。細かいことにとらわれるな。常に世界の科学者たる自覚をもて。
●労力を惜しむことなくマメに立ち働こう。何事も積極的に行動することが望まれる。
●判らないことは遠慮なくどんどん聞くこと。聞けば誰でも親切に教えて呉れるものである。
●自然科学の研究でもっとも大切なことはどんな些細な現象でも「何故こうなったのか」という疑問を驚きの心で見出すことであり、また見出すべく努力することが必要である。
●諸君が毎日帰る時に、病理玄関を出た際、西側の医化学の教室*を見よ!!彼らはものすごいファイトで研究しているぞ。諸君の帰る時、まだ蛍光灯の輝いているのを見るだろう。彼らに負けるな!!
* 第一講座 早石 修教授
http://www.brh.co.jp/s_library/j_site/scientistweb/no28/
* 第二講座 沼 正作教授
http://mail.mfour.med.kyoto-u.ac.jp/~htsukita/new-pub/Numa%20jidai.html
和歌山県立医科大学皮膚科
http://www.wakayama-med.ac.jp/med/hifu/derma/derma.html
大阪大学大学院医学系研究科教授
片山一朗 平成27(2015)年6月20日
アレルギー学会
アレルギー学会
学会会頭 斎藤博久
高輪プリンスホテル
2015.5月26-28日
大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学皮膚科学
教授 片山一朗

大阪大学大学院医学系研究科教授 片山一朗
平成27(2015)年6月20日
西山先生からのお便り
西山先生からのお便り
大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学皮膚科学
教授 片山一朗

西山先生からはおりにふれ、近況や励ましのお言葉、示唆に富むご助言、箴言を頂き、大切に保存させて頂いている。「昨年から少し講演会を控える」とお聞きしており、心配していたが、久しぶりに頂いたお便りを拝読させて頂く限り、お元気そうで何よりである。今回は強皮症での組織変化に関して、SclerosisとFibrosisが同じ意味で使用されている(硬化と線維化とは病理学的にも、生化学的にも異なる)、あるいは血管の硬化性の変化が充分論議されていない点や皮膚の石灰化が血管の変化よるとの以前からの考え方が反映されなくなったとのご意見を頂いた。我々もケロイドと限局性強皮症の成因が異なる事は良く理解しているが、実際の病理組織変化がどう異なるのか、強皮症での血管の硬化、内腔狭窄などの有無、組織ムチン沈着の部位などや皮膚の硬化、線維化がどこから生じるかなど、あまり考えなくなった事を反省する次第である。また下腿の両側性の硬化病変を来す疾患として、全身性強皮症以外にも好酸球性筋膜炎やHypodermitis sclerodermiformis, Scleromyxoedema,最近ではガドリニウムなどの造影剤による強皮症類似病変(腎性全身性線維症といわれている、添付文書では硬化と記載)があるが、動脈系、静脈系、リンパ管の循環障害などいづれが発症において中心的な役割を果たすか、ムチン沈着の有無やその機序など、かつて論議された重要な問題点が、今日忘れられつつあるようで、もう一度また皮膚脈管・膠原病研究会などで論議したいが、難しいかもしれない。同じ事はかつてこのコラムでも扱った、LSAとMorphea,あるいはAtrophoderma of Pasini PieriniとMoroheaの異同に関しても同じことがいえそうである。Atrophoderma of Pasini PieriniはAtrophic scleroderma D’embleeとも呼ばれるように硬化期を欠き急速に萎縮期に移行する特殊なMorpheaと考えられてきたが、Morpheaと言う病名に起因するLilac ringとよばれる特徴的な紫紅色調変化は見られず、やはり病因論的には異なる疾患と考えた方が良いとも考えるが、そのような議論をすることが難しい時代になった。皮膚の病理組織を勉強するセミナー自体は盛況と聞くが膠原病や血管炎など疾患の成因のみでなく、予後や治療方針の決定にも病理所見を良く理解し、深く知る事は重要であり、猛反省したい。
西山語録には多くの箴言があるが、以下のものは私が北里大学に在籍させて頂いた時に、よく聞かせて頂いた言葉で、今でもいつも繰り返し思い返し、自戒としている。「一例報告はつまらない、是非長期に観察した症例集積研究をしなさい。」この言葉はシェーグレン症候群や抗リン脂質抗体症候群を纏めるきっかけとなった。「ステロイドに頼らない治療を考えなさい。」という言葉によりステロイドを使用する意義、リバウンドの問題を考えるきっかけになり、ステロイドを使用しない外用療法を工夫することの面白さを知った.最近はさらにエスカレートして自分で使用したい新しい外用剤の作成に取り組んでおり、改めて皮膚科の臨床の面白さや皮膚という臓器の神秘性を再認識している。「膠原病はそれぞれの疾患で患者さんの、顔貌、性格、考え方、行動様式が異なりそこから診断されることも多い。紅斑などの皮膚症状、筋炎や血管障害でもそれぞれの疾患の特徴が、皮膚、筋組織や血管に現れる。」という言葉はまさに膠原病の臨床に携わる皮膚科医にとって金言であり、西山皮膚科学の真骨頂であるかと思う。西山先生から受け取ったお便りを読み、あらためて反省すべき事を再認識し、西山先生の言葉に触れる喜びを噛みしめている。
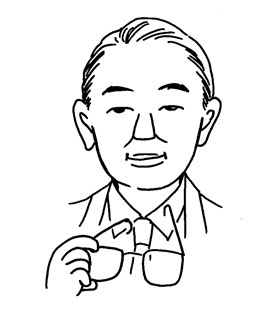

北里大学時代の写真から(教室秘書さんのイラスト画)
学会で西山先生が眼鏡を外され、眼鏡拭きでレンズをこすり始められると、その演題は???さらに首が左右に振られ出すとその演題は却下。教育的指導が必要な時には最後に天を仰いでマイクに向かわれたものである。今回は首を相当横に振っておられ、天を仰いでおられる姿が目に浮かぶ。
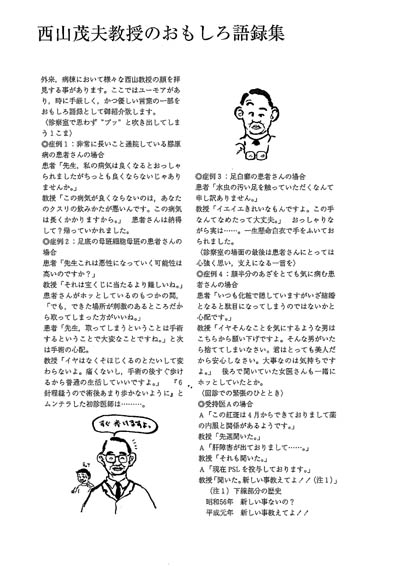
大阪大学大学院医学系研究科教授
片山一朗 平成27(2015)年5月13日
それでも伸びよ、天を目ざして:2015年春
それでも伸びよ、天を目ざして:2015年春
大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学皮膚科学
教授 片山一朗

今年も4月1日、7人の新しい皮膚科入局者を迎え、過日、入局歓迎会を開いた。今年は男性医師3人、女性医師4人の方で皆さん早くも病棟、関連病院で元気にスタートを切られている。スーパーローテートが開始されてはや10年が過ぎ日本の医療、医師教育制度が大きく変わった。特に研修医の大学離れ、医局離れ、そして大学院への進学者や海外留学希望者の減少が毎年この時期になると話題になる。その中でさらに2017年から専門医認定機構が新たな専門医制度を開始すること決定され、いまその制度上の問題点が論議されている(島田眞路、日本医事新報4732.2015.1.3、 JDAレター)。我々の原点である所属学会を無視した現在の新制度の問題点の詳細はまた島田眞路皮膚科学会理事長のコメントを参考にしていただきたいが、日本の専門医制度が基盤18学会+1学会のみではなく、多くのサブスペシャリテイー学会による専門医教育によっている現状を全く無視して新制度のプログラム作りが進行している事が大きな問題点であり、その先にある専門医の品質保証の担保とそのインセンテイブが全く考慮されていない点が挙げられる。実際、欧米の専門医の地位は非常に高く、日本の現状とは遥かにかけ離れた、若い人にとって大きなMotivationとなる待遇が得られる。逆にその対価として要求される大きな社会的責任、生涯に亘る研鑽や技術力の維持は非常に厳しいのは当然である。この10年のもう一つの問題点としてスーパーローテートシステム開始と平行して行われた大学院制度改革にともない、多くの基礎、臨床の教室が講座名称を変更し、特に基礎では何をやっている教室かが全く分からなくなった。確かにアメリカのように大統領がかわるとホワイトハウスのスタッフがすべて入れ替わるのと同様、大学でも教授がかわると、場合により開学以来蓄積されてきた多くの知的財産や貴重な医学資料、機器がすべて破棄され、そこでその教室の歴史に幕が下ろされる。scrap&buildにより新たな研究分野を創出するのは短期の結果が要求される科学の分野では重要かもしれないが、人間として,文化を継承して行く場合,大学の不毛化を加速させる危惧が常にある。大阪大学総長である平野俊夫先生が医学部長の頃、「大阪大学医学部の基礎教室がシャッター通り化している」との危惧を述べられ、大きく研究改革の方向に舵を切られ、最近は以前よりは活気が戻りつつあるが、新たな専門医制度の開始により、大学院への進学がさらに減少する事が予測される。ヨーロッパではどこに行っても新市街と旧市街が混在し、アメリカ型の量販店と伝統を引き継いだ職人が集まる商店街がうまく共存し、大切なその国の歴史、文化を後世に伝えている。翻って今の日本では日本の伝統ある職人芸が滅び、つい最近まで、そこ、ここにあった、地域の商店街が次々と消えていきつつある。大学というアカデミアでもその危機感を共有し、次の世代を育てていくのが我々の大きなや役割である。皮膚科という臨床医学を生涯の専門として選択し、我々の教室に参加された先生も是非自分自身の皮膚科学を確立し、次の世代に伝えて頂きたい。今年、皆さんに贈る言葉は大阪大学の偉大な先人で平野俊夫総長の師でもある山村雄一先生が平野先生に贈られた「樹はいくら伸びても天までとどかない。それでも伸びよ、天を目ざして」としたい。臨床医学とともに、その問題点を解決する基礎医学の分野にも是非、目を向け、楽しい皮膚科医生活を送ってください。
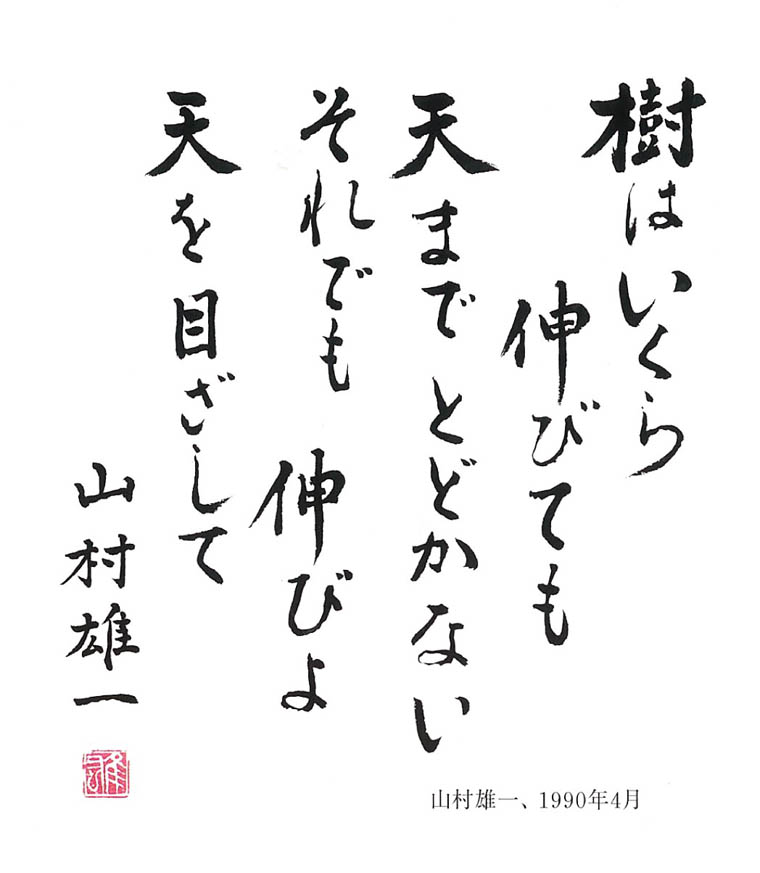
大阪大学大学院医学系研究科教授 片山一朗
平成27(2015)年4月吉日
アトピー性皮膚炎のアウトグローとバイオマーカー
アトピー性皮膚炎のアウトグローとバイオマーカー
第3回小児アトピー性皮膚炎フォーラム(PADフォーラム)
2015.3.14
TKPガーデンシテイ品川
大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学皮膚科学
教授 片山一朗
今年も小児科の先生方とアトピー性皮膚炎の治療や病態研究討論が楽しめる研究会に出席する機会があった。テーマは「小児アトピー性皮膚炎の全身症状と鑑別診断」、「アトピー性皮膚炎のバ難治化とバイオマーカー」、「アトピー性皮膚炎のバリア障害と免疫応答のクロストーク」の3つで、それぞれ皮膚科と小児科の先生からの講演があった。いくつか興味深い話題や論争があったので記録しておきたい。順天堂大浦安病院の須賀康教授はご専門の角化異常症の中でNetherton症候群を中心にPeeling skin syndromeなどの稀少疾患を紹介頂いた。Netherton症候群はLEKTIとよばれるSerin protease inhibitorをコードするSPINK5の遺伝子異常によりKalikelin 5,7,9などの酵素活性が亢進し、Corneodesmosinなどバリアに関わる角層蛋白の分解が亢進し、結果としてバリア障害が生じる。治療ガイドラインにもプロトピックの使用血中濃度の上昇が生じる可能性があり、禁止とされている。KAL5などはPAR2の活性化を介してTSLPなどケラチノサイト由来のTh2への分化因子を誘導することでNetherton 症候群で見られるアトピー性皮膚炎用の症状を呈すると考えられている。バリア機能異常の中心をなすと考えられたフィラグリンはその欠損マウスで特にフェノタイプが見られないこと、尋常性魚鱗瀬でもアトピー性皮膚炎などの症状は見られず、その意義はまた振り出しに戻っている。同様の遺伝性疾患であるNetherton症候群で持続性にTSLPの発現亢進が見られるのであれば、アレルギー疾患が成長とともに重症化するのか質問したが、寛解と増悪を繰り返すそうであり、特に喘息や食物アレルギーが重症化する訳でもなさそうである。我々が学生の頃、アトピー性皮膚炎はアウトグローする疾患として講義を受けた。SPINK5, Filaggrinなどの遺伝子異常があってもアトピー性皮膚炎の進展、重症化に関与しないのもしれない。過去アトピー性皮膚炎は適切に治療すればアウトグローする疾患であったのは事実であり、近年の重症成人患者の増加は環境の変化に加え、不適切な治療が大きな影響をしているのかと考えたが、SulzbergerやBensnierの論文を読むと100年近く前でも成人や高齢者のアトピー性皮膚炎としての記載があり、やはりアウトグローの問題もまた振り出しにもどってしまう。
もう一つは新しいバイオマーカーの話題でTARCに加えSCCA1. SCCA2, Periostinの紹介があった。TARCは皮疹が視診上正常化してもその値が高ければステロイド治療を継続すべきとの意見があるが、TARCが正常でも皮疹が改善しない例や皮膚炎が改善してもTARCが高い例もあり、多数例の検討が必要であろう。Williamsらの論文でもアトピー性皮膚炎の一見健常部でも病理組織で炎症が見られ、Subclinicalという表現で、Proactive療法の正当性を述べている(J Allergy Clin Immunol 2014;133:1615-25)。ただこの論文は26の論文から20編の論文を選び、Systematic reviewしたもので、すべて病理学的な検討をしたものでもなく(多くがプロトピック使用群)、使用する治療もステロイドやプロトピックが混在し、総投与量や軽快後の治療中止時期もはっきりとはしないと述べられている。アトピー性皮膚炎でのSubclinicalの定義は難しいが、座長を御一緒させて頂いた河野先生がおっしゃられた「治療を中断するとすぐに再燃する病態をSubclinicaalとした方がよい」という考え方も一理あるかと考えた。またペリオスチンは乳幼児期で成長期には高値を示すことで小児期のアトピー性皮膚炎のバイオマーカーとしては不適とのコメントがあった。ペリオスチンは組織リモデリングのさいに線維芽細胞から産生されることが明らかにされているが、痒疹ではあまり発現が見られないことが報告された。同様の現象はアーテミンでも見られ、アトピー性皮膚炎で発疹型によりバイオマーカーの意義を考える必要があるのかもしれない。乳幼児はどちらかというとバリア異常や発汗障害による乾燥型汎発性の表皮を中心とした湿疹病変や膿痂疹の合併などにびらん、滲出性の病変が主体であり、成人型に見られる強い苔癬化や痒疹性の病変などの真皮の慢性病病巣ともなうことは少ない。バイオマーカーも年齢や皮疹の性情で検討すべきなのかもしれない。実際、日本皮膚科学会の治療指針では乾燥肌主体の病変は保湿剤、痒疹、苔癬化は最強のステロイドの使用を推奨している。また成人型にはより複雑な難治化因子や悪化因子が関与しているのは過去に多くの報告がある。バイオマーカーのみでステロイドを長期に使用するリスクが危惧されるProactive療法は特に皮膚科以外の非専門医の先生には簡便なようで混乱の原因となるかもしれない(膠原病の診療も現在は抗核抗体、さらに特異抗体の有無で治療方針が決定され、皮膚症状の評価は病理検査も含めあまりなされなくなりつつある)。古江先生がかつて開業の先生方のデータを取り纏めて報告されたようにステロイド治療が適切に行われれば多くの症例は改善するが、半年間の使用で用量依存性に皮膚の副作用が出現し、また一定の割合で改善しない例が見られた。これがステロイドの使用量が少なかった(局所副作用は見られる)のか、鑑別診断、悪化因子の除去が不十分だったのか、デコイレセプター(ステロイド不応性)誘導、あるいは発疹型の差であったのか、先に述べたProactive療法の適応病変、使用外用剤の選択、軽快後の使用部位、中止時期の検討などと合わせ継続して、論議することが必要であると考えた。(勉強不足ですべての論文に目を通している訳ではない)。
大阪大学大学院医学系研究科教授 片山一朗
平成27(2015)年3月16日掲載
第78回日本皮膚科学会東京支部学術大会
第78回日本皮膚科学会東京支部学術大会
会頭 横関博雄東京医科歯科大学教授
会場 東京京王プラザホテル
会期 2015年2月21〜22日
テーマ —皮膚科における再生を目指したあらたな展開—
大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学皮膚科学
教授 片山一朗

第78回日本皮膚科学会東京支部学術大会が2月21日から2月22日までの2日間、東京京王プラザホテルで開催された。会頭の横関博雄東京医科歯科大学教授、事務局長の井川健先生には御礼申し上げると共に、お疲れさまでしたと言わせて頂きたい。昨年の77回大会は東京が大雪に見舞われ、参加者が少なく、交通マヒに加え、帰宅できない先生も居られ、会頭の照井正教授が大変苦労されたという話を思い出したが、今年は2,000人近い参加者があったそうで、何よりだった。ただ日曜の東京マラソンと重なり、ホテルがとりにくかったという話も聞いた。学会そのものは大成功で、横関先生の会頭講演「発汗研究の歴史から見えてくる新たな皮膚疾患の病態」から始まり、日本の発汗研究の創始者である名古屋大学の久野寧先生、横関先生が留学されていたアイオワ大学の佐藤賢三先生の単一汗腺の単離に基づく膨大な仕事を紹介された。

海外からは横関先生と長年、親交のあるミュンヘン大学のThomas Ruzickaが「New development of Hand Eczema」,ボン大学のThomas Bieber教授が「Atopic Dermatitis :lessons from the pathophysiology for the management」を講演されたほか、東京大の水島昇教授が「オートファジーによる細胞内分解」、大阪大の澤芳樹教授が「心筋再生治療の現状と展望」のタイトルで、基礎、臨床それぞれの分野で最近大きな成果をあげておられる2人の先生からの素晴らしい招待講演があった。特にBieber教授は今後重症例や難治例に次々と新しい生物製剤が登場することでアトピー性皮膚炎の根本的な治療が可能になるのではとの話があった。IgEの関与しないタイプのアトピー性皮膚炎への効果や、Bieber教授がご自身のTextの中で引用されている、種井良二先生(東京都健康長寿医療センター皮膚科部長)の提唱されているSenile atopic dermatitisについても言及されており、アトピー性皮膚炎が小児にとどまらず高齢者においても今後問題となる可能性につき述べられた。この問題は私と獨協大学の片桐教授とが座長を努めたシンポジウム「高齢患者をどう治療するか?」でもとりあげたが、昨今ステロイドの内服、外用が漫然と行われている老人性紅皮症が増加しており、その病態の解析を早急に進める必要性を感じた。教室の田原先生が阪大の症例を提示し、原因や悪化因子を明らかにし、患者指導、適切な外用療法の指導や光線療法を組み合わせる事で、多くの症例が改善していく事を報告された。(T Helper 2 Polarization in Senile Erythroderma with Elevated Levels of TARC and IgE. Nakano-Tahara M, Terao M, Nishioka M, Kitaba S, Murota H, Katayama I Dermatology. 2015;230(1):62-9.)。

祝辞を述べられるThomas Bieberボン大学教授
シンポジウムは東京医科歯科大学皮膚科で研究が進んでいる再生医療、好塩基球研究、発汗異常、悪性黒色腫などのテーマを中心に興味深いプログラムが組まれ、どの会場も満員の盛況であった。特に高山かおる先生が座長を努められたフットケアのセッションと三浦圭子先生が座長を務められた「お茶の水診断カンファレンス」はテレビなどで放映された話題や大学横断的に進められている勉強会の成果が取り上げられ、医科歯科大皮膚科のパワーを示す素晴らしい企画,内容であったと参加者からお聞きした。その他皮膚科教育の再構築、女性医師支援をテーマとする企画も組まれ、皆さん総会に匹敵する充実したプログラムを楽しまれたようである。また懇親会でも高山先生が素晴らしいフラダンスを披露されたそうで、FBなどでも絶賛されていた。
またこの東京支部学術大会開催と時期を同じくして東京医科歯科大学皮膚科開講70周年を迎えられ、その記念誌が参加者に配布された。私も「よく遊び、よく研究した時代を振り返って」のタイトルで、以下のエッセイを寄稿した
「横関先生、東京医科歯科大学皮膚科開講70周年おめでとうございます。
私は平成2年7月から平成8年の6月までの6年間、東京医科歯科大学の皮膚科に在籍させて頂きました。前任が北里大学皮膚科であり、そのまま医科歯科大学の方に移動した記憶があります。当時旧館(?)の6階に医局と教授室があり、助教授室は8階にありました。着任した時は研究室も多くの実験機器が埃を被っており、西岡先生が購入された超遠心器のみが輝いていた事を鮮明に思い出します。西岡先生は着任早々に旧い試薬類を処分され、翌日神田川に魚が浮いたという話もよく聞かされました。私が着任時まだ横関先生は北里大学から河北総合病院に出向されていた関係で、免疫の研究をやっていたのは浜松医大から大学院の研究を終えられ、帰局されていた佐藤貴浩先生(現防衛医大教授)のみであり、二人で研究室の大掃除をし、クリーンベンチを入れ、細胞の培養を開始しました。しかし培養フラスコで増えてくるのは真菌ばかりでさすがに気がめいりました。しかしそのような中で帰局された山本俊行先生(現福島医大教授)がブレオマイシン誘導性の強皮症マウスモデルの作成、松永剛先生がいち早く導入されたPCR-Primer合成器を使い、接触皮膚炎の3次元培養にモデルでのサイトカインmRNAの発現をPCR法で検討する実験を始められました。当時は私もまだ若く良く助教授室に泊まり込み、実験をしました。大体夜、8時前に出前をとりビールを飲んでいると、よく西岡先生が合流され、そのまま近くの飲み屋に席を移し、研究や臨床の話で盛り上がりました。
臨床的には当時、重症の成人型アトピー性皮膚炎がたくさん来院されステロイド忌避の問題も大きくマスコミに取り上げていた時期で、谷口裕子先生(現九段坂病院部長、塩田裕子先生)にはたくさんの症例を纏めあげて頂き、アトピー白内障やリバウンドの問題に関して素晴らしい仕事をして頂きました。また澤田泰之先生(現墨東病院部長)には膠原病患者の全身管理をやって頂き、たくさんの強皮症患者さんの治療を担当してもらいました。若い女性の皮膚筋炎患者や抗リン脂質抗体症候群の何人かを救命できなかった事も今となっては残念ではありますが、貴重な経験でした。このように臨床と研究に本当に充実した6年間でしたが、96年に長崎大学の教授に選ばれ、お茶の水を後にしました。」。
会期中に横関先生の還暦を祝う会が教室主催で開催され、多くの方が列席された。西山茂夫北里大学名誉教授からは 「汗」と揮毫された色紙が届けられた。

横関教授の還暦祝いの会。司会の高河慎介と奥様とともに。
大阪大学大学院医学系研究科教授 片山一朗
平成27(2015)年2月26日掲載
アトピー性皮膚炎治療研究会&日本皮膚科心身医学会
第20回アトピー性皮膚炎治療研究会
テーマ:「スアトピー性皮膚炎の痒み」
平成27年2月14日
第5回日本皮膚科心身医学会
テーマ:「皮膚科心身医学はじめの一歩」
平成27年2月15日
会頭:水谷 仁(三重大学大学院皮膚科学教授)
会場:鳥羽国際ホテル
大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学皮膚科学
教授 片山一朗

会場からのスナップ
ここ数年以上、日本の皮膚科学会、アレルギー学会関連でのアトピー性皮膚炎の治療に関する発表が激減しており、結果として、アトピー性皮膚炎の診療が問題なく行われているのかと誤解しがちである。逆にフィラグリンなどのバリア機能異常や食物アレルギーの経皮感作が小児科の先生を中心に活発に行われ、アトピー性皮膚炎発症のハイリスク患者の出生時からのスキンケア介入のアレルギーマーチ阻止効果の素晴らしい結果が公表され、小児科領域ではその研究が盛んである。皮膚科領域に置いては今後のIL31やIL4を標的とした分子標的薬や新たな痒み治療薬の登場までここ暫く痒みの治療や疫学研究、GWAS解析などの研究が主体であるようである。その意味でこの会は皮膚科領域のアトピー性皮膚炎の診療に携わる医師が年に1回集まり、共通のテーマで討論し合うユニークな研究会であり貴重な会であった。しかし、20回を経過し、世話人の中からも会員が高齢化している、ポスター発表を導入し若い方を参加させる方法論を進めるべきだとの意見が出てきた事も事実である。実際参加されている先生は地元のアトピー診療に携わっている方以外は司会や演者を努められる大御所の先生ばかりであり、若い先生の発表や討論への参加は殆どなかった。
その中で気がついた事を記録しておきたい。
江畑先生は痒みの評価に関するグローバルな委員会のメンバーでVAS、VRS(Verbal rating scale), NRS(Numerical rating scale)の評価などのコンセンサスMeeting に参加され、その成果を公表されている。現在ご自身が携わられている5D Itch scale の日本語版の作製状況とその成果を発表された。今後他疾患との比較が必要と述べられた。青木先生は日常生活における10 項目の言葉による評価(VeS)の有用性と今後の応用に関して口演された。私自身入浴習慣、就労の有無、基礎疾患による差などをどう反映させていくかを質問させて頂いた。ランチョンセミナーでは上出先生が睡眠障害の実態をご自身の研究をふまえ、口演された。江畑先生等と開発されたビデオによる掻破行動の検討結果や我々が発表した論文を引用して頂き、特にシクロスポリンが痒みとそれによる掻破行動を抑制する事で睡眠の改善効果があることを口演された。実際には100mを食前に内服すること、12週を目安に投薬する事で睡眠障害が改善するとのことであったが、初期量を150mgとやや高目に設定する、あるいは分2食後にするなどの意見がでた。私は、副作用発現のモニターをすることもなく一般の先生がシクロスポリンを使用するリスクや悪性リンパ腫発症の可能性など、今後後発薬が主体になった時の情報提供の問題や、離脱できない症例をどうするかなどをお聞きした。広島大学の秀先生からは2例の患者で問題なく休薬で来たとの発言があったが、座長の塩原先生からは何%位が離脱可能かとの質問もあり、10例位で2例とのコメントであった。塩原先生同様、私もあまりシクロスポリンは使用しないので参考になった。
午後からのシンポジウムは所用で聞けず、その後横関先生のスイートセミナーから会場に戻った。スギ花粉尾飛散時期に露出部に皮膚炎が生じやすい事、スクラッチパッチテストでCryJ1に即時反応に加え、遅発反応がでること、マウスでCryJ1による皮膚炎の惹起が可能であることなどを口演されたが、経皮感作されたマウスで花粉症が惹起されるのか?あるいは人のスギ花粉症が経皮感作されるか、その場合の経上気道・鼻粘膜感作との抗原提示がどう異なるのか、対応する抗原エピトープは同一かなどの検討が必要であろう。
その後は痒みの最新の知見につき、古江先生からお話があり、今後続々と新しい痒み治療薬が登場する予定との夢のある話を頂いた。その後唯一の一般演題があり、阪大から中野先生が、また獨協医大の片桐先生がそれぞれ痒疹の治療に対する発表をされた。中野先生には片岡先生から質問があり、タクロリムスを使用することも(我々は当然使用していない)予測されるエキシマを顔面に使用して、問題がないかという不思議な質問があった。日常生活で暴露される顔面の紫外線防御のことを考えてのご質問かと思うが、150mJの照射が問題になるのであろうか?またエキシマを一部に照射後、非照射部以外の病変も改善したが、ステロイドの効果でないかとの質問があった。そのあと秀先生からも「ステロイドの外用が不十分なだけではないか」との質問があった。今回の検討は複数の前治療施設でステロイド外用を行ったが無効で、阪大初診時、ステロイドの副作用が目立ち、減量などができない症例に、すべての前治療は継続し、エキシマライトの部分的な照射をオンしたのみである。試行したすべての患者の結果を解析したが、当方の初期の予想と全く逆の結果であり発表した旨コメントした。リバウンドなどで基礎治療薬を変更できず、部分照射部と非照射部でコントロールになるかと判断して頂けるかと考えたが、当方の説明不足だったかと反省している。一般的に、疫学研究や治療介入試験などでは対象とする患者やコホートが研究者の関与する範囲に限定されることが多く、Biasがかかる事が多い。ステロイド外用によるタイトコントロールに関しては以下の点について不明であり、また論文で発表して頂ければと思う。そこからまた、この治療法の是非が科学的に論議されることを期待したい。
○ ステロイドのタイトコントロールの登録症例がステロイドの未使用例か、Washout した症例なのか?
○ 対照として前治療は継続し、悪化因子の検討と除去を行った症例と比較したのか?
○ ステロイドの副作用が見られる症例も組み入れられたのか?
○ TARCが下がり、減量ないし中止できた例が登録症例の何%くらいおられたのか? また正常域まで低下するのに平均どれくらいの時間とステロイド量が必要となるのか?
○ 顔面のステロイドの使用もTARC値が正常化するまで継続するのか?
○ 皮疹改善後検査にてTARCが正常化を確認するまで最低一ヶ月以上(月1回の査定)の時間が必要であるが、その間もステロイド外用を継続するのか?
○ TARCの低下の見られない症例、特に小児例はどう治療されるのか? 特に片岡先生のような豊富な臨床経験がなく、皮疹の評価できない非専門医がこの治療を安易に行った時のリスクをどう考えられるのか?
○ TARCが下がらない場合悪性リンパ腫や他の炎症性疾患を鑑別できるのか?
○ TARCの産生細胞は現在なお不確定で、特異性にもまだ議論があり、血清値で副作用や感染症も含めたアトピー性皮膚炎の多様な皮膚症状をモニターすることは可能なのか?
ステロイドは抗炎症薬として効果があり適切な使用を行う事で有用性があることはコンセンサスが得られているが、世界のGLでは数週を目処にランクダウンあるいは土日に限定して使用する(Weekend therapy)など副作用の発現を押さえる使用法が推奨されている。
●Furue M et al. Clinical dose and adverse effects of topical steroids in daily management of atopic dermatitis. British Journal of Dermatol 148:128–133, 2003
●EIchenfield LE et al. . Guidelines of care for the management of atopic dermatitis. Section 2.Management and treatment of atopic dermatitis with topical therapies. JAAD.
2014 ;71(1):116-32.
また近年高齢者の湿疹患者に最強のステロイドの外用とステロイド薬の内服が長期に行われている例が増加している。これらはやはり安易にステロイドを処方し、悪化因子や背景疾患の是正、治療を検討せず、漫然と処方を継続している患者に多い。
●Nakano-Tahara M, et al. T Helper 2 Polarization in Senile Erythroderma with Elevated Levels of TARC and IgE. Dermatology. 2015;230(1):62-9.
繰り返しになるが、アトピー性皮膚炎の治療、特に難治例は悪化因子や背景因子の解決なしに十分な治療効果を得ることは難しい。逆に軽症例に過剰な治療を行う事も慎むべき事で、これらの点を科学的に評価し、問題点を吟味し、GLに反映させていく事が我々アレルギー疾患の診療に関わる医師のつとめと考える。現在の高齢者の紅皮症のなどの増加を見ると「ステロイドのタイトコントロール」という一一見Attractiveな治療法が一人歩きし、科学的な根拠なしに無批判に行われた場合、また20世紀後半の混乱した時代に逆行する可能性があると危惧する。本療法の結果をとりまとめた論文を示され、冷静な議論がなされる事を望む。
2日目の日本皮膚科心身医学会では「香りが精神、身体におよぼす効果」
とのタイトルで小森 照久教授(三重大学看護学科成人・精神看護学講座) のアロマに関するお話を興味深く拝聴した。特にバレリアンというアロマオイルは経口的にも処方可能でGABA代謝の改善を通じて、抗欝作用がある事を示された。また一般社団法人自然療法機構 理事の影山むつみさんがアロマ療法の実技を講演され、参考にさせて頂いた。痒みの治療にもアロマは有効との論文は多く、我々も積極的に本療法を日常診療に取り入れていきたい。勉強するべき事が増え、考えさせられる発表も多かった有益な研究会であった。

| アトピー性皮膚炎治療研究会第20 回シンポジウム プログラム | |
| 第5 回日本皮膚科心身医学会 プログラム |
新宿新都心皮膚研究会—三橋善比古先生を偲んで—
新宿新都心皮膚研究会 —三橋善比古先生を偲んで−
2015年2月1日(日)
ハイアットリージェンシー東京
大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学皮膚科学
教授 片山一朗
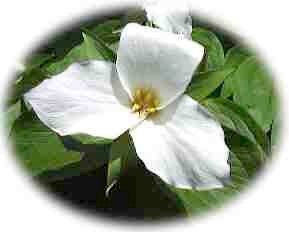
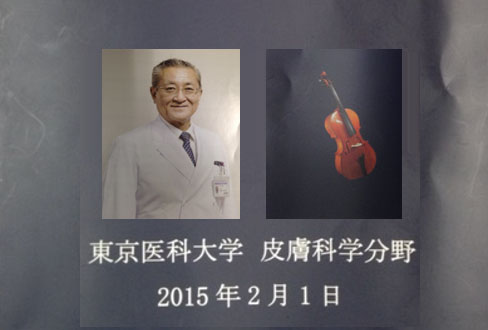
私自身は当日、彼と過ごした日や、熱い議論を行った時代を振り返り、彼の思い出を話をさせて頂いた。最後に北大寮歌「都ぞ弥生」で彼との暫くの間のお別れとしたい。
(110回日本皮膚科学会総会 大阪にて)

花の香漂う宴遊(うたげ)の莚(むしろ)
尽きせぬ奢(おごり)に濃き紅や
その春暮れては移ろう色の
夢こそ一時青き繁みに
燃えなん我胸想(おもい)を載せて
星影冴(さや)かに光れる北を
人の世の 清き国ぞとあこがれぬ
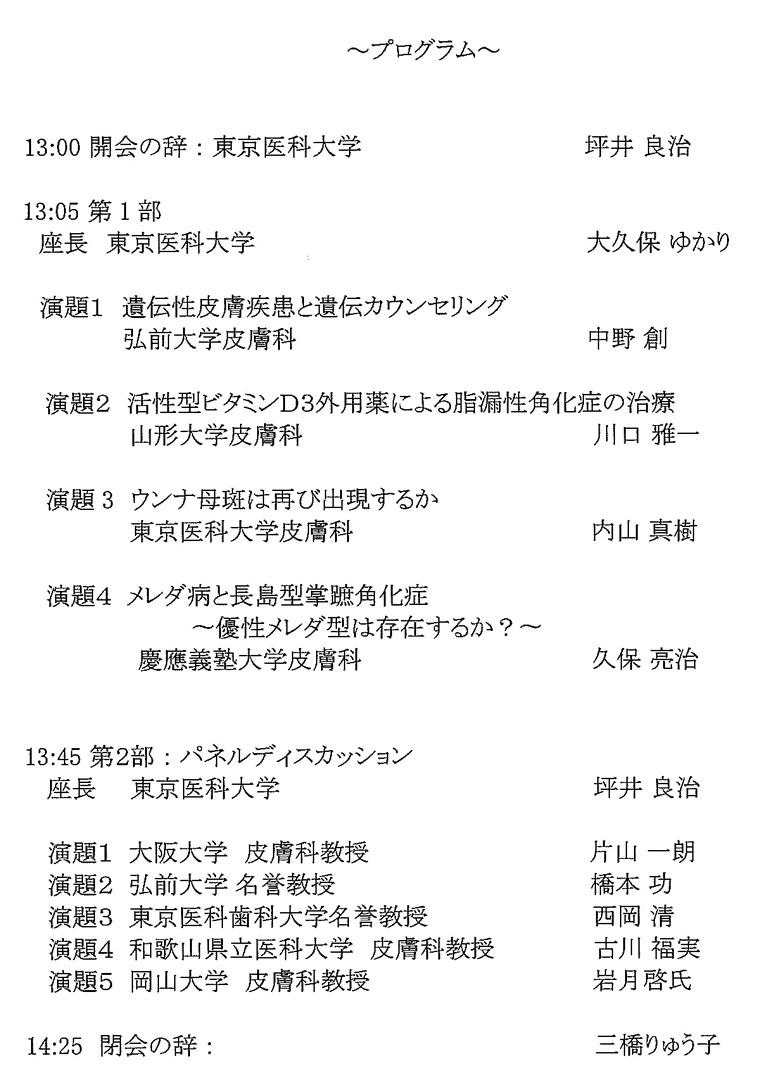

Leena Bruckner-Tuderman教授と三橋先生(2003年)
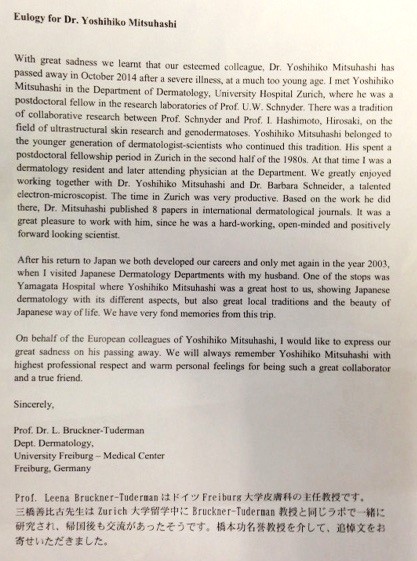
大阪大学大学院医学系研究科教授 片山一朗
平成27(2015)年2月5日掲載
第38回皮膚・脈管膠原病研究会
第38回皮膚・脈管膠原病研究会
会場:国際医療福祉大学三田病院三田ホール
会長:佐々木哲男 国際医療福祉大学熱海病院
会期:2015.1.23−24
大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学皮膚科学
教授 片山一朗
年初の最初の重要な学会である、皮膚脈管膠原病研究会に出席した。前日から東京で用務があり、久しぶりに初日の午前からの出席だったが、すでに結構な数の、しかも他の学会では悪性腫瘍学会くらいでしか見かけない若い男性医師の出席者が目立った。初日午前中は例年に比し、血管炎の演題が多く、活発な議論があった。これは2012年に血管炎の国際Chapel Hillコンセンサス会議による血管炎の改訂があり、病因論や分類が大きく変わった事も影響しているかと思う。特に我々の世代では Wegener, Churg- Strauss, Henoch-Schönleinなどの診断名に慣れ親しんだ世代にはその病名、名前を聞けば、ある程度臨床像や予後、病因論が共通の認識事項として共有できたが、PR3-ANCA, MPO-ANCA, IgA, Hypocomplementemicなど特定の施設でしか診断できず、またその病因論との関わりや特異性が不明の抗体や検査所見で分類する今回の改訂病名はどこかで見直しがあるのではと考える。Hypocomplementemic urticalial vasculitisはGammonの最初の報告例がSLEを合併しており、そのために低補体血症が強調されすぎているのではとの議論があった。またHenoch Schönlein Purpura (Anaphylactoid purpura)はIgA血管炎という無機質な名前になったが、歴史的には、1837年にSchönleinは関節の腫脹性疼痛と紫斑で発症した患者を初めて記述し、1874年にHenochが腹部疝痛・嘔吐・血性下痢などの腹部症状と紫斑で発症した患者を報告したのが本疾患の命名の由来であることを理解しておかないとIgA腎症におけるIgA1の沈着などIgAのサブクラス別の皮膚、消化管、腎などへ沈着した抗体の対応抗原解析を検討した時に混乱が生じる可能性もあると危惧され、私も演題、13、14に発言した。またANCA関連血管炎に関してもEGPA(Churg Strauss症候群)におけるMPO—ANCA陽性/陰性例の病理組織学的検討の発表があった。EGPAではMPO-ANCAは40%前後、MPAでは90%に陽性、またGPAではPR3−ANCAが30%程度に陽性とされるが、今回の発表(演題9)ではMPO-ANCA陽性例では好中球優位、陰性例では好酸球優位の細胞浸潤がみられたとのことで、あらためてEGPAの好酸球の病因論的な検討が必要と考えられる。好酸球の脱顆粒の有無による臨床像の差なども検討が望まれる。
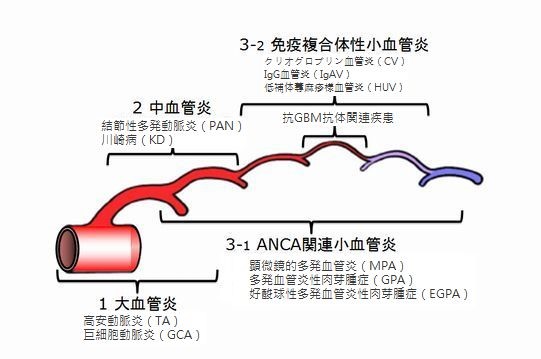
膠原病に関しては、皮膚筋炎でのMDA5抗体やTIF1γなど新しい疾患特異的かつ急性間質性肺炎や悪性腫瘍などの予後を決定する病態と密接に関わる新しい抗体の研究が進み、近々保険収載されるとのことで、本当に基礎から臨床に還元された素晴らしい成果かと考える。またMechanic hand に関連して抗アミノアシル tRNA 合成酵素(ARS)抗体陽性のPM/DMと診断される例で、筋炎症状を欠き、典型的な皮膚筋炎の皮膚症状を欠く症例をどう位置づけるかという質問をしたが、ARS症候群として経過を観察するというというコメントがあったぐらいで、皮膚筋炎の診断と治療の難しさを再認識した(演題52-54)。シェーグレン症候群が新しく国の難病に指定されたこと、また皮膚症状を重視したSLEの新しい診断基準が提示されたことで、関連する演題の発表も多く、多くの収穫を得た学会であった。さらに子宮頸癌ワクチン接種後に生じたSLE的な病態(演題60)やヒドロキシクロロキンの第3相試験の結果報告(65)なども記録しておくべき発表と考える。大阪大学から発表された山岡、林先生の演題はいづれも興味深かったが、現時点でははっきりとした病態は不明で適切な治療はなさそうで、今後の経過を注意深く観察する必要があると考える。
2年前のこの会で神崎保先生が、皮膚科からも症例報告のみでなく新たな研究成果を発表して頂きたいとの意見を頂戴したが、今回の発表を聞いた限り、若い先生の新しい視点からの発表が増加しており、その中から生まれる疑問を解決する研究を是非発展させて頂きたいと心より願う。
最後になるが千葉大の神戸直智准教授がWEBサイトに書かれていた「重要な症例を論文として記録する」という私の考え方に対するコメントを紹介し、学会記とさせて頂く。
「症例を記録するということの大切さ」
神戸 直智 → 片山先生
そうなのですよね。実は,それが一番確実な症例情報の保存方法であり,また後生に受け継がれていく貴重な(人類としての)財産となるのですよね。そして,今ある学問は,そうした先人達の蓄積の上に成り立っているのだと,感じる場面があります。築かれてきた先人達の英知を,ただ消費するだけでなく,何かしらを創造して,次に続く者達へと受け継いでいけたら‥‥と思います。

大阪大学大学院医学系研究科教授 片山一朗
平成27(2015)年1月30日掲載
2015年を迎えて:「葆光」―無心の知
2015年を迎えて:「葆光」―無心の知
大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学皮膚科学
教授 片山一朗
21世紀も、はや15年目となる2015年の新春を迎え、皆さん新たな気持ちで年頭の目標をスタートさせておられるかと思います。
私も、2004年に大阪大学に着任し、今年3月で在任期間が11年となります。私自身一つの施設に10年以上在籍した経験はなく、長崎大学の7年8ヶ月が一番長く勤務した大学になります。昨年の年末の同門会でも挨拶させて頂きましたが、10年以上の長期間、同じ施設にいますと、どうしてもその場に安住し、目の前の目標を達成する事のみに思考、行動が向かい、長期的な展望が描けなくなってきます、また組織論的にも色々と修理が必要な場所が出てきます。結果的に組織の衰退につながることが起こりやすくなります。



そして、その先にあるのは荘子(注1)、最近ではケン・ウィルバーのいう境界のない世界(注2)かと思いますし、西岡清先生から頂いた「遊」はまさにそのような世界に到達するための手段あるいは結果であると理解できるようになりました。毎年言ってきました、医学界、社会、そして世界をとりまく多くの問題も「遊」の考え方で生きれば些細なことになるのでしょう。無境界の世界に到達すると、すべて楽に生きて行くことができるということも私には重要な課題です。もちろんこれはあくまで私の個人的な考えであり、若い先生はまず世界の広さと自分の小ささを理解し、そして目の前に立ちふさがる高い壁を乗り越えて頂きたいと思います。そこから先に自分が本来やるべきことが見えてくるのではないかと思います。私も「遊」の世界、そして「無境界」の世界をめざし、今年も皮膚科学を楽しみたいと思います。
注1)荘子:逍遥遊篇より(抜粋)。
列子の飛翔はなお風に依存し、彼の超越はなお外に在るものにとらわれている。つまり彼の超越はまだ真に自由自在な絶対の境地には達していないのである。ところが天地の正常さにまかせ自然の変化にうち乗って、終極のない絶対無限の世界に遊ぶ者ともなると、彼はいったい何を頼みとすることがあるだろうか。 彼は、大自然の生成変化の極まりなきがごとく、一切の時間と空間を超えた絶対自由の世界に逍遥するから、何ものにも依存することなく、何ものにも束縛されることがない。
注2)立花隆「宇宙よりの帰還」最終章。エドミッチェルとの対話、司馬遼太郎。「空海の風景」、立花隆、司馬遼太郎「対談集」より抜粋。
月に行った宇宙飛行士は「神との一体感」など多くの神秘体験を経験し、地球に帰還後は伝道師やESP研究者などになった方もいるそうです。宇宙では精神が澄み渡り、Flicker-flash phenomenonとよばれる一瞬の脳の閃光現象を何度も経験するそうで、それは宇宙からの素粒子が脳の視神経回路に当たる事で生じるのではないかと考えられているそうです。私が今一番魅かれる考え方は「ケン・ウィルバーのいう境界のない世界、「無境界」であり、ミッチェルはそれを宇宙空間で突然湧き上がった神(キリスト教の神ではない)との一体感を感じた世界と述べています。
→出光美術館
http://www.idemitsu.co.jp/museum/index.html
→住友コレクション 泉屋博古館
http://www.sen-oku.or.jp/
大阪大学大学院医学系研究科教授 片山一朗
平成27年1月5日掲載
第438回日本皮膚科学会京滋地方会 宮地良樹京都大学皮膚科教授退任記念地方会
第438回日本皮膚科学会京滋地方会
宮地良樹京都大学皮膚科教授退任記念地方会
日時:平成26年12月19日(金)〜20日(土)
於: メルパルク京都 12月19日(金)
京都タワーホテル 12月20日(土)
大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学皮膚科学
教授 片山一朗
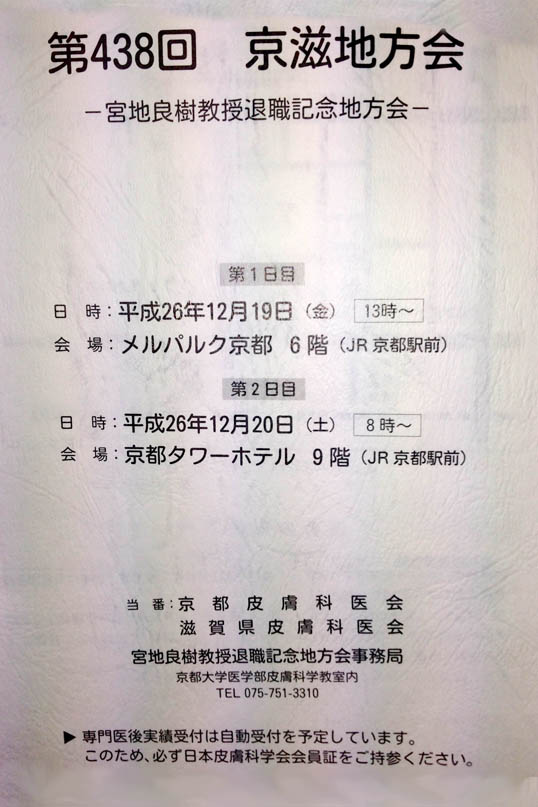
宮地良樹先生の退官記念京滋地方会に出席した。退官後は宮地名誉教授と呼ばれておられるようであるが、私と同じ卒業年度でまだ名誉教授という肩書きは早すぎると感じたのは私一人ではないと思うが、あらためて時の経過の早さに驚いている。宮地先生は私が研修医の頃から、京大のDTICカルテット(滝川雅浩浜松医大名誉教授など4名の若手京大皮膚科の先生方の頭文字からの愛称)に続く京大のRising starとして活躍されており、特に英語での発表や質疑応答は有名であった。またその頃から別の分野でも大変有名であった。(詳細は彼の現役最後の教本?である「紡ぐ言葉」のT教授、H先生の寄稿に詳しいそうである)。
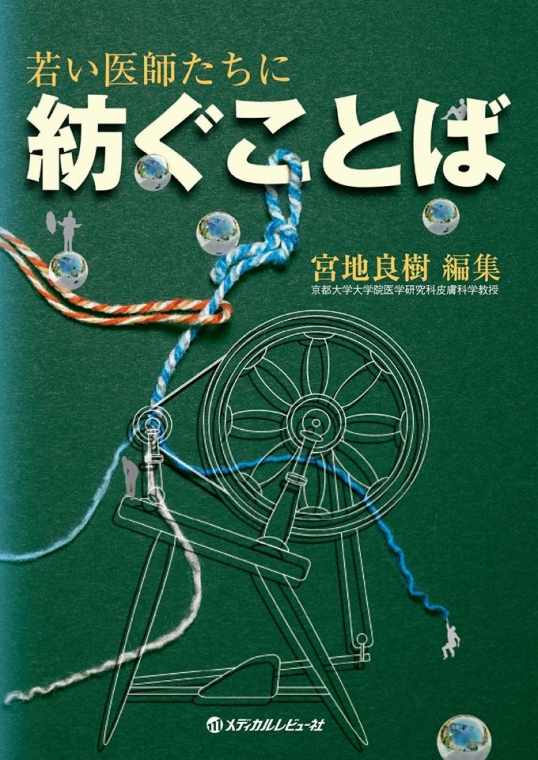

「記念講演開始、座長は盟友古川福実和歌山医大教授」
彼の様々な分野での活躍の軌跡は、先に述べた退官記念誌(紡ぐ言葉)やVisual Dermatologyの退官記念号(忘れ得ぬ患者さんたち)に記録されている。また今回の地方会でも多くの教授が出席され、口演、あるいは懇親会の席で彼の業績やエピソードを語られた。浜松医大の戸倉新樹教授はBad Yoshiki とGood Yoshiki (ちなみに時と状況によりBadとGoodが入れ替わるのは周知の事実)という名前で彼との思い出を語られ、あらためて彼の素晴らしいお人柄の一端を紹介された。私自身は彼が40歳(?)の若さで群馬大学の教授になられ、私が東京医科歯科大学の助教授として東京に異動してから特に親しくお付き合いして頂き、アレルギー関係の研究会でも良くご一緒させて頂いた。その頃からいわゆる「宮地本」と呼ばれる彼が企画編集された多くの教本に執筆させて頂いた。「よくまあ、次々とアイデアが出るものだ」と感心したのも懐かしい思い出である。彼の話では横積みにすると軽く彼の背丈を超えるそうである(この「宮地本」の意義も「紡ぐ言葉」のS教授の寄稿に詳しい)。下の写真は2002年EADVでプラハを訪れた時にたまたま奥様とご一緒の宮地先生とのスナップで懐かしい写真である。

その後私が長崎に移り少しお会いする機会は減ったが、2004年に大阪に戻ってからは「天王山カンファレンス」と名付けられた年一回の京大と阪大の研究会などで楽しい時間を共有することが出来た(リンク)。また2007年に古川福実和歌山医大教授と3人で対談した「病院皮膚科が生き残るために」(リンク)は今読み返しても宮地先生の先見性が随所に見られる。地方会では私もHomeostasisの二元論の観点から皮膚のリモデリングの話をさせて頂いた。
翌日は午前中の静かな時間に学会場近くの泉涌寺、雲龍院を訪れ、庭園や瞑想石を楽しませて頂いた。雲龍院本堂では女性が一人写経をされている姿が印象に残った。

「神社のような霊気の漂う泉涌寺参道」珍しい下り坂で、目の位置が本尊に合うそうである。

「泉涌寺のおめでたい七福神巡りの色紙」
宮地先生は現在滋賀成人病センター院長職として相変わらず忙しい毎日を過されているようであるが、FBを拝見する限り、海外、国内でグルメを楽しまれているようで、同世代の仲間として心より「無事の退官」をお祝いし、お疲れさまでしたと言わせて頂きます。
第39回日本研究皮膚科学会(JSID)
第39回日本研究皮膚科学会(JSID)
会長:片山一朗大阪大学皮膚科教授
会場:千里 ホテル阪急Expopark
会期:2014年12月12日−14日
大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学皮膚科学
教授 片山一朗
http://www.cs-oto.com/jsid39/
PROGRAM (pdf)
第39回日本研究皮膚科学会(JSID)を大阪大学が担当し、開催した。室田先生(事務局長)、小豆澤先生(実行委員長)を中心に2年間に亘り準備させて頂来成功のうちに終了した。

初日午後は飯塚一旭川医大名誉教授、塩原哲夫杏林大学教授が名誉会員に推薦され、認証式が行われた。お二人の先生には長年にわたり、公私共々にお世話になったが、今後もお元気で我々を指導して頂きたい。また海外からのEnk, Caughman, Christiano教授がそれぞれESDR, SID,前理事長、Tanioku Memorial Lecture 受賞者として名誉会員に推薦された。

今年のTanioku Memorial LectureはColombia 大学の皮膚科・遺伝・発生学教授のAngela Maria Christiano教授が受賞された。講演タイトルは「Genetics and immunology of alopecia areata」とされ、円形脱毛症に対するIL15を標的とする最新の治療を紹介され、さらにJAK阻害薬の効果にも言及された。我々も尋常性白斑への生物製剤の可能性を検討しており、大変興味深く拝聴した。
彼女は大変高名な先生ではあるが来日は今回が二回目で、我々の教室から彼女のラボに留学されていた梅垣知子先生が終始エスコートされ、彼女も日本の焼き肉やショッピングを楽しまれたそうである。また梅垣先生は最近Science Transl Med に発表された「Induced pluripotent stem cells from human revertant keratinocytes for the treatment of epidermolysis bullosa.」がPlenaryに選ばれ、素晴らしい発表をされた。彼女の成果は今後遺伝性皮膚疾患治療に大きなインパクトを与える事が期待される。今後も研究を継続して頂きたい。

(Tanioku Memorial LectureでのAngela Maria Christiano教授)
初日夕方からは天谷教授、Caughman SID理事長、Picard ESDR教授が紋付、袴姿で登壇され、Young Fellow Collegilalityの認証式が行われた。2年前の沖縄でのJSIDの琉球王朝衣装、昨年のエジンバラでのIIDにおけるスコットランドの民族衣装に引き続く仮装で、自ら挨拶でCostume fleakでDisguise
が大好きと言っておられ、大きな拍手を受けられていた。彼は今回の初日までが3年間の理事長職であり、本当に日本皮膚科学会の研究レベルを世界水準に高められ、心からご苦労様でしたと労いたい。次期理事長には東大の佐藤伸一先生が就任され、今後の日本の研究皮膚科学会を牽引していかれる。若手研究者の研究へのMotivationをどう高めていくか,健全な学会運営など課題は大きいかと思うがご尽力を願いたい。

今回は学会中イルミナイトとして太陽の塔がライトアップされ、また恒例のラーメンフェスティバルも時期をあわせて開催され、学会の合間に楽しまれた先生も多かったようである。また会場の阪急エキスポホテルは1970年の万博開催に合わせて建設されたようで、当時の香りがそのまま残されていた。ただコンビニやルームサービスもなく、ご迷惑をかけたようであるが、ある教授に言われた、Gordon Conferenceに出席しているようで、学会に集中できたと言われホットしたのも事実である。
今回は皮膚科学会のコンベンションチームに全面的にバックアップされ、室田先生、小豆澤先生の負担も少しは軽かったのでは勝手に思っているが、教室員の皆さんには心よりお礼を申し上げる。

(会場入り口にて)

(日本万国博覧会記念公園「太陽の塔」にて)
第40回大会は岡山にて岩月教授を会頭として開催される予定である。
大阪大学大学院医学系研究科教授 片山一朗
平成26(2014)年12月17日掲載
第44回日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会
第44回日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎総会学術大会
会長:相場節也 東北大学教授
会場:仙台国際センター
会期:2014年11月21-23日
大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学皮膚科学
教授 片山一朗

黄色から赤への紅葉が美しい杜の都、仙台で相場節也先生を会頭に第44回日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎総会学術大会が開催され、参加した。青葉通りは杜の都仙台を象徴するケヤキ並木で有名であるが、愛宕・上杉通りから広瀬通りの銀杏並木も美しく、大阪の御堂筋のよりもきれいとの話も聞いた。
さて会頭の相場先生は私よりやや若手世代の先生で、遥か昔、私が大学院〜留学帰りの頃、免疫学会で素晴らしい演題を発表されていた事を思いだす。特
にハプテン刺激後、表皮ランゲルハンス細胞が活性化、大型化し、かつ所属リンパ節へ遊走する事で数が減少するという素晴らしいデータを発表された時は、その美しい蛍光顕微鏡写真の画像とともに大変感激したことを思い出す。現在、ランゲルハンス細胞が抗原提示というよりは、むしろ免疫抑制的に作用するというLangerin k/oマウスを用いた研究が主流になりつつあるが、FITCをハプテンとしたランゲルハンス細胞の所属リンパ節への遊走や相場先生のデータを考えると感作相で重要な抗原提示細胞としてもう一度再検討が必要な気がするのは私だけではないのかと思う。その後も、相場先生はコンスタントに素晴らしい仕事を発表され続けているが、最近は酸化ストレスに関わる研究や接触皮膚炎でSpongiosisが形成される機序を見事に証明された研究が記憶に新しい。
また痒疹や白斑、皮膚のバリア機能など私の研究分野と重なる部分も多く、本大会でも関連するシンポジウムがあり、白斑関連のシンポジウムの演者としても参加させて頂いた。この他、「好塩基球」をキーワードとするシンポジウムでは防衛医大の佐藤貴浩教授の痒疹の病態形成に関わる好塩基球の動態、「経皮感作」では成育医療センターの大矢幸弘先生がアトピー性皮膚炎発症のハイリスク群に対する早期介入によりアトピー性皮膚炎発症が抑制出来るという、いづれも私も関与してきた研究が大きく花開いた講演であった。雑誌賞では教室の荒瀬規子先生が「手湿疹患者の労働生産性、生活の質、医療費に関する検討」で雑誌論文賞を受賞された(写真)。忙しい基礎研究を行われている環境下で、地道な臨床研究を取り纏められ、素晴らしい成果となった。心より拍手を送りたい。

また日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会は2015年10月から一般社団法人への移行を視野に、現在事務手続きを進めており、新代議員(今後は社員)選挙などを終え、承認された。新体制となる来年10月からはより公的な視点からの学会運営と社会貢献が要求される。アレルギー学会で審議されている総合アレルギー医としての相互乗り入れ体制や、日本専門医認定制度機構が予定している新しい専門医制度での日本アレルギー学会の位置づけなど先行き不透明な制度改革が進んでおり、日本のアレルギー診療を我々アレルギーを専門とする皮膚科医がどのような研修制度、診療体制で担っていくかを論議していく必要があるかと考える。またここ数年問題となっている化粧品や美容品などによる健康被害に対して、診断、患者指導、治療など皮膚アレルギーを専門とする皮膚科医が果たして来た役割は大きく、その意味でも本学会の果たす役割は今後益々大きくなると考えられ、若い先生方の積極的な参画を改めてお願いしたい。相場先生が学会テーマとされた「アレルギー診療のマエストロをめざして」はまさに時宜を得たものと考える。
一般演題も近年、非常にレベルが高くなってきており、若い先生方の熱意が伝わってくる演題が多い。特に興味深く聞いた演題としては演題番号36のエステサロン用高周波温熱治療器施術者において、施術中に出現し、再現可能であった全身性蕁麻疹、37のスピール膏貼付にて蕁麻疹が誘発されたアスピリン不耐症の一例、69のアロマセラピストに生じた職業性接触皮膚炎、130のサラシミツロウによる接触皮膚炎、144の梅干しによる食物依存性運動誘発性アナフィラキシーの一例など。いづれもふだんあまり経験しないアレルゲンや病態であり、あらためてこのような学会に参加する意義を感じた。

会期中は好天に恵まれ、晩秋の東北地方を楽しまれた先生も多かったと思う。素晴らしい学会を企画提供頂いた相場教授、山崎研司事務局長、菊池克子実行委員長にあらためてお礼を申し上げるとともに、来年の新体制下での初めての大会を運営される島根大、森田栄伸教授、千貫祐子事務局長のプロモーションスライドを最後に仙台を後にした。
大阪大学大学院医学系研究科教授 片山一朗
平成26(2014)年12月9日掲載
The 31th International Diploma Course in Dermatology and Dermatosurgery
The 31th International Diploma Course in
Dermatology and Dermatosurgery, Bangkok, Thailand
大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学皮膚科学
教授 片山一朗
大会長を務める第39回日本研究皮膚科学会を間近に控える11月下旬からの1週間バンコクでのDCDDに講師として出席した。このアジア諸国における国際的な若手皮膚科医を養成する教育コースは今から30年前に当時の小川秀興順天堂大学皮膚科教授(現理事長)がスカイクラブ会長であった安田利顕東邦大学名誉教授(前日本皮膚科学会理事長)とタイのInstitute of Dermatology のPreeya先生を中心に開始されたと聞いている。今年で31回目となるが、大体、東南アジア、最近は小川先生の関係でタンザニアやギニアなどアジア以外の国々からも参加する方が増えているそうである。ちなみに今年は当然タイからの参加者が最も多く12名で、ついでミャンマーが5人、パキスタン、タンザニアが3人、バングラデシュ、フィリピン2名、ギニア、スリランカ、カンボジア、マレーシア、セイシェル各一名の11か国32名であった。このうち日本皮膚科学会、順天堂大学、タイ国際開発協力機構が提供する奨学金受領者が9名、残りの23名は自費とのことであった。またJICAからも全面的なサポートがあるとのことである。1年間にわたるコースはそれぞれの出身国からバンコクに来られて生活しながらの受講ということで、裕福な階級層からの方と推察するが、逆にいうと東南アジア諸国でそれだけの受講料を払ってでも参加するくらいレベルの高いコースとの評価が定着しているためかとも考える。日本側の講師は小川秀興先生や北島康夫先生などの重鎮の方以外に島田先生など我々の同世代の先生が講師を務められている。私の前週は岡山大学の岩月先生が講師を務められており、彼から講義方法やバンコク諸事情などご教授いただいた。岩月先生の講義資料のハンドアウトを見せていただいたが、相当高いレベルで、最新の分子生物学のデータなども随所に盛り込まれており、受講者に聞いた話では、難しいが大変興味があり、チャンスさえあれば日本でPhDコースに進みたいという方も結構おられた。実際まだ皮膚科を選択されていない方もおられたが、彼らの理解力は素晴らしく、質問なども的確で、こちらが驚くほどの知識を持っている方もおられた。やはり世界は広く、日本にいるとガラパゴス化する危険性を再認識した。皮膚科の若い先生方も留学だけでなく、身近な所からどんどん世界の先生方との交流を深めて頂きたいと思う。
私の講義は以下の内容で1.5時間x12コマを行ったが、日本での講義に比べ、皆さん真剣に話を聞いてくれ、途中でもどんどん質問をしてくれるスタイルで、毎回結構ハードではあるが久しぶりに味合う、心地よい充実感、達成感を伴う講義であった。日本でもこれからは、どんどん英語で講義するような指導が文科省から来ているが、良いことだと思う。ただ30年の時間が経過し、そろそろタイの皮膚科医がリーダーシップをとりたいとの希望も出てきているようで、今後あらたな方向性の検討が必要な時代が来ているようである。
Dec.1 (Mon)
PM 1) Introduction himself and Allergic skin disease. Overview of contact dermatitis and drug eruption.
Dec.2 (Tue)
AM 2) New role of histamine in the skin: Overview of urticarial
PM 3) Collagen Vascular Disease: Scleroderma
Dec.3 (Wed)
AM 4)Vitiligo:guide line and treatment and Sjögren’s syndrome
PM 5) Itch and stress management
Dec.4 (Thu)
AM 6) Pathogenesis and guideline of atopic dermatitis Examinations and discussions

受講生の皆さんと。若い先生から訳ありの年輩の先生まで、皆さん輝く瞳と笑顔で講義を楽しんでくれたようです。


最終日、ミャンマーからの5人の先生と.ヤンゴンから2名マンダレーから3名とのこと。ミャンマーは皮膚科専門医が40人程度で学会組織もないが皆さん、大変優秀であった。
大阪大学大学院医学系研究科教授 片山一朗
平成26(2014)年12月6日掲載
追悼:三橋先生との熱い時代
追悼:三橋先生との熱い時代
大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学皮膚科学
教授 片山一朗
東京医大教授三橋善比古先生が10月18日、逝去された。謹んで彼の冥福を祈るとともに、彼が我々に残してくれた素晴らしい宝物を振り返り、彼が私個人だけではなく、皮膚科学会にとり、いかにかけがえのない人であったかを再認識した。
彼とは1971年に北大の医学部で同じクラスになったことから付き合いが始まった。今、思いかえしても、私より1歳年上の彼は随分大人に見えた。その後、コンパなどで親しく話しをするようになり、彼がTN大を1年で退学し、北大を再受験し、医学部に来た事や、実家が大きなリンゴ農園であること、ギター、チェロ、尺八など楽器演奏が得意なこと、落語に詳しい事、全国に吹き荒れた学生運動の嵐が収束に向かおうとしていた時代、日本がどこに向かおうとしているのかなど、私が知らない世界をたくさん教えてくれたことを思いだす。
卒業間近には、国家試験の勉強会を近くの喫茶店でよくやったが、そのあと4人ゲームやススキノに移動し、遅く迄議論したことも懐かしい思い出である。私自身、皮膚科医を選択したのは、当時札幌鉄道病院の皮膚科部長であった、T先生のポリクリで全身疾患としての皮膚科の面白さを教えて頂いた事が大きいが、同じような感性を三橋先生も持っておられ、皮膚疾患に関しても良く議論した事が決め手になったのかと今思う次第である。
皮膚科医になってからも、多くの学会で会うと、良く近くの飲み屋に移動し、議論した。今でも良く覚えているのは、1986年当時北里大学に移動し、西山茂夫先生のもとで、膠原病疾患の患者をたくさん見せて頂く機会があった。彼とも当然、SLEや皮膚筋炎の発疹や病因論を良く議論した。その中で、ゴットロン徴候に話が及び、チューリッヒ大学留学時Schnyder教授がGottron signは前腕尺側の紅斑といわれたそうである。Gottronの原著はなく彼の「Gottron und Schönfel」の教本には指関節背面と指背に見られる石膏ないし陶器色の萎縮斑との記載があるが、いわゆるゴットロン紅斑としては別に記載があることを教えて頂いた。後日、皮膚科の臨床(3 に「Gottronのsignとはこれのことかと,Gottron言い」という川柳を書いておられた。また当時SCLE、シェーグレン症候群、自己免疫性環状紅斑の違いを良く議論したが、私がなぜ紅斑は環状になるのかという議論で発疹の成り立ちに関して、多いに盛り上がった。彼はチューリッヒ大学でSchnyder教授のもとで表皮水疱症や角化症などの研究を進められ、皮膚科における臨床遺伝学の第一人者になられたが.皮膚の発疹学へのこだわりは強く、皮膚病診療の編集委員になられても、多くの興味ある皮膚疾患の報告の中で、発疹の成因論を彼独自の感性と広い知識で料理し、我々に届けてくれた。
参考として彼がこだわったDermadromeに関する総説を皮膚病診療「西岡清編集長」に許可を頂き、添付(1 させて頂く。また彼が皮膚病診療に寄稿した巻頭言(2 もあわせて読んで頂ければと思う。彼の皮膚病に対する熱い思いや患者、弱者、若い皮膚科医へのメッセージがひしひしと心に伝わってくる。
今回の早すぎる逝去は本当に無念と言わざるを得ないが、その中で彼の看病を最後迄努められた奥様と終始彼を支えて頂いた坪井良治教授には心よりお礼を申し上げ、お別れの言葉としたい。
※1皮膚病診療:30(6),2008~36(7),2014 「editorial」
※2皮膚病診療:31(7);795~798, 2009 展望「デルマドロームの概念」
※3皮膚臨床:31(7),833~834,1989 「Gottronのsign」
合掌 2014. 11.11日
大阪大学皮膚科教授 片山一朗

1986年6月 彼がチーリッヒ大学留学時(ESDR,SID合同国際研究皮膚科学会:ジュネーブ、レマン湖でのクルージング時)

1986年6月 彼がチーリッヒ大学留学時(ESDR,SID合同国際研究皮膚科学会:ジュネーブにて)。左より、増澤幹男先生(当時:北里大学皮膚科講師)、片山、三橋、西岡清東京医科歯科大学名誉教授(当時:北里大学皮膚科助教授)

1993年皮膚脈管膠原病研究会(福島にて)
岩月啓氏現岡山大学教授(当時福島医大助教授)
Zhang JZ現北京大学皮膚科教授(当時福島医大大学院)
大阪大学大学院医学系研究科教授 片山一朗
平成26年11月11日掲載
第65回日本皮膚科学会中部支部学術大会
第65回日本皮膚科学会中部支部学術大会
会長:岡本祐之 関西医科大学教授
会場:グランフロント大阪:コングレコンベンションセンター
会期:2014年10月25−26日
テーマ「せやねん、やっぱり皮膚科学」
大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学皮膚科学
教授 片山一朗

ただ予想外(予想通り)に阪神タイガースが日本シリーズに進出し、甲子園での初戦があり、参加者が減少するのでは?との心配や、大阪マラソンを日曜に控え、ホテルを取りにくかったなどの意見を耳にした。また私の大学同期の三橋善比古東京医大教授が10月18日にご逝去され、その告別式に参列した関係で初日の演題が聞けなかった。三橋教授の思い出はつきないが、また別の機会に述べたいと考えている。
今回、岡本会頭が学会のキャッチコピーにされたのは「せやねん、やっぱり皮膚科学」〜「やっぱり皮膚科は面白い」とのことで、先生のライフワークであるサルコイドーシスに関連する特別講演やシンポジウムが初日に組まれていたが、残念ながら拝聴できなかった。また次代の皮膚科医を育成するための『試験に出るシリーズ』や『匠が語るシリーズ』の教育講演は大変好評だったようである。
私自身、最近興味を持っている食物アレルギーのシンポジウムは2日目の午前中に開催され、5人の演者が講演され、補助椅子も出るほどの盛況であった。ただ、お一人の講演時間がやや短く、討論時間が足りなかったのは残念であった。
特に、横浜市大の猪又直子先生の遅発型納豆アレルギーの原因アレルゲンがポリガンマグルタミン酸であり、患者の80%以上が湘南サーファーであったこと、その原因がクラゲ刺傷であり、納豆菌が産生するポリガンマグルタミン酸がクラゲの毒胞にも含まれていることから、落語の3題噺ではないが、湘南サーファーと納豆アレルギーの関連性を明らかにされたのは大きな進歩と思う。また誘発試験でも一回目が誘発されず、二回目も油断した頃にアナフィラキシー症状がでたことなどの苦労話もされ、臨床研究の重要性を再認識した。会場からも「グルタミン酸は問題ないか?」との質問がでたが、特に問題はなさそうであるとのコメントがあった。同じような研究者の熱意が原因アレルゲンを明らかにした点で、名古屋保健衛生大学の矢上先生の赤い食品のアナフィラキシーの原因物質としての貝殻虫由来のコチニール色素とその莢雑物や牛肉アレルギーから子持カレイ、セツキシマブアレルギーに関わるαGalアレルギーを明らかにされた島根大学の千貫先生方の努力には心より敬意を表するとともに、岡本会頭の意図にも充分答えられた講演であった。
引き続き行われた特別講演2の辰巳治之教授の「インターネットの次代:「情報薬」によるFull Powered Medicineをめざしては情報薬という概念を提唱された辰巳先生の近未来の戦略的な日本の医療制度改革のお話であった。国民のビッグデータをどう活用し、どう日本の経済改革に反映させていくかというもので、非常に明快な語り口で、鋭く日本のインターネット医療の現状と将来を語って頂いた。私自身、昔、患者の健康データ管理が出来ていれば、少量の採血と問診結果を機械に入れればすぐに必要な薬剤が宅配便で届くような時代がくるかもしれないと思っていたが、手術支援ロボット・ダビンチの普及の速さを見ると、そのような日も近いのではと考えた。辰巳先生からは「どんどんスライド撮影して頂き、宣伝してください」と許可を得ているので、一部紹介いたします。
岡 本会頭、水野事務局長には学会が大成功に終わり、お祝いを申しあげるとともに、予測不可能なハプニングもありご苦労様でしたと言わせて頂きます。
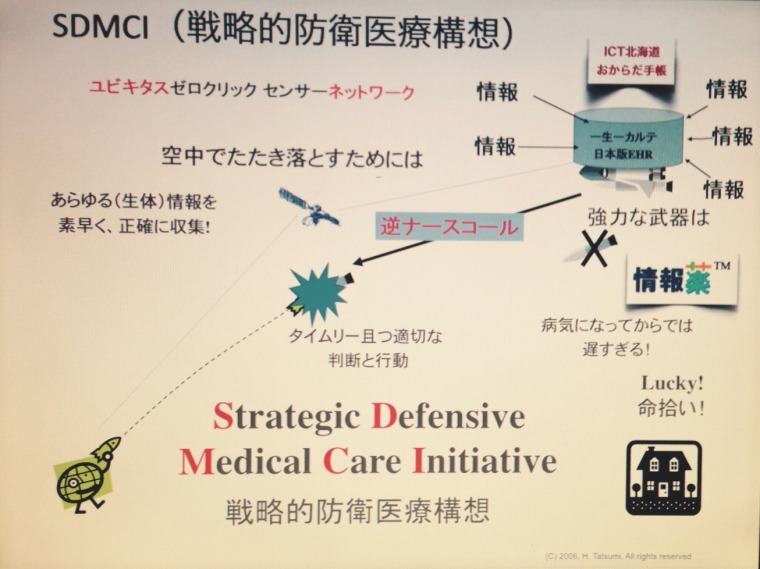
大阪大学大学院医学系研究科教授 片山一朗
平成26年10月27日掲載
10周年を迎えて
10周年を迎えて
大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学皮膚科学
教授 片山一朗
平成26年7月吉日
ご挨拶
私が2004年、大阪大学医学部に着任して今年の3月1日で10年が経過し、11年目を迎えることができました。6月21日、同門会で祝賀会を開いていただきました。関係者の皆様には、この場をかりて御礼申し上げます。
着任前に久しぶりに訪れた皮膚科学教室は中之島当時の医局、研究室に比較し、広く、機能的に整理されていましたが、佐野栄紀先生(現高知大学教授)などが留学されていたこともあり、人の気配があまり感じられませんでした。その中で、何回か引き継ぎに訪れた際にいつも研究室におられたのは金田真理先生(現講師)だけで、先生のライフワークである結節性硬化症のお話を熱く語っていただいた事を良く覚えております。
着任した2004年はスーパーローテートシステムが開始された年であり、新卒の先生のいない教室作りを開始することを余儀なくされました。また現在でもその解決策が見えてこない、女性医師の復帰支援や中堅医師の離職、大学院進学や海外留学希望者の減少が顕在化してきた時期でした。そのような中、長崎大学から大阪に来て頂いた室田浩之先生、金田先生、住友病院を経て帰局された佐野先生を中心に多くの医局員や秘書さん、技術員のかたがたの献身的なサポートで、より活力のある、そして多くの情報を世界に発信できる皮膚科学教室に育ってきました(活動内容は大阪大学皮膚科ホームページをご覧ください)。特に金田先生は全国の大学に勤務する女性皮膚科医(あえて言わせていただきます)のロールモデルとして、現在でも一番早く出勤し、最後に鍵をかけて帰られる生活を続けておられ、大阪大皮膚科がここまで成長してきたのは、本当に先生のご尽力のおかげと感謝しております。
私自身、良くコラムなどに「信頼と品位のある人と人との繋がりが何より大事」と繰り返しいってきました。長い人生で、縁もゆかりもない人間が、ここ千里が丘の地で、ある時間を共有し、何かを成し遂げ、そしてまた別の道に進んで行くのは奇跡ともいえる偶然ともいえますし、宇宙の神が書いた必然の出来事なのかもしれません。しかし、この10年間教室に在籍された方々が相互の信頼と尊敬の念を持って、大阪大学皮膚科学教室を発展させてこられたのは紛れもない事実です。「シンクロニシティ(Synchronicity):意味のある偶然の一致、共時性」という言葉は最近ある方から教えて頂いた言葉ですが、まさにこの10年間に大阪大学医学部皮膚科で偶然出会い、そして皮膚科医として成長されてきた先生方、そしてサポートして頂いたすべての方の今後のご自身の人生の目標が達成される事を願います。
残された任期はあまりありませんが、今までの仕事を集大成する過程で、若い世代に私の考える皮膚科学を伝えていきたいと考えます。また今の私の興味は人間の持つ、5感(視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚)をセンシングする分子がすべて皮膚に存在し、皮膚が人間の感覚や存在を規定しているのではないかということを知ることで、すでにロドプシン、TRPなど視覚、嗅覚、味覚などのセンサーの皮膚細胞での存在が明らかにされつつあります。今後も皮膚という臓器の重要さをさらに知り、その異常を是正し、若さを保つ作業の重要性を認識しながら、さらに皮膚科医としての研鑽を積んでいきたいと考えております。この10年間のご支援、ご助言にたいし心より感謝を申し上げ、返礼の言葉とさせていただきます。
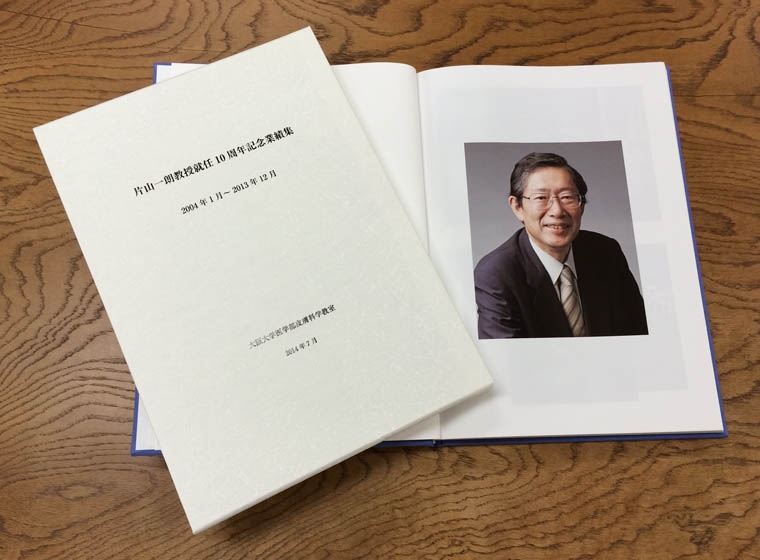
大阪大学大学院医学系研究科教授 片山一朗
平成26年9月30日掲載
EADC 2014 3rd East Asia Dermatology Congress
EADC 2014 3rd East Asia Dermatology Congress
President: Hee Chul Eun (韓国 ソウル大学教授)
Chikako Nishigori (日本 神戸大学教授)
Jie Zheng (中国 上海交通大学教授)
Venue: ICC Jeju
Date: 2014. 9. 24-26
大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学皮膚科学
教授 片山一朗
2012年の北京での第2回大会に引き続き、今回神戸大学の錦織教授が日本側の代表を務められた、韓国済州島での第3回EADCに参加した。錦織教授は9月初めのシンガポールの国際色素細胞学会、アルゼンチンでの学会から連続しての要職をつとめられ、さぞかしお疲れと心配していたが、開会式での挨拶や女子学生のアンケートをもとにした日本での女性医師サポート体制の現状に関する、教育講演など立派に勤められ、最終日は晴れ晴れとしたお姿を拝見した。事務局長を努められた永井先生共々ご苦労様でした。

岩月教授、張教授(北京大学)と懇親会にて
懇親会は2日目の夜に行われ、特別に参加されていた慈恵医大名誉教授の新村眞人先生が「今の3国間の歴史的な現実が日中韓の皮膚科医の協力で改善される事を心より願う」という素晴らしいスピーチをされ、大きな拍手が送られた。私も多くの知人に会う機会があり、多いに素晴らしい会を楽しませて頂いた。

済州島の民族舞踊

4,000年前に済州島の祖先にあたる3人の神人が現れたという伝説の三姓穴(雨が降ろうと、雪が降ろうと、一年中水がたまったり、雪が積もったりすることもないという不思議な穴)
大阪大学からは種村先生がメラノーマ、白斑に関する2題の教育講演をされたが、立派な内容で、多くの質問を受けられていた。以前の日韓、日中学会では参加者が座長と発表の施設の先生のみというセッションが多かったが、前回の北京での大会から様変わりし、特に中国の先生方の熱心さが目についた大会でもあった。私が座長を努めた皮膚腫瘍の教育コースでも虎ノ門病院の大原先生などに活発な質問があった。また谷先生は少量ゲムシタビンが著効した毛包性Mycosis fungoidesの症例報告と座長、楊先生は皮膚の線維化に関わるデコリンに関する最新の知見を発表された。
種村先生が同じセッションで発表された釜山東亜大学(Dong-A Universityの金(Ki-Ho Kim) 教授から韓国、日本、中国で東アジアでの白斑研究の組織を作ろうとの提案があり、来年の韓国での皮膚科学会に連動して第一回の研究会を開催しようとのコンセンサスが得られた。9月のシンガポールの大会でも日本で白斑の学会組織を作ってはとの提案がボルドー大学のTAIEB教授からあり、昨今の白斑研究の盛り上がりを感じさせるキックオフミーテイングであった。

韓国からはChul Jong Park (Chasolic Univ. 教授)、 Seung Chul Lee (Chonnamu National Univ Hosp教授)など白斑研究の主要メンバーが参加され、中国からも、北京、上海、香港などの大学から5人先生が参加された。
なおRADCは以前からあった日韓皮膚科学会と日中皮膚科学会が発展的に合同化した学会で2010年、第一回大会が 古江増隆九大教授を会頭として博多で開催され、北京に引き続き今回が3回目になる。アジア地域の合同学会はAsian Dermatological Congress (アジア全体), Regional Meeting of Dermatology(環太平洋地域)など他にもいくつかあるが、今大会には800人近い参加者があり、日本からは100人前後の参加があったそうである。次回は2016年、日本がHostとなり、浦安で開催される。
大阪大学大学院医学系研究科教授 片山一朗
平成26年9月30日掲載
第29回日本乾癬学会(高知)
第29回日本乾癬学会
会頭:佐野栄紀高知大教授
会期:平成26年9月19日(金)〜20日(土)
会場:高知市文化プラザ(高知市)
大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学皮膚科学
教授 片山一朗


同門の佐野栄紀第先生が会頭をつとめられた29回日本乾癬学会に参加した。阪大皮膚科からは林先生、山岡先生が口演し、谷、越智先生、関連施設からは日生病院の東山先生、岡田先生、吉良先生、樽谷先生など乾癬を専門とされる先生が参加されていた。大会のテーマは「Psoriasis more than skin deep」(PMSD)で、systemic inflammatory disease としての新しい乾癬の概念を全面に打ち出された学会を象徴するものであった。

(佐野先生の会頭挨拶)
初日の開会前、フランク・シナトラの歌う「I’ve got you under my skin」が
A会場の扉を通して聞こえてきた。会場に入るとスライドは高知の名所を紹介されており、会期中を通して、このメロディーがリフレインされた。(動画はこちら)
今大会の特徴は「Psoriasis more than skin deep」(PMSD)と銘打ったPMSDシンポジウムが2日間にわたり4つ(基礎研究、遺伝子、顆粒吸着療法、本音トーク)組まれていた事と、患者教育、患者会とのジョイントシンポジウムなど、より患者さんとの連携を深めるようなプログラムが組まれていた事で、最終日にはさらに会頭と患者さんたちが親睦を深められたそうである。本当に佐野先生の気配りと素晴らしいアイデアが随所に見られた素晴らしい学会であった。
私自身も可能な限り演題を拝聴し、記憶に残ったものを記録しておく。
最初のPMSDシンポで講演された住友病院院長の松澤佑次先生はメタボリックシンドロームの名付け親で、佐野先生も米国から帰国後、しばらく住友病院に勤務され、ご指導を受けられたとの事である。我々の教室でも皮膚の脂肪細胞でのサイトカイン産生を検討しているが、内臓脂肪細胞との本質的な差があるのか、Massとしての量の差なのか興味がある。再生医療にも内臓、皮下脂肪細胞が使用される時代であり、さらなる検討を期待したい。
我々の教室から、山岡先生がアバタセプトにより誘発された乾癬様皮疹を発表したが、関連してローザンヌ大学のMichel Gilliet先生から興味深い講演があった。 乾癬表皮で発現が亢進している抗菌ペププチドが自己DNAと複合体を作り、Plasmacytoid dendritic cellを活性化する際、Toll like receptor 7を介しIFNαなどを産生する。そして抗TNFαの存在下でその反応がさらに増幅する可能性やPradoxical reaction の際,このPlasmacytoid dendritic cellが病変部で増加しているなどきわめて興味深い内容であった。(Seminars in Immunopathology 2014. Immune sensing of nucleic acids in inflammatory skin diseases Olivier Demaria, Jeremy Di Domizio, Michel Gilliet. ) TLR7に関しては高知大の佐野先生らもそのリガンド刺激で乾癬様の病変が誘発されるのみでなく、SLEに似た病変が誘発される事を報告されており、生物製剤の使用や自然免疫の調節剤の使用に一石を投じる内容であった。Yokogawa M, Takaishi M, Nakajima K, Kamijima R, Fujimoto C, Kataoka S, Terada Y, Sano S.
Arthritis Rheumatol. 2014 Mar;66(3):694-706.
今回は一般演題が殆ど生物製剤一色の感があったが、PMSD4ではバイオ製剤で制御が困難な症例にMTXや従来の治療を再評価、再使用することの意義に関しても講演があった。ただパネラーからの一方通行の話で消化不良の感は否めなかったが、最後に佐野先生がバイオ無効な症例の皮膚の下にある全身疾患の治療や患者指導を行う事の重要性を再度強調されたことは大きなインパクトを与えられたと思う。もう一つのトピックスであった、関節症性乾癬(PsA)に関しては、米国のMease教授からの詳細な講演があり、私が座長を努めたが、彼自身リウマチ医で、今後皮膚科医との連携の重要性を示唆されていた。教室の林先生も早期診断における関節エコーの有用性を講演されたが、関節リウマチ同様
早期診断、早期バイオ導入でどの程度重症化を押さえる事が可能か今後の検討が必要と考える。また最近保険適応となった顆粒球吸着療法に関しては、導入後炎症性サイトカインの抑制のみでなく、創傷治癒に関与するようなProgenitor cellが誘導される可能性が報告され、壊疽性膿皮症などへの応用も期待される。
今回の学会はすべての意味で素晴らしかったが、学会終了後訪れた、牧野富太郎を記念する牧野植物園も日本には珍しい植物を展示しており、充分楽しむ事ができた。はりまや橋でかんざしを買った坊さんは隣接する31番札所の竹林寺の住職と帰りのタクシーの運転手から聞いた。本大会を開催された会長の佐野栄紀教授、事務局長の中島英貴先生や高知大学医学部皮膚科学教室の皆様に感謝いたします。
大阪大学大学院情報統合医学皮膚科
片山一朗 平成26年9月22日掲載
第22回世界色素細胞学会 (IPCC)
第22回世界色素細胞学会 (IPCC)
Organising President IPCC 2014 :
Dr Boon Kee Goh (Mount Elizabeth Medical Centre Singapore)
会場:Shangri-La Hotel Singapore
会期:2014年9月4日−7日
大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学皮膚科学
教授 片山一朗


第22回世界色素細胞学会がシンガポールで開催され、出席した。この学会は3年に一回,開催され、前回は2011年にAlain Taieb ボルドー大学教授を会頭にボルドーで開催され、我々大阪大学のメンバーも5人が出席した。今回はDr Boon Kee Gohを会頭として、Asian Society for Pigment Cell Research (ASPCR), Dermatological Society of Singapore (DSS), International Federation of Pigment Cell Societies のSister society と27th Annual Scientific Meeting of the DSSの共同開催として行われた


私は前日のVitiligoの診断基準作成の委員会に出席するために一足先にシンガポールに入った。大阪大学からは金田、種村、西岡、揚さん姉、弟(揚飛)の計7名が出席した。
Vitiligoの診断基準作成委員会(Vitiligo Global Issue Consensus Conference)は第一回がボルドーで開催され、新しい分類基準が提唱された(PCMR 2012 May;25(3):E1-13.)以後年2回、程度国際学会などのさいに開催され、Koebner現象や活動性の定義などが論議されてきた。今回は患者の治療の満足度や改善の評価法、重症度など事前にネット会議で審議されてきた事が討論された。参加者も多く、特にインドなど、白斑患者が歴史的に差別されてきた文化的な背景を重視する、乾癬などの炎症性疾患の評価(PASI75)と美容的な要素が加味される白斑の改善度(VASI75)は重みが違うなど活発な討論があった。この委員会をサポートする組織としてアトピーの疫学研究で有名なノッチンガム大学のWilliams 教授のグループがあり、EBMに基づいた世界標準の治療の評価システムの構築が進んでおり、日本からは私と山形大の鈴木民夫教授、聖マリ大の川上民祐准教授が出席したが、今後もより多くの先生が参加されるのが良いかと思う。

Vitiligo Global Issue Consensus Conferenceの参加メンバー
特に今回ボストンのJohn Harris がIFNγでドライヴされるCXCL10(IP10)が白斑部のケラチノサイトで発現増強しており、STAT1, JAK1をTargetとする分子標的薬の可能性を示唆する講演やTARCの遺伝子導入によるTregの誘導、ラパマイシンの適用など新たな治療薬の登場を見据えた動きと連動していると考えられ、これはアトピー性皮膚炎でも同様の分子標的薬の開発が進んでいる事の裏付けかと考える。このほか印象に残った演題としてはストレス負荷時や白斑部のメラノサイトでe-cadherinが減少し、メラノサイトのケラチノサイトとの接着性の減少、メラノサイトの減少に繋がる(CS38)、重力負荷をかけた白斑部表皮シートでは健常部に比し、メラノサイトが角層側に移動する(ケラチノサイトとの接合性が減少する)(P116)、尋常性白斑の汎発型で色素増強ではなくビタミンD軟膏とルチノール外用で色素ムラが改善する報告(P149)(これはカネボウ白斑の治療に応用可能と考える)、カネボウ白斑の原因物質であるロドデノールがオートファジーの阻害でより低濃度でメラノサイトの障害を生じる事(p113)などがあった。日本での加齢学会での講演のため4日以降はメラノーマ中心の演題が聞けなかったが、今回は会頭がGoh先生であったせいか吸引水疱蓋からトリプシン処理で表皮細胞を得、植皮するなど白斑の演題が多数あり、多くの参加者が色素細胞研究が大きく変化しつつある変換期と認識されていた。次回は2017年にデンバーNorris教授が会頭を努められるとの事である。

演者John Harris 座長はGoh, Taieb, Barsch

懇親会後の懇親会(ラッフルズホテル、Long Barにて)
大阪大学大学院情報統合医学皮膚科 片山一朗
平成26年9月9日掲載
2013年 年報序文
2013年 年報序文
片山一朗 大阪大学大学院情報統合医学皮膚科学
(2014.8.22)
大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学皮膚科学
教授 片山一朗
粘菌(Slime mold)と組織論
私が大阪大学医学部に着任して今年の3月1日で10年が経過し、11年目を迎えることができました。おかげさまで、多くの医局員や秘書さん、技術員のかたがたの献身的なサポートで、より活力のある、そして多くの情報を世界に発信できる皮膚科学教室に育ってきました。年報も十巻目となり第一巻と比較しますとその質・量や他施設との共同研究など驚くほどの変貌が見られます。次のステージに向けて教室員や同門の先生が各人のやりたいことをさらに進めていただければ10年後はまた別の素晴らしい年報が我々の眼前に現れてくるかと思います。
粘菌(Slime mold)は和歌山県が生んだ南方熊楠の研究で有名な植物と動物両方の性質をもつ,非常にしたたかな生活様式をもつユニークな生き物です。 「他の星からこの地球に、落ちてきた生物の原型ではないかと」言う生命学者もいます。熊楠は生涯でNatureに50編の論文を発表し、現在でもその記録は破られていないそうですが、そのうちの2編が粘菌に関する研究です。彼はまた「東洋の星座」、「宵の明星と暁の明星」など神秘的な題名の論文もNatureに投稿しています。粘菌は適当な条件下で発芽してアメーバ状の細胞となり,周囲の餌(大腸菌などのバクテリア)あるいは栄養豊富な培養液を取り込みながら増殖します.湿度、温度、日照などの周囲環境の変化や栄養源が枯渇して飢餓状態になると,単細胞はやがて集合して多細胞体を構築し,分化・パターン形成の方向に移行します(マウンド、スラッグ)。そして環境が改善するとまた元の個々の生命体に戻っていきます。このような粘菌の行動パターンは私が理想とする組織像にかさなります。私自身は教室員の個性を大事にし、自分のやりたいことを自由にやってもらうように指導しています。そして教室に危機が迫った時や何か大きなミッションを命ぜられた時などには、個々の医局員が少しづつ機能的なユニットを形成し、最終的には粘菌のマウンドあるいはスラッグとよばれる巨大な集合体を作り、正しい方向性を決定することで、危機を免れ、あるいは目的を達成し、その後は個々の構成員に戻り、また個性的な生活を始めます。この巨大化した組織のヘッドは決して私ではなく、構成員が それぞれ、精神的な繋がりを持つことで生まれた新たな精神・生命体とも言うべきものかと思います。私の目指す大阪大学皮膚科はまさにこのような生命体であり、この10年間でその形が見えてきました。今後また次の10年でどう育っていくか楽しみです。粘菌の行動様式は都市交通や上下水道の設計にも応用されていますが、私自身、このような未知の生命体の行動様式に強く魅かれます。そのような流れの中で私は人間の持つ、5感(視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚)の皮膚での支配原理を知りたいと思うようになりました。5感をセンシングする分子がすべて皮膚に存在し、皮膚が人間の感覚や存在を規定しているのではないかということ、ですでにロドプシン、TRPなど視覚、嗅覚、味覚などのセンサーの皮膚細胞での存在が明らかにされつつあります。皮膚という臓器の重要さをさらに知り、その異常を是正し、若さを保つ作業の重要性を認識しながら、さらに皮膚科医としての研鑽を積んでいきたいと考えております。この10年間のご支援、ご助言にたいし心より御礼を申し上げます。

表紙の言葉 「チベットの山岳」
山頭火の有名な短歌に「分け入っても分け入っても青い山」がある。 この写真は大阪大学着任時チベットにアトピー性皮膚炎の健診に行った時に飛行機から撮ったヒマラヤの写真である。アトピー性皮膚炎の病態は一つ山を越えるとさらに高い山が前に立ちふさがる。一度神になり天空から眺めると、アトピー性皮膚炎が俯瞰できるかもしれない。
最後に、この10年間の英語原著論文数を年報から纏めてみた。1stは片山が1st author、2nd/Last, それ以外(多くは共同研究の論文)、他ラボは片山が著者では入っていない論文である。2004年の着任時から5年間は片山が著者として入っている論文数は半分以下であり、6年目からようやくある程度教室発のオリジナルな仕事が出だしたかと思う。昨年はかなり数が減少したが、これはこの2年間で海外留学者が7人と急増したことによるかと考えている。
今後も赤字部分増えていくように努力したいと考えている。
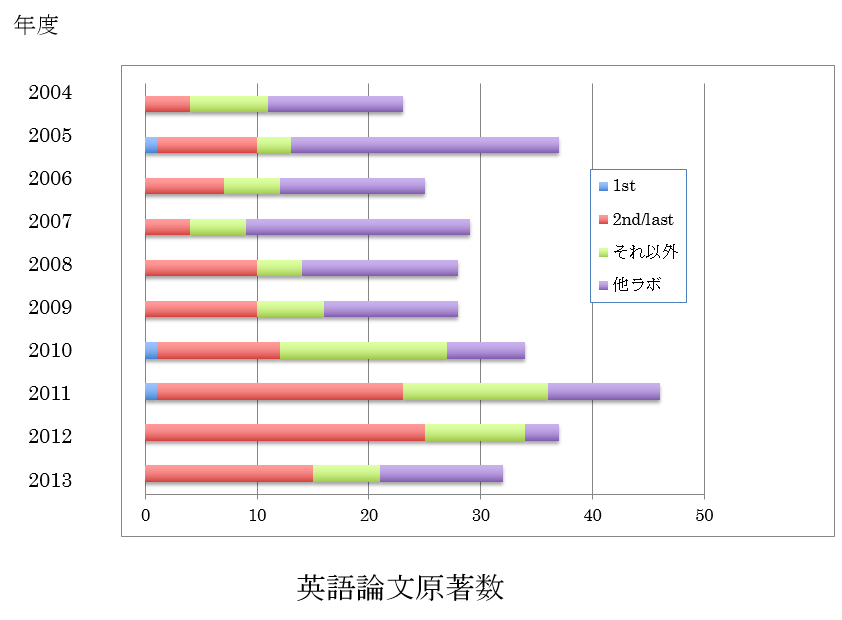
大阪大学大学院情報統合医学皮膚科 片山一朗
平成26年8月22日掲載
第1回汗と皮膚疾患の研究会
第1回汗と皮膚疾患の研究会
平成26年8月2日
東京
大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学皮膚科学
教授 片山一朗

世話人のお一人の杏林大学の塩原教授がまず基調講演としてご自身の最新の研究成果を発表された。特に歯科用のシリコンを用いたImpression mold法(Shiohara T et al. Current Probl Dermatol 41:68-79,2011)を用いた発汗の研究は初めて聞かれた先生には驚きの連続であったと思うが、塩原先生ご自身は最近の汗の研究が活発になり、その分総説の執筆依頼も増えて、コピペーの連続と謙遜されていたが。特に痒疹、扁平苔癬、アミロイド苔癬が汗管を初発部位とし、Dermocidinなどの汗に特異的な抗菌ペプチドが皮膚に漏れでることで発汗の低下や汗管周囲性の炎症反応が生じること、ヘパリン類似物質含有クリームのODTで発汗と皮膚症状の改善が見られること、2週間の外用でアミロイドが消失(炎症反応と貪食像が見られる)するというびっくりするようなデータを提示された。私も以前からトコレチナート軟膏をアミロイド苔癬に、また活性型ビタミンD3軟膏を痒疹に使用して良い成績を得ているがさすがにアミロイドの消失は見られなかった。ただ炎症反応に伴い改善が見られるとの事で前治療のステロイドの中止の影響などの検討も必要と考える。
基調講演のもうお一人の先生は千葉大神経内科の朝比奈正人教授による内科医の立場からの発汗異常のお話でAIGA(Acquired idiopathic generalized anhidrosis)や糖尿病、POEMS症候群などの病態に関する最新の研究成果を教えていただいた。私自身、発汗が交感神経支配のアセチルコリン誘導性の現象である事が温熱性、精神性発汗いづれにおいてもあてはまるのか質問したが、はっきりしないとのことであった。また自律神経と知覚神経のクロストークの可能性に関しては反射性交感神経ジストロフィー(CRPS/RSD)で研究が進んでいるそうで、この考え方は減汗性コリン性蕁麻疹などの発症機序にも応用できないかと考えている(参考図)。このほか先日退官された旭川医大名誉教授の飯塚一先生が生後から一歳までの乳幼児の角層機能の大変貴重なデータを発表された。また愛媛大学からは汗に含まれるIL1やIL31がケラチノサイトに作用し、IL6などの炎症サイトカインの誘導を関してインフラマゾーム非依存性に炎症反応を起こす可能性を報告された。 全体の講演を聞いて汗の研究が活発に進んでいる事を感じたが、一つ若い先生に注文しておきたいのは発汗の過去の研究の歴史を十分勉強し、今手に入る技術で何が明らかにできるか? あるいは残された臨床の疑問点を解決するためにどのようなツールの開発が必要か考えて頂くと、さらに汗の研究に対する興味が増すと思う。その場合必ず過去の研究をクレジットし、プライオリテイをはっきりさせて頂きたいし、特に日本の研究者の仕事も適切に評価して頂きたい。かつて田上八朗東北大学名誉教授が日本人の研究者は日本人の論文を引用しないと嘆かれていたことを思い出した。
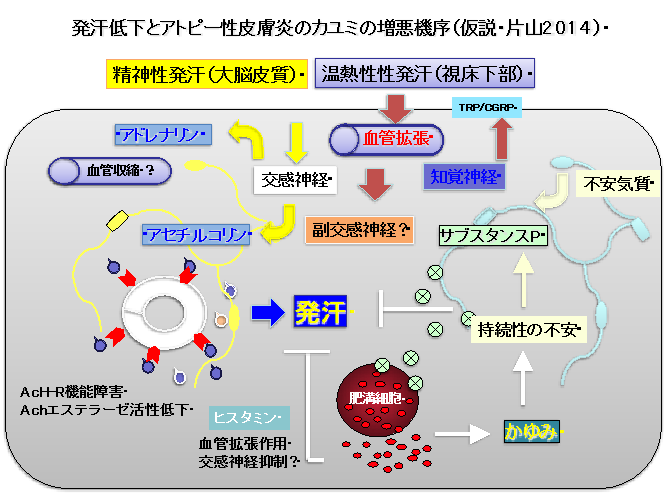
大阪大学大学院情報統合医学皮膚科
片山一朗 平成26年8月7日掲載
アレルギー疾患対策基本法案と口腔アレルギー症候群
アレルギー疾患対策基本法案と口腔アレルギー症候群
大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学皮膚科学
教授 片山一朗
先日のアレルギー学会の理事会にて、西間三馨先生から「アレルギー疾患対策基本法案」が6月20日参議院にて可決されたことが報告された。
本法案は医系議員が5年以上(?)にわたりその作成と国会での承認に尽力されてきた法案である。その詳細は公開されているPDFを参照されたいが、その前文に「本法律案は、アレルギー疾患が国民生活に多大な影響を及ぼしている現状及びアレルギー疾患が生活環境に係る多様かつ複合的な要因によって発生し、かつ、重症化することに鑑み、アレルギー疾患対策を総合的に推進するため、アレルギー疾患対策に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体、医療保険者、国民、医師その他の医療関係者及び学校等の設置者又は管理者の責務を明らかにし、並びにアレルギー疾患対策の推進に関する指針の策定等について定めるとともに、アレルギー疾患対策の基本となる事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。」と書かれており、一 「この法律において「アレルギー疾患」とは、気管支ぜん息、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎、花粉症、食物アレルギーその他アレルゲンに起因する免疫反応による人の生体に有害な局所的又は全身的反応に係る疾患であって政令で定めるものをいう。」と明記されている。
アレルギー疾患が初めて法的に「アレルゲンに起因する免疫反応による人の生体に有害な局所的又は全身的反応に係る疾患」と定義された。西間先生によればこの法案が可決されたことで、アレルギー疾患に関わる国会での審議に対する議員の熱の入れ方が大きく変わる可能性や、従来、アレルギー疾患の対策上欠けていたジグソーパズルの空白を埋める作業が非常にやりやすくなるとの話があった。

大阪大学大学院情報統合医学皮膚科 片山一朗
平成26年7月8日掲載
第11回日独皮膚科学会(GJSD)
第11回日独皮膚科学会
German-Japanese Society of Dermatology (GJSD)
会頭:Alexander Enk Heidelberg University教授
会場:Marriot Hotel Heidelberg
会期:2014年6月11−14日
大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学皮膚科学
教授 片山一朗
日独皮膚科学会はハイデルベルグ大学教授のアレクサンダー・エンク先生が第11回大会の会頭を務められ、初夏と言うより真夏を思わせるドイツの古都ハイデルベルグで開催された。西山茂夫北里大学名誉教授、植木宏明川崎医大名誉教授は残念ながら欠席されていた。前回書いたように本学会はドイツに留学された先生を中心に組織された学会で、第一回大会はドイツHeidelbergでHornstein先生を会頭に開催された。その後、3年毎に日独交互に開催されている。日本では過去、植木先生が倉敷で第2回大会を開催され、その後西山先生が箱根、西岡清東京医科歯科大学名誉教授が奈良、勝岡憲生先生が横浜.荒瀬誠二先生が徳島で開催された。ちなみにドイツ側はSchopf, Freiburg大学教授、Happle, Marburg大学教授、Mauer, Dresden大学教授、Elsner, Jena大学教授がそれぞれ開催されている。私もMarburg以来参加しており,2002年に西岡先生が開催された時には長崎でPost Congress Meetingを担当させて頂いた。雲仙などに案内し、温泉や海の幸を楽しんで頂いたことを思い出した。今回はより日独の交流を密にする目的で、会頭のEnk先生とも親しい、島田眞路山梨大教授、戸倉芳樹浜松医大教授、天谷雅行慶応大学教授なども参加され、日本側からは最終的に新入会員が20名も増えて会員数が100名近くとなりドイツ側の倍になったそうである。発表はドイツ側、日本側からあわせて39題の口頭発表と27題のポスター発表があった。今回もElsner教授以外に、Munchen大学のThomas Ruzicka教授、Andreas Wollenberg 教授、Hidelberg大学のDiepgen教授などと再会できた。大阪大学からは片山、種村篤、田中文、永田尚子、廣畑彩希が参加、発表した。

ハイデルベルク大学のAlte Aula
大会は6月11日夜のWellcome reception(ハイデルベルク大学のAlte Aula)から開始されたが、我々はフランクフルトからのバスの便が悪く出席できなかった。参加された荒瀬先生からのお話では立食で日本人の参加者の方が多かったそうである。ただゲーテの有名な「若きウェルテルの悩み」の舞台がハイデルベルクの街だと思っていたが、実際はフランクフルトの北のヴェツラーという街とのことであった。

翌日の朝8時30分からは天谷教授のKey note Lecture、その後一般の口頭発表が続いた。今回は日本の若い先生方の活躍が目立った学会で、英語での発表とその後の討論もしっかりと受け答えされる先生が多かった。ただポスター発表に回された演題にも多くの素晴らしい仕事があったが殆ど討論がなかったのは今後の宿題かと考える。2日目の夜は旧市街に繰り出し、オープンテラスでのドイツ料理とワイン、ビールを楽しんだ。その後引き上げる途中で西岡清先生ご夫妻とばったり会い、自然と二次会になった。その席で、西岡清先生から最近の若い先生とは、コミュニケーションを取るのが難しくなったと、いつもの少しシニカルな口調で語られた。久しぶりの西岡節を堪能し、教室の若い先生方も日本の皮膚科学者を代表する偉い先生と話が出来、得るところも多かったようである。また午後の乾癬のセッションで膿疱性乾癬には乾癬から移行するタイプと高熱とともに膿疱性の病変が発症する von Zumbusch型の2型があり、Munchen大学名誉教授のPlewig先生から、von Zumbuschがミュンヘン大学の教授であり、ミュンヘン大学には彼に関する資料も多く残されていることをおっしゃられた。翌日の感染症のセッションでもPlewig先生はHansen病がベルゲンを中心としたノルウェーに多く、ノルウェーの医師Hansenが風土病的な要素があることを報告した事を歴史的に述べられ、免疫が低下した患者では疥癬が重症化することを話され、ノルウェー疥癬の由来がやっと理解できた。最近の先生方はかつてHansen病がLeprosy, Aussatzなどと呼ばれていたことなど知らない世代となりつつあるが、病気の歴史的な経過を勉強しておくとさらに皮膚科学が面白くなるかと改めて思った講演であった。Plewiig教授は「Pantheon of Dermatology」という、歴史に名前を残す皮膚科医の業績や人物像を紹介した素晴らしい教本を昨年上梓されたが若い先生も是非一読されることをお勧めする。
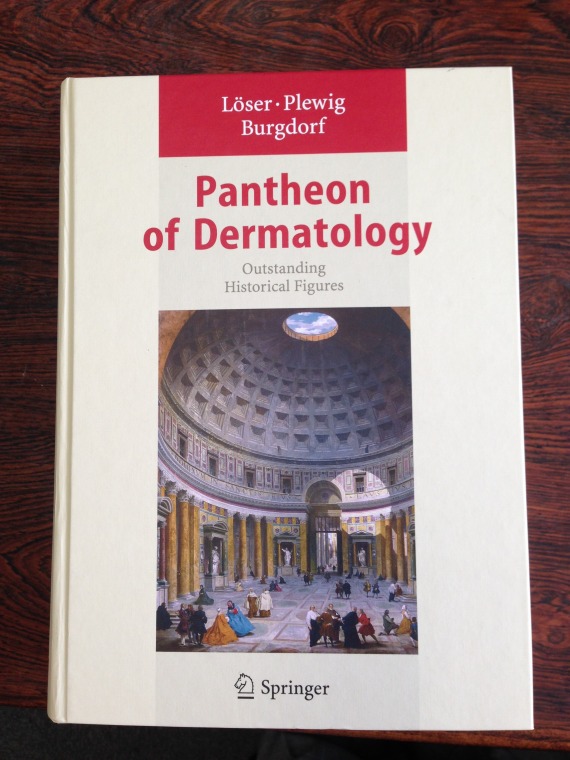
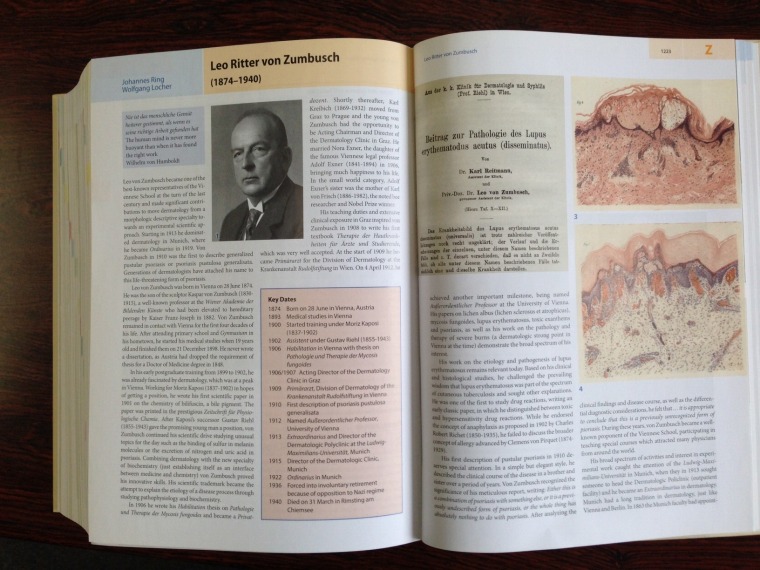
このほか、Hand Eczemaに関する口演が2題あり、職業病としての重要さを認識し、治療を積極的に皮膚科医が指導することの重要性を強調されていた。ドイツの皮膚科学は伝統的に全身を診て治療することが要求されてきたが、K大学のS教授に聞くとかつて200床あったミュンヘン大学の病床が現在は50床にまで、減少していることや、薬疹を疑っても積極的な検査をしなくなってきているようで、ドイツの皮膚科学も少し様変わりしてきているのかもしれない。
ただ私の友人、E教授が自家用飛行機を持っている、あるいはEn教授が6,000本の貴重なワインを所有しているというような話を聞くと日本の皮膚科教授との差が身にしみる気がするのもやむを得ないかとも思う。日本の若い世代のモチベーションがあがるような国策を是非進めていただきたいと願うのは私だけではなかったのではないかとこの原稿を書いていて思った次第である。
ただ毎回参加するたびに感心するのはリタイアされた先生方が非常に活動的で、また驚くほど博識であり、専門外の分野でも鋭いコメントを発せられることで、我々の世代も、もっと勉強することがあることを再認識させられる。Post congress meetingはミュンヘン大学のThomas Ruzicka教授が担当された。
次回は2016年に東京医科歯科大学教授の横関博雄先生を会頭に、Post congress meetingは福島医大の山本俊幸先生が開催される予定で今から楽しみにしている。

大阪大学大学院情報統合医学皮膚科 片山一朗
平成26年6月18日掲載
飯塚一旭川医大皮膚科教授退任記念地方会
第398回日本皮膚科学会北海道地方会
飯塚一旭川医科大学皮膚科教授退任記念地方会
日時:平成26年6月7日(土)〜8日(日)
於: 旭川グランドホテル
大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学皮膚科学
教授 片山一朗
私の敬愛し、また最も尊敬する皮膚科医である飯塚一旭川医大皮膚科教授の退任記念地方会に出席した。全国から64の演題発表があり、阪大からは越智沙織先生が「皮膚炎症における表皮細胞内コルチゾール再活性化酵素(11βHSD1)の動態解析」を発表された。時間が限られていたが、大阪市大の鶴田教授からNFκBの活性化シグナルのどの経路を押さえるのかとの質問があった。最終的なリン酸化の阻害のみをみている段階であり、多分炎症に関わるシグナルや自然免疫、アポトーシス、ユビキチン化など広範囲のシグナル伝達系にも影響を与えているかと考えている。
記念講演では、飯塚先生のライフワークである尋常性乾癬の組織構築の数理解析モデルをお話された。退官は副学長としての任期が終了する今月末で、7月からは札幌で研究生活を継続されるそうで、先生の今後の益々の研究の発展とご健勝を祈年するとともに我々の指導も引き続きお願いしたい。なお退任記念誌に寄稿した私の原稿を添付させていただく。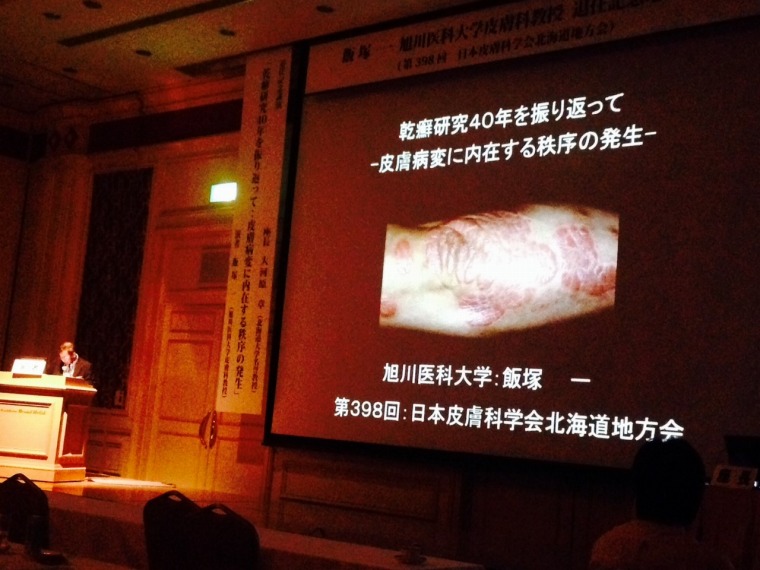
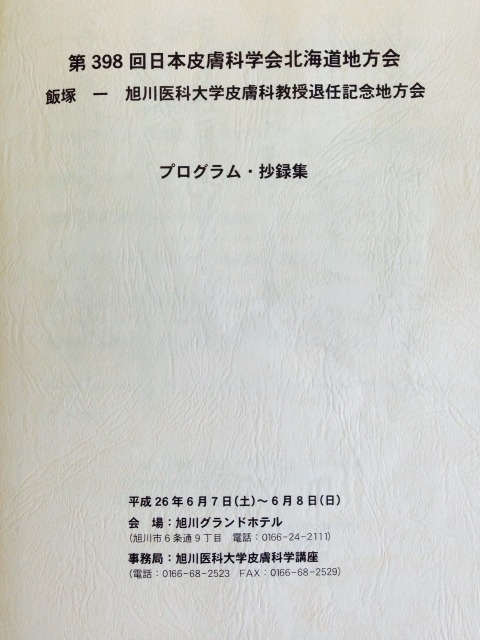
乾癬とサグラダ・ファミリア
飯塚先生、長年にわたるご指導ありがとうございました。先生は私が北大の学生時代から雲の上の方で、退官をお迎えになる現在、私が皮膚科を選んだ理由も先生の存在があったような気がしております。卒業後私は大阪大学の皮膚科に入局し、西岡清先生のご指導で皮膚の免疫学、接触皮膚炎の研究を開始し、飯塚先生のご専門が表皮細胞の生化学、乾癬の研究だったこともあり、若い頃はあまり先生と学問的な話をした記憶がありませんでした。その後私が北里大学に移り、安田利顕先生や西山茂夫先生の主宰されていた皮膚脈管膠原病研究会などに参加するようになり、その会での先生の深い臨床の知識や質問の鋭さにいつも勉強する意欲をかき立てられたものです。また懇親会などの席で西山茂夫先生が「皮膚の病理学的な所見を論理的に説明できるのは飯塚先生と九大の今山先生だけだ」とよく言われていたことも思い出します。その後1996年に私が長崎大学の教授になり、一度長崎地方会での講演を御願いしたときのお話は強く心に残っております。その時の講演タイトルは確か「乾癬とリモデリング」だったかと思いますが、その中で先生が乾癬の病理組織反応を論理的に解説され、6角格子は一番安定な構造で乾癬の表皮と真皮はお互いに影響を与えながら、最終的にPsoriatic architectureと表現される真皮乳頭が6角格子の形をとる組織反応が構築されると言われた事を鮮明に覚えております(もちろん難解な数式を用いたお話は、私の理解の範囲外でした)。その当時、私もアトピー性皮膚炎の表皮変化が真皮の影響を強く受けているのではないかと思い、アトピー性皮膚炎の線維芽細胞の研究を開始した時期で、アレルギー炎症の慢性化を考える言葉として「組織リモデリング」が使用され出した頃でした。もちろん飯塚ワールドのリモデリングとは全く異なる概念ですが、私には飯塚先生がスライドで示された乾癬のモデル(真皮乳頭)の構造がちょうどバレンシアの青い空に向かい、そびえ立つガウディの尖塔のイメージとして頭に浮かび、サグラダ・ファミリアが遥かな時を超えて完成していく像と飯塚先生が追求されている乾癬という疾患の謎の解明が不思議に頭の中で一致した記憶があります。ガウディは「神は急がない」という言葉を残していますが、私には、飯塚先生の生き方、研究スタイルはむしろ開高健の言葉として有名になったローマ帝国初代皇帝アウグストゥスの言葉「悠々として急げ」に近いような気がしております。ガウディの聖家族教会は今も世界中から多くの職人が集まり、いつ完成するのか誰にも分からない中で、建築が継続されています。飯塚先生には退官後も乾癬の謎の解明に興味を持つ若者を指導し、悠々と研究を楽しんで頂きたいと願っております。
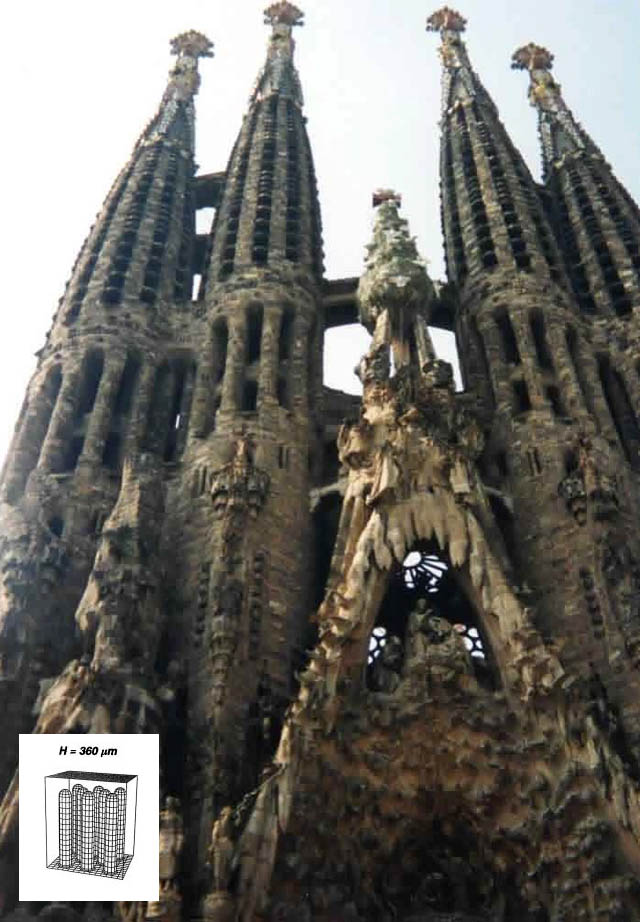
サグダラ・ファミリア(片山撮影1996)と
乾癬の組織構築モデル(JDS 2004.35:93-99)
大阪大学大学院情報統合医学皮膚科 片山一朗
平成26年6月9日掲載
第113回日本皮膚科学会総会
第113回日本皮膚科学会総会
会頭 岩月啓氏 岡山大学皮膚科教授
会場 京都国際会議場
会期 2014年5月30日〜6月1日
テーマ —皮膚科の職人魂—
大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学皮膚科学
教授 片山一朗
第113回日本皮膚科学会総会が5月30日から6月1日までの3日間、新緑から初夏の京都国際会議場で開催された。会頭の岩月啓氏教授、事務局長の青山裕美先生、実行委員長の山崎修先生には5,000人(実際には6,000人?)を越す参加者を迎えられ、大成功のうちに大会を終えられたこと、心よりお祝いと御礼を申し上げたい。今大会のメインテーマは「皮膚科の職人魂」で、会場の各所にそのロゴが見受けられた。また教室員が主演のプロモーションビデオや地元児島のジーンズ、コングレバック、記念白衣、きびだんごなど会頭のお人柄、教室員の一致団結ぶりを示す岡山色に溢れた学会であった。私も病院用のジーンズを早々に購入した。

学術大会は例年通り岩月教授の会頭講演から開始された。座長を務められた荒田次郎先生は岩月教授同様フランス学派の先生でその思い出を交えながら岩月教授の紹介をされたのが印象的であった。講演ではまず岡山大学の歴史を紹介され、研究皮膚科学会の谷奥喜平記念講演で有名な谷奥喜平教授、野原望教授の時代に岡山大学の皮膚科が大きく発展し、全国に多くの教授を輩出されたことを述べられた。岩月教授は我々の世代では珍しく、きわめて日常臨床を大事にされる先生であり、また次世代の若手医師や学生教育に熱心な先生で、その哲学を述べられ、会員に大きな感動を与えていただいた。またこれは以前から我々も考えていたことで、今では入手不可能でかつ読むことが困難な皮膚疾患の、原語による原著の日本語訳(岡山大学OBの大熊登などの先生方のご尽力と聞いている)を特にフランス人皮膚科医が記載した論文に限定して、会員に配布されたことは素晴らしい事業で、今後の学会の事業のあり方を考える上でも貴重なことと考える。実際岩月教授ご自身がパリに行かれ、原著の収集やサンルイ病院などに残された膨大なムラージュもご覧になり、撮影されてきたそうである。
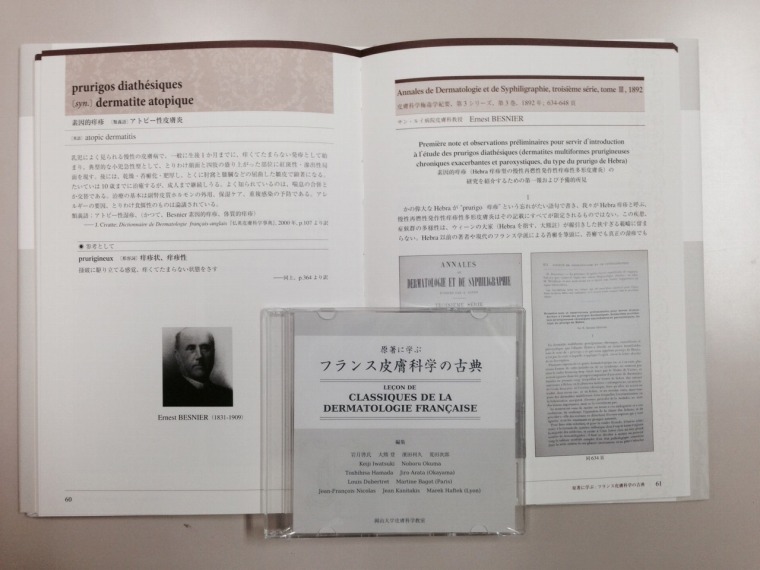
「Pririgos Besnierの項」
会頭講演に引き続き、皆見賞の受賞講演、ランチョンセミナー、教育講演が漸次開始された。今大会は岩月教授ご尽力の魅力的なプログラムによるところがきわめて大きいと思われるが、初日のランチョンから多くの会員が参加し、広い京都国際会議場が最終日の最後のセッションまで人で溢れ、素晴らしい会となったことは岡山大学の先生方にとってもこの数年のご努力が報われ、本当に良かったと思う。
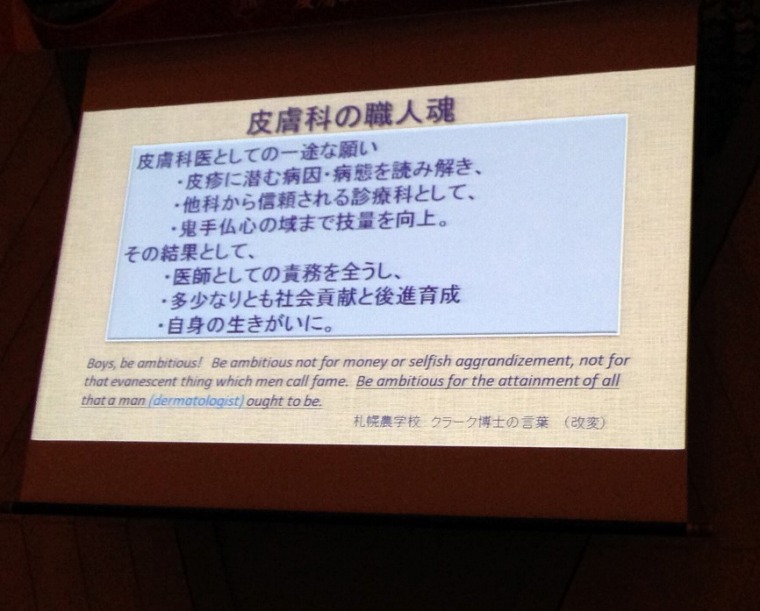
教育講演も昨年までと異なりオーガナイザーが積極的に議論を盛り上げられ、上から目線の一方通行でなく、演者と聴衆が双方向性の議論を楽しめる本来の学会に戻りつつあると感じられた。岩月教授が提示された学会プログラムの見直しは皮膚科学会の将来計画委員会で進められていくと聞いている。ぜひ受け身でなく若手参画型であり、なおかつ会員全体が相互に皮膚科学の伝統、職人魂を継承していける学会にして頂きたいと願う次第である。実際私と東京医科歯科大学の横関博雄教授がオーガナイザーをつとめた教育講演「汗関連疾患の謎に迫る」は若手から大御所の教授まで、他人の仕事の引用でなく、それぞれご自身が手を汚され、ご自身の哲学を述べられた講演で、質疑応答も時間を超えて、盛り上がり、大変満足したセッションであった。他の教育講演もオーガナイザーの工夫の溢れたセッションが多かったそうで、会員の先生方の評判も「素晴らしかった」という賞賛の声ばかりであった。また岩月教授が大切にされているアジアの皮膚科医の連携では[Agora for Asian Dermatologists]のセッションが設けられ、教室の揚先生も発表した。例年空席の目立つ土肥記念国際交換講座は今年はこれも岩月教授のアイデアで、場所をウェスチン都ホテルに移して、行われ、会場では軽食を楽しみながらカリフォルニア大学サンジエゴ校のGallo教授のライブ講演を楽しむことができ、今後の土肥記念講演の参考になったかとおもう。私は他の会議で聞くことができなかったが、アブストラクト賞として口頭発表の機会が与えられた若手の先生には大きなモチベーションの向上に繋がったかと思う。
一般演題はすべてポスター発表であり、今回もデジタルポスターが採用されていた。昨年の早石祥子先生に続き、今年も藤森裕梨先生が「皮膚潰瘍を合併した膠原病疾患における血清HMGB1の推移」でポスター賞を受賞された。終始指導された山岡俊文先生ご苦労様でした。例年通り、すべてのポスターを見て回ったが、阪大の発表はどれもレベルが高く、来年もまたポスター賞をめざし頑張っていただきたい。もちろん英文論文にすることが大前提であるが。
最後に繰り返しになるが、この数年ややマンネリ化しつつあった皮膚科学会総会が会頭のアイデアでかくも素晴らしい会になるということを実感できた113回大会であった。岩月教授と岡山大学皮膚科学教室の先生方に改めてお礼を申し上げたい。

大阪大学大学院情報統合医学皮膚科 片山一朗
平成26年6月5日掲載
8th Georg Rajka Symposium on Atopic Dermatitis
ISAD 2014 21st-23rd May 2014
8th Georg Rajka Symposium on Atopic Dermatitis
East Midlands Conference Centre, Nottingham, UK
President: Prof. Hywel Williams Univ. Nottingham UK
大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学皮膚科学
教授 片山一朗
新緑の英国ノッチンガムで開催された第8回 8th Georg Rajka Symposium on Atopic Dermatitis (通称ライカシンポジウム)に参加した。この会はHanifin & Rajkaの診断基準で有名なノルウェーの皮膚科医George Rajka教授が1979年に第1回大会をオスロで開催され以後2〜3年に1回開催されている。日本でも2008年に浜松医大の瀧川雅浩教授を会頭として第5回大会が開催されている。
本第8回大会の会頭はアトピー性皮膚炎の疫学、EBM研究で世界をリードされているノッチンガム大学皮膚科ハイウェル・ウィリアムズ教授で、アトピー性皮膚炎の病因、病態、疫学、治療などに関して招請講演9,口演33,ポスター88題、および、学会企画3企画の発表、講演があった。また大阪大学からは片山、室田、寺尾、小野、山鹿の5名が発表、座長として参加した。

(開会の挨拶をされるWilliams教授)
我々は初日から参加したが、最初のセッションのテーマは「病因」で,アトピー性皮膚炎でのフィラグリンの遺伝子変異を世界に先駆けて発表したAlan Irvineが最近の知見をReviewした。まずフィラグリンの遺伝子変異があるとネコが悪化因子になることや、ピーナッツアレルギーが生じやすくなるという興味ある話から講演が開始され、遺伝性の皮膚疾患ではEctodermal dysplasiaやWiskott Aldrich症候群などが鑑別疾患として重要であること、欧米と日本ではその変異の頻度に差があること、Extrinsic ADでその頻度が高くなりTh2アレルギーが誘導されやすいこと、皮膚のpHが上昇するとバリア機能が障害されることなどを分かりやすく纏められた。この他一般講演では、29週以前の早産児ではバリア機能の未熟さに反して、アトピー性皮膚炎の発症リスクが低下する、Grass pollenの実験的な曝露で湿疹性の皮膚病変が誘導される(我々が報告したスギ花粉皮膚炎の実験的な証明)、英国などの硬水がアトピー性皮膚炎のリスクを上げる、イヌのピーナツアレルギー経皮感作モデルなど興味深い発表がたくさんあった。
2日目は午前中の「発症機序」のセッションで三重大の水谷教授がマウスの皮膚の掻破音の採音とビデオの掻破行動が正のきれいな相関を示すことを報告された。水谷教授は「Pori Pori」教授としてすでに高名であると聞いた。また浜松医大の戸倉教授は角層の蛋白の網羅的な解析をされており、分化マーカーの差や細菌由来の蛋白をどう除外するかなどの質問があった。午後はヒスタミンがH1,H4レセプターを介して皮膚のタイトジャンクション蛋白の発現を抑制するとの興味ある発表があった。
午後の「予防とその結果」のセッションは私も座長を務めさせて頂いた。Probioticsの予防効果のレビューのあと、スキンケア介入によるアトピー性皮膚炎の発症予防効果の途中経過報告が英国、日本から合ったが。入浴指導などの群とあまり有意差がないような印象で、もう少し多数例で長期の観察が必要と感じた。WilliamsはHOMEI-III研究でOutcome measureのCriteriaの確立を現在進めており、その発表もあった。Symptoms, Signs, Longterm control, QOLなどが重要な評価項目になるということがすでに合意されており、さらに重症度の定義、バイオマーカー、Proactive療法などが討論された。個人的には皮膚の炎症の評価をどう客観的に評価するか、いつ中止するか、用いる外用剤をどう決めるかなど解決すべき点も多い。三日目は帰国のため午前の「治療」のセッションのみ聞いた。重症例の治療アルゴリズム、IL4R抗体の効果などのほかタール療法がAryl hydricarbon receptor を介して皮膚炎を抑えるという興味深い発表があった。 NottinghamはRobin Hoodが活躍した町ということでホームページもNottingham城の前にある像が使われており、我々も記念写真撮影をし、最終日にはNottingham城に立ち寄った。


今大会はWilliamas教授の行き届いた配慮で非常にスムーズに会が進行した。2日目の夜に開催された懇親会ではWilliams教授自身が作詞、作曲されたRaika教授を称える歌が披露され、アンコールの声と拍手が鳴りやまなかった。またRajka記念メダルが婦人からJonathan Silverbergに授与された。

次回は2016年にブラジル、サンパウロで開催される予定である。最近の日本皮膚科学会、アレルギー関連学会でもアトピー性皮膚炎の発表が減っているという印象はあるが、病因、治療、疫学などまだまだわからない点が多く残されており、若い先生方の参加が望まれる。
参考までに今回の発表の抄録PDFを添付するので参考にしていただければと思う。
抄録PDF:
ISAD 2014 Invited Speaker Oral Abstracts V2
ISAD 2014 Submitted Oral Abstracts
ISAD 2014 Submitted Poster Abstracts
南方熊楠とSTAP細胞
南方熊楠とSTAP細胞
大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学皮膚科学
教授 片山一朗
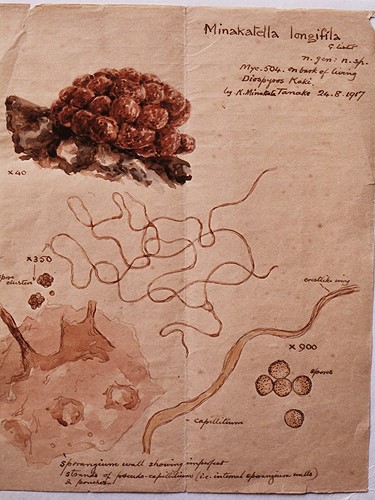
写真:
Minakatela Lomgifilia Lister
南方熊楠博物館Web-siteより
http://www.minakata.org/
大阪大学大学院情報統合医学皮膚科 片山一朗
平成26年5月14日掲載
第26回日本アレルギー学会春季臨床大会
第26回日本アレルギー学会春季臨床大会
会長:眞弓光文福井大学長 会期:2014.5.9-11
会場:国立京都国際会議場
テーマ:
「アレルギー克服への新たな挑戦
~研究と診療のReciprocal Interaction~」
大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学皮膚科学
教授 片山一朗

今年から日本アレルギー学会が年一回の開催となり、5000名を越す多くの参加者があったそうである。大阪大学からは4題の発表があり、内2題はミニシンポジウムに採択された。発表された西岡、田原、小野、越智先生御苦労様でした。どの演題も注目されたようで私にも、発表後結構意見を頂いた。
室田先生は東アジア・アレルギーシンポジウムの企画を担当され、先生が推薦された大阪大学基盤研の川端先生のiPS細胞からの肥満細胞の誘導はFLK1とCARの発現パターンでHematopoietic cell と心筋細胞への2方向性の分化がみられることをきれいに示され、さらに用いる増殖因子(IL3.IL4)/SCF,IL6により粘膜型と結合織型肥満細胞に誘導出来ることを示され、今後の臨床応用が期待できるかと思う。ただ最終的な培養系がメチルセルロース法でのコロニー形成法であり、細胞の回収法など工夫が必要と考える。今回も総合アレルギー医育成へ向けた教育プログラムが多く組まれており、会員の関心の深さが見られた。特に毎年秋に開催されていた秋季大会は今年からは総合アレルギー医育成のための教育プログラムを中心とする講習会になる予定で、太田健副会長を中心に今プログラムが作成中である。また舌下免疫療法の教育プログラムも受講希望者が多く、今後鼻学会と連携して講習会が開催されるそうである。この講習会の受講証明がないとe-learning受けられず処方も出来ないそうで、今後ダニの舌下免疫療法など皮膚科医も知識を得ておく必要がある。2017年から開始される専門医認定機構による専門医認定は基盤18学会+総合診療科と平行して、アレルギー学会などSubspeciality学会の専門医制度改革も進められており、長期計画委員会、専門医制度委員会などの合同委員会でカリキュラム、研修プログラム、研修施設の認定基準などが論議されている.しかし皮膚科学会でも論議が継続されているが、国の長期的な方針が見えずらく、実際の研修プログラムが固定されるのに、もう少し時間がかかりそうである。このような専門医改革と平行して学会事務局主導の大会運営、学術委員会の委員による査読での優秀な一般演題の選定や、学術委員会と大会長の合議制による学会プログラムの作成などあらたな学会の運営改革も進行している。
会期中少し時間がとれ、叡山鉄道を利用して新緑の鞍馬山に登り、鞍馬寺、貴船神社を参拝し、心身ともリフレッシュさせて頂いた。


大阪大学大学院情報統合医学皮膚科 片山一朗
平成26年5月13日掲載
長崎大學医学部皮膚科学教室開講100周年記念
長崎大學医学部皮膚科学教室開講100周年記念
日本皮膚科学会長崎地方会第322回例会
2014. 4.12-13
長崎ベストウェスタンプレミアホテル
長崎大學良順会館
大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学皮膚科学
教授 片山一朗
長崎大學皮膚科学教室が開講100周年の記念すべき年をお迎えになるということで、この度記念式典、地方会で講演、祝辞を述べる機会をいただいた(写真、プログラム)。
長崎大學医学部はオランダ人医師、J.L.C Pompe Van Meedervoortが1857年11月12日に設立した長崎医学伝習所をその礎とし、以後多くの蘭学、西洋医学の人材を輩出し、日本の近代医学の発展に貢献したのは皆さんご存知の通りである。私自身は現在13代目の教授である宇谷厚志先生の前々任11代教授として、1996年7月1日付けで着任し、2004年2月28日まで7年9ヶ月奉職させていただいた。私が在任中,長崎大學医学部開講140周年記念祝賀会が催されたことも懐かしく思いおこされた。
私の記念講演の演題は「皮膚の恒常性とアレルギー:長崎医学から学んだこと」とし、長崎大學在任中に研究を開始し、大阪大学に転任後も継続している研究を紹介させて頂いた。まず私の前任の吉田彦太郎先生と阿南貞男先生が着手された、長崎大學新入生のアトピー性皮膚炎検診の成果を紹介させて頂いた。この研究はアトピー性皮膚炎の疫学研究の継続的な研究として画期的な成果を残し、大阪大学でも2011年から3年間行った厚労省の思春期アレルギー患者の動態研究と医療経済への影響という班研究に繋がった。次にベ・サンゼ先生が見いだした、非神経組織である皮膚のケラチノサイトが神経ペプチドであるサブスタンスPを産生し、Th2型アレルギーを増幅すること、アトピー性皮膚炎病変部由来の線維芽細胞はサイトカイン刺激への高反応性を継代培養後も維持し、Atopic fibroblastともいうべき形質を獲得していることを紹介した。この研究は現在室田先生がアーテミンという新たな神経成長因子を発見した研究に繋がり、痒みの研究に大きな貢献をしている。次に熱帯医学研究所の小坂教授と共同研究し、江石先生が見いだされたアトピー性皮膚炎での発汗機能の低下にかんする研究を紹介した。この仕事が松井佐起先生、室田先生の2光子顕微鏡によるエクリン汗腺の発汗動態を世界に先駆けて記録した画期的な研究に繋がり、講演後の懇親会でも多くの賞賛の声を頂いた。さらに長崎大學で開始した尋常性白斑にたいする活性型ビタミンD3の臨床研究がTh17疾患としての自己免疫性白斑の病態解明に繋がり、抗IL17A抗体の治療効果の検討まで進んでいること、腫瘍医学の松山俊文教授の指導で開始したTNF受容体p55ノックアウトマウスでのブレオマイシン誘導性強皮症モデルで強皮症のライフサイクルが1週間で見られることの発見、そして抗IL6受容体抗体の人への応用が進んでいることを話させて頂いた。私自身長崎大學で蒔いた種が大阪の地で大きく育っていることを再認識した今回の記念地方会でもあった。また長崎大學で一緒に働いた多くの先生方と再会でき、「当時の仕事の意味がやっと分かった」、そして、「今の仕事に繋がり大変嬉しい」とのコメントも頂き本当にありがたく、久し振りに感動した夜でもあった。最初に祝辞を頂いた片峰茂学長からは2001年に私が会頭を務めたシンポジウム「皮膚感染症の新たな視点」でプリオン病に関する講演を頂いたことにも触れて頂き、あのときの講演が片峰先生の研究にもブレークスルーになったという嬉しいコメントや河野茂元医学部長、現病院長からも私と同じ頃に教授に就任した時のエピソードを紹介して頂いた。野北先生は昨年101歳でご逝去された。あと1年間お元気であればと残念であったが、逆に若い元気な皮膚科医が育ちつつある現状を見て安堵されているかとも思った。
懇親会後は銅座に席を移し、長崎大學のラボの方や当時の弟子の先生方と懐かしいグラスを傾けた。この席には東京から遅れて参加した室田先生、翌日の発表を控えた山岡先生も同席し、懐かしい話に時間の経つのも忘れ話し込んだ。この後の3次会には博多から駆けつけてくれたベ・サンゼ先生や獨協医大の濱崎洋一郎教授など男のみの6人で日が変わるまで私の昔なじみのお店で楽しい時間を共有することができた。
また学会中、長崎のお菓子とともに歴代の教授の写真を印刷したチョコ(写真)も提供され、翌日特別講演をされた京都大学の宮地先生からは私のチョコが一番売れていると聞いた。
2日間に亘り立派な会を主催して頂いた宇谷教授、教室の先生、そして
懐かしい、同門の先生には心より御礼を申し上げ、今後の長崎大學皮膚科のさらなる発展を願って御礼の言葉としたい。

記念式典で挨拶される宇谷厚志教授


大阪大学大学院情報統合医学皮膚科 片山一朗
平成26年4月15日掲載
大阪大学皮膚科学教室着任10周年を迎えて
大阪大学皮膚科学教室着任10周年を迎えて
「シンクロニシティ:Synchronicity」と「粘菌:Slime mold」
平成26年3月5日
大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学皮膚科学
教授 片山一朗
私と室田浩之君が大阪大学医学部に着任して今年の3月1日で10年が経過し、11年目を迎えることができました。大変ありがたいことに、3月5日と6月21日の2回それぞれ、医局、同門会で祝賀会を開いていただくことになりました。関係者の皆様には、この場をかりて御礼申し上げます。私は大阪大学医学部で研修医、大学院生活を送りましたが、室田君は長崎というのんびりした安住の地から、大阪という魅力的でかつ混沌とした、そして、大阪弁が標準語の街にこられてさぞかし大変だったかと思います。実際、私も20年ぶりに大学に戻った時にはじつに多くの出来事(事件)が続け様に起こり、当時の病院長から門戸厄神にいってお祓いを受けてこいといわれました。しかしその後は多くの医局員や秘書さん、技術員のかたがたの献身的なサポートで、より活力のある、そして多くの情報を世界に発信できる皮膚科学教室に育ってきました。私自身良くコラムなどに「信頼と品位のある人と人との繋がりが何より大事」と繰り返しいってきました。長い人生で、縁もゆかりもない人間が、ここ千里が丘の地で、ある時間を共有し、何かを成し遂げ、そしてまた別の道に進んで行くのは奇跡ともいえる偶然ともいえますし、宇宙の神が書いた必然の出来事なのかもしれません。しかし、この10年間教室に在籍された方々が相互の信頼と尊敬の念を持って、大阪大学皮膚科学教室を発展させてこられたのは紛れもない事実です。「シンクロニシティ(Synchronicity):意味のある偶然の一致、共時性」という言葉は最近ある方から教えて頂いた言葉ですが、まさにこの10年間に大阪大学医学部皮膚科で偶然出会い、そして皮膚科医として成長されてきた先生方、そしてサポートして頂いたすべての方の今後のご自身の人生の目標が達成される事を願います。
粘菌(Slime mold)は南方熊楠の世界的な研究で有名な植物と動物両方の性質をもつ,非常にしたたかな生活様式をもつユニークな生き物です.「他の星からこの地球に、落ちてきた生物の原型ではないかと」言う生命学者もいます。最終的に子実体と呼ばれる植物的な構造を形成しますがアメーバのように子実体は胞子群とそれを支える細胞性の柄(死細胞)からなり.胞子は適当な条件下で発芽してアメーバ状の細胞となり,周囲の餌(大腸菌などのバクテリア)あるいは栄養豊富な培養液を取り込みながら増殖します(図).湿度、温度、日照などの周囲環境の変化や栄養源が枯渇して飢餓状態になると,単細胞はやがて集合して多細胞体を構築し,分化・パターン形成の方向に移行します(マウンド、スラッグ)。そして環境が改善するとまた元の個々の生命体に戻っていきます。このような粘菌の行動パターンは私が理想とする組織像にかさなります。私自身は大阪大学皮膚科に属する方には個人の個性を大事にし、自分のやりたいことを自由にやってもらうように指導しています。そして皮膚科学教室に危機が迫った時や何か大きなミッションを命ぜられた時などには、個々の医局員が少しづつ機能的なユニットを形成し、最終的には粘菌のマウンドあるいはスラッグとよばれる巨大な集合体を作り、正しい方向性を決定することで、危機を免れ、あるいは目的を達成し、その後は個々の構成員に戻り、また個性的な生活を始めます。この巨大化した組織のヘッドは決して私ではなく、構成員がそれぞれ精神的な繋がりを持つことで生まれた新たな精神・生命体とも言うべきものかと思います。私の目指す大阪大学皮膚科はまさにこのような生命体であり、この10年間でその形が見えてきました。今後また次の10年でどう育っていくか楽しみです。
今の私の興味は人間の持つ、5感(視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚)をセンシングする分子がすべて皮膚に存在し、皮膚が人間の感覚や存在を規定しているのではないかということを知ることで、すでにロドプシン、TRPなど視覚、嗅覚、味覚などのセンサーの皮膚細胞での存在が明らかにされつつあります。皮膚という臓器の重要さをさらに知り、その異常を是正し、若さを保つ作業の重要性を認識しながら、さらに皮膚科医としての研鑽を積んでいきたいと考えております。この10年間のご支援、ご助言にたいし心より
御礼を申し上げ、お祝いの挨拶とさせていただきます。
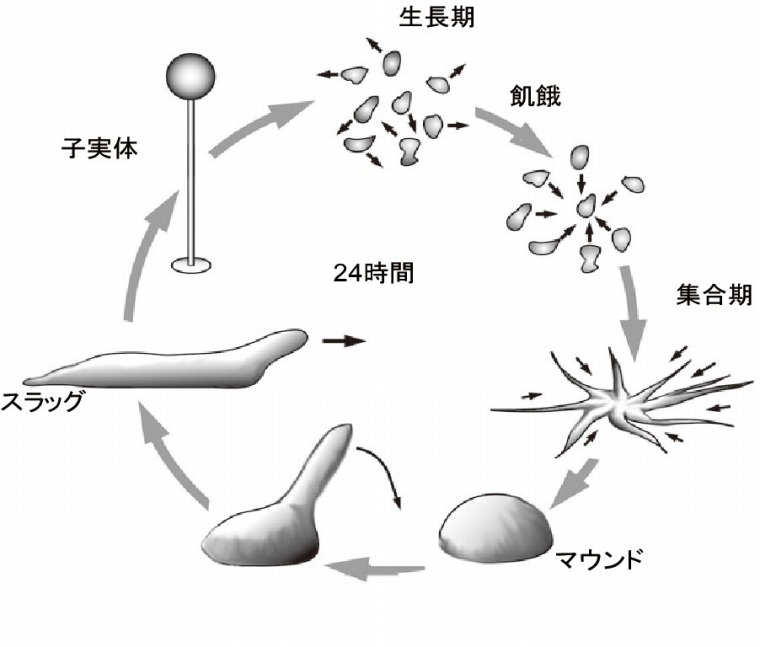
細胞性粘菌の生活環
「モデル生物:細胞性粘菌」(前田靖夫氏編)から引用 PP.I -II
大阪大学大学院情報統合医学皮膚科 片山一朗
平成26年3月5日掲載
第19回アトピー性皮膚炎治療研究会
第19回アトピー性皮膚炎治療研究会
平成26年2月2日(日)
会頭:秀 道広 (広島大学大学院皮膚科学教授)
広島大学医学部広仁会館
テーマ:「ステロイド治療を総括する」
大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学皮膚科学
教授 片山一朗
この会は皮膚科領域のアトピー性皮膚炎の診療に携わる医師が年に1回集まり、共通のテーマで討論し合うユニークな研究会である。第1回は1996年に代表世話人の青木敏之先生(当時羽曳野病院副院長)が「アトピー性皮膚炎の治療効果の判定法」というテーマで開催された。私は「アトピー性皮膚炎の治療マーカー」というテーマで2005年に第10回大会を大阪で担当させていただき、多くの先生が参加され、活発な討論を頂いた。以後はガイドラインの普及による、難治例の減少などによりこの回もだんだん参加者が減り、ここ数年は皮膚脈管膠原病研究会と重なることが多く、久し振りの出席となった。今回はテーマがステロイド治療に関したもので、日曜開催ということもあり、久し振りに200名を越える多数の出席者が活発な討論を行い、満足のいく会であった。
金沢大学の竹原教授のワークショップ「アトピー性皮膚炎治療におけるガイドラインの役割」のキーノートレクチャーから大会は開始された。最近の若い先生は20世紀後半のアトピー性皮膚炎治療の混乱やガイドライン作成の経緯もあまり知らないという前提で、食物アレルギーにおける皮膚科医と小児科医の対立、ニュースステーションでのステロイドバッシング特集、アトピービジネスという言葉の誕生の歴史を簡潔に纏められ、ガイドラインが作成された背景を述べられた。脱ステロイド療法の今日的評価やステロイド忌避患者の対応に関して討論がなされたが、それぞれ診ている患者集団が異なることや、治療のゴール、用いる評価方法が異なるなどの意見が述べられた。私自身は同じ視点、同じ方法論で患者を診療、加療し、同じ評価方法で治療の効果判定を行うことが重要と考える。片岡葉子先生は血清TARC価を指標として、治療のゴールを明確に患者に示すことの重要性を指摘し、ステロイドも寛解導入、維持、漸減とメリハリの利いた使用法を行うことを提唱された。アトピー性皮膚炎の治療に精通した皮膚科専門医が行えば短期的には良い結果が期待できることは参加した殆どの医師が共感を示していたが、非専門医が長期に管理する場合、かつての難治性顔面紅斑やコントロールが困難な例が再び増加してくる可能性が危惧される。また指標となるべきTARC価が必ずしも指標にならない例の存在することの具体例に関してフロアからの指摘がいくつかあった。ガイドラインの討論同様、各施設で診療している患者の重症度や年齢、治療歴、悪化因子などが異なり、同じ尺度で治療を行うことの難しさをあらためて感じ、私もコメントした次第である。特に安易なステロイドの使用が難治性の高齢者の紅皮症の原因となりつつある現状があり、あらためて長期管理の重要性での論議が必要と考える。このテーマに関しては最後のセッションで片桐一元教授が本人自らのアトピー性皮膚炎を例にとり、キーノートレクチャーを行い、塩原哲夫教授が座長として意見を取り纏められた。フロアからは皮膚症状が手湿疹などのみとなってもアトピー性皮膚炎の非改善例として取り扱うのかなどの意見がでたが、あまり有益な議論にはならなかった。むしろ片桐教授が指摘された、日本のみならず、海外の検討でも、必ず10〜20%の難治例が残る理由とそのような難治例をどう治療していくかが問題であるとの指摘が重く受け止められた。ちなみに片岡先生の施設でも退院で軽快した症例の再燃が30%前後ありいかにタイトコントロールしてもコントロールが困難な症例が存在するようである。
この他特別講演としてステロイドの最新情報、中国のアトピー性皮膚炎の現状、汗抗原の解析の話があった。
来年は三重大学の担当で2月14日(土)の開催予定である。

会場(広島大学医学部広仁会館)
大阪大学大学院情報統合医学皮膚科 片山一朗
平成26年2月3日掲載
誤診し易い皮膚疾患
誤診し易い皮膚疾患
大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学皮膚科学
教授 片山一朗
西山茂夫先生の名著「誤診し易い皮膚疾患」(金原出版、1968)(写真1)が皮膚病診療誌の増刊号として再版された(写真2)。この教本は我々の世代より10年以上先輩の先生方が良く読まれていたそうで、長い間、絶版のままであったが、今回、井上勝平宮崎医大名誉教授のご尽力で若い先生方にも読んで貰えることとなった。私自身、学生時代は上野賢一先生の「皮膚科学」(Minor Dermatology金芳堂)、皮膚科医になってからはTextbook of Dermatology (Rookの教本 Blackwell)などを良く読んだ。幸か不幸か西山先生のこの教本は1996年に長崎大學に行くまで知らず、また手に入れることも困難で、同じく名著の誉れの高い「皮膚病アトラス」(文光堂)で勉強させて頂いていた。いつ頃か忘れたが、日本医大教授の幸野健先生がこの教本をコピーで読んでいるとの話を聞き、私もアマゾンで手に入れた(写真)。西山先生が今回の改訂版の前書きで書かれているが、原著は通勤途中の電車の中で、僅か3週間で執筆されたそうで、写真は一葉も使用されていなかった。今回の改訂版では西山コレクションからたくさんのカラー臨床写真が掲載されており、簡潔な説明とあわせ、読みやすく編集されている。原著の特徴はこれも先生が前書きに書かれているように、「個疹ないし病変を理解し、個々の患者の全身的要因を背景とした個体病理学的考え方」に基づき、誤診しやすい皮膚疾患(特に炎症性疾患)を中心に簡潔にその診方、考え方が記載されている点かと考える。若い先生には、特に各章の最初に書かれている原発疹、続発疹あるいはその疾患の定義を良く読まれることを薦める。そこに西山皮膚科学の真髄が書かれている。かつてある学会で皮膚科診断学に関するDebateがあり、丘疹と結節の違いをめぐって某大学の教授との論争があった。西山先生は「トマトは大きくともトマトであり、カボチャは小さくてもカボチャである」と相手を論破された時の興奮を思い出しつつ再版の「丘疹」、「結節」を読んだ。(西山先生の皮膚病診療の巻頭言にも多くの診断学についての記載があり、私のコラム2013年の「皮膚科疾患の病名と診断名を考える」に許可を得て掲載している)。また、5年前から尋常性白斑の研究をしており、白斑と乾癬に共通する病因があるのではとの発想から研究を進めている。最初に発表した時、乾癬では脱色素斑は見られないとの意見を頂いたが、「誤診し易い皮膚疾患」の白斑と間違いやすい皮膚疾患に「乾癬」と書かれているのを見た時には、我が意を得た気がした。この点に関しては昨年、暮れのJIDにRockfeller大学皮膚科から発表があり、今後IL17A阻害薬の白斑への応用などが期待出来るのではと考えている(IL-17 and TNF synergistically modulate cytokine expression while suppressing melanogenesis: potential relevance to psoriasis. J Invest Dermatol. 2013;133(12):2741-52)。この本を読めば、若い先生は皮膚科の臨床がさらに面白くなるのは間違いなく、また我々の世代以下のベテランの先生にも色々な読み解き方のできる教本ではと考える。西山先生は昭和40年代初頭、皮膚科の臨床Vol9-12にシリーズで「組織のみかた」を書かれているが,これもまた、監修して若い先生に読んで頂きたい内容である。(Online化されれば、手軽にダウンロード、自炊が可能になるとは思うが。いずれにしても若い先生には、是非、一読を勧めたい名著である。


大阪大学大学院情報統合医学皮膚科
片山一朗 平成26年1月7日掲載
2014年を迎えて :「Innovative Dermatology from Osaka」
2014年を迎えて :「Innovative Dermatology from Osaka」
大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学皮膚科学
教授 片山一朗
皆様新年を迎え、新たな気持ちで診療、研究そして自身の年頭の目標をスタートさせておられるかと思います。
私も、今年3月で大阪大学に着任10年となります。着任時の教室作りのテーマとして、「明るく、楽しい皮膚病診療と開かれた教室運営」とし、大阪大学発の研究と創薬を自由に進めていただくこと、関連病院は部長の専門性を全面にうちだし、特徴のある診療を行うようにお願いいたしました。全国の教授からはやや覚めた視点のご意見を頂いた記憶がありましたが、教室、関連病院、関連大学、同門の先生方のご支援、ご尽力で大阪大学皮膚科学教室も大きく発展してまいりました。今年は12月に第39回の日本研究皮膚科学会を開催させて頂きます。大会のテーマは「Global Tuning of Innovative Dermatology」とし、2日目夜から翌日は審良静男教授の特別講演や阪大の先生方を中心としたInnovation forumを予定しております。次の10年のさらなる発展のためにも、本大会を基軸に研究を発展させ、大阪発の新しい皮膚科学の情報を日本のみならず、世界に発信させていく必要があります。
さて、日本の医療改革は二十世紀末の大学の法人化と大学院大学への移行に端を発し、10年前私が大阪大学に着任した年に開始されたスーパーローテートシステムの導入、学会とは異なる専門医認定機構によるあらたな専門医制度の開始やTPPの締結による医療での規制緩和など米国の医療に追従する形で進められてきました。そして今年からは大学などの研究機関には日本版NIH方式として厳しいグラント申請が課せられ、パスした研究のみに予算が重点配分されると聞いております。昨年米国のいくつかの大学を訪問したおり、研究者に聞いた話では、Publish or Perishの傾向はさらに進み、高名な皮膚科の教授もグラントが獲得できなければポジションを維持できなくなりつつあるそうです。逆もまた真で、ハーバードの皮膚科の主任教授はMelanocyteの幹細胞研究で高名で、学会などではPediatric Oncologisitと紹介されるDavid Fisherですが、臨床に関してはDay surgeryが主体の小さな皮膚科のようです。またコロンビア大学はAngella Christianoの業績で皮膚科としては有名ですが、主任教授の専門が何かを知る日本の教授は少ないかと思います。このような現状を考えると日本でも今後大学で皮膚科の看板をあげ続けていくためには皮膚という臓器に特化した、高度で新しい発想の研究が要求されて行くかと思いますし、結果として創薬につながり、他科の医療に貢献できる研究が優先的にグラントを取るかと思います。ただあまりにも基礎研究にシフトするとその大学から臨床科としての皮膚科学は消えていくかもしれませんし、長期的にはその地域の皮膚病診療にも大きな影響のでることが予想されます。逆に先に述べた臨床医としての豊かな経験や患者のニーズに基づいた視点からInnovativeな研究テーマを提案できれば、皮膚という臓器の特性を生かしたすばらしい研究や創薬開発、新しい生命論の提示なども可能になっていくかと思います。
この10年間皮膚科はどちらかというとPassiveな環境下でNegativeな議論を繰り返してきたのではないかと反省しております。今後はActiveな態度で積極的に研究、臨床に取り組んでいける環境を提供し、より普遍性のある研究、高度な医療、創薬開発を担うことのできるPositive thinkingの皮膚科医を一人でも多く育てることを最大のミッションとしていきたいと考えております。
昨年の免疫学会で慶応大学の天谷雅行教授はSurface Barriologyという、聞き慣れない、あらたな領域のシンポジストに選ばれておられます。ここ数年基礎医学研究の分野では消化管、気道、皮膚など外界と接する臓器に共通する新たな研究テーマ、創薬基盤が整いつつありますが残念ながら欧米も含め、皮膚科医がこの領域の研究に積極的に参画しているとは思えません。このほかにもアレルギー・自己免疫疾患、遺伝性疾患、悪性腫瘍など臨床医学に共通する研究テーマや紫外線に対する生体反応、かゆみの認知機能、新しい機器、方法論を用いた皮膚の生理機能解析など皮膚科医しか関与できない重要な研究テーマもたくさんあります。2014年が皮膚科学にとってInnovation 元年になることを願う次第です。
あらためて先生方のご協力をお願いいたします。
大阪大学大学院情報統合医学皮膚科 片山一朗
平成26年1月6日掲載
2013年アレルギー学会関連
2013年アレルギー学会関連
第63回日本アレルギー学会秋季学術大会
会長:大久保公裕 日本医科大学耳鼻科教授
会場:ホテルニューオータニ
会期:2013年11月28-30日
テーマ「Unity—領域を越えたアレルギー疾患治療へ」
大阪大学大学院医学系研究科分子病態医学
皮膚科教授 片山一朗
今年は日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会・総会学術大会と一部日程が重なり、後半は出席できなかった。大久保会頭のご配慮で皮膚科関連の演題は初日にしていただき、例年になく皮膚科からの出題も多かった。また来年度からはアレルギー学会が年一回の春開催となり、秋のアレルギー学会は今年が最後となった。以前は11月から12月にかけ日本免疫学会と日本アレルギー学会がその年の最後の学会となることが多く、一年の研究を振り返るのが常であった。この数年は免疫学会に参加することもなくなり、研究皮膚科学会がその代わりの学会となり、時代もかわったと実感する。さて今年は司会、委員会や理事会などが多く、一般演題を殆ど聞くことが出来ず残念であった。その中で印象に残ったのは耳鼻科、内科領域からステロイド抵抗性のアレルギー性鼻炎や喘息の演題やシンポジウムが組まれていたことである。以前から喘息ではステロイド抵抗性の定義がPSL20mg1週間内服でFEV1の15%以上の改善が認められないと定義されていたが、鼻炎、皮膚炎では抵抗性を数値化することがむずかしく、研究の進展は見られなかった。今回山形大学の太田先生の発表では、吸入ステロイドの効果が不十分な症例ではステロイドの核内レセプターでSplicing variantとしてNon-functionalなGRβデコイレセプター発現細胞が鼻炎局所に高頻度に見られることを報告されていた。我々の教室でも研究が進行している内因性コーチゾール転換酵素(11βHydroxysteroid dehydrogenase1)などが外来性のステロイドの効果発現を調節している可能性を報告された。また金沢の皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会で理研の茂呂先生がNatural helper cell がSTAT5依存性にIL33とTSLPの存在下でステロイド抵抗性の病態を示すようになるという興味深い成果を報告された。今後重症のアレルギー疾患治療における免疫抑制剤の選択に重要な知見と考えられた。
第43回日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎総会学術大会
会長:竹原和彦 金沢大学教授
会場:ホテル日航金沢 会期:2013年11月29-12月1日

今年4月から、古川福実先生の後任として日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会の理事長を拝命した関係で、前日から多くの委員会があった。特に日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会の一般社団法人への移行とそのための選挙法の改定の問題が論議され、2015年をめどに法人移行する案が承認された。法人化により、より公益性が重視されるようになり、学会としての社会的な評価もあがることが予測される。この他の大きな問題点として、日本専門医制度認定機構によるあらたな専門医制度が2017年度から開始されるが、皮膚のアレルギー疾患の専門医が日本アレルギー学会の専門医制度の資格をどのようにして取るのか、あるいはその意義がどうかなどまだ不透明な点も多く、今後の進捗状況の確認が重要と考える。この問題は日本アレルギー学会の専門医制度委員会や将来検討委員会でも論議されているが、内科領域のアレルギー疾患専門医に関しても日本呼吸器学会や総合診療医との棲み分けや教育プログラムをどうするかでまだ議論百出の状態である。
また今回の学会の大きな特徴はすべての一般演題がポスター発表と口演を(一題10分)義務付けられていたとことで、いつも消化不良になる学会が多いが、久し振りに討論を楽しむことができた。
来年の44回総会は11月21〜23日、東北大の相場節也教授を会頭に仙台市で開催される。若い先生方も奮って演題を発表下さい。
大阪大学大学院情報統合医学皮膚科 片山一朗
平成25年12月25日掲載
第25回日本色素細胞学会
第25回日本色素細胞学会
会頭:片山一朗 大阪大学教授
会場:大阪大学 銀杏会館
会期:2013年11月16日−17日
大阪大学大学院医学系研究科分子病態医学
皮膚科教授 片山一朗
第25回日本色素細胞学会を大阪大学銀杏会館で開催させて頂いた。学会は紅葉のきれいな万博記念公園を望む、ホテルエキスポパークでの理事会から始まった。来年はシンガポールで国際色素細胞学会が開催される関係で、日本での色素細胞学会はなく、2015年度は札幌医大の山下利春教授を会頭として同じ日程で開催されることが決定された。

今回は33の一般演題に加え、Key Note Lecture 3題、国際シンポジウム「Autophagy」3題、ランチョンセミナー2題、美白化粧品による白斑関連演題3題の発表があった。昨年の長浜バイオ大学での24回大会同様、若い研究者(特に男性)の参加、発表が多く、聞いていて気持ちがよかった。また今年から一般演題も英語での発表が多く、皆さん英語で充分な討論をされており、いよいよこの学会も国際化してきたと感じた。朝一番のKey note lecture で講演された山形大学の鈴木教授の内容は、蒙古斑の起源から日本人の皮膚色の決定因子まで科学的な基盤に立ち、かつ文化人類学的な要素の強い内容であり、極めて興味深い内容であった。あとから聞いた話では、調査に行かれたのはモンゴルの首都ウランバートルからさらに西に1000キロ移動が必要な場所で、昨今、報道で良く耳にする新疆ウイグル自治区に近い所とのことであった。私自身は蒙古斑が進化論的にどのような意味を持つのか興味があったが、皮膚色決定に関わる遺伝子や皮膚癌発症のリスク遺伝子など今後多くの貴重なデータが得られるものと期待される。
ランチョンセミナーは今回事務局長を務めた種村篤先生の留学していたロサンゼルス、John Wayne Cancer InstituteのDave SB Hoon教授がメラノーマの発症、脳転移などの進展に関わるメラノーマ細胞のEpigeneticな変化に関する最新のデータを講演された。彼のラボには現在教室の清原君も留学しているが、メラノーマなど、ガンに特化した臨床、研究を行っており、日本からは外科系の留学生が多いとのことであった。午後の演題はメラニン合成、分解に関わる基礎的な発表が多く、慣れない用語も多く、さらなる勉強が必要と感じた。シンポジウム「Autophagy」では、この分野の世界的な権威である大阪大学の吉森保教授が最新のデータを中心に講演され、最後のスライドでは、ケラチノサイトのAutophagyの機能により皮膚色が決定されると言う大変興味深い実験結果を示された。(J Invest Dermatol 2013)。また今回、米国UC Irvine校のAnand Ganesan先生は網羅的な遺伝子解析の結果、見いだされた、Autophagy regulator であるWIPI1のsiRNAを用いた研究でAutophagyがメラニンの合成に関与していることを示された。教室の揚先生は結節性硬化症での白斑にラパマイシンが効果を示すことより、Autophagy誘導に関わるmTOR機能の解析モデルとして培養メラノサイトのメラニン色素合成に対するsiTS1/TS2を用いてのデータを発表された。日本語のみでなく英語も堪能で、立派に質疑応答をこなされ、発表後はいくつかの共同研究の話があったようである。このほか東北大学の皮膚科からはメラノソーム輸送に関わるRab11aの制御にTLR2など自然免疫を介するシグナルの重要性や脂肪組織由来幹細胞から単離したMuse細胞が10種類の因子の存在下でメラノサイトに分化することを見事に証明した発表をされ、多くの質問が飛び交った。とくに多能性幹細胞で癌化しないMuse細胞を用いることで白斑の治療が可能になるかと思うし、メラノサイトの発生や分化の研究にも多くの情報を提供しうる素晴らしい研究であり、今後の発展を期待したい。このほか岐阜大学の國定教授は山形大学の鈴木先生と共同研究されているK5プロモーターにより、SCF遺伝子を導入したマウスが基底層にメラノサイトを持つこと、4種類の皮膚色をもつフェノタイプが得られたことを報告され、今後の研究に応用されることを話された。私自身は胎生期にメラノサイトの幹細胞が毛嚢バルジ領域に遊走するのはSCFなどの濃度勾配で決定されると理解していたが、SCFの基底細胞での発現によりバルジ領域からどのようにメラノサイトの基底膜上の分布が決定されるのか興味がある。3日間にわたり協力頂いた西田健樹技官、二上さん、荒木さん、杉山さんを初め多くの医局の先生に心より感謝します。

理事の先生方と迎賓館にて
大阪大学大学院情報統合医学皮膚科 片山一朗
平成25年11月19日掲載
2013年支部総会(西日本支部、中部支部)
2013年支部総会
大阪大学大学院医学系研究科分子病態医学
皮膚科教授 片山一朗
第64回日本皮膚科学会中部支部学術大会
会長:松永佳世子 名古屋保健衛生大学教授
会場:名古屋国際会議場 会期:2013年11月2-3日
テーマ「早く、きれいに、親切に、適切な医療費で治す:皮膚科のQuality Indicator 医療の質を考えよう」
第65回日本皮膚科学会西部支部学術大会
会長:金蔵拓郎 鹿児島大学教授
会場:鹿児島県民交流センター
会期:2013年11月9-10日
テーマ「原点回帰」
毎年9-10月は日本皮膚科学会の3支部学術大会が開催されるが、今年は3
つの大会のうち中部支部と西部支部総会に参加する機会があった。それぞれの会で印象的だった講演を聞いて感じたことを記録しておきたい。

会長の松永佳世子教授は接触皮膚炎の研究でご高名であり、パッチテストの標準化や医薬品・医薬部外品などによる健康被害調査研究にも積極的に参画されている。本学会でも「茶の雫石鹸」、「美白化粧品による白斑」など講演があり、活発な討論が行われた。大会のテーマ「早く、きれいに、親切に、適切な医療費で治す:皮膚科のQuality Indicator 医療の質を考えよう」に沿い、それぞれのセッションで会長推薦の特別講師が皮膚疾患のQuality Indicatorをどう評価し、臨床に応用していくかを述べられた。
内科疾患などに比べ、皮膚疾患は数値による評価が難しく、今後乾癬のPASIやアトピー性皮膚炎などの痒みのVAS、DLQIなどを指標とした治療の質の評価が行われていくかと考える。ただこの分野で先駆的な方である聖路加国際病院の福井次矢病院長のお話を聞いたが、あまり個々の医師の評価を厳密にするとガイドライン同様、医師の裁量権が失われ、結果として医療の質が低下する危険性が生じるかもしれない。特に米国の医療に追従している今の日本の医療ではTPPの導入が本格化すれば、大手保険会社の評価基準により、使用できる医療が極端に制限されることも危惧され、経営効率と医師の裁量権のバランスをどうとるのか、結果として患者の不利益が生じないかなどの議論がもっと必要と感じたのは私だけではなかったのではないかと思う。大阪大学からは、吉岡先生がEctodermal dysplasiaでの発汗障害、村上先生がBirt-Hogg-Dube syndromeをいづれも金田真理先生の指導で報告された。前者はEDARADD遺伝子、後者はFolliclulin遺伝子の変異が証明された。近年Hypohidrotic/anhidrotic ectodermal dysplasia患者が高頻度にアトピー性皮膚炎様症状を呈することが報告され、注目されている。吉岡先生の他の同疾患患者での解析でもフィラグリン遺伝子変異はないようで、むしろ乏汗による角層水分量の低下などが皮膚炎発症に関与する可能性が考えられ、現在検討中である。またBirt-Hogg-Dube syndromeは金田先生のライフワークである結節性硬化症の近縁疾患で、やはりmTOR関連分子の異常により腎腫瘍などが生じる。皮膚病変としてはFibrofolliculoma, Fibrous papule of the noseなど顔面に過誤腫様の小結節が多発することで注意が必要である。

金蔵会頭の原点回帰は、西部支部を中心とした大学を代表とする若手先生方の研究発表による3つのシンポジウムと臨床に特化した一般演題に示されていた。スーパーローテート開始後のマンパワー不足により西部支部でも若手指導医の減少により大きな影響が出ていると聞いていたが、そのような中、基礎研究と皮膚科の臨床への回帰をテーマとされた金倉会頭の思いが伝わる大会であった。シンポジウムで聞いた講演では、特に島根大の千貫先生のお話しが強く印象に残った。Molecular allergology としてアレルゲンコンポーネントの測定の重要さを強調され、また今話題の獣肉アレルギーとセツキシマブ(EGF阻害分子標的薬)、子持ちカレイのアナフィラキシーに共通してαGAL-αGALの糖鎖2分子がアレルゲンとなる可能性を示された。さらに血液型がAB型とB型はαGAL-αGALの糖鎖を持つことより免疫寛容となり、O型とA型はαGAL一分子であることからこのアレルギーのリスクが高くなることを報告された。ちなみに千貫先生はリスクあり、師匠の森田教授はリスク無しとのことであった。
大阪大学からは林先生がツ反により急性増悪した膿疱性乾癬、加藤先生がモガムリズマブ(抗CCR4抗体)により治療したATLの3例を発表した。いづれも活発な討論が行われ、特にATLに関しては翌日のモーニングセミナーでも大阪大学の症例が取り上げられ、今後腫瘤型のATLへの効果検討やMFへの適応拡大が話題となった。鹿児島は島津藩〜明治維新の史跡も多く残され、皆さん学会の合間に散策され、鹿児島の食も堪能されたようである。私自身は帰りのタクシーが高速出口5キロ位から変な振動と大きな破裂音を起こし、エンストしてしまった。タクシーが爆発するのではとの危惧と飛行機に乗り遅れるとの心配で、久し振りに焦ったが、幸い通りかかった一台の車がわざわざ、破裂音を聞きつけ、バックで戻って下さり、親切なドライバーの方に空港まで送っていただいた。腎臓内科の先生とのことであったが、翌日大学に行くと小豆澤先生に彼からメールがあったようで、小豆澤先生の大学の同窓生と言うことがわかり、その偶然と無事帰宅出来たことにあらためて感謝した次第である。これも桜島の御利益とあらためて金蔵会頭に御礼を申し上げたい。
大阪大学大学院情報統合医学皮膚科 片山一朗
平成25年11月14日掲載
天王山カンファレンスの終了にあたって
天王山カンファレンスの終了にあたって
大阪大学大学院医学系研究科分子病態医学
皮膚科教授 片山一朗
第10回天王山カンファレンス
日時:平成25年10月19日(土曜日)15:00‐17:00
場所:京都大学楽友会館 2F 講演室
京都市左京区吉田2本松町

さてこの天王山カンファレンスは2004年に私が大阪大学に着任したおり、宮地教授から京大と阪大で若手の研究会をやろうということで始まり、今回の十回で一応、閉会となり、来年度からは新たな世話人を中心により若手が参加しやすい会に模様替えとなる。
第一回が始まった2004年はスーパーローテートが開始された年で、新入医局員はなく、また大学院生は殆どおらず、どうなるかと思いつつ、宮地教授の申し入れを受け入れた。京大と阪大で交互に開催し、若手中心の研究発表と相互の研究者の交流を目的としたこの会は当初、両大学2演題づつの計4題の演題発表から始まったが、その後大学院生や留学生も増え、質の高い会として毎回参加するのが楽しみになった。会の名前の「天王山カンファレンス」は豊臣秀吉と明智光秀の山崎の合戦にちなみ宮地教授がつけられたが、宮地教授の総括では京大と阪大の合戦は一応引き分けと言うことにして頂いた。
さて私自身この会の閉会にあたり、この10年を振り返ってみた。スーパーローテート開始後、日本の医療は大きく変わり、地域格差、診療間格差が大きく進み、また基礎研究室への大学院生の進学者とMD研究者の減少、そして海外留学者の大幅な衰退傾向が顕著になってきた。大阪大学でも一時期その傾向は明らかで、時に平野医学部長(現総長)が基礎教室はシャッター通り化していると揶揄されることもあった。ただここ数年カリキュラムの改変やあらたなMD、PhDシステムの導入、初期研修の見直し、研究費の増額などで、少し明るい日射しが見えてきたのではないかと考えている。我々の皮膚科教室においても、若い先生の研究へのモチベーションは着任時にくらべて上がっていると思うし、現在6名が海外でポスドク生活をエンジョイ?している。これらの良い流れは関連病院部長の協力と若手指導に尽力頂いているスタッフの先生の努力によるところが大であるが、もう一つの大きな力はやはり若い先生が天王山カンファレンスで発表した自信とそのあと相互の医局でFace to Faceで顔の見える議論を深められたことによる研究の楽しさと苦しさを肌で感じられたことに寄るところが大きいと考えている。この意味でも宮地教授にはあらためて感謝したい。
ただ最近驚いたこととして、9月のボストンの学会に参加した時、ハーバードのDavid FisherがPediatric oncologistとして紹介されたこと、Research Gateで勤務先の選択肢をクリックするとDivision of Dermatologyと出てきたことである。米国の皮膚科の人気は高く、毎年少数の優秀な学生が皮膚科医を選択するらしいが、彼らは研究よりもより安定した臨床医の路を歩むらしいと聞いたことがある。また訴訟のリスクが高い米国式の医療システムの中では自分の専門以外の患者は見なくなっているらしく、ハーバードでもDay surgeryとPhDによる研究が中心になっていると仄聞する。結果として皮膚科の守備範囲は狭くなり、DepartmentがDivisionに格下げされたのかと納得したした次第である。この傾向はドイツでもみられるようで、かつてBraun Falco教授の頃、病床数200床を越すことで知られていたミュンヘン大学皮膚科も代が変わるにつれその病床数は半分づつ減り、現在は50床を切るところまできているそうである。安定から衰退への路は驚くほど簡単に進むことはかつての歴史が教えている。大きく変わる医療環境や社会制度の中で皮膚科医が胸を張って診療を行い、臨床の疑問に基づいた基礎研究を通して、創薬や他科に貢献し、結果として新たな生命現象の謎を解明することで皮膚科医の存在価値を高めることは可能と考える。そのためには天王山カンファレンスに参加してきた若い先生方が叡智を持ち寄り、次の時代の皮膚科学を創出して頂きたいと願う次第である。
宮地先生ありがとうございました。
![]() 第1回天王山カンファレンスプログラム 平成16年10月16日 担当:大阪大
第1回天王山カンファレンスプログラム 平成16年10月16日 担当:大阪大
![]() 第10回天王山カンファレンスプログラム平成25年10月19日 担当:京都大
第10回天王山カンファレンスプログラム平成25年10月19日 担当:京都大
大阪大学大学院情報統合医学皮膚科 片山一朗
平成25年10月21日掲載
7th World Congress of Itch (WCI)
7th World Congress of Itch (WCI)
Boston World Trade Center. September 21-23
President: Ethan A Lerner
大阪大学大学院医学系研究科分子病態医学
皮膚科教授 片山一朗


理事会で2015年の学会プレゼンをする室田先生

会場のSeaside World Trade Center
この学会は痒みに興味を持つ研究者ということで、神経解剖、神経生理の先生の参加が多く、その他薬理学、麻酔科医、皮膚科医、公衆衛生・疫学研究者、企業の方が会員の主体をなす。ただ、皮膚科医は少なく、アトピー性皮膚炎やアレルギーが専門の先生はほとんど見かけず、今後臨床系の会員を増やすことが重要な課題と考える。
学会前日は午後から理事会が開かれ、私も参加したが皆さん主張が激しく、なかなかこちらの意見を通すのが難しく、これも今後の検討課題となった。夕方からはKuraishi Distinguished Lectureなどの特別講演が2つあり、その後Welcome partyが開催された。
翌日は朝8時からボストンのWorld Trade Center の2会場で2日間の学会が始まった。今回の演題の大きな流れは、臨床では、腎透析、胆汁鬱滞、悪性腫瘍など全身疾患にともなうカユミの病態と治療、カユミの評価法などが創薬に向けて活発に討論された。基礎では●ヒスタミン受容体とは異なる、あらたな知覚神経のカユミ受容体であるMrgprs (Mas-related G-protein-coupled receptors、MrgprsA3はクロロキン、BAM8-22など、MrgprsDはβアラニンなどがリガンドとなる)やNPPB (natriuretic peptide B, NPPBとその受容体を欠いたマウスにGRPを注入すると、痒みへの強い反応を示し、またGRP受容体を欠いたマウスはNppbを脊髄へと注入しても痒みへの反応を示さない)の報告●TLR4欠損マウスでドライスキンにともなうカユミが減弱する●Th2シフトに関与するTSLPがPAR2で活性化されるCa依存性のORAI1/NFATによりケラチノサイトから産生され、直接末梢神経に作用する(特にこの研究が皮膚科医から報告されたことに驚いた)●κ受容体アゴニストである内因性オピオイドのDynorpyin Aがカユミの新しい伝達系であるGastrin releasing peptide(GRP)とβEndrphinの2つの異なる伝達系のカユミを抑制するなどの興味深い発表があった。
学会終了後はケネデイ博物館にバスで移動し、懇親会が開催された。夜遅くまで素晴らしい食事と音楽を楽しみながら学会の続きの熱い議論が続いた。

翌日も終日学会に参加し、山賀先生が初めての海外の学会デビューをされ、
質問にも明確に答えられていた。
今回の会頭のEthan Lerner教授は有名なマサチセッツ総合病院(MGP)の皮膚生理部門の教授で日本の資生堂の研究者とも親しく、大変気さくな方で、司会進行を一人ですべてこなされていた。会場となったWorld Trade Centerは港に面した近代的な施設で、ボストンの旧市街からは少し離れており、学会に参加された先生方を充分案内できず、申し訳ないと仰っていた。カユミ感覚は痛みとは異なり軽視されがちで皮膚科医の参加も少なかったが、特に内科疾患にともなうカユミは内科や麻酔科の医者が大変、精力的に研究を進めており、このままでは皮膚科医の存在価値がなくなるのではと危惧した学会でもあった.帰路ニューヨークに立ち寄り、来年大阪大学が担当する研究皮膚科学会で谷奥記念講演を行うコロンビア大学のAngela Christiano教授を訪問した。彼女は玉井先生ともどもUitto教授の弟子にあたり、研究領域は表皮水疱症の再生医療、最近では家族性の脱毛症の研究をされている。阪大から留学されている梅垣先生はRevertant mosaicismの患者皮膚からiPS細胞を樹立し、その臨床応用の研究を進めており、セミナーで最新の成果を聞かせて頂いた。阪大からも室田先生、山賀先生が講演し、多くの聴講者と討論し、大変有意義な訪問となった。Angela教授は20年前の京都で開催された世界研究皮膚科学会に来られたのみで、2回目の来日となる来年12月の講演を今から楽しみにしている。
大阪大学大学院情報統合医学皮膚科 片山一朗
平成25年9月27日掲載
第8回箱根カンファレンス(兵庫県淡路島)
第8回箱根カンファレンス 2013. 8.24-25
淡路島 夢舞台
大阪大学大学院医学系研究科分子病態医学
皮膚科教授 片山一朗
この研究会は皮膚科の若手の免疫・アレルギー研究者を育成する目的で、1999年に、西岡清先生(当時東京医科歯科大学皮膚科教授)と故玉置邦彦先生(当時東京大学皮膚科教授)を代表世話人として年1回開催されてきた。手元にある第一回のプログラム記録集に書かれた西岡先生、玉置先生の挨拶を転載させて頂くが、第1回と第2回は西伊豆の大仁で、第3回からは箱根に場所を変えて6回まで開催された。その後2005年からは現在の箱根カンファレンス」と名前が変更され、島田眞路先生(山梨大学皮膚科教授)、片山一朗(大阪大学皮膚科教授)、古江増隆先生(九州大学皮膚科教授)を代表世話人として千葉の上総アカデミアを会場として開催されてきた。今年の第8回大会で一応この会は終了するとのことで今回当番幹事を務めた私の希望で淡路島・夢舞台で開催させて頂き、来年からは新しい代表世話人の先生方を中心にRenewalした会になる予定である。西岡先生が第一回研究会記録集の挨拶に書かれているように、この会は皮膚科の若手研究者がネクタイを外し、本音で皮膚科学の色々な問題点を語り合うことを目的とし、一演題1時間から1時間30分(特別講演)の発表を5題拝聴し、発表の途中でもどんどん質問し、会の終了後は懇親会、その後は会員の部屋で遅くまで、議論が続いた。
このような会は当時なく、毎年の研究会に参加するのが楽しみで、多くの若い先生方や基礎医学の高名な先生方と知り合いになることができたこと、この会から多くの教授が誕生したこともこの会の大きな功績かと考える。このようなコンセプトの会の開催は今後難しいかもしれないが、是非来年からの新たな会にこの伝統を残して頂きたい。
さて演題であるが、先ず大阪大学の環境・生体機能学講座教授の竹田潤二先生に「表現型を基盤とした遺伝学解析」というタイトルで講演頂いた。竹田先生は高知大学の佐野栄紀教授との共同研究でSTAT3を始めとする様々な表皮特異的な遺伝子改変マウスを作成されてきた世界的に大変高名な先生である。今回はトランスポゾンシステムを用いて特定の遺伝子をランダムに消去することで生じる遺伝子異常のフェノタイプ解析を中心にお話しされた。大変難しい話で半分も理解することが出来なかったが、今iPS細胞を用いた研究で何が問題か、今後どういう風に発展していくかを熱く語って頂いた。翌日の会員講演で話題提供された東京医科歯科大の井川先生とも、iPS細胞からケラチノサイトを作成する過程で、ガン遺伝子を含む山中ファクターをどう除くかを共同研究されている。Bloom遺伝子を用いたpiggybackトランスポゾンシステムを用いることで山中ファクターを除いたiPS細胞から分化させたヒトケラチノサイトはより正常の細胞に近く、臨床応用に向け有用であることが井川先生から示された。皮膚疾患患者から誘導したケラチノサイトを用いることで、様々な疾患の病態解明や有効な治療法の検討、さらに変異遺伝子や欠損遺伝子を修正、導入した細胞から皮膚組織を作成ないし、幹細胞の導入などが可能となることが予測され、今後爆発的にその研究が進むことが期待されている。ただ皮膚科領域からの若手のこの分野への参入はまだ少ないようで、今回の研究成果がその端緒になることを願っている。
お二人目の大阪大学、免疫フロンティア研究センター免疫化学部門教授の荒瀬尚からは「ペア型レセプターと自己免疫疾患」というタイトルで講演頂いた。荒瀬教授は単純ヘルペスウイルスがPILRαと呼ばれるペア型レセプターを介してヒトマクロファージに感染する機構をCell誌に発表された、やはり世界的に高名な先生である。今回の講演では細胞質のunfolding proteinをClass 2に乗せて膜面に発現させると効率的な病原性の自己抗体が誘導される可能性を関節リウマチ(リウマチ因子)、橋本病(抗サイログロブリン抗体)、抗リン脂質抗体症候群をモデルとして講演され、多くの白熱した議論が飛び交った。我々の研究室でも奥様の荒瀬規子先生を中心に白斑などの自己抗体の検討を共同研究させて頂いている。翌日は先に述べた井川先生からヒトiPS由来ケラチノサイトのお話しを、東北大学皮膚科の山崎研司先生からは「自然免疫機構の表皮細胞への影響」というタイトルで、主として抗菌ペプチドに関わる研究の流れと抗菌ペプチドで誘導されるIL36の最新の研究成果をお話し頂いた。また熊本大学の神仁正寿先生には「microRNAと免疫が関わる皮膚疾患」というタイトルでSJS・TENの発症に関わるmicroRNA,強皮症でのmicroRNAの動態をお話し頂いた。今回で泊まり込みでの研究会は最後となるが、日本研究皮膚科学会のきさらぎ塾などにそのコンセプトが引き継がれることを願っている。
大阪大学大学院情報統合医学皮膚科 片山一朗
平成25年8月26日掲載
メラノーマ治療は誰が担うのか?8th WCM
8th World Congress of Melanoma
2013. 7.17-20
Hamburg International Convention Center
大阪大学大学院医学系研究科分子病態医学
皮膚科教授 片山一朗
メラノーマの治療に関する国際学会がハンブルクで開催され、参加した。
大阪大学からは種村、田中文、林先生がそれぞれ演題を発表された。メラノーマに特化した学会に参加したのは初めてで、日本の皮膚科関連施設からはメラノーマを積極的に診療されているガンセンターや大学関係者などごく少数の参加者のみであった。メラノーマの診療に皮膚科医が関与しない米国などからは殆ど出題がなかったようである。逆に切除、診断、後療法などすべてに皮膚科医が関わるドイツ診療圈からは多くの出題が有り、今後のメラノーマに皮膚科医がどのように関わるのかを考える上で、今回の学会は大いに参考になった。
我々は大会前日の夜フランクフルト経由でハンブルク入りしたが、大阪とあまり差のない暑さであった。あとで聞くと到着の前まで雨模様の寒い日が続いていたようで、ドイツ北部としては珍しい好天が会期中続いた。翌日は朝から晩までメラノーマ漬けであった。特に最近の分子標的薬と抗体療法の進歩は目をみはるものがあった。種村先生の話ではステージ4の患者の腫瘍が消失し、再発もなく治療が継続出来る時代が近いようである。特に抗PD-1抗体や抗CTLA4抗体とBRAF阻害薬などの組み合わせと休薬期間をうまく調節することで薬剤耐性も生じにくくなるようで、今後のメラノーマ治療が大きく変わることが予想されると関西医大の為政先生から伺った。またSpitz nevusはメラノーマとの鑑別が困難な母斑であるが、最近Atypical Spitz Nevusとブドウ膜のメラノーマなどでBAP1 (BRCA1-Associated Protein 1)と呼ばれる分子の遺伝子変異や発現低下が見られることが注目されている。特にatypical spitz tumorと総称される腫瘍で、大型のEpithelioid様細胞に異型性が見られ、このような細胞に特異的にBAP1の消失と高率にBRAFの遺伝子変異が見られるとのことで、メラノーマとの異同や治療介入などホットなDiscussion を誘っていた。Busam KJ, et al.Combined BRAF(V600E)-positive melanocytic lesions with large epithelioid cells lacking BAP1 expression and conventional nevomelanocytes. Am J Surg Pathol. 2013;37(2):193-9.
懇親会はNetworking Eveningとして会議場に隣接する庭園で行われ、
日本からの参加の先生方と情報交換を兼ね、楽しい時間を過ごすことができた。2日目以降も初日同様、新しいメラノーマの治療薬の治療成績や疫学研究、分子診断学などの講演が行われ、最終日にはメラノーマ以外の皮膚腫瘍の臨床、基礎研究のセッションがEuropean Association of Dermatooncology(EADO)との共催で行われていた。特にメラノーマの治療に関しては非常に戦略的な計画のもとで行われた研究が多く、症例数も最低でも3桁後半から4桁で、欧米で確立されている国家レベルでの患者登録システムを早く日本でも導入する必要性を強く感じた。会期中、ドイツの皮膚科でのメラノーマ治療の実態を知る目的で、近くのLubeck大学皮膚科を訪問した。Zillikins教授、Paus教授ともに夏休みで不在であったが、留学中の岩田浩明先生(岐阜大)、古賀浩嗣先生(久留米大)のお二人の先生、ロシアから留学されているArtem先生や病棟医に外来、病棟、研究室を案内して頂いた。米国、英国では皮膚科がかなり細分化、分業化されており、腫瘍や膠原病など皮膚科医が関与する領域がかなり狭くなっているがドイツ圈では100を越すベッド、独自の病棟、外来、検査室、研究室などを備え、皮膚科で完結する医療が行われている。Lubeck大学皮膚科でもメラノーマ以外にも、水疱症、膠原病、腫瘍、乾癬、静脈瘤など広範囲の疾患を診療されていた。米国ではメラノーマはダーモスコピーをやる程度で診断は病理、治療は腫瘍外科、腫瘍内科、再建は形成外科に任せる施設が増えている。分業や連携システムが整備されていない日本で将来的にメラノーマなどの疾患の治療を誰が、どう行うか不安に思うことも多かったが、今回、米国式皮膚科学の対極にあるドイツの皮膚科でのメラノーマに対する取り組みを知る機会を得て、多いに勇気づけられた。逆にこれだけ新たな治療が次々と登場する時代であるからこそ、スーパーローテートで救急や全身管理を経験された次の世代を担う若い先生には全身疾患としての皮膚病の治療に取り組み、その武器として臨床腫瘍学や皮膚外科を修め、病理の読める皮膚科医になって頂きたいし、そのための研修システムを皮膚科学会全体で取り組んで行く必要があると考える。腫瘍内科的な素養は乾癬の分子標的薬治療が役にたつと思うし、阪大でも病理、放射線科、形成外科などとの定期的な症例カンファレンスなどをさらに推進して行くつもりである。日本では女性医師の復帰支援が大きな問題となっているが、Lubeck大学では女性医師が指導者層の中心を占め、先に述べた多くの疾患を診療され、自分が興味を持つ疾患の基礎研究をおこなうことで皮膚科の臨床に奥行きを持たせる努力をされていた。日本でも同じ事はできるはずであり、その具体的な戦略を頭に描き、阪大および関連施設の先生にも積極的に難治性の疾患に取り組んで頂きたいと願いつつ、ハンブルクの街を後にし、帰国の途についた。

会場近くのAussenalster湖(夜9時を過ぎた頃)
大阪大学大学院情報統合医学皮膚科 片山一朗
平成25年7月25日掲載
第112回日本皮膚科学会総会
第112回日本皮膚科学会総会
会頭 川島 眞 東京女子医科大学教授
会場 パシフィコ横浜
会期 2013年6月14日~16日
テーマ -いま望まれる皮膚科心療-
大阪大学大学院医学系研究科分子病態医学
皮膚科教授 片山一朗
第112回日本皮膚科学会総会が6月14日から6月16日までの3日間、横浜パシフィコで開催された。会頭の川島眞教授、事務局長の石黒直子先生、実行委員長の常深裕一郎先生には5,000人を越す参加者を迎えられ、大成功のうちに大会を終えられたこと、心よりお祝いと御礼申し上げる次第である。特に2年前の110回大会が東北大震災のために中止となり、開催まで、緊張の連続であったかと思います、御苦労様でした。
学術大会は例年通り川島教授の会頭講演から開始された。座長を務められた肥田野信先生は80歳を越えてもお元気で、原稿無しで川島先生の御略歴を紹介された。講演では川島先生御自身で開拓された皮膚科領域でのパピローマウイルス研究、バリア病としてのアトピー性皮膚炎の提唱、そして大会のメインテーマである皮膚病診療における心の問題を述べられた。また御逝去された久木田淳先生が総会を大変楽しみにされていたことや研修医の頃の懐かしい写真も紹介された。
学会はパシフィコ横浜での教育講演、スポンサードセミナーと展示場でのポスター発表に分かれていたが、天候に概ね恵まれ、2会場を行き来する参加者も多かった。印象に残った講演としては今年の皆見賞を受賞された山梨大学の川村龍吉先生の実験的亜鉛欠乏症の講演が挙げられる。彼の研究の中心は、故玉置邦彦先生、古江増隆先生が山梨医大におられた頃に指導を受けられたランゲルハンス細胞の研究で、その後留学されたNIHでHIV研究も大いに発展させられた。その中でマウスを亜鉛欠乏食で飼育すると皮膚炎が生じるが、その際に表皮からランゲルハンス細胞が消失することを見いだされたことから本研究を開始されたようである。クロトンオイルで生じる一次刺激性皮膚炎が亜鉛欠乏で悪化するさい、表皮細胞から産生されるATPによる細胞障害が生じること、野生型マウスではATP産生をランゲルハンス細胞由来のCD39が抑制するが、亜鉛欠乏マウスではランゲルハンス細胞の消失にともない、その抑制機序が低下することで皮膚炎が悪化することを見事に証明された。数年前に彼から人の亜鉛欠乏症のサンプルが充分手に入らず、reviseのまま論文受理が進んでいないことを相談された。その時に30数年前に私が研修医であった頃担当し、発表したAcrodermatitis enteropathicaとZinc deficiencyの症例を思い出し、西田技官に探して貰ったところ、ブロック標本が残っており、無事彼に提供することができた。今回、臨床検体を整理し、保存しておくこと、論文とし記録しておくことの重要さを再認識すると同時に、古典的な亜鉛華軟膏の作用機序を今日的な視点で見事に解明された川村先生の受賞に心より拍手を送りたい。

講演される川村先生と座長の島田先生
また最終日のランチョンセミナーで教室の室田浩之先生が講演した「汗と温度の指導箋」は広い第一会場がほぼ満席になるほどの盛況で、ここ数年の教室の研究成果を見事に纏めて貰った。広島大学から汗の成分中に癜風菌由来抗原が含まれ、アトピー性皮膚炎の悪化に関与するとのテレビ報道や精製汗抗原特異的IgE ELISAの測定法の開発が最優秀ポスター賞に選考されたこともあり、多くの聴衆が来られたのかと推察する。汗抗原の解析は今後も継続して検証されるべき点が多くあると考えるが、今まであまり関心の払われて来なかった皮膚疾患における汗の役割に多くの皮膚科医が興味を示しだしたことは大いに歓迎すべきことであり、室田先生にはさらなる研究の進展を期待したい。
最終日、最後の女性医師問題のセッションに途中から出席したが、演者の先生方の熱意が感じられる講演内容であった。今まで、形式を変えてさまざまな視点からこの会をリードされてきた塩原先生、橋本先生に御礼を申し上げると共に、今後はより具体的な女性医師復帰支援策を行政に働きかけていく必要があると感じた。また私の経験からは、女性医師のみが参加するのではなくそのパートナーや子供の面倒を見て貰っている方などにも参加していただき、女性医師のみならず、病院皮膚科診療の現状を理解していただくことも今後重要と考える。その意味で竹田総合病院皮膚科の岸本先生が呈示された内容(P8-2)は重い課題として心に残った。教育講演は私が参加した幾つかのセッションで、従来の壁を破り、若手講師が御自身の研究の最新の内容も発表されており、我々にも楽しめる内容であった。来年の113回の総会会頭である、岩月教授もあらたな形式の教育講演を考えておられているようで、楽しみにしている。

東大阪市立総合病院時代の症例を丁寧に検討され、その後110回大会への発表予定が中止になり、より時間をかけて大阪大学皮膚科の症例を纏めて貰った成果が受賞となったことで今回の受賞はなによりの贈り物であった。すべてのポスターを見て回ったが大阪大学からの発表ポスターはすべて質も高く、良く検討された内容であり、皆さんの努力にあらためて拍手を送りたい。あとは是非英語での論文化を待ちたい。
参加された皆さん、また留守を守ってくれた先生方お疲れ様でした。
大阪大学大学院情報統合医学皮膚科 片山一朗
平成25年6月18日掲載
第6回International Investigative Dermatology (IID)
第6回International Investigative Dermatology (IID)
会長:Alexander Enk 教授(ハイデルベルク大学)
会場:エジンバラ国際会議場
会期:2013年5月8-11日
大阪大学大学院医学系研究科分子病態医学
皮膚科教授 片山一朗


開会式 ‘(段上右より、Enk, 天谷、Kupper教授)
大阪大学大学院情報統合医学皮膚科 片山一朗
平成25年5月20日掲載
アトピー性皮膚炎の疫学研究と今後の検討課題について
アトピー性皮膚炎の疫学研究と今後の検討課題について
大阪大学大学院医学系研究科分子病態医学
皮膚科教授 片山一朗
最近の皮膚科学会やアレルギー学会、アトピー性皮膚炎治療研究会などに参加すると、アトピー性皮膚炎に関する演題の減少と共に、参加者間の議論も少なくなってきていると考えるのは私だけではないと思う。その理由はいくつか考えられるが、かつての熱心な先生方が定年を迎えられ、参加されなくなったことにくわえ、ガイドラインの普及による重症患者の減少(実態は不明)、最近の行き過ぎた、経営効率化による病院でのアトピー性皮膚炎患者診療の縮小(コストに反映されにくい)などが大きな理由と考えられる。しかしながら世界的にはアトピー性皮膚炎の基礎研究は大きく進み、疫学研究なども次々と新しい情報が発信されている。研究においては基礎の免疫学者が、また臨床に関しては小児科、小児皮膚科、疫学・公衆衛生学、アレルギー科などの医師からの報告が多いように感じられる。その理由として病院皮膚科医が扱うアトピー性皮膚炎が小児から思春期、成人患者にシフトしつつある現状も大きいようである。実際小児患者は小児科で診療を受けることが多く、思春期の患者は学校、塾などで皮膚科での診療自体をあまり受けていない現状があり、皮膚科医と小児科医が診る患者が異なりつつある。結果として病態や治療に関しての小児科医と皮膚科医の興味がかつての食物アレルギーやステロイドバッシングの時代とは異なる形で乖離しつつあるのではないかと考えている(最近はフィラグリンの遺伝多型とスキンケア、食物アレルギーの経皮感作など共通の話題が出てきてはいるが本質的な議論にはいたっていない)。
そのような現状を打破する目的で先日小児科医と皮膚科医が集まるアトピー性皮膚炎の研究会が開催されたが、その中で私が感じた問題点を何点か記録に残しておきたい。
1. 経過:アトピー性皮膚炎の経過は近年大きく変貌してきているが、その実
態は必ずしも明らかではない。大阪大学でも一昨年から後方視野的にアトピー性皮膚炎の経過や治療歴を検討しており(Kijima A et al. Allergology International. 2013;62:105-112)、思春期再燃、初発などの従来記載の乏しい患者が増加してきており、それぞれの患者年齢で悪化因子や非寛解因子などが異なる結果が得られつつある。(in preparation)。同じような観察結果は最近ドイツからも報告されており(Garmhausen D,et al.Allergy. 2013;68(4):498-506)、今後世界的な実態調査が必要と考えている。また小児アトピー性皮膚炎の研究会ではあるが都立長寿医療センターの種井良二先生から高齢者のアトピー性皮膚炎は存在するか、あるとしたらどのような臨床的な特徴があるかの講演があった。われわれも高齢者の慢性の湿疹性の病変を繰り返す患者の中に臨床的にも高齢者のアトピー性皮膚炎と言わざるを得ない一群の患者が存在し、その特徴と意義を検討している。アトピー性皮膚炎の命名者のSulzbergerもアトピー性皮膚炎は乳児、小児、成人の三型があり、特に成人型はアトピー素因があるか、乳幼児期にアトピー性皮膚炎があったことを重視しているが、思春期初発型や高齢発症型は記載していない。むしろ脂漏性湿疹、接触皮膚炎、細菌疹などをしっかり鑑別することを強調している(Hill LW, Sulzberger MB: Evolution of atopic dermatitis. Archives of Dermatology and Syphilogogy 32: 451, 1935 )。フィラグリンやセラミドの減少、IgE, TARC値の上昇が高齢患者でも見られることより小児患者との対比研究も今後の重要な課題と考える。
2. 治療:九州大の古江教授科のEBMに基づいたアトピー性皮膚炎の治療の講演があった。科学的な視点と根拠に基づく外用療法は参加した多くの若い皮膚科医、小児科医には大変有益であったと思う。最近のGWASの研究成果から、バリア機能、自然免疫、ビタミンD代謝関連酵素に関わる遺伝子群の解析結果と今後の新たな治療戦略の話も紹介された。近年アトピー性皮膚炎の短期治療マーカであるTARCは世界的には我が国でのみ保険収載されており、治療によるTARCの低下率でステロイドなどの治療効果を定量的に評価できるかもしれないという大変興味深いデータを紹介された。(ちなみにステロイドはSest 4点、VS 2点、TAC/S は1点、Mは0.5点で計算)。TARCがあまり上昇しない顔面・頚部限局型、痒疹型、乾燥性湿疹型でも低下率で評価できれば有用な指標になるかと考える。フロアからも正常域でも臨床症状によりその値が低下することもあり、今後の検討が必要との発言があり、来年は私と群馬大学小児科の荒川教授が当番であり、このテーマを取り上げたいと考えている。ただアトピー性皮膚炎が慢性の疾患であり、アトピー性皮膚炎の治療に精通していない医師が短期のステロイド外用などの治療効果のみで皮膚炎を評価すると、悪化因子などの見落としに繋がることも危惧される。
3.発症・悪化因子・痒み: 先に述べたように、現在フィラグリンの研究は世界的なトレンドである。慶応大学の海老原先生はフィラグリン遺伝子多型の患者は本邦でもその頻度に地域差、施設差などがあり、また患者数はまだ少ないが、正常型と変異型で重症度や経過、検査成績に有意な差は認められず、また遺伝子改変マウスでも野生型と大きな差が無く、フィラグリン欠損によるバリア障害や皮膚症状は魚鱗癬に関連する可能性、あるいは代償性機序によるバリアの改善などの可能性を話された。ただハイリスク患者の出生時からの大規模スキンケア介入の結果はまだ公表されておらず、フィラグリン遺伝子多型患者でネコ同居によるアトピー性皮膚炎発症のリスクが上昇するとの報告もされており、フィラグリンの意義はまだ不明である。アトピー性皮膚炎における食物アレルギーの関与は様々な角度から論議されたが、現時点では発症因子とするよりは合併症、あるいは悪化因子とした方がよいとの意見が多かったようである。感作経路としては従来の経消化管感作から経皮感作への流れのようであるが、T cell epitopeとB cell epitopeの感作経路による抗原性の差異などの検討が必要かと考える。さらに最近の報告で血清ビタミンDレベルとアレルギー疾患、食物アレルギーの発症リスクを検討した報告が増加している。まだその評価は確定してはおらず、来年のテーマとしてとりあげたい。
大阪大学皮膚科教室では2011年度から厚生労働省の疫学研究班の課題研究として大阪大学の新入生アトピー性皮膚炎検診を開始し、今年までに3回の検診を行い、彼らがどの診療科でどのような治療を受け、その満足度はどうだったか、現在も皮膚炎を持つ学生が今の皮膚炎の状況や悪化因子、原因をどう考えているか、今後どのような治療を希望しているかなど解決すべき問題点が次々と明らかになってきている。かつてアトピー性皮膚炎は小児期の病気であり自然軽快すると習ったが、その経過は大きく変貌してきており、小児科医と皮膚科医の密接な協力や情報交換がより必要な時代になってきている。この会がそのような目的に沿う形で発展していけば何よりである。

Ernest-Henri BESNIER (1831-1909)
大阪大学大学院情報統合医学皮膚科
片山一朗 平成25年4月22日掲載
Festina lente. 悠々として急げ
Festina lente. 悠々として急げ
大阪大学大学院医学系研究科分子病態医学
皮膚科教授 片山一朗
今年も大阪大学皮膚科学教室に新しい仲間を迎える事ができ、4月3日、銀杏会館で歓迎会を開きました。ここ数年、春先は日本皮膚科学会、日本アレルギー学会などの会頭として準備に時間をとられ、新しく来られた先生方とゆっくり話しをする機会がありませんでしたが、久しぶりに歓迎の挨拶をさせて頂きました。出身大学、経歴は皆さんさまざまですが、これからの長い医師人生の中では大阪大学皮膚科が皆さんの皮膚科医としてのハヴになります。
昔、私が北大の学生時代にベストセラーになった小説に五木寛之の「デラシネの旗」があります。「デラシネ」(フランス語:déraciné)は「根無し草」という意味で,我々の世代は彼の生き方に共感を示した者もたくさんいました。私自身も北大を卒業後、大阪大、北里大、東京医科歯科大、長崎大と全国を転々とし、そのつど自分を「デラシネ」的な存在と思ってきましたが、皮膚科医としての行動規範のルーツは常に大阪大学皮膚科で受けた教育や先輩、同僚の先生達との交流だったような気がしています。新研修システムが始まった2004年より、医師としての最初のImprintingを受ける大切な時期に2年間の細切れ教育を受けざるを得ない、また大学医局で多様な価値観を持つ先輩、同僚との交流を持たずにストレート研修病院で医師となる最近の若い医師達をみていると、彼らが10年後、20年後一体何を頼りに医師として生きて行くのか、やや不安に思う時があり、先の「デラシネ」という言葉を最近とみに思い出します。その是非には論議があり、良い悪いは簡単には言えませんが、私自身、一人前の医師になるには良い意味での徒弟制度が不可欠であり、多くの先輩、同僚と議論を深め、他大学、他分野の先生と交流して技量を深かめて行く事が必要と考えています。今年我々の仲間になった先生には是非、それぞれの思い描く医師、そして皮膚科医になって頂きたいと思います。ただこれからの長い医師人生の中で時に大きな障害、壁が立ちふさがるか思います。その時には一歩後戻りして,考える事を勧めます。無理に進むと視野はその分狭くなりますが、一歩引く事で視野は逆に広がります。私の好きな言葉に「悠々として急げ」があります。開高健の言葉として有名になりましたがもともとはローマ帝国初代皇帝アウグストゥスの座右の銘とのことで、困ったこと、予期せぬ出来事が起こった時、研究、臨床で行き詰まった時にはこの言葉を思い出します。今全国の大学では新人が何年も入ってこない皮膚科教室が増えていることを聞きますが、改めてその責任の重さを感じるとともに、多くの皆さんと一緒に皮膚科医として働けることに感謝して、歓迎の言葉にしたいと思います。

大阪大学皮膚科 片山一朗
平成25年4月18日一部修正
2012年年報序文「皮膚科研究の新しい流れ」
2012年年報序文
「皮膚科研究の新しい流れ」
大阪大学大学院医学系研究科情報統合医学
皮膚科教授 片山一朗
今年も年報を発刊する時期となりました。2012年は2004年に大阪大学に着任以来、着手した研究がようやく論文化されるようになった、私とっては大変大事な年になりました。スーパーローテート開始の年から2年間は関連病院の人事も含め、とても落ち着いて研究が出来る環境ではありませんでしたが、教室や関連病院の先生の理解と協力で若い先生が研究に興味を持ち、大学院にも進む方がふえてきました。留学希望者の減少が論議される昨今ですが、昨年から今年にかけては大学院修了者も含め米国に留学し、あらたな環境で研究を開始したいと希望する人も現れるようになりました。マンパワー不足は大阪大学のみでなく全国的な現象ですが、留学というチャンスを得られた先生は是非その成果を大阪に持ち帰り、次の世代の先生に伝えて頂きたいと思います。
さて最近の研究のトピックスはiPS細胞の作成とその臨床応用に集中していますが、もう一つの大きな流れが生体イメージングかと思います。そのパイオニアである石井優教授の講演を始めて拝聴したのは今から5年前位の教室主宰セミナーで、そのライブ画像の素晴らしさは教室の先生にも大きなインパクトを与えてくれたようです。私自身は大学院生の頃、恩師の西岡先生が皮膚の血流の測定機器開発研究をされていた時、皮膚の炎症細胞の動態を見ることの出来る機械を開発し、新たな皮膚の病理学を創り出したいと仰っていたことを思い出しました。その当時の技術では無理ということでしたが、30年以上の時を経てその願いが実現したことになります。教室では数年前からアトピー性皮膚炎患者のバリア機能解析と発汗機能の解析研究を開始し、Optical coherence tomography(光干渉断層法)という機器を使い、汗孔から排出される汗のビジュアル画像の解析研究をしていましたが、石井研の大学院生を通じて汗腺のライブイメージングにも成功しました。研究を行った松井先生、室田先生の撮影された世界で初めての能動発汗の画像を見せていただいたときには本当に感激しました。現在さらに他の研究プロジェクトにもこの方法を用いて面白いデータがでてきており、従来の二次元皮膚病理学から三次元皮膚病理学、さらに時空を越えた四次元皮膚病理学の時代が来る日も近いことが予感されます。また新しいトレーサーを用いたfMRIをマウスで検討することが出来る時代になり、今まで不可能と考えられていた新たな生体イメージングも可能になってきています。皮膚科学は元々皮膚疾患を医師自身の眼で直視し、病理所見を観察することで最終診断を行う学問ですが、新たな生体観察法技術の出現は皮膚科医の専売特許であった皮膚の病理学がより広い臨床分野に広がることを予想させます。これに近いことは生物製剤による乾癬などの治療にもあてはまるかもしれません。21世紀となり医学の基礎研究は驚くほど急速に、かつ、着実に進んでおり、その研究領域の境界は益々ファジーになりつつあります。iPS研究が皮膚の線維芽細胞の初期化から始まったように、我々皮膚科医も皮膚という臓器を大切にし、そこで起きている生命現象を理解する新たな研究手法を創り出す必要があります。この努力を怠れば、皮膚科医の存在価値は基礎研究のみでなく、臨床医学の分野でも消えていくのではと考えています。今年5月に英国エジンバラで開催される国際研究皮膚科学会(IID)に出席する予定ですが、世界の皮膚科研究がどのような方向に進もうとしているのか、自分の眼で確認することを楽しみにしています。
大阪大学皮膚科 片山一朗
2013年3月12日
Outcome measures vitiligo consensus conference
Outcome measures vitiligo consensus conference
Venue:Surfcomber hotel. Miami USA
2013.2.28
大阪大学大学院医学系研究科分子病態医学
皮膚科教授 片山一朗
尋常性白斑の診断、分類、治療目標とその評価法に関する世界の共通指針を作成する目標のTASK Force Meeting の第1回会議が2010年の世界皮膚科学会(ソウル)で開催され、その後世界色素細胞学会(2010、ボルドー)、欧州皮膚科学会(2012、プラハ)と開催され、今回AADにあわせてマイアミでその4回目の会議が開催された。この会議は欧州の尋常性白斑の診療GL作成委員会を母体に発足し、欧州、米国、アフリカ、豪州、西アジア、東アジアの研究者が集まり、討論が繰り広げられ、世界の尋常性白斑のGLや治療指針の方向性を知るには重要な会議で、第一回から参加している。ボルドーの会議で新しい分類基準が策定され、PCMR誌に発表された。今回は予想される新たな色素異常症の治療薬の評価のための国際的な基準の作成を目的とし、今後何回かの会議を経て2014年の国際色素細胞学会で策定される予定である。アトピー性皮膚炎でも同様の試みが英国のHywell Williams 教授を中心にHOMEI, HOMEII会議として開催され、今年4月にはSanjegoでHOMEIII会議が開かれる。世界水準の診断基準や治療評価の進展を理解するためには日本からも積極的に参加していくことが必要で、参加希望の方はHOMEIIIのホームページを参照して下さい、(白斑会議はSemiclosed)。今回の会議では以下の6項目の評価について今後議論を深めることが決まった。
1Repigmentation
2Cosmetically acceptable repigmentation
3Quality of life
4Maintenance of gained repigmentation
5Cessation of spread
6Side effects and harms

帰路NYのコロンビア大のAngella Christiano教授に来年、大阪大学が担当するJSIDのTanioku Kihei Memorial Award の講演をお願いし、また表皮水疱症のモザイク細胞を用いた骨髄細胞移植研究の進展を討論するため、彼女のラボに留学中の梅垣先生とお会いでき、今後の方向性を確認することができた。
丁度前日に結婚されたばかりの梅垣先生はご多忙の中、お世話になり御礼を申し上げる次第である。
(会場スナップ)
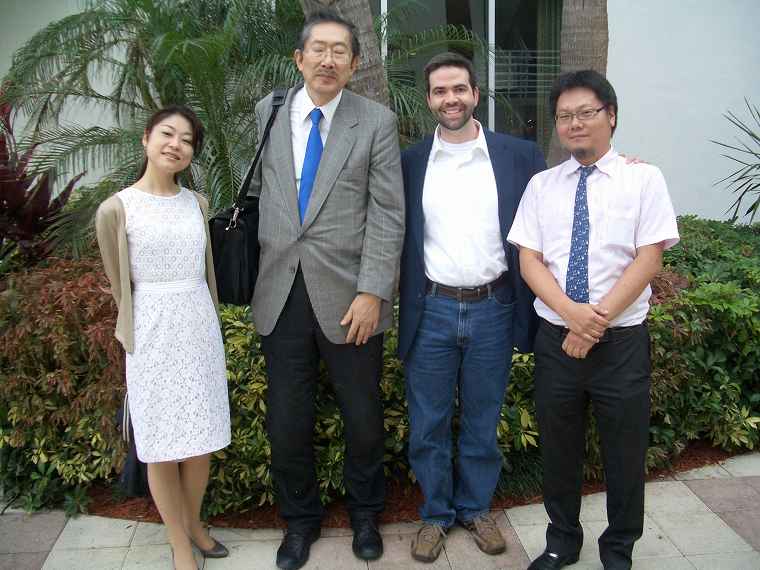
MGHのJohn Harris先生と白斑のマウスモデルを作成された若手研究者
大阪大学皮膚科 片山一朗
2013年3月12日
皮膚科疾患の病名と診断名を考える
皮膚科疾患の病名と診断名を考える
大阪大学大学院医学系研究科分子病態医学
皮膚科教授 片山一朗
第36回皮膚・脈管膠原病研究会報告の続きで、一部重複するが個人的な意見も含め感じたことを述べたい。またご意見をいただければ幸甚である。
一つは今回、血管炎のセッションなどで討論があった血管炎の新しいChapel Hill分類に関する討議でChurg-Strauss SyndromeがEosinophilic Granulomatosis with Polyangiitis (EGPA), WegnerGranulomatosisが Granulomatosis with Polyangiitis、Henoch–Schönlein purpura PurpuraがIgA Vasclulitisと言う病名に変わるなど我々が長年なじんできた病名が消え、診断名として組織所見や病因にもとづいた名前が採用されたことである。また極力最初の記載者の名前を外していることも特徴で、その背景にはナチスに協力した最初の報告者を外すためなどの理由があったと聞いた。臨床的に蛍光抗体直接法ができない施設では診断できない、あるいは関節症状や消化管症状がないがIgAの沈着が見られる皮膚の血管炎も同じIgA Vasclulitisという病名になる可能性がある。以前西山茂夫先生が皮膚病診療で指摘されているように学術的な統計や疫学調査に加え、最近はその結果のガイドラインや治療アルゴリズムへの適用などより幾つかの病名の候補から簡便で普遍的な診断名が選択される時代的な要請もあるかと考える(※西山茂夫 皮膚病診診療1989. 11:547)。ただ皮膚疾患の場合、同じような皮膚の表現型でも病因論が異なる場合や炎症性疾患の場合、組織反応が採取部位、経時的な変化、全身疾患、年齢的な影響を受けることに加え、複数の疾患が合併することも多く、当然治療への反応性も異なる。今後皮膚科医全体で考えていくべき大きな問題かと考える。
二つめの問題点として、今回もMorpheaとして報告された症例報告の組織反応としてLSAとする意見とMorpheaの立場からの意見が見られた。以前他誌で「似たもの同士」という企画があったが、明らかに異なる疾患の鑑別に関する論点が中心であった。もともとLSAは歴史的には1887年のHallopeauの報告以来Morpheaとの異同が論議されてきたが、その決着は得られていない。2003 年にLSAではextracellular matrix protein 1に対する自己抗体が高頻度に見られることが報告され(Oyama N Lancet 2003. 362:118-23.)その後も検討が続けられている。また我々も一人の患者に扁平苔癬、LSA, Sclerodermaの3つの異なる病理組織所見を認め、同様の症例が弘前大学からも報告されている(Sawamura D et al. J Dermatol 1998. 25:409-411.)。さらに最近Bullous MorpheaとLSAの合併例がトルコから報告された(Sirin Yasaret al. ,Ann Dermatol 23, Suppl. 3, 2011)これらの点よりLSAとMorpheaは似てはいるが異なる疾患としたほうが良さそうである。同様の議論は数年前のこの会でAtrophoderma of Pasini PieriniとMoroheaの異同に関してあった。この2疾患も1923年の報告以来Morphea との異同の論議が続き、JablonskaのMorpheaのスペクトラムの疾患という論文で決着がついたかと考えられてきたが、対立する意見もあり、また最近はBorrelia burgdorferi感染症を重視する論文も増えてきている。Atrophoderma of Pasini PieriniはAtrophic scleroderma d’embleeとも呼ばれるように硬化期を欠き急速に萎縮期に移行する特殊なMorpheaと考えられてきたが、Morpheaと言う病名に起因するLilac ringとよばれる特徴的な紫紅色調変化は見られず、やはり病因論的には異なる疾患と考えた方が良いとも考える。ただ組織硬化の点から見ると我々が検討しているTNFαR のノックアウトマウスではブレオマイシンの投与で通常4W程度かかる組織硬化がたかだか2日で生じ、2Wには萎縮期に移行する所見が見られる(Murota H et al. Arthritis Rheum. 2003; 48:1117-25.)ことより、同様の経過がPasini Pierini型のAtrophodermaで生じているのかもしれない。いづれにしても以前の本会にはこのような論争に決着を付けていただけるたくさんの先生が参加されていたが、それぞれの専門領域がより高度で狭まり、研究や雑務にとられる時間の増えた現在、もう一度原著にもどり、組織を良く観察する努力が必要と反省する。
最後の点として1,2の議論とも関連するがやはり皮膚科医は発疹や病理組織の細かい所見にこだわりを持ち続けることと、多くの仲間と学会や研究会で討論すること、新しい知見を得る努力と時には原著に戻り、問題となる疾患の歴史的な位置付けを勉強することが重要で、そのことが新しい病因論の提唱や研究分野の開拓につながるのではないかと考える。
※「西山茂夫 皮膚病診診療1989. 11:547」については著者の西山茂夫先生および株式会社協和企画の掲載許可を頂いています。
大阪大学皮膚科 片山一朗
2013年3月(一部訂正)
第36回皮膚・脈管膠原病研究会を終えて
第36回皮膚・脈管膠原病研究会を終えて
会場:大阪ライフサイエンス
大阪大学大学院医学系研究科分子病態医学
皮膚科教授 片山一朗
2013年1月25日と26日の2日間に亘り上記学会を開催した。山岡先生(補佐、室田先生)を事務局長とし、二上さんをはじめとする秘書さん、西田さんを中心にこの2年ほど準備をしてきた。開催案内に書いたように、この研究会(学会ではない)は私が医者になった年に第一回大会が開催され、北里大学に異動した1987年からほぼ毎年参加している思い入れのある会である。以前は故安田利顕先生が会員であった六本木の国際文化会館が会場であり、西山茂夫先生、植木宏明先生、井上勝平先生や西岡清先生、西川武二先生などが一番前の席を占められ、若い発表者は緊張感にあふれ、高揚した気持ちで発表した。診断や解釈、が不十分であると徹底的にしかしきわめて教育的な指導を受けることができた。また終了時間も予定時間をはるか超える事が多かったが、充実した時間を過ごすことができた。
大会は血管炎のセッションから開始され、朝9時から多くの参加者に登録頂いた。これも例年通り陳先生、勝岡先生、川名先生がほぼすべての演題に多くのコメントをされていた。ただ名誉会員のある先生が「治療や新しい病因論の討論がなく、遠路出席した甲斐がないと」遠回しに言われた。ある意味発表、討論がマンネリしてきたことや本会が仲良しクラブ化してきた(?)ことへのご意見と拝聴した。このような意見は懇親会でも聞き、多いに再考したいと考える。やはり若い先生が新しい切り口で症例や研究成果を提示し、偉い先生を打ち負かすくらいの議論をしていくことが必要だろう。その点で、2日目のモーニングセミナーの室田先生の講演は血管炎や膠原病の温度過敏に新たな視点を投げかけるもので、もっと多くの先生に聞いて頂きたい充実した内容であった。
また今回、話題となったのが血管炎の新しいChapel Hill分類2012で、私自身アメリカ式の即物的な病名や臨床を無視した分類には?????であったが、皮膚科医が一人もいない委員会で決められた事が原因とのことで、残念であった。参加された先生から間接的に聞いた話ではChurg-Strauss SyndromeがEosinophilic Granulomatosis with Polyangiitis (EGPA),WegnerGranulomatosisが Granulomatosis with Polyangiitis、Henoch-Schönlein purpura がIgA Vasclulitisと言う病名に変わるなど極力最初の記載者の名前を外すようである。このことは特に蛍光抗体直説法ができない施設では診断できない、あるいはHyper-γglobulinemic purpuraなどIgAの沈着が見られる皮膚の血管炎も同じ病名になる可能性がある。同じ事は病態不明のままMikulicz病や抗SSA抗体陰性の一部のSjogren症候群がIgG4関連疾患という病名になりつつある現状に近い。このような流れは、ガイドライン、治療アルゴリズムに沿うよう、病名が病因論的に修正されていることによるかと思うが、、EBMとNet医療が全盛の昨今、抗しがたい流れなのかもしれない。
今回は話題にならなかったが抗セントロメア抗体陽性のシェーグレン症候群の検討(認識する抗原エピトープの差)や、皮膚筋炎のあらたな自己抗体と皮膚症状発現の検討、皮膚型結節性動脈周囲炎とLivedoido Vasculopathyなど、討論すべきことはたくさんあるはずだが、関連演題が殆どなかった。やはり指導者の努力が必要と思うと同時に、ワークショップなどの形式で毎年テーマを決めて徹底的に討論するなどの工夫が必要なのだろうか?この点はまた世話人会で意見を聞きたいと考えている。
阪大からは越智、井上、山鹿、花房、山岡の各先生が発表されたが、それぞれ良く考察された立派な発表演題で是非英文論文として記録に残して頂きたい。特に山岡先生の発表されたHIVが見いだされたSebopsoriasisの発表は診断名や組織反応の是非に議論がシフトし、なぜSeboposriasisという病名をあえて付けたかという本質的な議論にならなかったのが残念であった。HIVで乾癬と脂漏性皮膚炎が重症化するのはよく知られたことであり、Pityrosporum感染症などが両疾患で発症因子である可能性などを包含するのではと考えている。例年に比べ、若い男性医師の出席が目についたが、いくつかの重要な宿題が残った大会であった。2日間に亘り、学会を手伝って頂いた医局の先生、秘書さんには心からお礼を申し上げたい。

開会式

熱い討論
2013年1月
2013年を迎えて。OKYとイクジイ
2013年を迎えて。
OKYとイクジイ
大阪大学大学院医学系研究科分子病態医学
皮膚科教授 片山一朗
2013年を迎え、私も時計の針をリセットし、新たな気持ちで皮膚病診療と研究に取り組んで行きたいと考えている。
昨年暮から新年に届いた日本皮膚科学会雑誌で女性医師問題と新しい専門医制度が大きく取り上げられている。皮膚科の危機が叫ばれて久しいが、スーパーローテート制度同様、国が医療政策の一環として第三者による専門医認定機構によるあらたな専門医制度の導入に本格的に舵をきった事で、従来の皮膚疾患の診療形態が大きく変わる事が予想される。その詳細は塩原教授がJDAレターに詳しく書かれているので是非一読して頂きたい。
アメリカでは皮膚科はDepartmentから内科の一部門としてのDivisionに格下げ(?)されている施設が増えているようで、名門の大学でも皮膚科以外の出身の主任教授が誕生し、外来もDay surgeryなどの収益がでる診療に特化されつつあるとの話しも聞く。また米国で開業された先生に伺うと治療の決定権は保険会社が握り、医師の裁量権はないに等しく、またバカ高い医療保険の支払いが限度となりつつあるのが現状とのことである。実際私の外来に来られた方がアメリカで黒色腫の手術をすると1,000万近くかかるので日本で手術を受けたいとの話しや韓国への医療ツアービジネスが繁盛しているとの話しも聞く。同様の事は英国でも起こっているようで、オーストラリアなどに移住する医者も増えているようである。このような中、包括的なTPPの導入によるアメリカの保険会社の参入が危惧され、塩原教授のおっしゃる黒船の来襲が目の前迄迫っている。過去、元寇では神風が吹き、幕末の変革期には勝海舟や吉田松陰などの有能な人物が多数現れ、日本の植民地化を未然に阻止した。今回の医療改革に関しては皮膚科の場合、病院皮膚科の低い売り上げや重症患者の診療拒否(マンパワー不足)、に加え、塩原教授の危惧されているように総合診療科の導入による診療科存続の問題が現実のものとなってきた。このような逆風の中で皮膚科学会でも先に揚げた問題提起が開始された。
過去の歴史は大きな変革の波を止めることは誰にもできないことを教えている。このような状況に対応するためには正確な情報の共有や現場の医師も交えた討論と国への働きかけが何より重要かと考えるが、現状は塩原教授が述べておられるように必ずしも十分ではない。女性医師問題はここ数年橋本公二前理事長などのご尽力で問題点と対応策が目に見える形で共有出来るようになってきたが、個々の医局の事情もあり、理想と現実の大きな乖離から、次のステップに進んでいないのが現状かと考える。
「OKY」と言う言葉は今年、元日の日経新聞の一面の掲載されていた記事からの引用で「お前、来て、やってみろ」の略語とのことである。海外や企業の現場の第一線で苦労されている方々がお題目のみ唱える執行部に向かって使う言葉らしい。私自身偉そうな事を言える立場ではないが、今我々にできる事は他科から、そして患者から信頼される医療を提供すること、そしてその医療を担ってくれる若い世代を責任を持って育てて行く以外にないと考える。そのためには今こそ皮膚科の面白さを率先して教える献身的なリーダーを支援し、また「OKY」と言わざるを得ない現場の医師の声をもっと取り上げて行くこと、「イクジイ」(イクメンにはもはや頼れない?)に代表される退職された有能な医師に積極的に女性医師をサポートして頂く事かと考え、私の教室でも実行している。 昨年末に届いた111回日本皮膚科学会総会のProceedingに「東日本大震災の福島県皮膚科診療に与えた影響と、福島医大の今」という論文が掲載されている。その是非を問う資格は私にはないが、震災後も現場に留まり、劣悪な環境下と風評の中で皮膚科医としての職務を全うされた福島医大皮膚科教室の7人の先生方には心からの賞賛を送りたいし、それぞれの与えられた環境で頑張る全ての医師に大きな勇気を与えて頂いたと感謝する。
「してもらうことばかりのみ求むるは
年若けれど心は老いたり」
2017年の開国に備え、準備するために皮膚科医の叡智の結集が必要であるが最後の言葉は今年頂いた塩原教授の賀状から紹介させて頂いた。私も心が老いないように、若い先生方と一緒に前に進みたい。
2013年1月
もう一つの山中ファクター
もう一つの山中ファクター
皮膚科教授 片山一朗

平成24年10月22日掲載
歴史は繰り返すのか?
歴史は繰り返すのか?
皮膚科教授 片山一朗
2012年4月に博多で開催された28回日本臨床皮膚科医会に出席し、占部治邦九大名誉教授のご講演「真菌症の変遷」を拝聴する機会があった。占部先生には久しぶりでお会いしたが、お元気そうであった。私が長崎大学に着任して直ぐに会頭を仰せつかった西部支部総会にお越し頂き、大会を楽しんで頂き、また西部支部での人のつきあい方を教えて頂いた事を思い出しながら講演を聞いた。第二次大戦後から現在にいたる福岡県における皮膚真菌症の移り変わりを先生ご自身が集積された膨大な疫学研究のデータと貴重な症例提示を中心に、淡々とした口調でお話しされたが、このような連続性のある研究の重要性を再認識するとともに、日本人のある時代の社会背景の記録としても大変興味深く拝聴し,久しぶりに満足感の得られた講演であった。
日本の多くの大学医学部では今、大学院改革のさらなる流れの中で、病理学、解剖学、生理学、生化学などの講座名が消え、主任教授の専門領域をキーワードとした米国式の即物的な名前を直訳した教室名が使用されている。結果として、100年近くに亘り集積された貴重な日本の医学資料は廃棄される運命を辿り、さらに多くの教室員の努力の上に醸し出されていた教室のスピリットが消え去りつつある。大学法人化、新研修制度の導入と平行して進められた大学院改革は時代に即した効率的な研究組織の構築、新しい研究領域の創出、競争原理の導入、そして何より若いMD研究者の参入を促すためであったと理解している。しかし改革が始まり10年近くが経過した現在、発表論文数や海外への留学希望者の減少が大きな問題となっている。基礎研究室のMD研究者は激減し、結果として流行の最先端にあるNon-MD研究者が研究の中心を担う時代になっている。米国では大統領、企業に限らずトップが交代すると前任者の組織はすべて新しいものに変わるが、十分な論議を経ずに、異なる歴史、文化、経済構造、そして何より彼らとは異なる価値感を持つ日本人が米国の後追いをすることの危険性は当初から指摘されていた。結果的には国の方針やトップがコロコロ変わり、小泉改革後はTPP問題を含めすべて米国の言うままに動き、哲学のない目先の利益に左右される政策が進められている。
話は変わるがここ数年、毎年ミャンマー(ビルマ)を訪問している。最初にヤンゴン(ラングーン)市内に入った時には私の子供時代、まさに占部先生が最も活躍されていた頃の日本にタイムスリップした感覚に襲われた。ロンジーと呼ばれる民族衣装に下着だけの人々で溢れ変える市街地は混沌としてはいるが不思議な安堵感を与えてくれたが、今年訪れた時にはその空気が変わり、ホテル代も昨年の3倍となっていた。米国の経済制裁の解除による欧米資本の参入結果とのことである。今後占部先生の示されたような変遷がヤンゴンにも訪れるのかと感慨深かったが、ヤンゴン総合病院で講演後質問に来た6人の皮膚科レジデント達の眼は皆、久しく日本で見なかった素晴らしい輝きをはなっていた。帰国後米国式の改革結果がでるのはいつかと考えている。
平成24年9月18日
ロンドンオリンピック2012
ロンドンオリンピック2012
皮膚科教授 片山一朗
7月27日に開幕した第30回ロンドンオリンピックは日本が金メダルこそ7個と少なかったが過去最高の38個のメダルを獲得し、8月12日に閉会した。大会中何度か明け方迄テレビ中継を観戦し、寝不足が続いた先生も多かったと思う。アメリカや中国などの圧倒的な強さの中でやはり最も印象に残ったのはなでしこジャパンや女子バレー、レスリング、水泳など女性選手の活躍と男子フェンシングで最後の1秒でドイツに逆転した太田雄貴選手の素晴らしい試合だったかと思う。なでしこの佐々木監督やiPADを駆使して選手を指導した真鍋監督など,女性医師の占める位置が高い全国の皮膚科教授にも、その指導哲学や手法など、おおいに参考になったかと思う。また北島康介の前コーチで,今回寺川綾をはじめとする日本水泳選手団のコーチを務めた平井伯昌さんの「勝ち続けることでアスリートは尊敬される。楽な練習なんてない。克己心を身につけるための練習がきついのはあたりまえ。康介には世界で多くの人とふれあって欲しい。指導者がいなくてもセルフマネージメントできる選手を育てることがコーチとしての目標だ。」(週間朝日8月10日号)の言葉も印象に残った。
阪大の皮膚科でも、教官の先生方が若い研修医や大学院生を指導してくれているが、同じ気持ちで次ぎの時代の皮膚科医を育てて頂きたい。またオリンピックでの女性選手の活躍と同様、今年から来年にかけて4人のママさん皮膚科医が相次いで海外に行かれるが、是非見聞を拡げ、帰国後はまた皮膚科医として活躍して頂きたい。
さてオリンピック終了と相前後して北方領土、竹島、尖閣諸島などの領有権を巡る問題が一気に噴出した。オリンピックが部族間の戦争が続く古代ギリシャでつかの間の休戦を目的として開催されたことが思い出されるが、現代に生きる我々にも現実の厳しさを思い知らされる。世界は今Overconnectedとも言われるくらいインターネットやFacebookなどで結ばれ、多くの情報が手に入る時代になったが、その中で実態のない経済活動が多くの弊害を生みだし、リーマンショックやギリシャ危機が世界を襲い、そして日本の国力低下が現実のものになりつつある。世界がデフレスパイラルに陥った時、現実の世界はいかに苛酷であるかをあらためて再認識するが、今後我々はどのように生きて行けば良いのかそれぞれが考えていかざるをえない時代になっている(アエラ 2012.9.10 No37.内田樹 大市民講座 「アメリカ抜きはありえない」)。
同じ問題は皮膚科という小さな社会に生きる我々皮膚科医にも当てはまる。日本の大学は明治時代の大学設置、敗戦による新制大学の誕生に引き続き、20世紀後半に始まった大学院改革に大きく振り回されている。大学も従来の日本型相互扶助型(組織依存型)からアメリカ型個人主義に近い組織運営に移行しつつある。今後は組織防衛の意味からも個人が個々に独立しながら伝統の継承と組織維持を重視するユダヤ人型の考え方に日本的な武士道精神を付加したあらたな組織の構築が必要ではないかと考えている。
2012年9月4日
同門会ご挨拶
同門会ご挨拶
皮膚科教授 片山一朗
大阪大学大学院医学系研究科情報統合医学
皮膚科 教授 片山一朗
7月に入り、梅雨明け宣言と同時に大阪も猛暑の日が続いています。首相官邸前の原発再稼働抗議デモ、TPP参加による日本の医療の産業化問題、オスプレイの導入、尖閣列島の国有化、大阪都構想など暑い季節がよりヒートアップしそうですが、世界の中での日本の在り方を国民全体で議論できる良いチャンスかと考えます。
皮膚科学も新臨床研修制度が開始されて8年が経過し、都市部と非都市部の格差と地域による診療格差がより顕在化してきています。日本皮膚科学会では将来の皮膚科を担う女性医師問題の解決策として塩原教授のご尽力によるメンター・メンティによる相談制度が稼働し始めました。また大学間の壁を越えた医師の交流による医療格差の是正に関する取り組みも各地で始まっているようです。
皮膚科学は今、新たな治療薬や機器が導入され「診断の時代」から「治療の時代」へ移行しつつあります。その中で皮膚を介して全身を診て、治療することのできる皮膚科医のニーズはますます。大きくなることが予想されます。
このようなダイナミックな変化の中、今年は新入医局員の紹介欄にあるように阿部、井上、岡田、小野、加藤、神谷、須磨、竹原、中山、山田の10人の新しい先生を大阪大学皮膚科学教室に迎えることとなりました。また9月から福山、10月から関先生が同門会に加わられます。皆さん出身大学、世代はそれぞれ異なりますが、モチベーションの高い先生ばかりであり、大阪大学皮膚科教室の一員として、大いに発展されることを期待しております。
医局の動きとしては4月から種村篤先生が医局長に就任し、忙しい中、関連病院の責任者と話し合いを持たれ、若い先生をどう教育するか、同門会との有機的な連携をどう進めるかを懸命に考えて頂いております。その中で今年より、若手皮膚科医に対する集中クルズス(2〜3ヶ月に一回、関連病院部長、大阪大学教官)を開始しました。昨今全国の大学では実用的な皮膚科学、あるいは皮膚科学の伝統的な診断、治療などの講義が減少しているようで、大阪大学皮膚科の一員となられた先生に同門意識を持って貰うことも目的の一つとして、このような集まりを企画した次第です。今後開業の先生にも是非講義していただく機会を作って行きたいと考えておりますのでご協力お願いいたします。また大阪大学皮膚科ホームページも大きく改変いたしました。当初、クラウドを用いた医局員内での運用を考えていたのですが、若い先生から、ホームページも充実させ、大阪大学皮膚科の情報を全国に発信させることが重要との意見を頂き、西田さんに無理をお願いして、現在の形式を作って頂きました(現在英語版も作成中)。ご意見などありましたら、随時改変し、よりよいものにしていきたいと考えております。
今年は24回日本アレルギー学会春季大会を室田浩之事務局長を中心とした教室の先生のご尽力で大成功のうちに終えることができました。来年は皮膚脈管・膠原病研究会、日本色素細胞学会、日本研究皮膚科学会などを担当することになっております。同門の先生にもまたご指導、ご鞭撻をお願い申し上げます。
最後になりましたが、私も新臨床研修制度が開始された2004年に大阪大学に着任し、はや還暦を迎える歳になりました。初心に帰り、また若い先生共々大阪大学の発展に尽力していきたいと考えております。
平成24年7月23日
コントロールの重要さ
コントロールの重要さ
皮膚科教授 片山一朗
私が基礎研究を始めた頃の大阪大学皮膚科の第2研究室は大学紛争がようやく落ち着き、研究を再開された先生方やその仲間が頻繁に出入りされ、狭くはあったが、熱気が溢れる、今から思うと夢のような場所であった。研修医から講師の先生迄、経歴も世代も異なる皮膚科医(基礎や他科の先生も出入りされていた)が集まり朝から夜遅くまで実験や臨床の話が尽きることなく繰り広げられていた。その中でいつも言われたのはコントロールを取ることの重要さであった。どうしても研究を始めた頃は新しい発見に目を奪われ、その再現性を繰り返すことが実験の主体になる。その中で越えられない壁が出てくる。その時に壁を乗り越える最も重要なことが適切なPositiveコントロールとNegativeコントロールをしっかり取っておくことであることを理解した。マウスの数や実験プレート、試薬の値段、細胞数などを考えると、つい陽性データの比較実験が主体となり、大切なコントロールをとることを忘れがちになる。西岡先生からは「基礎と臨床の研究の差はどれだけコントロールの実験を行えるか、どれだけ自分であらたな解析手技、手法を創り出せるかである」、「他人の作った抗体や細胞株を用いる、他の臓器で証明されたことを皮膚に応用するだけの実験は決してやるな」とよく言われた。現在のTop journalではSupplementary figureとして多くのデータが添付されているが、昔の論文はその部分がなく、Material MethodsやDiscussionに簡単に触れられたOne sentenceから著者達の努力をいかに読み取れるが研究者の最も重要な資質であったと考える。現在論文のSuppleの部分はその意味から若い先生には有益で、恵まれた時代になったとも考える。また「その時の常識で理解できないデータが出ても決して棄てはいけない」とも良く言われた。
話は変わるが先日の病理カンファレンスで、久し振りに担当者と主治医を一喝してしまった。研究と同じで、病理所見も初学者はどうしても臨床診断名に囚われ、その病名の組織所見に合う所見だけをピックアップし、不都合な部分は切り捨ててしまう。結果として全く違う病名が病理診断となり、治療へも大きな影響を与えてしまう。皮膚疾患は臨床的な表現型は同じに見えても、その病因や組織反応は全く異なることがあり、その確認のために病理診断がある。研究と同じでまずNegative コントロールとして正常の皮膚組織像を理解し、年齢や部位による差を考慮していく必要がある。さらにPositive controlとして腫瘍、炎症、沈着症、肉芽腫、母斑などその病理標本の診断名に記載された疾患と病理像の差異を考えていく。重要なことは弱拡大で正常組織では見られない所見を認識することと組織反応の特徴を大きく捉えることであり、臨床診断名と合う所見、合わない所見を整理し、臨床像をその病理所見で説明できるか考えることである。このようなプロセスから的確な病理診断を下せなければさらに特殊染色や他の病理医の意見を求める。回診などでも理解できない検査所見や教科書にあわない症状を言ってくれない研修医が時にいるが、病理診断や基礎研究でも同様で決して不都合な真実を隠しては行けない。抗生物質の発見に代表される偉大な発見の多くは、その時代の常識では理解できないもので、発見者がその場にいなければ、さらに多くの時間が必要であったことは科学史が教えている。
説教じみた話になってしまったが、怒り放しの一方通行では申し訳ないのでフォローの文として読んで頂ければと思う次第である。
2012年6月27日
2nd EASTERN ASIA DERMATOLOGY CONGRESS
2nd EASTERN ASIA DERMATOLOGY CONGRESS
皮膚科教授 片山一朗
President: Jianzhong Zhang(張建中)
Professor, Department of Dermatology
Peking University People’s Hospital
Venue: China National Convention Center, Beijing
Date: 2012. June 13-15
6.14日 招待会での張教授の挨拶風景

私はアトピー生皮膚炎のセミナーで張教授とともにドイツのWollenberg, 韓国のKim先生の座長を、色素細胞のセッションで中国Gao教授と座長を務めさせていただいた。アトピー性皮膚炎のセッションではタクロリムスのProactive therapyがテーマで、この療法の登場により患者のQOLのみでなく、医療経済的にみても大きな改善効果があること、週一回の外用でも十分効果があることが報告され注目された。なお張教授より中国ではアトピー性皮膚炎の診断が必ずしも正確に診断されておらず、あるいはアトピー性皮膚炎自体が少なく湿疹と言う病名で片付けられ、十分な治療が受けられない患者が多いとのコメントがあった。Dr. Wollenbergからは中国はまだTh1優位の状態で今後患者が増加するだろうとのコメントがあった。実際2年前上海で小児科の先生方と話しをする機会があったが、彼らもアトピー性皮膚炎という言葉は使用せず、乳児・小児湿疹という病名と,その原因は食物アレルギーであると言っていた。かつて日本でも同じ議論があったことを思い出したが、内因性と外因性アトピーを考える時、地域差や工業化の程度なども考慮する必要があるかもしれないと感じた。
色素細胞関連では中国からCOX2阻害薬がメラニン産生を制御するとの興味深いコメントがあったが、演者が代理の方で十分なコメントのなかったのが残念であった。阪大からは室田、谷、山岡先生がORALに選ばれたが皆さんうまく発表され、質疑応答も活発であった。花房、楊、糸井先生はポスター発表された。阪大皮膚科からの海外での発表も最近は増加し、皆さんプレゼンがうまくなっており、何よりである。また海外発表の大きなメリットとして発表前に十分文献的考察をしておけば、そのまま英文論文として投稿できることで、阪大の論文発表の増加に貢献している。自分で経験した症例、発見した知見、生命現象を英語で論文として報告することは大学人の義務であることを学生や医局の先生にも言っているが、その成果がでてきたかと考えている。
北京観光は到着した日にそのまま万里の長城見物に出かけたが、現地に到着したのがケーブルカーの最終便時間を一分過ぎており、楊さんの懸命の交渉も実らず、はるか山頂の長城を見上げるのみで終わってしまった。ちなみに無事(?)観光された先生の話では長城はラッシュアワーなみのものすごい人であふれかえり、K大学の先生は50m近く崖を滑り落ち、危うく大けがを免れたとのことであった。
最終日夜は国賓招待に使われる釣魚台でJapan Nightが企画され、会場では見かけなかった先生も多く見かけた、庭園は蘇州の山水をモチーフに造られたそうでライトアップが大変美しかった。一般の観光客は入園不可で、中国側と交渉していただいた岩月会頭の御尽力とあとで聞いた。北京は10数年ぶりの再訪だったが、町並みが驚くほどきれいになり、街中に溢れていた自転車も姿を消していた。以前の公務員体質丸出しのホテルや商店の店員や受付の対応が大きく改善し、むしろ地方からでてきたばかりのようなスタッフが多く、好感がもてた。
次回の済州島の第3回大会を楽しみに会場をあとにした。
2012年6月
第111回日本皮膚科学会総会
第111回日本皮膚科学会総会
大阪大学大学院医学系研究科分子病態医学
皮膚科教授 片山一朗
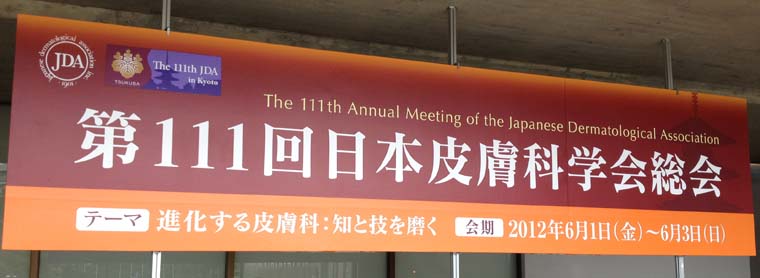
会頭 大塚藤男 筑波大学教授
会場 国立京都国際会議場
会期 2012年6月6月1日〜3日
テーマ —進化する皮膚科:知と技を磨く
第111回日本皮膚科学会総会が6月1日から6月3日までの3日間、京都国際会議場で開催された。会頭の大塚藤夫筑波大教授、事務局長の川内先生には御礼申し上げると共に、大変お疲れさまでした。私も109回総会を大阪で開催しましたが、会場が遠くはなれた京都ということで、準備など本当に大変だったかと思います。昨年の110回大会が東北大震災のために中止となったせいか、今年は5、000人近い参加者があったそうで、何よりでした。また最終日午後には医療支援のボランテイアを担当された先生方の講演があり、このような未曾有の災害時に皮膚科医として何がどのようにできるか、何を記録として残しておくべきかを考えさせられた。最後に統括・指揮された飯島正文前理事長より挨拶と感謝状が演者に贈られた。
学術大会は大塚会頭の会頭講演から開始された。20分という短時間で筑波大学の歩みを紹介された中で、初代教授の上野賢一先生がこの大会への参加を楽しみにしておられたが、4月4日に逝去されたことをお話しされた。上野先生の小皮膚科学書(通称:マイナーデルマ)で勉強した我々の世代には、いわゆる記載皮膚科学に代表されるドイツ皮膚科学の時代が終わったという感慨が残った。
その後、最終日まで、スポンサードセミナー、教育講演や特別講演などを聞いた。最も印象に残ったのは東大形成外科の光嶋教授のSuper microsurgeryの講演であった。最初のスライドから驚くようなプレゼンであったが世界の形成外科をリードされる「神の手」の凄さを初めて目にした私には、あらためて皮膚科医がやるべき仕事が何であるかを考えさせられた講演であった。またコロラド大のRoop教授のiPS細胞を用いた先天性表皮水疱症の治療の可能性に関する講演は今後の難治性皮膚疾患の新たな可能性を示唆するものだった。阪大でも7月から玉井教授の骨髄細胞を用いた新たな治療が開始されるが、今迄、全く治療法のなかった遺伝性皮膚疾患を治せる時代に皮膚科医であることを感謝している。別の教育講演で教室の金田真理先生が講演された結節性硬化症のAngiofibromaの外用療法も同じレベルで世界に発信出来る研究であることを参加した先生方から聞き、あらためて金田先生の長年の努力に敬意を表したい。
最終日、塩原先生の女性医師問題のセッションで、塩原先生は講演の最初にJohn F Kennedyの有名な大統領就任演説「ask not what your country can do for you
– ask what you can do for your country.」を紹介された。Countryは学会、教室、家族、指導者、同僚、後輩など様々な言葉に置き換えられるが、大事なのは医師を目指そうと決意した時の気持ちを持ち続けることであることを強調された。講演後の質疑応答での一人医長の女性医師の発言は逆に研究をしたくてもできない彼女の悔しさが身にしみた。我々の世代の責任として一生続けられる研究テーマをいかにして彼らに提供できるか、見つけた人の研究をいかにして支援出来るかを考えさせられた。塩原先生の行われたアンケートから浮かび上がった問題点として、指導者として残れる女性医師のサポート体制の確立が何より重要であるという結論にも同意したい。
教育講演は毎年同じテーマを行うことで、複数年の参加で皮膚科の進歩をカバーできるとの主旨で開始されたが、今後もう少し余裕を持ったプログラムとし、質疑応答の時間を充分にとる、専門医を対象としたより高度な内容のプログラムを提供して欲しいとの声も聞かれた。拝聴した講演の中では、2日目朝のMSでMRIの造影剤に使用するガドリニウムによるNephrogenic systemic fibrosis(NSF)が有益であった。名前は知っていたが、実際の皮膚症状や使用基準など参考になった。
一般演題はすべてポスター発表であり、今回からデジタルポスターが採用されたが、会場が少し離れており,やや不便であった。また企業展示も例年に比較してやや寂しい印象であった。ポスター賞はその多くが症例集積研究で,多忙な中での長年の地道なご努力の成果が報われたような仕事であり、是非英文化して世界にその成果を発信して頂きたい。最後になるが今回マルホ賞を受賞された斎田先生のダーモスコピーの一連の仕事は、先生自身お話されたように、「当初誰も注目を払わない、あるいは猛批判を浴びた研究が現在は教科書に採用されるようになった」ことにあらためて先生に拍手を送りたい。
2012年6月
山田瑞穂先生のこと
山田瑞穂先生のこと
大阪大学大学院医学系研究科分子病態医学
皮膚科教授 片山一朗
先日和歌山医大皮膚科のホームページを見ていたら古川教授のコラムに山田瑞穂先生の随筆が掲載されていた。(下記)
「山田瑞穗 (浜松医大名誉教授、皮膚科学、副学長)
「私の歩んだ道」11
皮膚病診療:Vol.24, No.10; 70~1174, 協和企画(2002)」
山田瑞穂先生は浜松医大の初代教授として1977年に着任され、1990年に退官後は病院長、副学長も務められ、2004年1月4日ご逝去された。私自身、山田先生に直接ご指導をうけたことはないが、初めてお目にかかったのは西岡清先生(当時大阪大学皮膚科助手)とご一緒に開講間もない浜松医大皮膚科で開催された皮膚免疫セミナーに参加した時だったと記憶している。セミナー前に教授室や研究室(何もなかった?)を案内していただいた。教授室に飾られたボトルシップと免疫セミナーがやたら難しかったことのみを記憶している。今回山田先生の随想を拝読し、当時のことが懐かしく思い出された。今の時代山田先生を知る若い人は殆ど居られないと思うし、あのような経歴の中で志を高く持たれ、人間的な魅力に満ちあふれた山田先生のような教授が誕生する可能性はゼロに近いと思うが、若い先生に山田先生の生き方も大いに参考になるかと思い、一部下記に引用し、紹介させていただいた(興味のある方は和歌山医大皮膚科ホームページにアクセスすると、原文が読めます)。あわせて古川教授のボスだった京都大学名誉教授(病理学)のメッセージも推薦します。
以下引用(下線筆者)
I. 自立・而立
翌27年に厚生技官に任官し,はじめのうちこそ,医長の大矢全節先生からご指導を受けたが,先生は英語,ロシア語の医学辞典,フランス語の医学史の執筆等にご多忙であったので,実情は自分1人で勉強しながら診療していたようなものであった.
毎日の外来診療も皮膚病は診断,治療とも目でみて,手で触れることができるし,学会,地方会,集談会には必ず演題を出して出席し,討論に耳を傾けて勉強した.当時は病理組織などは誰もが知らなかった.手術はインターンの延長という点もあって,外科,整形外科,婦人科の手術を手伝い,教えてもらって勉強した.
毎日100人以上の患者を診察し,昼食は2時,3時を過ぎ,猫に荒らされて何もなくなっていたこともあった.手術はほとんど毎日2・3例あり,腎臓摘出の日は必ず泊まり,前立腺の手術には難儀したが,まがりなりにも一人前の皮膚科泌尿器科医であったと思う.
忙しい病院勤務の合間を縫って,語学が苦手の私が,日仏会館の夜学に通い,大学とは違って,年齢も社会的身分もいろいろな人たちと,楽しくフランス語の勉強をしたが,のちのちフランス語の論文を書くのに役立った.
自分勝手な興味からWassermann反応について実験していたところ,それを実験家兎梅毒でやってみろと山本俊平教授にいわれ,睾丸にスピロヘータを接種した家兎を提げて,教室のWassermannの天鷲技官が実験の手伝いにきてくださったりして,なんとか学位論文に辿り着くことができたが,50ページに余る論文の掲載料を払うことができないし,医長の大矢先生と診療上の意見の相違もあって,7年後にはるか僻地,四国の宇和島に赴任した.
IV. 13年目の新人医局員
京大本部直属の保健診療所の外科・皮膚科助手の席が当てがわれ,13年目の新人医局員の生活が始まった.それまでの経験等は一切捨ててまったくの新人として,若い人たちの中に埋没した.それでも自分の懐の痛まない研究に従事させてもらい,新しいテクニックを用いての組織化学の論文を国際誌J.I.D.に掲載できた.
しかし,このテクニックを血液に応用して得た新しい知見の論文が,イギリスの血液学の雑誌に受理され掲載が決まっていたのに,最終段階で写真にゴミがついているとして拒否されたのは痛恨の極みで,標本・資料保存の重大さを身にしみて感じたが,教室には顕微鏡写真を撮れる者がなく,あらためて日本光学から顕微鏡の構造,光軸の合わせ方,絞りの調節,レンズの磨き方等を教えてもらったりもした.島田での経験もあり,いろいろな勉強会を企画,実施した.
保健診療所の講師は辞退し,少し遅れて皮膚科専任となり,講師となったが,教室員の一番最後に名札がかかっていた.舞い戻りのアウトサイダーの私が医局をまとめるのはむずかしいことであった.かの大学紛争時,教授は会議会議でほとんど不在,助教授は敵前逃亡同然の長期病気欠勤という状況で,「貴君が大学にいる意義は何か」といわゆる“教室会議”で吊るし上げられたりもした.「皮膚科紀要」の編集,これを維持するために,次々に治験論文をまとめ,また若い人たちに症例報告を書いてもらうのもたいへんであったが,真菌専門の渡辺講師が赴任されてからは,関西の真菌の勉強会を主催せざるをえなくなり,付け焼刃的な知識しかない私にはさらにたいへんであった.
大学に在籍するかぎり,自分自身の研鑚もさることながら,組織の維持が重要であることは論を待たない.紛争を機に,自分にとっても組織にとっても意義が薄れてきたので,身を引くべきであろうと,いろいろ批判はあったが,大阪赤十字病院からの招聘にこたえて,赴任することとなった.
V. 気が狂ったか?
短期間ならなんとかなるだろうと,満員電車で往復4時間という過酷な通勤に耐えて大阪まで通った.当時,大学では研究はもちろん,勉強会などもすべてストップしていたので,天理病院の渡辺医長,神戸市民病院の宋医長と相談し,交代で臨床の勉強会を企画したが,結局,私の大阪赤十字病院で毎月実施することになり,計70回余,この3病院,京大病院のほかからも大勢の若い皮膚科医が症例,標本,スライドなどを持ち寄って参加し,賑やかに実りの多い勉強会が行われた.
大学病院では構成員の専門性が重視され,すべての疾患に目を向けることは不可能であるが,この病院では部長である私がすべてを統括していたので,おそらく大学よりも豊富ないろいろな症例のすべてに目が届き,もちろん,責任も重大であったが,たいへん勉強になった.
前から電顕には関心があったが,京大では病院に1台しかない電顕の皮膚科の割り当てが減るので,邪魔をしないように遠慮していた.この病院には電子顕微鏡があるが,病理の専門家以外,あまり利用されていないことがわかったので,早速,この電子顕微鏡を使わせてもらうこととなり,京大病理学教室の電顕テクニシャンの第一人者藤岡氏に出張指導をしてもらう話がまとまった.40歳を過ぎて,一から新しいテクニックを,しかも電顕には最悪の気候時に始めるということで,大方の批判は気が狂ったのではないかということであった.包理など標本をつくるのは一緒に習い始めた女医の吉永さんのほうがずっと上手なので一任し,私は機械の操作がなんとかできるようになると,多数症例についての観察,撮影,現像,スライドづくりなどに没頭した.一方,まだ免疫学的意義の確立していなかった薬疹の原因,その他の抗原刺激によるリンパ球幼若化現象についても検討していたが,PHAによる幼若化現象リンパ球の微細構造の観察をさらに進めて(すでに手掛けられていた上皮系,色素細胞系科の電顕的研究の後追いは空しいので)真皮について観察はしてみてはどうかと考えたが,真皮には線維芽細胞,組織球,細網細胞,リンパ球など種々の酒類の細胞があり,同定が不可能なので誰も手をつけないのだと聞かされた.しかし,敢えて真皮の浸潤細胞の電顕的観察に,また,内科はもちろん病理の人たちにもT細胞リンパ腫に関する認識の過ちから,菌状息肉症,Sezary症候群の独立性が危うくなっていたこともあり,究極的には皮膚のリンフォーマの研究に発展した.
医師,看護婦のストライキに嫌気がさし,この病院をなんとか脱出したいと考えていた時,各県に1医大という構想が発展して新設医大ラッシュが始まり,奇しくもその網の一端に引っ掛かって浜松医大の教授に内定した.
留学の経験がまったくないので,有給休暇のすべてをまとめてとらせて欲しいと無理をいい,1ヵ月あまり,アメリカの大学,学会を歴訪できたのは幸いであった.一方,講義のためのスライド,組織,医局員の勉強のための医学雑誌のバックナンバー,教本の整備など,新しい教室づくりの準備も結構たいへんであった.
VI. これが教授というものか
昭和52年4月,浜松医科大学教授に任官した.官舎に転入,居住が指定され,毎週会議だけはあるのだが,仕事をする場所も,居る場所もない,という状態がどのくらい続いただろうか.何をしていたのか,いまでは何も覚えてはいない.
器具等は,順次予算措置が講じられて,いずれは購入されるのだとはいっても,やっとでき上がったがらんとした研究室には,学生実習用の顕微鏡が1台と,ミクロトームがぽつんと置いてあった.病院で診療が始まったのは11月が終わるころであった.これで一体何ができるというのだろうか? 私自身は何もできなくても仕方がないとして,一緒に赴任した田上助教授はどうしていただろうか,なんとも申し訳のないかぎりであった.
50歳を過ぎて,とくに私のようにどさ回りをしてきた者が,臨床経験や学生の教育などでは指導力を発揮できるとしても,研究の面で終始医局員をリードし続けることはむずかしい.幸いにも,私とコンビを組んだ田上助教授は組織学的診断でも,研究でも京大皮膚科のナンバーワンであったので,とくに研究面での教室の運営をすべて彼に任せて,私は,大学は医師養成のための教育機関であるという名目のもと,学生の教育に力を注ぐこととした.あるいは迷惑であったかもしれないが,彼は思う存分に腕を発揮して,昭和59年に東北大学教授に栄転した.しかし,私は医学教育にのめり込んで,教育担当の副学長になってしまい,後任の瀧川助教授には,教室全体の運営までも背負わせてさらに迷惑をかけることになってしまった.early clinical exposure,新しい医学概論,死の医学の教育などを提案したが,世間より一回り早過ぎたかも知れない.少し間を置いて次にまた,医療担当副学長・病院長に就任し,無能のまま赤字の解消に専念せざるをえぬはめとなり,もはや皮膚科教授としては完全に失格であった.
不毛の土地で,静岡地方会を単独で運営するため,各地の方々を招いたり,免疫セミナーと称する若手研究者の勉強会を開いて自由に討論する雰囲気をつくったり,後には皮膚リンフォーマ研究会という病理,血液内科の人たちと一緒の学会をつくったりして,視野の広い臨床家,研究者の育成に努力したつもりである.
たとえ教授が非力・無能であっても,優秀なスタッフが思う存分に腕を振るえば,その教室・医局はどんどん成長し,発展するということは,この浜松医大皮膚科の実体をみていただければわかると思う.静岡県下のほとんどの病院を関連病院として配下に置いているし,個々の業績をフォローすることはとてもできないが,われわれの開発した「高周波による皮膚角層水分測定装置」を提げてデビューした田上教授は文字どおり世界の皮膚生理学の第一人者であるし,瀧川教授は国際皮膚リンパ腫学会会長として活躍,森口教授(形成外科),古川教授,岩月教授も川崎医大,和歌山医大,岡山大学でそれぞれ活躍している.
2012年
宮坂昌之教授退官講義
宮坂昌之先生の最終講義
大阪大学大学院医学系研究科分子病態医学
皮膚科教授 片山一朗
2012年3月、宮坂昌之教授(免疫動態学)が大阪大学医学部を定年退官され、その最終講義を聞く機会があった。宮坂教授は我々皮膚免疫学をテーマとする皮膚科医にとっては神様のような存在で、学会のみでなく、エレベーター中や構内などでいつお会いしても全身にオーラを発しておられる先生であった。弟さんの宮坂信之東京医科歯科大学病院長ともども若い頃から剣道をたしなまれ、お二人とも凛とした古武士を彷彿させる風貌や言動が大変良く似ている。退官講義では先生の一貫した研究哲学やその方法論、日本における免疫学の発展の中での御自身による研究の評価に加え、長野県上田市での幼少時代の思い出から始まり、スイスバーゼルでの留学の話や大阪大学医学部着任前後の裏話など興味尽きないお話しが続いた、その中で宮坂教授が再三取り上げられた以下の言葉が心に残った。皮膚科の若い先生に紹介したく免疫動態学教室ホームページより一部を引用させていただいた。
” In Vivo Veritas”−時間のかかる免疫学 宮坂 昌之(大阪大学名誉教授)
ワイン通の間によく知られている言葉に”In Vino Veritas”というものがある。これはラテン語で、直訳すると、ワイン(Vino)の中に真理(Veritas)がある、すなわち、ワインというものは奥行きの深いもので、ワインを飲むとともに次第にその真理が見えてくる、ということのようである。
私が留学したオーストラリア国立大学ジョン・カーティン研究所のBede Morris教授は、In vivoの免疫学にこだわり、生体内でのリンパ球の再循環現象を仔細に調べ、リンパ球、樹状細胞は常に生体内を徘徊するダイナミックな存在であり、免疫反応のダイナミズムはこれらの細胞の動態変化を反映するものであるということを主張した人である。このMorris教授は、自他共に認める大変なワイン通で、よくIn Vino Veritasという言葉を用いながらわれわれにワインの蘊蓄を語ってくれた。彼のワイン談義が進むにつれ必ず出てくるのは、Vino(ワイン)も素晴らしいが、Vivo(生体)の精妙さも負けず劣らず素晴らしいということであった。そしてMorris教授は”In Vino Veritas”を”In Vivo Veritas”と言い換え、まさに「生体の中に真実がある」という金言ともいうべきものをひねり出した。
私はオーストラリア留学以来現在に至るまで、リンパ球ホーミングの分子機構に興味をもち、研究を続けているが、研究を続ければ続けるほど、”In Vivo Veritas”という言葉の重みを感じるとともに、生体の中のイベントの精妙さの仕組みをもっともっと知りたいと思うようになってきている。そして、この言葉の素晴らしさ、大切さを研究室の人たちにも是非知って欲しいと思い、”In Vivo Veritas”を額に入れて、毎年、研究室から卒業していく人たちに送っている。医科学の研究をするにあっては、in vitroの仕事をしていても、分子中心の仕事をしても、常に生体の中で何が起きているのか?という視点を持ちながら仕事を進めることが大事で、生体の中にあることを知ってこそ、その研究の価値が出ると考えているからである。
私の研究しているリンパ球ホーミングの分子機構は、分子レベルでの研究が進むにつれ、リンパ球特異的接着分子(ホーミングレセプター)、血管内皮細胞特異的接着分子(vascular addressin)や、リンパ球上のインテグリンを活性化するケモカイン群など、舞台を構成する様々な役者たちの存在などが次々に明らかになっている。しかし、in vitroでは、ホーミングレセプターといわれるL-セレクチンとその糖鎖リガンドとされる硫酸化シアリルルイスXだけでリンパ球のローリング現象が起こり、そこに特定のケモカインを作用させるだけでナイーブTリンパ球の接着の誘導をひきおこすことができるものの、これはホーミング現象のほんの一部を反映しているだけである。HEV (high endothelial venule; 高内皮細静脈)においてナイーブB細胞の接着制御をするケモカインはまだ明らかになっていず、また、メモリーリンパ球や他のリンパ球サブセットのリンパ球の局所へのホーミング機構にも不明な点が多い。さらに、リンパ球が局所にホーミングした後にそこを離れるメカニズムも不明である。最近、冬虫夏草由来の新しい免疫抑制剤FTY720が、sphingosine-1-phosphate receptorに対するagonistであるとともに、リンパ節からのリンパ球移動(離脱)を抑制することが報告され、リンパ球の動態制御に新しい制御機構があることが推測されている。アトピー性皮膚炎をはじめとする慢性炎症では、局所に継続的にエフェクターリンパ球が移住し、またこれらのリンパ球が局所から離れないために炎症が遷延すると考えられているが、このような新しい分子機構は病態制御の観点からも興味深い。
リンパ節以外の二次リンパ組織に目を転ずると、腸管リンパ組織へのリンパ球の選択的移住の問題はかなり分子レベルで明らかになってきたものの、脾臓へのリンパ球集積のメカニズムは不明である。特に、脾臓の白脾髄にはリンパ球が選択的に集積するが、どのようにしてその選択性が保証されているのかは不明である。さらに、白脾髄をさらに細かく見ると、胚中心、濾胞間領域、辺縁帯(marginal zone)が存在し、それぞれの領域には特徴的なリンパ球サブセットや樹状細胞が存在するが、この局在のメカニズムも不明である。また、肝臓や肺などはリンパ組織ではないが、正常状態で、常に多数のリンパ球が臓器内に存在する。しかしこれら臓器へのリンパ球集積の機構も明らかでない。
より個体発生に近いレベルに目を転ずると、ここでもいくつもわからないことがある。たとえば胸腺や骨髄などの一次リンパ組織への前駆細胞の移住や、二次リンパ組織の原基への前駆細胞の移住のメカニズムである。果たして特定の細胞が目的性をもって移住(ホーミング)しているのか、それともランダムに移住したものが局所で然るべき性質を獲得しているのであろうか?このような現象には、まだまだ新しい接着分子、新しいケモカインの存在が予想されるとともに、これらの機能を時空的に制御するメカニズムの存在が考えられる。最近われわれは、ケモカインを局所で捕捉する機構には多様性があり、特定のケモカイン群は特定の場所に局在する分子群によって、ある場合にはポジティブに提示され、ある場合には不活化されることを示唆する結果を得ているが、このような分子群の存在はリンパ球の動態に関する一連の反応を時空的に制御する機構をなすものの一つかも知れない。
これらの問題はin vivoのことであり、簡単にはin vitroの実験系として切り出すことは出来ず、その分、手間のかかる仕事になる。しかし、生体の中にあることを知ってこそ価値があるという立場から、今後さらにIn Vivo Veritasにこだわりin vivoの免疫学とそれを媒介する分子機構について研究を進めていきたいと考えている。
(文科省特定領域研究「免疫シグナル伝達」ニュース No.6 掲載、平成14年6月発行)
2012年
第35回皮膚脈管膠原病研究会
第35回皮膚脈管膠原病研究会
大阪大学大学院医学系研究科分子病態医学
皮膚科教授 片山一朗
2012.2.16-17 東京(京王プラザホテル)
土田哲也教授(埼玉医大皮膚科)
毎年恒例の皮膚脈管膠原病研究会に出席した。今回は伊丹始発の羽田行きに乗り、なんとか血管炎のセッションに間に合った。済生会中央病院の陳科栄先生、聖マリアンナ医科大学の川上民裕先生、北里大学の勝岡憲生先生などの熱い討論を大いに楽しんだ。特に抗リン脂質抗体症候群の最近の病因論やワーファリンの使用法など大いに参考になった。
午後は壊疽性膿皮症とバイオロジックス療法、IgG4関連Mikulicz病の話題、SLEなどの新しいトピックスが発表され、初日の最終セッションは私もシェーグレン症候群関連の座長を務めた。2日目は皮膚筋炎、強皮症、成人Still病関連の演題が発表された。特に新しい自己抗体(TIF1γ)の悪性腫瘍合併皮膚筋炎の早期診断での有用性に関してはホットな討論が繰り広げられ、今後の日常臨床での測定への普及が望まれる。大阪大学皮膚科からは糸井沙織(水疱と白斑をともなった男子SLE),中野真由(トシリズマブによる好中球性皮膚症Paradoxical SLE)、北場俊(悪性腫瘍を伴わない皮膚筋炎におけるNSEの意義)、田中文(Flame figureを認めた蕁麻疹様紅斑)の四演題が発表され、いづれも多くの質問、意見が出され得るところも大きかった。
本研究会は我々にとっては二世代以上前になる西山茂夫先生(北里大学名誉教授)、植木宏明先生(川崎医大名誉教授)、坂本邦樹先生(奈良医大名誉教授)など錚々たる先生達が中心になって設立された会で、奇しくも私が医者になった年に第一回が開催された。80年代当時は膠原病のみならず血管腫や腫瘍などの演題も多く出題され、多くの高名な先生方が熱い議論をされていたのが若い私にとり刺激的でまた診療や研究意欲を大いに高めてくれた。この会はスライド一枚で問題点を呈示し、十分な議論を行うことがポリシーであり、最盛期には夜10時を過ぎても会が終了せず、会長の先生がやきもきする姿を今も懐かしく思い出す。昨今インターネットの普及により多くの情報を瞬時に手に入れることが可能な時代になり、また画像診断なども普及してきたが、やはり臨床の現場の最前線で患者を診る医者が本音で病気の成り立ちや治療を討論することが若い先生方にはなによりの勉強になるかと考えた次第である。大学院改革や初期研修制度の導入前後のある時期、世代交代と重なり、一時的にこの会もやや勢いを失いつつあったが、ここ2〜3年は若い世代の参加が徐々に増加し、熱い議論で会場が盛り上がることも増えてきたと感じる。臓器別診療が主流の現在、患者の皮膚から得られる情報を治療にフィードバックできる皮膚科医の存在価値は益々重要になってきている。是非教室の若い先生もこの会に参加して、今膠原病、血管病変の診療に何が求められているかを肌で感じて頂き、討論の輪に積極的に参入して頂きたい。
2012年
光皮膚科学研究会設立大会
光皮膚科学研究会設立大会
大阪大学大学院医学系研究科分子病態医学
皮膚科教授 片山一朗
日本の皮膚の光生物学研究は古いようで新しく、1975年に設立されたUV-ABClub(紫外線研究会)に始まる。この会は故佐藤吉昭先生、故三浦隆先生、市橋正光先生が創設され、その後、野中薫雄先生、堀尾武先生、松尾聿郎先生など光生物学を専門とする先生方が次々と参加され、日本の光生物学の発展に寄与された(Visual Dermatol 10:442,2011 市橋正光。光皮膚科学の歩み)がClosedの会であったため、昨年の第40回を区切りとして、今回の光皮膚科学研究会へ引き継がれることになった。私も発起人の一人として第一回の本会に出席し、市橋先生のキーノートスピーチの座長を務めさせていただいた。今後この会の発展に寄与できればと考えている。ただ今回はまだその概要が充分衆知されていなかったためか、若い先生方の参加が少なく、今後光生物学の重要性を若い皮膚科医に広げていくことの必要性を痛感した。皮膚科においては紫外線発ガン、光老化、光アレルギーの研究が主体であるが、臨床においても光線治療は益々重要な武器になりつつある。検査法、診断法と合わせ学ぶことは多い。若い先生方にも今後積極的にこの研究会への参加を勧める次第である。代表世話人になられた上出教授のお話では今後ホームページの立ち上げや、学会への移行のための組織造りなど大変なご苦労があるかと思うが、世話人一同結束して支えて行きたいと考えている。
光皮膚科学研究会設立大会
2012.3.25 東京(東京慈恵医大)
上出良一教授(東京慈恵医大第三病院皮膚科)
2012年
皮膚科医の矜恃と後期専門医教育
皮膚科医の矜恃と後期専門医教育
大阪大学大学院医学系研究科分子病態医学
皮膚科教授 片山一朗
ここしばらく少し嬉しいことが続いた。一つは若い医局員たちの「最近の講演会はあまり聞きに行く気になれない。もう少し最近の基礎研究の進歩を勉強できる会を企画して貰いたい」という声を耳にしたことである。最近はどの学会、どの講演会も新しい薬剤やガイドラインに関する内容の話が多く、演者も同じような顔ぶれである。私も良く講演を依頼されるが、知らない間に同じ穴の狢になっており、大いに反省させられた。もう一つは初期研修の義務化が開始されて以後、大学院に進む若い医師が激減し、私の大学でも危機が叫ばれている。そのような中で、子供さんもおられる卒後17年目の女性医師の方が、しっかりとした基礎研究をやりたいと、今年から大学院に進まれた。またもうひとり卒後6年目の育児中の女性医師が大学院にこられることになった。日本の医療、研究が米国のスタイルを追随していることは良く聞くが、実際米国の基礎研究はMDがほとんど関与せず、留学生やPhDが担っているのは米国の学会に参加すればよく分かる。日本の現状もまさにその後を追っているようで、今後の基礎研究を担うMDの養成が不可欠の現況であるが、私の周りだけでも、少し明るさが見えてきたようで、この機会に少し皮膚科を取り巻く昨今の医療環境について考えてみた。
この1〜2年、医者の離職や地域・診療科による医師数の偏在がマスコミによく取り上げられる。そのような大きな変化の中で、私が専門とする皮膚科学は、もちろん地域差はあるが、初期研修修了後に研修を希望する医師が増加している。逆に「楽な診療科」、「儲かる診療科」の一つとして皮膚科がとりあげられ、このような事態が、結果として「命に関わる病気」をとり扱っている診療科を希望する医師の減少に繋がっているという、皮膚科医の「品格」を貶めるような論調の記事を目にする機会も多い。しかし臨床各科において、診療の対象となる疾患が開業医、一般病院、地域基幹病院、大学病院で異なるのは当然であり、またどの診療科においても多かれ少なかれ生命に関わる、あるいは患者の社会的・個人的QOLに大きな影響を与える疾患を診療しているのである。楽な科と世間で思われている皮膚科で扱う疾患は膠原病からメラノーマまで実に多様であり、対症療法に甘んじざるを得ない難治性、重症の疾患が数多く存在する。主治医の熱意により診断や予後が決定され、また、他科との連携により全身の病態を理解して、はじめて治療が可能になる病態、疾患も多い。その意味で、皮膚科は常に時代の先端の医学を理解する努力が要求される診療科である。臓器別診療の時代となり、初期研修二年間の間に全身を診るトレーニングを受けた新しい世代の医師が皮膚科の分野にどんどん参入してくれることで、皮膚科医が皮膚という臓器のスペシャリストとして、他科の医者と対等に討論し、医療の中で大きな役割を担い、医療経済の改善に貢献していける、そして先に述べたような基礎研究を志す若い医師のモチベーションが高まると考えるのは私に限らないと思う。ただそのような楽観的な考え方の対極として、いくつかの現実的な問題が出てきているのも事実である。それはスーパーローテートシステムの開始時から予測されたことであるが、医師としてあるいは社会人としての初期教育が十分に行えないという現状である。すでに崩壊したとされる医局制度が再び見直され始めているのは、医療・医学が師匠と弟子という人間関係に裏付けられた徒弟制度により継承され、その中で新たな技術を身につけ、新しい研究を創り出していくという、ドイツ式の医学教育をある部分で肯定する指導医が増えてきたせいかと考える。実際二年間何を勉強していたのかと思う新人を迎えた経験をもつ先生も多いと思う。批判はあるが、医局という組織のなかで同じ釜の飯を食うことにより、生涯に亘る良き師弟関係、同僚としての強い繋がりを構築でき、結果として、良質な医療を提供できたと考える我々の世代から見ると、今後医局に属さず、後期研修を終える医師の中には、医師としての根幹部分を十分身につけることが出来ず、本来の医師としての矜恃を理解しないまま、無為な日々を送る人が出てくるのではないかと危惧する。
もう一つは、女性医師の増加と出産・育児による休職ないし、離職の問題がある。同世代の教授達の間で、いつも話題になる。医師の離職や引き上げの問題は日々マスコミに取り上げられるが、女性医師の離職の現状、実働医師数の実態や復職支援、託児所の整備など全く取り上げられないのが不思議である。学会での動きはあるが、一個人、一学会の力ではどうにもならない。ではどうするか?これは私見ではあるが、女性医師を含めた我々医師の矜恃をもう一度考えてみることである。医師としての最大の喜び、モチベーション維持の原動力はどのような疾患であれ、病気が治り、患者さんに感謝されることである。個々の医師の価値観の多様性が重視される時代ではあるが、医師としての矜恃を次の時代の医療を担う若い人に伝えていくのが我々世代の役割かと夢想する。
2012年
今が旬の研究トピックは?
今が旬の研究トピックは?
大阪大学大学院医学系研究科分子病態医学
皮膚科教授 片山一朗
旬の研究とはどういう研究か?それは自分自身が作り出すものです。
私が研究らしいことをやり始めてもう30年以上経過しますが、その間免疫・アレルギー学の分野は大きく発展・拡大してきました。皮膚科に入局し研究を始めた頃、私の恩師で皮膚の免疫・アレルギー学のパイオニア的な存在であった西岡清先生(東京医科歯科大学名誉教授、横浜市立みなと赤十字病院院長)から言われた「免疫学は非常にFlexibleな学問で、どのような疾患も研究対象になるし、何を研究しても面白い結果がでると思います。」という言葉を折にふれ思い出します。個人的な意見になりますが、旬の研究というものはあくまで自分が創り出していくものであり、人がやっている研究は2〜3年もすれば時代遅れになってしまいます。私が研究を開始した頃ブレークスルーとなった研究はKohlerとMilsteinがノーベル賞を受賞したモノクローナル抗体作成の応用でした。その時まで活性のみ証明されながら蛋白質として捉えることの出来なかったサイトカインがT細胞ハイブリドーマの手法を用いて初めて明らかにされたのです。その後蛋白の同定とその受容体が次々と明らかにされ、サイトカイン遺伝子のクローニング、リコンビナント蛋白の作成、PCR法による遺伝子解析、遺伝子改変マウスの作成、核酸医薬の開発、そしてクローン動物の作成、今をときめくiPS細胞の作成に繋がってきました。私はこのような免疫学の発展過程を時系列で見てきた訳ですが、振り返って見ると、その時期、その時代の学会の参加者が熱く議論するテーマが旬の研究であり、討論の中で浮かび上がってきた研究の方法論や哲学を理解し、自分の研究に取り入れることが私の研究の根幹にあったと思います。最初に新しい研究を創りだすことが旬の研究であると偉そうなことを言いましたが、どのような研究であれ、自分自身がワクワクしながら、実験結果が出るのを待ち、次の研究方法を考えていくのが、自分にとっての旬の研究であり、その結果が国際誌に掲載され、他の研究者に引用され、臨床に反映されていくのが臨床科における研究の醍醐味かと思います。実際論文を国際誌に投稿し、結果が航空便で戻るまでの時間が待ち遠しく、毎日郵便ポストを見に行くのが日課でした。
21世紀の免疫学研究のターニングポイント;そして免疫学はどこに向かうか?
利根川進博士により免疫学の命題であった免疫グロブリンやT細胞受容体の抗原認識レパートアーの多様性が明らかにされ、「自己」と「非自己」の認識機序が分子生物学的に解明されたことにより、一時期もう免疫学は終わったといわれ、免疫学会でも次の命題を模索する時代がありました。その時のブレークスルーとなったのは感染症免疫や自然免疫の最初の免疫応答の引き金を引く受容体(Toll-like receptor)と調節性T細胞の発見、そしてバイオロジックスの臨床応用でした。ただ実際の基礎免疫学のトレンドと皮膚免疫学のトレンドが必ずしも一致しないのも確かです。と言いますのも皮膚科医の興味が皮膚という臓器を中心にして起こる生命現象を理解し、感染症、腫瘍、アレルギー、老化など免疫が関与する皮膚疾患の新しい病態解析法や治療法の開発にあるからだと思います。例を挙げれば、今で言うインターロイキン1がケラチノサイトから産生されるのを最初に見つけ報告したのは皮膚科医でした。免疫活性物質が非免疫組織の構成細胞からも産生されるという発見は現在脂肪細胞が産生するアデイポサイトカインの研究に繋がるなど生命医学に大きなインパクトを与えました。またSTAT3, STAT6, NFκBなどの転写因子をターゲットにした新しい核酸医薬の臨床応用が開始されていますが、これも動物モデルの作成から皮膚科医がリーダーシップをとり、研究を進めた皮膚科発の素晴らしい成果です。
21世紀の皮膚免疫・アレルギー研究のホットポイント
「アトピー性皮膚炎」バリア機能とアレルギー:ニワトリが先か卵が先か?
アトピー性皮膚炎はIgEの過剰産生により起こるとするアレルギー説と皮膚のバリア機能異常という非アレルギー機序説の2つの学説により湿疹病変が形成されるという考え方があり、どちらが重要かという議論が続いて来ました。2006年遺伝性の角化異常症である魚鱗癬と関連すると考えられていたFilaggrinという蛋白をコードする遺伝子の異常がアトピー性皮膚炎を持つヨーロッパ人の9%に見られ、喘息発症にも密接に関連することが報告されました。結果として現在アトピーアレルギー説は少し後退し、「バリア異常先にありき」という様相を呈しております。ただTh2サイトカインがFilaggrinの発現を抑制するという論文もあり、また最初の論議に戻りつつあります。我々はこのような病態を一連の連続した異常と捉え、どちらもアトピー性皮膚炎の発症に重要であるとの考え方を報告しております。またこれは始まったばかりの新しい研究テーマですが、皮膚という末梢の臓器が中枢と同じような様々な神経伝達物質、ホルモンを産生し、いわゆる神経・内分泌・免疫の調節機構を生体の最外層で担っていることが報告されてきています。近い将来皮膚の恒常性の異常を是正することで、自己免疫疾患やアレルギー疾患の制御が可能になるかもしれません。
「接触皮膚炎」:抗原提示細胞とその責任分子は何か?
長い間接触皮膚炎の発現に表皮に分布するLangerhans細胞(LC)が抗原提示細胞として機能し、Class II分子拘束性のCD4陽性細胞が重要と考えられてきました。しかし、Class IIノックアウトマウスでむしろ皮膚反応が増強し、CD4陽性細胞はむしろ皮膚炎の発症を抑制するとの報告がなされ、さらにLangerin(CD207)遺伝子にジフテリア毒素遺伝子を組み込み、LCを消失させたマウスで逆に皮膚反応の増強が生じる事や真皮樹状細胞がLCより有効に抗原提示する、真皮樹状細胞もLangerinを発現するなど、次々と新しい報告がなされ、接触皮膚炎の抗原認識機構と合わせ,混沌とした状況になってきています。ただマウスとヒトではLCの機能や表皮への遊走機序も異なると考えられており、新しい展開が期待されています。この問題への解決策としてすでにヒト型の免疫システムで再構築されたマウスモデルが作成されており、次のステップとしてケラチノサイトや線維芽細胞、そしてリンパ組織をヒト型に置き換えたマウスを作成することで、ヒトでの生命現象をマウスで評価出来る時代も近いのではないかと考えます。我々の研究室でもそのようなアプローチを開始しております。またもうひとつの方法論としてiPS細胞を用いて、ヒト型の解析システムを構築する方法やコンピューターを用いてバーチャル細胞、バーチャル組織を作り、薬物や生体活性物質の評価を行う研究も進んでおり、今後面白そうな研究テーマが目白押しの状況かと思います。
「薬疹」:ウイルス感染症と迅速に鑑別する方法は?
手術患者に抗生剤を投与後全身に発疹が出た場合や外来で感冒様症状の患者が市販薬内服後に痒い発疹が出てきた場合など、「薬疹でしょうか?」と他科の医者から相談を受けることも良く経験します。この場合薬剤内服のタイミングや臨床症状などから原因薬を決められることが多いのですが、最終的には薬剤パッチテストやリンパ球刺激試験などの結果を見て最終判断します。ただその手技が1週間以上かかり、ウイルス感染などの関与を否定することも困難です。そのためウイルス感染と薬剤刺激で異なる活性化分子や転写シグナルなどを迅速に探索する手技の開発が望まれます。もしこのような検査が可能になれば、依頼されて24時間以内に自信を持って、この薬剤は中止して下さいと言えるようになると思います。
「乾癬」:なぜ癌に成りにくいか?
乾癬の研究は常に時代の最先端の成果、研究技術、知識を取り入れて進んできました。
かつては表皮細胞のcAMPと細胞増殖、細胞分化の研究が主体であり、その後CD4陽性細胞の重要性、最近はTh17細胞とTIP-DCの役割が大きくクローズアップされ、抗lL12.23p40抗体の素晴らしい臨床効果が明らかにされつつあります。また高知大学の佐野榮紀先生により、STAT3を標的とした新しい治療戦略が開始されつつあります。しかし私にとっては増殖スピードが桁違いに亢進している乾癬表細胞がなぜ癌になりにくいのか、なんのために、このような細胞回転の亢進が生じるかの方に興味があります。そこから癌の発生の仕組みやその制御法が見つかるのではないかといつも考えます。
「蕁麻疹」蕁麻疹はアレルギーか?
蕁麻疹の研究はアトピー性皮膚炎同様肥満細胞とIgE抗体というI型アレルギーの観点から進められてきました。しかし実際の日常診療できれいなアレルギー性の機序が証明される蕁麻疹は10〜15%程度で殆どは物理的な刺激、感染症、ストレスなどの関与が考えられる非アレルギー的な機序で生じる蕁麻疹かと思います。これは私の個人的な意見ですが膨疹反応を誘導するのはヒスタミンで良いかと思いますが、個々の患者さんで肥満細胞のヒスタミンの遊離閾値が低下していることが蕁麻疹の発症要因になっているのかと考えております。ここでもやはり神経・内分泌・免疫というキーワードが蕁麻疹の謎を解明するヒントをくれるかと考えております。特にコリン性蕁麻疹や機械性蕁麻疹などはその良いモデルになるかもしれません。
「膠原病」:皮膚科医の参加する研究は?
膠原病は最近の傾向として免疫内科、膠原病科などの内科で診断、加療されることが多くなってきています。皮膚科医は初期の皮膚病変をバイオプシーし、診断するに留まり、その後は内科で治療方針が決められ、経過を見ることも少なくなってきています。しかしながら内臓悪性腫瘍が皮膚筋炎の発症、進展にどのように関わるのか、SLEの光線過敏がどのような機序で生じるのか、強皮症の皮膚硬化とレイノー現象がどうクロストークするのか、そしてもっとも本質的な問いであるなぜ自己免疫疾患が発症する過程で臓器特異性、疾患特異性が規定されるのか、まだまだ未知のことばかりであり、皮膚科医の参画すべき分野は多いと考えます。我々の研究室でもそのような発想での研究を行っております。是非若い多くの皮膚科医がこの謎に迫って欲しいものです。
最後に多くの研究者が折にふれ述べている、研究への態度として、一つのテーマを徹底して追いかけること(継続の重要性)、現時点の知識で説明出来ないデータやネガテイヴデータを棄てないこと(そこに宝の埋もれていることは多い、臨床も然り)、アンテナを高くし、常に他分野の進歩を取り入れること(我々は臨床医であり、治療に応用できることが重要)、そして仲間と徹底的に討論すること(良いアイデアは仲間との何気ない話の中から生まれることが多いようです)などが挙げられるかと思いすし、そのような研究者にSerendipityの神様が舞い降りると信じます。是非皮膚科の臨床を徹底的に勉強し、そこから出てくる疑問を自分の手で解決していく楽しみを見つけて頂きたいと思います。
2012年
皮膚科の面白さをどう伝えるか
皮膚科の面白さをどう伝えるか
大阪大学大学院医学系研究科分子病態医学
皮膚科教授 片山一朗
前回の本稿で述べたように,今年で皮膚科医になり35年を迎えるが数ある医学分野の中で,皮膚科という,特殊な科(?)を専攻したかと,新ためて考えてみた。以下の文は私が研修医1年目に大阪大学皮膚科開講75周年に寄稿した雑文で当時の私の気持ちを書いた部分の一部の抜粋である。「私が皮膚科を選んだ理由として、学生時代,病棟実習で皮膚科をローテートした時,T先生の言われた言葉が大きな比重を占めていた様に思う。それは次の様なものである。『皮膚科というのは,他科に比べ,割と暇な時間が持てやすい,医学以外の分野に首を,つっ込む事も可能である。事実背はそういう人物が皮膚科には多かった。しかし一万で,皮膚科程未知の部分が多く残されている科は他にない諸君にやる気きえあれば,こんな奥行の深いおもしろい分野は少ない。』
1年間という短い期間ではあるが,種々の疾患を持った人々が,原因も分らないまま,対症療法に甘んじている姿を見るにつけ,この言葉が思い出きれ,何かやらなければという気にさせられる。まだ臨床経験が零に等しい私ではあるが,生体が,皮膚というキャンバスの上に,かくも多彩な表現をし得るという事も大きな驚きであった。今,皮膚科医としてスタート地点に立ったばかりの私であるが,この生体の作り出す神秘な現象の1つでも解明出来ればと考えている。そして多くの先生運に一歩でも近づく様努力したいと思う。」このような気持ちで以後多くの大学、病院で皮膚疾患を持つ患者の診療を行って来た。今あらためて皮膚科の魅力を考えてみると、皮膚科学という学問は皮膚疾患を持つ患者の発疹の観察と病歴の聴取から五感を総動員して診断し、必要なら自分で生検して,病理診断を行い、最終の最も適切な医療を選択するという自己完結型の医療を行えることある。自分で色々な文献を渉猟して、今迄にない病態を見いだした時や多くの医療施設を廻り治らなかった疾患が自分の考えた治療を行う事で、瞬く間に軽快し患者さんから感謝される時の歓びは、皮膚科医に成って本当に良かったと思う瞬間である。今も新たな治療の開発が要求される難治性の皮膚疾患は悪性黒色種などの皮膚腫瘍や強皮症などの膠原病疾患、先天性疾患など多く残され、その治療や新規治療の開発に全力を尽くしている。難治疾患とは別に、今後皮膚科医として明らかにしたい病態や治療としてシェーグレン症候群の環状紅斑がどのような機序で生じるか、尋常性白斑の色素異常を病因論に基づき、どう治すか、アトピー性皮膚炎の根本的な治療をどう行うかなどがある。白斑のガイドライン作成やアトピー性皮膚炎の疫学研究や厚労省の班研究などにも採択され、また先に挙げた難知性疾患は多くの基礎の先生方との共同研究で新規治療の開発を進めている。このような研究をとおして皮膚科の面白さを教室の若い先生方に伝えて行きたいと考えている。
2011年
次世代の皮膚科医をどう育てるか?
次世代の皮膚科医をどう育てるか?
大阪大学大学院医学系研究科分子病態医学
皮膚科教授 片山一朗
皮膚科医になり35年を迎える。昨年の東北大震災以降、医療のあり方が問われ、災害時そして現代医療の中での皮膚科医の役割が見直されている。被災地で実際に患者の診療に携わられた先生のお話を聞いたが、初期には外傷などの応急手当などの知識が要求され、少し安定した時期には皮膚の感染症、褥瘡・潰瘍の管理、アトピー性皮膚炎などの慢性疾患の治療、そして入浴が出来ない事によるカユミのコントロールなどが必要とされたそうである。薬剤や医療機器が不足する中、最善の努力を果たされ先生方には心から敬意を表するとともにあらためて現代医療の中で皮膚科医が果たすべき役割が明らかになったと考える。皮膚科診療の最も大きな特徴は皮膚科医自身が長い経験の中で身に付けた皮膚科医の眼である。視診だけで有る程度の診断を行い、血算、検尿などの簡単な臨床検査や皮膚症状以外の粘膜や爪甲の変化や詳細な病歴の聴取により正確な診断と適切な治療が選択出来る事である。このような低コスト医療が一時期医療効率を厳しく求められる中、採算性の面から厳しく問われ、実際定員の削減など大きな打撃を受けた施設も多いと思う。しかし皮膚科の外来を受診される患者さんは皮膚病以外にも多くの疾患を持たれている方も多い。主訴以外の症候から全身疾患を見つけることも多く,皮膚科医の醍醐味である。被災医療とも関連するが、多くの医師との連携が必要な疾患をもつ患者の医療で皮膚科医が果たす役割は大きく、また時にチーム医療のリーダーとしての責務を果たす場合も多い。かつて長崎大学に勤務をしていた時に、ある離島医療の病院長から皮膚科医の派遣を依頼されたことがある。その時にまだ皮膚科医としての経験が2〜3年しかないが、最も信頼できる先生(Y医師、その後M女性医師)の方に一人医長で勤務して頂いた事がある。周囲に皮膚科医が全くおらず、また充分な診療機器もなかった病院で、多くの皮膚疾患患者を診療するのみならず、患者の合併症を見いだし、他科に紹介することで病院の患者受診数を一気に増加させ、病院長から多いに感謝されたことがある。彼らの尊敬すべき点は自分が紹介した患者の検査や手術にも可能な限り参加し,皮膚科医としての意見も言われていたことで、あとから院長から聞いた話しでは、Y医師は脳外科のオペにもネーベンとして参加し、大学に戻る頃には素晴らしい皮膚科医に成長されていた。本来このような医師を育成することを目的としたスーパーローテートではあるが、残念ながら彼らのような医師は減少しているようである。先の震災での皮膚医の役割を考えた時、彼らのような医師を育成していくことが我々に要求されているのではないかとあらためて考えてる。
2011年
臨床アレルギー学は面白い
臨床アレルギー学は面白い
大阪大学大学院医学系研究科分子病態医学
皮膚科教授 片山一朗
花粉症、気管支喘息、アトピー性皮膚炎などのアレルギー疾患は国民病とも呼ばれて久しいが、患者はいまだ増加傾向にあり、その難治化や慢性化が問題となっている。皮膚科領域でもアトピー性皮膚炎、蕁麻疹、薬疹、接触皮膚炎、食物アレルギーなどあらたな病態、病因論、治療法が報告されている。
最近のトピックスとしては食物アレルギーが経皮的な感作で生じる可能性が報告され、フィラグリンの遺伝多型をもつ患者ではペット飼育、イヌではなく、ネコがアトピー性皮膚炎のリスクを高めること、そのような患者に早期のスキンケア介入を行うことで、喘息、鼻炎への進行を阻止できる可能性が報告されている。このような流れの中、21世紀となり、急速に進むグローバリゼーションと社会・医療経済・地球環境のダイナミックな変化の中に生活する患者(患者予備群)の現状に見合ったアレルギー疾患の発症と進展を防ぐ新たなプロジェクトが必要とされている。
また限られた医療資源をより効率的に活用するための医療経済学的な見地からのアレルギー疾患患者の動態や治療の実態解析も重要な検討課題と考えられるが、二つの研究を有機的に結ぶ成果は得られていない。この問題の解決のためにはアレルギー診療に関わる多くの医師やメデイカルパートナーが診療科を越え、横断的にアレルギー患者の治療経過と生活習慣・悪化因子の詳細な解析を行い、科学的な根拠に基づく生活指導と治療方針を示すことで、より効率的な医療を国民に提示していくことが必要であり、かつ重要な課題と考える。我々も大阪大学の新入生を対象としたアレルギー検診を2011年度から開始したが、彼らの生活習慣、小児期から思春期におけるアレルギー歴や治療の現状などであらたな知見が見いだされ、引き続き検討を行いたいと考えている。ただ一つ杞憂する点として、日本アレルギー学会への皮膚科医の参加が近年とみに減少していることがあげられる。連携学会である日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会では逆に参加者も増加しており、また発表内容も素晴らしい演題が増え、その成果は皮膚科関連の機関学会誌や本誌「皮膚病診療」に多くの論文が投稿されている。是非皮膚のアレルギーのプロフェッショナルである皮膚科医が他の分野の先生方とも交流し、日本のアレルギー学のレベルを上げて頂きたいと考える。今年マスコミなどでも大きく取り上げられ、患者認定などで皮膚科医が大きな役割を演じている「茶の雫石鹸」による皮膚アレルギーの問題は、そのような連携の良いモデルかと考える。時代は収益を上げる医療が巾を効かせ、利益率が低く(保険点数が低い)時間のかかるアレルギー疾患の診療は敬遠される傾向にあるが、是非若い先生方がコの分野に参入し、社会貢献のみならず新たな稼げるアレルギー診療を創出し、病院の経営改善にも貢献していただきたいと願う次第でである。
2011年
大人のいない国から
大人のいない国から
大阪大学大学院医学系研究科分子病態医学
皮膚科教授 片山一朗
本年度から秘書さんのご尽力で年報の発刊が半年早くなり、3月25日の今巻頭言を書いている。2週間前の2011年3月11日は1000年に一度の大震災が東北日本を襲った日として、日本人には消すことの出来ない記憶が長く残るものと思われる。震災当日は午後3時前に研究室の若い人と実験の打ち合わせをしていたが、何か目が回ると周りの皆さんが言い出した。私自身は何も感じなかったが、あとで知り合いの方に聞くとメニエールや脳卒中の発作かと思った方が多かったようである。
直ぐに医局のテレビを見ると、固定映像で海岸線が映し出されていたが、いつもテロップで出る各地の震度が全く画面に出ず、地震の規模も良く分からなかった。その後まもなくして大津波が防波堤を越え、家々を飲み込み、船を岸壁に押し上げる映像に変わった。その後の被害は想像を絶するもので、震度も我々が経験した阪神大震災の100数十倍の規模であったという。この原稿を書いている現在、原発事故もスリーマイル島のレベルを越えたとの報道があり、今後の動向は予測出来ないが、多くの犠牲者のご冥福を祈り、個人の出来る範囲で復興のお手伝いが出来ればと考えている。この間世界中から多くのお見舞いやサポートメールを頂き、あらためて、友人達の心遣いに感謝すると共に、世界の中での日本の占める大きさと世界の近さを再認識した。また連日、安全な場所で、一方通行の談話を述べる現民主党政府や原発関連企業トップの危機管理のなさと現場での命を省みず、復旧に頑張っておられる方々の意識レベルの差を報道で見るにつけ、我々、医療界でも同じ現象が進行していることを再認識している。
大阪大学総長の鷲田清一氏と仏文学者の内田樹師の対談の中で、「日本には高度成長期の70年代を境に子供のような精神構造の老人と大人になれない子供だけの「大人のいない国」になってしまったと述べられている。その理由として、両氏は戦後生まれが大勢を占めるようになった日本人がアメリカの傘の中で周辺諸国から隔離された、精密な機械と規則の中で自分の権利のみ主張し、義務を果たさない、あたかも子供の判断力で行動すれば完結する世界(ガラパゴス化という流行語にもたとえられる)に安住するようになった点を挙げられている。昨今の医学部学生や若くして開業していく医師を見ていると両氏の意見に賛同したくなる現実が眼の前にある。
そんな中、今年になり教室関連の会で、お二人の皮膚科名誉教授の先生にご講演をお願いした。両先生に共通したのは昔ながらの35mmスライドプロジェクターで、少し色の褪せたスライドを用いられて、御自身の基礎、臨床研究を長時間に亘り、後輩への継承を意識された情熱に溢れたお話を頂いたことである。私も含め最近の講演会はパワーポイントで作成された手の込んだスライドやアニメを用いたものが殆どであるが、多くは簡単にダウンロードが出来るようになった他人の論文からの引用やネットで集めたアンケート結果を元にした内容である。お二人の先生方の御自身で観察し、その結果を徹底的に分析し、自ら作図された図表を用いて作成されたオリジナルな論文をからのスライド写真を用いての講演との落差は大きく、まさに我々子供の世界で生きている者と、大人の社会で生き抜いて来られた両先生の凄さのあまりにも大きな差を認識した。やはり日々自身で努力して得た結果を世界に向けて問い、その中で本当に重要な本質を見抜く力を自ら身につける努力を継続し、若い次代の先生方に伝えていくことが大人になることだと考える次第である。
2010年
再考:皮膚科指導医の役割
再考:皮膚科指導医の役割
大阪大学大学院医学系研究科分子病態医学
皮膚科教授 片山一朗
藤原正彦氏の「国家の品格」がベストセラーになり、2006年度の流行語大賞に「品格」が選ばれて以降、この「品格」という言葉をキーワードとして様々な意見が飛び交うようになった。この背景には、20世紀後半から21世紀になり、本来の職業人、学生、あるいは一般の市民の持つ行動規範や社会の中で果たすべき責任や義務といった、長い歴史の中で我々日本人の中に確立したと考えられていた支柱が大きく揺らいできたことが挙げられる。
藤原先生は教鞭を執られるお茶の水女子大で、学生に新渡戸稲造の『武士道』をかわきりに内村鑑三『代表的日本人』など11冊のテキストの名著講義セミナーを開催されておられ、その中での女子大生とのやりとりを纏めた「名著講義」が昨年出版された。私自身氏が取り上げられた名著の殆どを読んでおらず、女子大生と同レベルで大きな事が言えるわけではないが、当初全く興味を示さなかった新入学生達がセミナーの進行ととともに、本来の日本人としての品格や、立ち居振る舞いを理解するようになる過程が氏の辛口のユーモアを交得た文章で、生き生きと語られている。
昨今ポリクリ学生、そして皮膚科の新人でも教科書(教本と呼べる)を持たない学生が増えており、まして英語の教科書など見たこともないと堂々と述べる学生や新人がいることに驚くことがある。とどめは「皮膚科を専攻する気はありませんから教科書は不要です」という言葉である。本来臨床医学とは長い医学の歴史の中で先人達が観察、経験し、記載・口承されてきた病態、病因、診断法、治療を現代に生きる我々が網羅的に評価・吟味し、理解することで目の前の患者の病気を治す事と理解されるが、昨今の講義にも出ず、まして教科書も持たない学生が、どのように患者を診断し、治療していくか、考えるだけで目の前が暗くなることをも多い。実際スーパーローテートや日本語での記載が要求される訴訟時代の電子カルテの開始後、皮膚科を全く勉強していないローテーターや日々の診療に追われ、じっくりと古典的な皮膚科学を勉強する時間のとれない新入医局員をどう教育するかは全国の大学、一般研修病院でも大きな問題になりつつあるかと思う。それに拍車をかけるのが専門医修得のための不完全な論文執筆後は全く論文を書かなくなる専門医(?)の増加やかつてはどこの大学にもいた使命感に燃えた皮膚科指導医の離職かと思われる。そうなると先に挙げた藤原先生の言う皮膚科の品格や皮膚科医の矜恃という最もわれわれにとって根源的な支柱を欠いた皮膚科医がどんどん世の中に増え、結果として、皮膚科不要論という、先の仕分け作業の際に問題となった皮膚科バッシングがさらに進むことが危惧される。若い皮膚科医に皮膚科学の面白さを再認識させ、他科の医者、あるいは行政、研究者と対等な議論をするためにも、ここは皮膚科指導医が藤原先生にならい学会、論文指導だけでなく、かつては良く見かけたRookやLeverの教本あるいは各責任指導者が選択した代表的な皮膚科の原著論文輪読会を再開し、正しい皮膚科学を再教育する時期にきているのかもしれない。
2010年
「コーチャン教授」の退官に寄せて
「コーチャン教授」の退官に寄せて
大阪大学大学院医学系研究科分子病態医学
皮膚科教授 片山一朗
橋本公二先生、無事退官の日を迎えられ、心よりお慶び申し上げます。
月並みな言葉ですが、愛媛大学教授、医学部長のみならず日本皮膚科学会、日本研究皮膚科学会理事長や厚生労働省研究班班長など本当に多くの激務を無事努めあげられたことおめでとうございます。素晴らしい研究の業績と共に、行政や学会運営の場でも先生は飄々とした、しかし説得力のある物言いで多くの案件の落としどころを的確に捉え、次々と解決策や新たな提案を示されることで日本の皮膚科学に大きな足跡を残されたかと思います。
先生には大阪大学皮膚科に入局以来30有余年の長きに亘り、兄貴分として公私にご指導頂き、多くの楽しい思い出を残して頂きました。特に私が研修医の頃はオーベンとして、内科で研修をされた先生から全身管理の仕方や他科とのつきあい方など多くのことを教えて頂きました。大阪大学皮膚科には当時研究室が三つあり、先生は一研で、当時流行の先端であった天疱瘡患者のHLA解析を行っておられました。今から思うと先生は常に研究のトレンドを鋭敏に嗅ぎ取る特別な能力を持っておられるようで、その後の先生の研究は皆さんご存じのとおりで、短期間の間に、愛媛大学皮膚科学教室を世界的なレベルに育てられ、表皮の分化、再生医療、重症薬剤過敏症など世界的な業績を次々と上げられ、松山の地で大きく開花したと思います。また私が所属していた二研では当時狭い部屋にピーク時10人を越す人がひしめいていましたが、部屋頭が高安進大分医大名誉教授、その下に西岡清東京医科歯科大学名誉教授、新海浤千葉大名誉教授がおられ、いつも研究のピリピリした雰囲気が立ちこめていました。そんな雰囲気も「コーチャン」(佐野榮紀高知大学教授命名?)のニックネームで呼ばれておられた橋本先生が少し徳島訛り(?)のある大阪弁とともに入ってこられた途端、一気に和やかな空気に変わり、実験などで疲れた頃には先生の登場を心待ちにしたものです。先生はコントラクトブリッジなどカードゲームが滅法強いことでも有名ですが、その頃は麻雀が主流で、時に京大の先生と遊んだことも懐かしい思い出です。またこれも遊びの話で恐縮ですが、私は学生時代からモダンジャズが好きで、ジャズ喫茶に出入りし、好きなミュージシャンのレコードなど集めていました。ある時橋本先生もジャズが好きだと言うことが分かり、一気に親近感がましました。当時の教室主宰者であった佐野榮春教授は関西では有名なオーデイオマニアで、良く先生のご自宅で素晴らしい機器でレコードを聴かせて頂きましたが、いつも橋本先生がそばにおられ、オーデイオやレコード談義で盛り上がったものです。私が東京のほうに移動し、暫くお会いしない時期があったのですが、平成7年に先生が愛媛の教授に就任された一年後の平成8年に私も長崎大学の教授に招聘され、その後は西部支部で大変お世話になりました。今は西部支部も大きく様変わりしましたがその当時は多くの怖い教授が現役でおられ、中部や東京支部とは異なる西部独特の世界がありました。そんな中でも橋本先生は大阪時代と変わらないスタイルで遊びや勉強の指導をしていただき、本当にありがたく思っております。 退官後も忙しい日々が続くかとは思いますが、また昔の時代に戻り、楽しい時間が共有できることを願っております。
2010年11月1日 大阪大学皮膚科教授 片山一朗
KISARAGI-JYUKU
KISARAGI-JYUKU
大阪大学大学院医学系研究科分子病態医学
皮膚科教授 片山一朗
今年の2月11日から13日まで、日本研究皮膚科学会主催の若手皮膚科医を対象としたセミナー「KISARAGI- JYUKU」が沖縄で開催され、我々の教室からも寺尾美香先生が参加された。大いに刺激を受けられ、モチベーションも上がったようで、御自身の研究のみでなく若手指導にも大いにその成果を発揮して頂いている。このセミナーは日本研究皮膚科学会理事長の戸倉先生の胆いりで始まったものであり、若手のチューターとの2泊3日の泊まり込みの中で各自の研究を発表し、徹底的に討論をするという企画である。免疫学会などでも同じようなセミナーがあるが、「KISARAGI- JYUKU」はチューターの講義のみでなく、自分の研究成果を英語でプレゼンし、徹底的に同じ世代の研究者と討論をする点で異なるようである。
何年か前に私が研究皮膚科学会の理事の頃、当時の理事長の島田先生に最近のJSIDは口演、ポスター発表いづれも若手が十分に討論する時間が減っているようだと話をしたことがある。島田先生は昔から免疫学会や研究皮膚科学会の熱い時代を共にした仲間で大いに盛り上がった記憶がある。私の専門分野である免疫学が大きく発展する前後の時代はワークショップとして多くの研究テーマが、若手の座長の司会で時間を超えて徹底的に討論され、大いに勉強になったものだが、ある時期から分野を少し離れると、全く理解不能の時代となり、結果として、大きな会場で少数の研究者が討論するスタイルに変貌していった。
今回参加した寺尾先生にセミナーの評価を聞いたところ、これは参加者が皮膚科の若手に限定されていたためかと思うが、自分の研究分野以外でも徹底的な討論の過程で何が重要か、どのような手法が自分の研究に取り入れられるか、そして何より同じ世代の皮膚科医が何を考え、どこに向かおうとしているかが分かり、大いに参加した意義があったと答えてくれた。
昨今若い皮膚科医の研究離れや出産を契機に皮膚科そのものから逃避していく女性医師が増えているが、少なくともこの数年の研究皮膚科学会では多くの若い先生が出題し、「KISARAGI- JYUKU」に参加して、英語で討論できる熱い研究者が育っているのは心強い限りである。新しい学会の在り方を示していただいた戸倉理事長をはじめ、チューターの先生方には心より敬意を表したい。
研究面と並んでこの数年我々の周りで問題となっているのが後期研修医の教育や先に述べた女性医師の離職をどう解決するかということである。臨床医学とは長い歴史の中で先人達が観察、経験し、記載・口承されてきた病態、病因、診断法、治療を現代に生きる我々が網羅的に評価・吟味し、理解することで目の前の患者の病気を治す事と理解される。スーパーローテートシステムの開始や日本語での記載が要求される訴訟時代の電子カルテの導入後、皮膚科を全く勉強していないローテーターや日々の診療に追われ、じっくりと古典的な皮膚科学を勉強する時間のとれない新入医局員をどう教育するかは全国の大学、一般研修病院でも大きな問題になりつつある。それに拍車をかけるのが専門医修得のための不完全な論文執筆後は全く論文を書かなくなる専門医(?)の増加やかつてはどこの大学にもいた使命感に燃えた皮膚科指導医の離職かと思われる。ここは「KISARAGI- JYUKU」に倣い、若い皮膚科指導医が専門医試験用の学会、論文指導だけでなく、本来の正しい皮膚科学を再教育する時期にきているのかもしれないと考える。
モチベーションの高い次の時代を担ってくれる医師を学会全体で育てることで、皮膚科医が皮膚という臓器のスペシャリストとして、他科の医者と対等に討論し、医療の中で大きな役割を担い、医療経済の改善に貢献していける、そして先に述べたような基礎研究を志す若い医師のモチベーションが高まると考えるのは私に限らない。医局という組織のなかで同じ釜の飯を食うことにより、生涯に亘る良き師弟関係、同僚としての強い繋がりを構築でき、結果として、良質な医療を提供できたと考える我々の世代から見ると、今後医局に属さず、後期研修を終える医師の中には、医師としての根幹部分を十分身につけることが出来ず、本来の医師としての矜恃を理解しないまま、無為な日々を送る人が出てくるのではないかと危惧する。いまや70%を超える女性皮膚科医にも医師になった頃の熱い使命感を思い出し、将来の指導者を目指して大いに奮起していただきたい。
飢餓状況における粘菌集団の行動軌跡
東京大学 澤井哲先生のホームページより
2009年
IT時代の「皮膚病診療」
IT時代の「皮膚病診療」
大阪大学大学院医学系研究科分子病態医学
皮膚科教授 片山一朗
「皮膚病診療」発刊30周年を祝し、素晴らしい本誌を読む機会を与えて続けて頂いた歴代編集者の先生方に敬意を表します。また長年adovisorの末席に加えて頂き、地方会のプログラムなどの提供で、少しは編集のお役に立てておればと思います。今回編集部から「皮膚病診療」について要望、批評をという依頼を受けましたが、一読者として今後も「皮膚病診療」が現在の編集スタイルを守られ、廃刊することなく、毎月手元に届けて頂くことを願う次第です。私自身は創刊号の「ヘルペスをめぐって」以来、毎号欠かさず読ませて頂き、折に触れ、分からない症例があればバックナンバーの論文で勉強させて頂いております。「皮膚病診療」の大きな特徴と魅力は本当に皮膚病診療の好きな編集者により全国から選ばれた症例報告が気軽に読めるという点、症例に対する読者の疑問点などが声欄に迅速に掲載される点、時宜を得た総説、対談、そして、歴代の編集者の巻頭言、編集後記などに書かれている、振り返って読むたびに得ることの多い含蓄に富んだ言葉にあるかと思います。初代の編集長であり、創刊者である安田利顕先生は発刊の辞において、「皮膚病診療」の創刊の目的を「広く皮膚病診療にあたっておられる一般医に対しての情報誌を提供することである。」と述べられておられます。この点は本当に特筆されることであり、ともすれば皮膚科という狭い世界で皮膚しか診なくなりがちな皮膚科医にたいして、全身を診ること、他の領域の進歩を常に自己の診療に取り入れることの重要さを示された安田利顕先生の先見性による偉大なご業績かと思います。最近の若い先生を見ていると、インターネットでキーワード検索した文献や書店にあふれているマニュアル本ばかり読んでいるようで皮膚病診療を購読して隅から隅まで読んでいる人は少なくなっているようです。これは私の同年代の先生方が共通して感じられていることかと思いますが、かつては普通に見られた医局あるいは同門の先輩から後輩へ脈々と受け継がれてきた教室の伝統が継承されにくい時代なったことの反映かもしれません。私が30代位までは酒の席で皮膚病診療の「○○号」にこんな症例が載っていた、あるいは巻頭言で「△△先生」がこんなことを言っておられたという話から座が一気に盛り上がり、皮膚科の話から他科の話、研究、文学の話まで夜半を過ぎても話が尽きない時代がありました。逆にいうと殆どの先生が皮膚病診療を読んでおられ、また個々の先生がそれぞれの編集者に共感を覚えて皮膚科学を勉強し、仲間と議論する過程で自分自身の独自の皮膚科学を創り、磨きをかけてこられたのかと思います。時代が移り、先に述べたような若い医者が簡単にインターネットで情報を得、EBMという名前の元にガイドラインに沿ったマニュアル医療を行わざるを得なくなった昨今の医療環境では、従来以上に手作りの香りに満ちた「皮膚病診療」の存在価値は大きくなると思いますし、指導的役割にいる皮膚科医は安田利顕先生の考えておられた皮膚病診療の意義をもう一度念頭において次の時代の皮膚科医を育てていく責任があると考えております。以前皮膚病診療の特集号で「聞き慣れない病名2005」を企画された時に、私もアンケートを書かせて頂きましたが、従来全く記載のない疾患、新しい病因の発見により名前が変わった疾患、全く同じ疾患でありながら、診療科により別名が使われている疾患などがあることなどを勉強させて頂いた記憶があります。この特集号への読者からの意見に対して西山先生が、聞き慣れない名前の病気の場合、まずシノニム(同義語)の有無ないし鑑別診断を明確にすることの重要性を巻頭言で述べておられます(皮膚病診療28: 9, 2006)。さらにシノニムの有無の確認の困難さにも言及されておられますが、よほど勉強しないと正確な診断にいたらない皮膚科学の難しさを考えさせられるとともに、皮膚病診療の面白さも再確認した次第です。話は少し脱線しますが、その中で西山先生はBurning mouth syndromeに少なくとも10種のシノニムがあると述べられています。また別の巻頭言(皮膚病診療13:671,1991)で15番目の鱗屑としてlatente Schuppenとして殿風の見えない鱗屑をあげておられますし、炎症の病因の差による紅斑の色調表現にも言及されておられます。西山先生からは北里時代「ドーム状の結節」のドームや「菌状息肉種」の病名のキノコの由来に関しても教えて頂いた記憶があります。現在「皮膚病診療」で浅井俊也先生の皮膚科トリビアが連載されており毎号楽しく読ませて頂いていますが、一度是非皮膚科トレビアの特集号を組んで頂き、皮膚病の語源や診療に関する蘊蓄を先輩の先生方に語って頂きたいと思います。最後になりますが今後も、時代とともに変化していく皮膚病診療の良質な情報を届けて頂くことを願っております。
2009年
大阪大学医学部皮膚科からのメッセージ
大阪大学医学部皮膚科からのメッセージ
大阪大学大学院医学系研究科分子病態医学
皮膚科教授 片山一朗
大阪大学皮膚科学教室は1903年櫻根孝之進初代教授による教室開講から数えまして私で7代目になる日本でも有数の伝統ある皮膚科学講座です。
教室の特徴は実学を重視していることで、私自身は難治性の皮膚疾患を持つ患者さんに対して、現時点で一番新しい、かつEBMに基づいた治療手技を提供することを目標としております。専門外来をおいて特に力を入れている疾患はアレルギー疾患(アトピー性皮膚炎、薬疹、接触皮膚炎、乾癬)、膠原病(強皮症、皮膚筋炎、シェーグレン症候群)、皮膚潰瘍、遺伝性皮膚疾患、悪性腫瘍などで、研究もこれらの疾患の病態解析と新規治療の開発を目標としており、臨床と研究が有機的に結びつき、その成果が患者さんに還元出来るよう教室員を指導しております。もうひとつの特徴はホームページをご覧になれば分かると思いますが関連病院が充実していることで、大阪府全域に亘り、かつ部長の専門性がはっきりしていることで、後期研修期間をローテートする間に様々な疾患を研修することが可能です。また学閥はなく、全国どこの大学出身でも受け入れ可能ですが原則的には最初に大阪大学皮膚科に入局して頂き、1ヶ月間の大学研修後それぞれの関連病院で研修を開始して頂いております。また女性スタッフも多く、出産、育休、職場復帰など各医師のニーズに答えられる様なシステムを構築しております。私自身は北海道大学を卒業し、大阪大学皮膚科に入局し、その後基幹病院勤務(医員)を経て、北里大学(講師)、東京医科歯科大学、(助教授)、長崎大学(教授)などで多様な勤務形態を経験し、臨床・研究の研鑽をしてきました。新しく大阪大学で研修を希望される先生方に望むことは、先ず社会人として、患者や同僚から信頼されること、多様な医療環境下で皮膚科医としての腕を磨き、その中から生まれた疑問点や新しい医療技術、治療法のヒントを大学で解決していく姿勢を持って頂きたいこと、そして、皮膚科の臨床、基礎研究を問わず、自分自身がワクワクしながら仕事に打ち込めるテーマを是非探して欲しいと言うことです。皆さんの参加をお待ちしております。
2008年
病院皮膚科が生き残るために
月刊「皮膚病診療」Vol.30, No.3
「病院皮膚科が生き残るために」
2007年11月2日開催
大阪大学大学院医学系研究科分子病態医学
皮膚科教授 片山一朗
宮地良樹先生
京都大学医学部皮膚科教授
古川福実先生
和歌山県立医科大学皮膚科教授
片山一朗先生(司会)
大阪大学大学院医学系研究科皮膚科教授
はじめに
片山 過日、“病院皮膚科医が「燃え尽きない」ために”という議題で日本皮膚科学会勤務医問題委員会が開かれました。本日はその報告を交えて同委員長を務められた宮地良樹先生と古川福実先生とともにお話を進めていきたいと思います。まず宮地先生からお願いいたします。
宮地 病院皮膚科の現状問題として、“医療崩壊”がキーワードになってくると思います。小児科や婦人科を中心に医師が疲弊して辞めていくという“立ち去りサボタージュ”がある中で、皮膚科には救急対応もなく、比較的楽な商売をしているとみられ、夜起こされない、死なない、変わらない、儲からないといくつもの“ない”があり、昔から“第4内科”といわれてきました。しかし、いま、病院勤務医が疲弊して辞めていき、研修半ばで開業する医師が非常に増えているという状況があります。大学でも教室の先生が辞めていく状況はある程度ありますが、勤務医の先生がそれほど緊迫した状況だとは思っておりませんでした。日皮会の理事会の中でも、日皮会として病院皮膚科の問題を取り上げるべきではないかという意見も出ましたので、私が委員会を立ち上げてメンバーを集め、半年間で3、4回集まって議論しました。現状分析をし、病院勤務医が疲弊せずにやりがいをもって、燃え尽きないためにどういう具体的な方策を提示できるかに焦点を絞り、具体的にまとめました(日皮会誌:117, 1399, 2007)。
地方の勤務医と都会の勤務医の現状
片山 最初の問いかけが勤務医の先生からだったということですが、大学と勤務医でかなり状況は違うと思いますし、地方と都会でもまた状況は違うかと思います。古川先生、現状はいかがでしょうか?
古川 和歌山県は京都、大阪に比べれば地方の範疇に入るとおもいます。現在、公立病院に常勤で出ているところが3つか4つあります。各先生方は一生懸命頑張っているのだけれど、収入の面、とくに一人医長は夏休みがとれない、あるいは本人が病気になったときにどうするかという問題があります。加えて和歌山県は南北に長いですから。新宮など特急で3時間ぐらいかかりますから、とくに緊急の場合にどのような応援体制を組むかという問題があります。
宮地 南北問題もあるのですね。
古川 一人医長でいろいろな苦労が累積していくと、まず身体的に疲弊していきます。また、公立病院はどこでも赤字ですから、市長さんの方針によって病院の医師の給料が下げられてしまうこともあります。ですから一人医長は身体的に辛く、なおかつ全体が赤字で給料が減らされてしまえば、やり場のない疲弊感のようなものがでてきて、しかたなく開業されていくというのが実態だと思います。
あるいは逆に2人を3人に増やそうという病院もあります。院外処方の場合、私は年間売上が1億5,000万円ぐらいになったら3人にしたいという目標を立てています。売上はせいぜい月々1,000万円でしょう。ただ、良心的に皮膚科の診療に費やしていると、1億5,000万円を算出するにはへとへとになるまで部長ががんばらなければまず続きません。なおかつ若い人を指導していると身体的に疲労で続けられないと思います。ご質問の地方と都会の違いは煎じ詰めれば病院の数の問題と入局者の数が根本にあると思います。
片山 古川先生が教授に就任されたのは新研修医制度が始まる前だと思いますが、その前後でとくに大きな変化をお感じになられますか。
古川 もともと和歌山県立医大は3カ月ごとのローテーションで内科と外科と9科を回ればあとはどこを回ってもよかったのです。制度的には卒業後3年目に入局するというのは変わりませんでしたが、新研修制度では皮膚科を回ったとしても数カ月でその時点でチョイスが減ってくるので、従来は内科や外科に行こうと思っていた人で皮膚科に興味をもってくれた人に入ってもらうという考えだったのですがそれが成り立たなくなりました。新研修医制度になってローテーターの数も減り、入局者の数もゼロではないもののかなり減りました。
片山 宮地先生、新研修医制度導入の前後で京都大学は何か変わった動きはありますか。
宮地 ありますね。京都大学でも昔は開業する先生はあまり多くありませんでしたが、最近は開業志向が強くなってきましたまた、教室への帰属意識が希薄になっている感じもいたします。何年かいて、専門医をとり、学位をとり、お礼奉公をしてから開業するという流れがある程度ありますから、かつてのようにその微妙なバランスを踏まえて、地方の病院にもやむをえず赴任する、といったしきたりはもう完璧に壊れましたね。
今回の新研修医制度が、入局者の変動も含めて病院皮膚科が廃れていく一因かと思います。くしくもそのせいで地方の病院がつぶれていくということもおこっています。
按分ルールで不利な病院皮膚科
宮地 皮膚科の収益が少ないことも大きな問題だと思います。開業医の先生はおおむね儲かっていますので、皮膚科が赤字になる構造になっているとは思えません。経営担当の副院長をしている私からみますと、病院の分析で稼働額の大きいところは儲かっているという錯覚がおこってしまうことも、儲からないといわれている一因だと思います。京大ではこのようなことがありました。高価な機械やMRベッドを購入したり、心臓血管外科や循環器内科のように非常に医療材料の高いものを使ったりした結果、請求額が上がる一方で収益は上がらなかったため、大学は心臓血管外科を一度とめたところ、全体に占める材料費の医療費率が33%ぐらい下がり、病院全体の収支が黒字になっています。このことから、儲かっていないといわれる一因に按分ルールがあると考えられます。皮膚科は高価なMRやCTはあまり使わないのに、設備投資が全科で按分されるため、計算上不利になっているのです。
勤務医と開業医の住み分けを
宮地 また、病院皮膚科に適した治療体系を生かし、common diseaseは開業医の先生にお任せして“住み分け”する必要があると思います。入院が必要な急性疾患としての蜂窩織炎や帯状疱疹、膠原病や、技術が必要な皮膚外科など、単なる薬物依存治療ではないもので病院皮膚科に適したものを受け入れることによって収益を上げることが重要だと思います。現在の勤務医の外来体系では、実地医科の先生と同じようなcommon diseaseを診ているような気がしますが、湿疹やみずむしなど病気をただ診て薬を処方するという薬物依存の治療ではあまり収益につながらないのではないでしょうか。
また、一般的には収益は外来15人分で入院1人分といわれています。だから15人診るよりは1人入院させたほうがペイするわけです。つまり、収益の点からいえば、100人外来で診るよりは、5人入院させたほうがいいという話になります。今後の病院皮膚科は一般の実地医科の先生との住み分けを明確にして、common diseaseであれば紹介されても返し、入院へのシフトを図るほうがよいでしょう。
片山 皮膚科では開業医の先生が提供できる医療と、勤務医あるいは大学でないと提供できない医療が区別しにくい部分があります。京大が膠原病や、外科的な手術でかなり収入を得ておられるように、今後は病院皮膚科と開業医の先生との役割を区別し、住み分けることになると思います。
宮地 Common disease以上であったら病院に行ってもらうようにして、開業医の先生はご自分がたとえばアレルギーなどのサブスペシャリティをもっていたら、それを発揮していいと思います。
それに対して、病院はcommon diseaseの患者さんが開業医から紹介されてきたら、きちんと説明して逆紹介で返して、外来をむやみに増やさず、病院皮膚科に適した患者さんだけを診るようにするとよいと思います。紹介状をもってくる患者さんのほうがそうでない患者さんの3倍くらい入院につながる可能性が高いのです。病院皮膚科は入院につながる患者さんを診るというのが私は原則だと思います。そうでなかったら実地医科の先生にお願いしていいわけです。このとき、受け皿の勤務医はきちんとしたスキルをもたなければいけません。トレーニングによって手術がきるようにしておいたり、膠原病を診られるようにしたり、一味違うものをトレーニングするようにするのが望ましいでしょう。手術はしないという大学もあったり、膠原病は内科医に回すところもありますが、それらは病院皮膚科がある程度コミットすべきであり、また、そうしなければ、薬物依存の湿疹、みずむししか診れない医者になりかねません。教育ができていないことが開業医との差別化ができていない一つの背景にあると私は思います。
皮膚科学会のほうで(?を)立ち上げましたが、日臨皮にも申し入れて江藤隆史先生が担当理事になって一定のリスクを担保してほしいことや、どういった患者さんを病院に紹介したらいいかという指針を出すとおっしゃっています。
それから今後、来年4月の第107回日皮会総会でもシンポジウムをいたしますし、秋の支部総会でも病院皮膚科の問題点をテーマにしてワークショップやシンポジウムを組み、病院が崩壊したら開業医もつぶれるという危機感を共有し、住み分けていくことがお互いが燃え尽きないようになる秘訣であると、呼びかけていきたいと思います。
今後、たとえば韓国のように、湿疹、みずむしの薬がすべてOTCにスイッチされることはありうると思います。すると、韓国同様、ほとんど処方しているだけで処置しない開業医は経営が破綻します。病院にcommon diseaseは開業医に返しなさいといったら医療経済上は行政としては金がかからないわけですが、そうなったときの対処法を考えておかなければ、8割の開業医はつぶれると思います。韓国の開業医は美容と外科に移行したようです。アメリカも一時そうでした。勤務医の問題だけではなく、皮膚科全体の問題として危機感をもつべき事柄だと思います。
また今回の勤務医問題委員会では、実地医科の先生は、合併症もトラブルもない急性患者を診てパッと治すのがいちばん収益が上がるようになっているいまの保険体制が問題だという意見がありました。帯状疱疹でも少しでもリスクがあると病院に紹介するというのが、開業医の最近の傾向です。病院勤務医のもとには医師の説明不足で不満のある患者さんや「診断が違っている」、「治らない」といった患者さんが流れてきます。外来で時間を使って説明をしても全然収益にならずトラブルの後始末ばかりさせられているきらいもあります。その一方、開業医はリスクのない患者だけを診て収益を上げるという構造になっています。こういった図式がある中で、開業医の先生も後方支援病院としての病院があるからこそ外来診療ができているのですから、そこを支えるという認識をもって、応分のリスク負担をしていただきたいものです。お互いに住み分けて支えていかないと共倒れになるだろうと思います。
反対に勤務医がどんどん開業に流れたら、開業医は飽和します。2007年、私のいる京都市左京区で7人ほど開業したそうです。地方や過疎地では開業医は非常に流行っていますが、飽和状態の都会では開業医の中の食いつぶしもおこると思うので、開業医の先生には医療制度の中での構造をよく見据えて住み分けることにご理解いたきだきいですね。
格差問題を解決してマンパワーを増やす
片山 病院の診療をいかに効率よくするかということは大きな問題になっています。近年、重症でリスクの多い患者さんが大学、あるいは基幹病院に集まる傾向が非常に強くなってきたのですが、そこで一番問題なのはマンパワーです。私が長崎大学にいたときも関連病院ではだいたい一人医長でかなりの病気に対応していたのですが、いまは本来の医療以外の問題でリスク管理の時間のかかる患者さんが増えています。そうなると物理的な面に加え、もっと問題なのはメンタルにかなり疲弊している若い先生たちが増えてきていることです。実際、阪大でも何人かの先生が、そういった患者さんの対応でかなり燃え尽きてしまう傾向がみられました。病診連携、あるいは病病連携にもつながりますし、マンパワーをいかに増やすかという戦略的な問題も解決していかなければならないでしょう。宮地先生がおっしゃったように医療効率をうまくやればさらに1人か2人ぐらい雇ってくれる資金は病院にあると思うのですが、古川先生はマンパワーの戦略について何かお考えをおもちですか。
古川 少々話がそれるかもしれませんが、大学間格差をなくしていくことも1つの方法だと思います。都会の大学と地方の大学では入局者の数が違い、京大、阪大では毎年10人以上入局しているという話も聞きます。地方大学は、たとえば和歌山であれば平均して1人とかゼロとか2人です。ところが実際、地方の大学といえども入局者が1人か2人ではたまらないですよね。日皮会としてやはり地域の配分、皮膚科への配分を考えていただきたいという思いがあります。
宮地 古川先生がおっしゃった格差問題に関しては違う意味で以前、日皮会の理事会でも問題になりました。いまの制度では、たとえば一人専門医の専門医の認定施設に1人で行った場合、極端な話、まったく手術しない先生であっても5年いて試験さえ通れば専門医が取れてしまいます。しかし、やはりある程度大きなレベルも小さなレベルも経験しないと専門医として無理があるのではないでしょうか。たとえば眼科の学会では、専門医制度の中に大学病院での研修を1年義務づけています。皮膚科でもやはり最初にエクスポーズされるものが湿疹、みずむしだけ診るような病院ではなく、膠原病も悪性腫瘍もある大学でエクスポーズされてこないと、やはりよくない。そういった経験を義務づけることに意義があると思います。
もう1つは、1つの大学があまりたくさん採用しないほうがいいと思います。アメリカでも3人2人くらいしか取りません。いい大学はコンペティションの100倍になっているでしょう。トレーニング、指導できる人数というのはおのずと限界がありますから、総数によっていろいろな研修に行くようにするという現状のシステムを今後変えていくべきだと思います。
もう1つは地方に行かれる医師に関しても、いま、一番の解決方法は専門医制度の中に1年間、一人医長のように地域病院の皮膚科の研修を義務づけるようにすることだと思います。
マンパワーを病院に集約させる
古川 一人医長のところは病院長と交渉して、将来2人にしてくれるならば残すけれど、1人のままでいいというのであれば引き揚げます、というように、集約化を図ることでもマンパワーを増強できると思います。
先ほど宮地先生がおっしゃいましたが、昔は何年かいて専門医をとり、学位をとり、お礼奉公をしてそれから開業するという流れがありました。新研修制度でそれがなくなってしまったいま、希望者がいない、従えない、あるいは一人医長のままで病院がいいというのであれば、Bという病院は2人でいいですよといってくれているからそちらに集約しますと、決断するようになりました。
宮地 この問題はやはり非常に重要で、集約することによって皮膚科の診療の質も高められ、医師の休みも取れるようになり、2人以上いればお互いに刺激にもなりますし、大学にも勉強にも来られるメリットがあります。森田明理先生の実例では1人のところを2人にすることによって入院を増やせて、収入が2人分以上になったというデータを出して病院長に交渉したという実績があります。1人で疲弊するのではなく、2人でやれば相乗効果があります。京大も基本的には一人医長は解消する方向でいま動いてはいます。
また、先ほどお話した按分ルール以外にも、皮膚科の病院内での果たしている役割をアピールするべきです。他科からの依頼を受けるといった収益の上がらないところで貢献したり、薬疹を診たり褥瘡対策をしたりして貢献していることを、大学側は病院に対して主張することも重要だと私は思います。
女性医師の応援態勢
片山 私が長崎大にいたときに、もうすでに教室の女性医師のお産後の職場復帰はかなりむずかしくなっておりました。その当時、ワークシェアリングやフレックスタイム制導入である程度うまくいっていたのですが、女性医師がいかに職場復帰するかということがまずマンパワーの一番大きな問題かという感じがしています。
古川 和歌山医大でも女性の医師が増えて、マンパワーの調整に苦慮しております。医局14人中6対8で女性が多く、いま現在3人が産休です。なんとかしてあげたいのですが、入局者が多くないとだめな一方、入局者が多くなってくると定員の問題でどこに置いておくか…というジレンマが常にあります。大学院が一番よいのでしょうけれど、そのような若い人は研究を希望しない、という堂々巡りで完全に閉塞状況です。
片山 従来は非常勤のポストがあるためにうまく人事交流ができていたと思いますが、新臨床研修医制度が始まってから、非常勤の定員が大学で制限されて人事交流が不自由になったのは大きな変化です。京都大学での定員はいかがでしょうか。
宮地 昔はいくらでも採用できましたが、いまは5、6人です。それをオーバーする場合には半年交替するなど工夫しています。
いま4割の医学生が女性ですから将来は半分になってもおかしくないわけで、すでに半分以上が女性である皮膚科はウーマンパワーを生かし、フレックスタイムや大学病院を利用して妊娠・出産後に復帰できる体制を整えることをもっと考えるべきでしょう。私のところでも確かにいまでも数人、そういう人がいますし、実際に戻ってくる先生も何人もいますから、そのようなロールモデルをつくるのも大切でしょう。たとえば、なかなか復帰できない場合には最初からパートで来てもらったり、なおかつそういった人材をプールして何人かで回して自分がちょうど子どもが熱を出して行けない日は違う人が代行するようにするといった手段を講じるなど、ウーマンパワーを活用することを真剣に考えないといけないと思います。
片山 従来、女性の出産育児を医局全体でカバーしていた部分があるかと思いますが、ここ2年以内に入った女性医師の何人かに聞いてみたところ、スーパーローテートが始まって一人ひとりがかなり孤立している感じが全国の病院でみられます。横の連携がかなり希薄になっているという証で、是否があるかと思いますが、崩壊してきている昔の医局全体で人を育てるというシステムをもう一度復帰させるのも1つの方法ではないかという気がします。またこれも現場の声と行政の間で乖離が見られる点かと思いますが、余り女性医師支援が過ぎると、今度は逆に男性医師のモチベーションの低下や、診療内容の偏りなどにより、勤務医全体の存在基盤が危うくなるかと危惧しています。
DPC導入の影響
片山 少し話が出ましたが、次に病院の中での皮膚科の位置づけについてです。ある関連病院の院長さんから「皮膚科はなんぼ儲けても知れているから、そんなに稼がんでよろしい」といわれました。皮膚科が稼ぐ分は他の大きな科でカバーしているから、それよりも病院の中での皮膚科の存在感を示すほうがよほど重要であると思います。その院長の先生からはもしそうであれば定員ぐらい、ある程度増やしてあげるし、非常勤であればもう別に人数制限しないということをおっしゃっていただいています。院長が外科系か内科系かで考えが変わってくると思うのですが、そういう考え方もあります。
宮地 医療の質を上げたり、勤務医は保険制度をもっと知るべきですね。大学でそういったトレーニングを受けないことがよくないでしょう。
片山 私もそう思います。
宮地 病院の経営のほうをやっていると、皮膚科に限らずDPCのコーディングだけでも多くの体系が変わります。もちろん自分の皮膚科医療のミッションは変えるべきではありませんが、外泊の日数を減らしたら1億円損失になることや、保険制度の適用を知るなど、少しの心遣いで収益が上がるということはいくらでもあるのです。皮膚科医も病院の中の1つの診療科として、稼ぐときは稼ぐという姿勢が存在意義を示すことになり、それによっていろいろな機器を買うこともできるわけです。
片山 DPCということでいいますと、関連病院でも、ここ数年でかなりDPCが導入されてきて、いろいろな問題が出てきているようです。従来のクリニカルパスどおりではDPCがあって赤字になるところもありますし、ジェネリック医薬品に切り替えて赤字を減らしている病院もあったり、病院の方針として先発品のままで赤字になっているところもまだ比較的残っていて、結果として病院医療が縮小していかざるをえないというようなことがあります。
宮地 私のところでは今度DPCのコーディング専用に医師を配置することにしております。DPCでは外科系の手術などをした場合には、手術をしてなるべく合併症なしに早く退院するほうが収益が上がる構造になっていますよね。逆に抗がん剤などの高価な薬品、あるいは生物製剤を使うと即赤字になりますから、それを解消するには数日間入院してもらう必要があります。また、皮膚科であればたとえば特定保険医療材料やドレッシング剤、それにガーゼ1つにしてもコストがかかっているという感覚をもつことが大切です。われわれが知るべきことですし、開業されたらもっと熱心にやるのではないでしょうか。勤務医はコスト意識にいままで無頓着でしたが、医療の質を変えることなくいまの医療制度の中で生き残れるかということを知ることは非常に大事です。
ホームページの活用
片山 和歌山医大では古川先生が膠原病、全身疾患をかなり前面に出されていますし、准教授の山本有紀先生も積極的に手術をされることを公表されていますので、和歌山の皮膚科開業医の先生にとってどのような患者さんを和歌山医大に送るか決めやすくてわかりやすいと思います。
全国的にみると各大学でどのような医療を行っているかわからないことが比較的多いですね。そこで専門外来などでホームページを充実させて、アウトカムがこれぐらいだと開業の先生などに情報提供し、病診連携を図るというのはいかがでしょうか。
古川先生はさらに何か具体的にやられているのですか。
古川 和歌山市は40万都市で大学病院と日赤病院と労災病院の3つしかなく、皮膚科である勤務医、病院の絶対数が足りないので和歌山医大では紹介患者の半分はほぼ他科からのものです。皮膚科の開業医の先生方には和歌山医大の特徴をある程度理解していただいておりますが、小児科や内科との連携においては当科の特徴をアピールすることは非常に重要で、当初私は大学病院だから京都大学や大阪大学のように“いい百貨店”を目指そうと思ったのです。ところが7、8年経ってみると地理的な状況、それからマンパワーの問題、財政的な問題、独法化した後の問題を考えると、百貨店にはなりえないことを実感しています。そこで、いくつかの専門店を併せた特徴ある病院、皮膚科として、皮膚外科と膠原病と美容の3本柱を立てました。皮膚科の先生からはある程度理解されていますが、特化した場合は、片山先生にも宮地先生にもお越しいただいたことがありましたように、他の領域は講師の方を招いた勉強会でスキルアップしていくしかないと思っています。
いずれにしても皮膚外科、皮膚悪性腫瘍、膠原病の医師を育てるのは非常に時間がかかって、第2、第3のサブスペシャリティをもった医師を簡単に養成できるかというと、なかなかむずかしいところがありますよね。ですから専門店がいくつか集まった皮膚科にしようと思っているのですが、まだ途上です。
また、ホームページについてはとにかく見てくれる人が何人かいるだろうという想定のもとに、私が毎月更新しています。
宮地 先生が更新されているのですか。
古川 はい。
片山 若い先生によると、教授のポリシーがはっきりしているところに、ある程度シンパシーを感じている人が多いですし、ホームページというのはその際の重要な情報源になるようです。
医療事故対策・危機管理のシステムづくり
片山 話題を次に移します。大阪では地域柄なかなか対応のむずかしい患者さんが多く、基幹病院に集まってきます。皮膚科に限らず、どの科の先生の間でもかなり問題になっています。先ほど申し上げたように、医師がかなりメンタル面で追い詰められる例があり、大阪大学病院の場合、すぐに病院の弁護士さんに相談するシステムを2006年から導入し、医療問題として対処するようになりました。
宮地 京都大学でも行っています。
片山 その結果、大学としてはある程度よくなってきましたが、基幹病院ではまだまだ弁護士に相談できる体制ができていないようです。それに対応する一つの手段として、アレルギー学会の西間馨理事長が医療訴訟などの問題があった際に会員が相談できる窓口をつくりました。大阪大学病院では、若い先生が患者さんにクレームをつけられて、看護師が患者さんに殴られたという事例がありましたが、そういった際の対応の相談をできずにいるような状況が積み重なると、疲弊して辞めていくという先ほどの“立ち去りサボタージュ”が発生するようになっていくと思います。
病院として、大学はおそらく危機管理マニュアルはしっかりしてきていると思いますが、関連病院のレベルで宮地先生のところはいかがですか。
宮地 大学は確かに医長などがいますが、京大ではそういった場合に対応する弁護士もいてマニュアルが全部整っており、トラブルをおこした場合には、診療拒否まで行っています。
片山 そうですか。
宮地 医師の立場が上にあり、患者さんにいうことを聞きなさいという時代があり、徐々に患者さんの地位が向上してきて患者さんが意見をいえるようになったことはいいことだと思うのですが、対等になって、いまでは「患者様」と呼ぶほど逆転している時代です。京都大学病院では患者様と呼ぶのはやめています。
古川 和歌山県医大もやめています。
宮地 情報を共有して対等であるべきものが必要以上の権利意識をもって、「自分はお客さんだ」というのはおかしいと思います。そういう患者さんには毅然とした態度を取るべきでしょう。明らかに理不尽な主張もあります。ただ、いま片山先生がおっしゃったように病院のレベルではまだ対応は遅れているのでしょうね。私のところでは病院で問題があった場合にも大学にまで相談に来ます。良し悪しはさておき、大学はいまだに権威が残っており、権威を背景にしてそのような患者さんに説明すると納得するというところもあります。しかし、開業医の先生の説明不足を病院皮膚科医が補っている面もあるし、病院皮膚科医や専門医の不十分な点を大学が補っている面もあるでしょう。そのような構造で支えあっていくのはよいことですから、病院でもそういうシステムをつくってほしいと思いますけどね。
片山 和歌山もそういうシステムですか。
古川 同じですね。病院でも医長になる人が年齢的にも経験的にもキャリアがあればなんとか吸収してくれるし、病院の事務との折衝もやりますが、医長が若い場合はどうしていいかわからないので戸惑うことが多々あります。そういう場合は大学を紹介します。大学の存在価値の一端がそこにありますから。
宮地 そのようなトラブルに対処するとき、一人医長の場合は後がないので追い詰められることになるでしょう。集約化して、1科に2人いれば相談もできますし、目にみえないところでも効果があると思います。
片山 つい最近、医療事故調査委員会を国が立ち上げて、医者の医療事故や過失が刑罰になるかどうか検討するシステムをつくろうとしていますね。
福島の産婦人科が逮捕された件がありましたが、実際に本来、医師は医療でトラブルがおこった場合、刑事罰になる確率が2割ですか。
宮地 そうですね。これは日本の傾向で、アメリカではそういうことがありません。
片山 逆ですか。
宮地 ええ。事故の予防のためには刑事罰をやってもなんの意味もないという考え方です。どうしたら事故をおこさないかのほうが大事です。「刑事罰があるなら何もしないのが一番いい」となってしまいます。手術しなければ手術の事故はおこらない、だから本当は手術したいと思うけれどやめておこう、というように、どんどんわれわれは防御的になりますよね。いまそういうベクトルが働きつつあります。これは患者さんにとって不幸だと思います。
古川 患者さんに全部情報公開をして「医師を選んでください」となるわけでしょう。ただ、患者さんが選ぶのはむずかしいと思います。
片山 宮地先生のお話は非常に好意的にとらえるからそうなのですが、逆の見方でいうと、裁判で判例が決まれば、その判例に従って次々と決まっていくでしょう。
宮地 そうですね。とんでもない判例がずいぶんあります。
片山 皮膚科だけでも、事例と対応を学会レベルで集積した対応マニュアルをつくらないといけないでしょう。
宮地 そうですね。学会ではまだそこまでやっていないですね。でもそれもサポートの一つでしょうね。このままでは医療がどんどん萎縮していきます。患者さんにとって不幸だと思います。日臨皮はまだ弁護しがあるかもしれませんが今後、苦言を呈しても、日臨皮はそれほど反応しなかったですから少し強調していこうと思っています。その開業医の先生に対してはいまいったリスクを負担することもありますし、社会の中の皮膚科の存在意義ということを考えると、在宅の患者さんを診たり往診したり、あるいは学校保健に参加するなどの方法があると思います。
片山 大阪ではかなりそういう活動は盛んですね。
宮地 そういうサンプルをみて、いまはともすると1日100人患者を診ていれば儲かるし、何かトラブルがあったらすぐどこかへ回すという発想の人が少なくないと思います。それだけでは皮膚科全体まで行き詰るということを理解してもらわなければ、いまのままでは実地医科も崩壊すると思います。社会に対して皮膚科の存在意義を示すのが実地医科の先生の役割でもあると思います。
大学と病院の関係
片山 次に、かなり研究離れになってきている大学の問題についてです。大阪大学でも先ほど十何人入るという話がありましたが、ほとんどが研究志向ではありません。臨床医を目指したいという方が多くて、本当に何のために医師になったかわからないような人が増えてきたと思います。京都大学の場合、逆にかなり昔から研究志向でどんどんいい仕事をされたと思いますが、宮地先生いかがでしょうか。
宮地 そうですね。京大ではたくさん採りましたが、やはり同じ傾向は窺えますから私は来年からは少しずつ京大も教育する方針に変えていきたいと思っています。確かになかなかたくさん教育できない面もあるので、研究志向の人優先とまではいかなくても、厳選してしっかり教育できるような医師を増やすよう、少しずつシフトしていきたいと思います。
ある先生が「大阪大学に入局すると田舎はないけれど京都大学に行くと田舎に赴任させられる」といわれたらしいです。日本海のほう、福井、豊岡、小野の病院に派遣すると多くが辞めていきます。女性の医師が増えて、家庭があったり旦那さんの都合があったりすると、辞めます。だから私のところでも和歌山の南北問題ではないけれど、今後は撤退する病院も出てくると思います。結局、近畿一円に集約するようになり、そうなると転勤の必要がなくなり出産後も戻りやすくなります。昔、グループで支えられるというので、京大は小倉、島根まで送っていましたが、すでに小倉は撤退して2007年いっぱいで島根も止めます。その次は日本海となっていくわけです。
古川 それはよくないですね。
宮地 なんらかの制度的な方策を施してもらわないと、もう限界です。もう1人、ある病院に赴任させて、2人ぐらい辞めて1組で3人ぐらい失いますから。そうなったら撤退するよりしかたがありません。さきほどの専門医の条件でいえば、1年間の地域の病院赴任を全部の学科が必須にしたら解決すると思います。
片山 昔、京都大学で今村貞夫先生が博士論文と専門医の論文を1つずつ書きなさいとおっしゃいましたね。
宮地 今村先生は学位は英文論文2編書くようにといって厳しかったですね。しかしいま、専門医をとるのが大事です。じわじわと医療崩壊が婦人科や小児科のように皮膚科の領域に押し寄せていますが未然に防ぎたいところです。それぞれの職域で、勤務医だけではなくて開業の先生も大学の先生も同じように危機感教育は大事だろうと問題提起をしているわけですが、今後どのようにしてこれを数年かけて生かしていくかということが問われています。
片山 私自身、今後女性医師には出産、育児の期間に比較的自由のきく大学院に行き、そこである程度の期間研究に従事するように指導しております。もちろん現時点では彼女達は臨床研修と専門医取得の方が関心が高く、研究への意欲は低いのですが、基礎の教授達と連携して、研究の楽しさをアピール出来る機会を多く提供できるようにしています。また大阪大学でも今年から社会人大学院を導入し、保育所などの設備も拡充しております。長い目でみるとやはり若いときに何かに打ち込み、成果として論文まで発表している先生は開業されても、指導的な立場で活躍されているようですし、皮膚科の診療に関しても問題意識をもたれている先生が多いようです。
皮膚科の存在意義をアピールするには
片山 最近の傾向として、若い人は3Kを避けて儲かるから皮膚科を選択する率が高いということがよくマスコミで出てきます。他科からも、われわれはこれだけたいへんな目にあっているのに一方で皮膚科は…という認識でとらえられています。開業医のみならず、勤務医に対しても他科からのバッシングがかなり強くなりつつあるのではないかと思います。そうなると病院の中のポジショニングにも良い影響を与えないでしょう。われわれはいかにそういったことに反撃していくかも考えていく必要があると思います。
宮地 それには病院で皮膚科の専門性を発揮することでしょう。いま、昔とは変容してきている大学病院や病院勤務の実態をアピールすることが欠けているのではないでしょうか。皮膚科は非常にシャイな人が多いとは思いますが。
片山 宮地先生と古川先生はアピールがお上手と思うのですが、その点いかがですか。
古川 病院の中で、その部署の中で発言して「あの人は怒らせると怖い」というぐらいに病院側に思わせないと、どんどん軽くみられて不利になります。確かに病院長の立場からいうと皮膚科は売上は少ないですし、9時5時とはいわないまでも他の科に比べると夜中に脳外や麻酔科が緊急手術をやっているようなことが基本的にはない。そういう切り口でどんどん責められておとなしくきいているだけだとすぐ外堀を埋められてしまう。そういうときに反論するだけの自分の城の実力と、存在感を常にアピールすることです。とっさにいわれたときに切り返すだけの根性がないと、やはり皮膚科はつぶれるので、皮膚科の教授もそろそろバーンアウトしてしまうという時代なのでしょうか。日々戦場みたいなところはありませんか。副院長の宮地先生はいかがですか。
宮地 経営上はさきほど申しましたように稼働額にみな惑わされています。種類とは全然違うのだということを図らずも今回、京都大学は露呈しました。非常に赤字だというのがなぜこれほど黒字になったか。心臓血管外科をやめたことも大きな要因ですが、さきほどの按分ルールや稼働額ではないのだということを主張すべきでしょう。やはり皮膚科は皮膚科で患者だけでなくて医師のアメニティ、QOLも大事だと思います。それを尊重する人が皮膚科に来るのは全然問題ないと思います。
また、手術が好きで、朝から昼まで走り回って酒を飲んで寝ようというのが外科系のイメージの1つにあると思います。そうではなく、私生活も大事にして、医師は内科というのもやりながら楽しみながら、仕事が終わったら自分の私生活もアメニティも大切にするというのは大事でしょう。
古川 しかし、病院全体で100人入局してたとえば1/3くらい皮膚科にいくという状況はいかがなものかというのもわかる気がします。
宮地 そうですね。2006年、確か形成外科が一番伸び率が高くて皮膚科も多かったでしょう。京大でも2006年の入局した百何人のうち形成と皮膚科だけで3割ぐらいを占めました。外科などは3人しか入りませんでした。これはいかがなものか。ですから少しうちも減らして厳選しましょうという動きになりました。
古川 大勢入ること自体はいいと思いますが悪性腫瘍を診られたり、ケモができ、手術ができる、膠原病をきちんとほとんどできるようないい医師を育てていただき、地方に回していただければいいのです。
片山 結局大勢入ってもどれだけきちんと教育ができるかということにかかってくると思いますね。阪大でも中途半端な皮膚科医が増えて、それが首を絞めていくみたいな状況です。
古川 そうですね。結局、湿疹、みずむししか診れない医師になりますよね。
宮地 将来的に1大学3人に絞るようにしたら、いろいろなところに赴任してもらえるようになるでしょう。
古川 将来といわず次年からそうしてください。
宮地 3人に絞って、その代わり専門医を置くようにして、明らかな差別化をしていけば、自分たちの職域を護ることになり、質の高い医師を養成することにつながります。前向きに検討したらいいと思います。3人ずつ採っても全国87大学で約260人、十分じゃないですか。
古川 地方の私のところは1人2人しか入らないですが、いままでなんとかやれているのは、途中で辞める人がほとんどいなかったからです。1人入っても3人辞めて、2人減っていたらもう立ち行きません。
片山 いえ、そんなことはないと思います。いまの都会に集まっている人は、そのうち全部ゼロに近くなってくると思いますね。
宮地 というのも都会志向の人はみな、東京は人口が多くて、東京出身だから東京に帰りたいということですし、次はブランド志向です。東大医科歯科系は行きたい、となるわけですよ。そのような格差があるのが現状です。地域の格差、診療科の格差、男女格差。まさに格差社会ですよ。そこを皮膚科の中でもいろいろ検討することが必要でしょう。
片山 つまり、きちんとした皮膚科医を医局、あるいは皮膚科学会全体で育てていくという形にならざるをえないと思いますし、先ほど宮地先生がおっしゃった開業医の先生とも決して敵対関係ではなくて、うまく教育するための医局が必要になってきます。
皮膚科専門医による美容皮膚科
片山 いま、美容皮膚科を希望されている方が多いですね。古川先生はいかがお考えですか。
古川 私は大学で美容皮膚科関係のことをやっていますので、研修医からの問い合わせは多いのですが、その段階で、少なくとも皮膚科専門医の資格を取るまでは外科もやっていただくし、褥瘡、潰瘍、火傷もやっていただき、先のことはその後に相談します。
最初から美容だけというのはありえないでしょうというふうにいっておりますが、そういう方は私のところにはほとんど来ません。それは私の大学でのあり方なのですが、ただ一般美容皮膚科というのはいま2,000人を超えるような状況にあって、日本皮膚科学会の傘下の団体では一番大きいですよね。そのなかでタイミングよく、日本皮膚科学会の専門医の上に指導専門医、日本皮膚科学会美容皮膚科・レーザー指導専門医をつくり、きちんと皮膚科のことを勉強して、皮膚病の診断がきちんとできる人でないと認めないという制度はつくっています。
宮地 皮膚科専門医を通った人にしか美容の専門医を与えないと強調するのは大事なことで、たとえば形成外科学会の講義を受けましたけれど、形成外科医とか非専門医は美容の専門医を取れません。ですから美容皮膚科専門医と名前がついて美容外科専門医は取れるのは当然のことであり、それによってわれわれは自分たちのスペシャリティを護る。場合によってはもっと標榜制度に対しても介入すべきだと思いますよ。専門医制度ももちろんもつべきです。
今後は社会の目がもっと厳しくなってくれば、患者さんは医師を選択するのに美容皮膚科専門医をもっているかどうか判断基準にするでしょう。そのときにいまの制度でいけば皮膚科専門医以外はなれませんからね。形成外科医もなれないですし。いまははそういう過渡期です。淘汰されるべきだと思うし、商売がうまい人はやるでしょうけれど、基本的には美容皮膚科専門医というのは評判がよくないものです。理事会で絶対に守るべきだといっています。
片山 そういう現状がありますね。医科審議会は医師でない人がやっているわけでしょう。それが一番大きな問題ですね。
古川 これは日皮会、日臨皮というレベルあるいは日本美容皮膚科学会で解決できることでしょう。
宮地 皮膚科学会の中にもそういう保険のことをやっている人がいますので、学会としてもいまの専門医の標榜制度を護ったり、あるいはロビー活動をして点数を上げたりするようにしてはいかがでしょうか。眼科の臨眼というのは学会が護ろうとして、それをロビー活動に使っていますね。米国でも同様で、乾癬の患者さんは人口の2%いるので、上院議員2人落とせるくらいのものすごい圧力団体になりうる。
片山 すごいらしいですね。
宮地 政治を動かせるすごいパワーなんですよ。眼科の点数が高いのは、ひとえにロビー活動の効果だと思います。だから皮膚科学会もそういうロビー活動を介して護るということをしないといけないでしょう。ロビー活動は皮膚科医を護る1つの手段ですね。
古川 日皮会で美容の制度をつくってもらったら、皮膚科学会あるいは日本臨床皮膚外科学会が学会の質を各傘下の会がレベルを上げるようにしないといけないでしょう。ランチョンセミナー、特別講義、シンポジウムなど、美容皮膚科学会は日本臨床皮膚科学会のレベルをやはり上げていかないといけないだろうし、美容関係でも割合学位を出して、その後1年ぐらいは臨床を経験させますからね。
テーマは与えようによってはあるので、やっている立場、レベルを上げさせる。また、われわれのような世代では傘下の学会のクオリティを上げるように、ときには強圧的な手段もとってシェイプアップし、きちんとレベルアップしていかないといけないのだろうと思っております。
片山 ぜひそのあたりはお願いしたいと思います。あと数年したら自然淘汰で落ち着くところに落ち着いていくとは思うのですが、それまでの過程でまた問題が出てくると思うので、ぜひよろしくお願いします。
本日はどうもありがとうございました。これで座談会を終わりにしたいと思います。
出典・許諾(©協和企画)
『皮膚病診療』 Vol.30,p.331,2008
座談会「病院皮膚科が生き残るために」
2007年
皮膚科医の矜恃
皮膚科医の矜恃
大阪大学大学院医学系研究科分子病態医学
皮膚科教授 片山一朗
今年から年報の発刊時期が早くなるとのことで、ゴールデンウィーク前に巻頭言を書くことになり、皮膚科を取り巻く昨今の医療環境について考えてみました。
この1〜2年、医者の離職や地域・診療科による医師数の偏在がマスコミによく取り上げられます。そのような大きな変化の中で、皮膚科学は、もちろん地域差はありますが、初期研修修了後に後期研修を希望する医師が増加しています。逆に「楽な診療科」、「儲かる診療科」の一つとして皮膚科がとりあげられ、このような事態が、結果として「命に関わる病気」をとり扱っている診療科を希望する医師の減少に繋がっているという、皮膚科医の「品格」を貶めるような論調の記事を目にする機会も多いようです。しかし臨床各科において、診療の対象となる疾患が開業医、一般病院、地域基幹病院、大学病院で異なるのは当然であり、またどの診療科においても多かれ少なかれ、生命に関わる、あるいは患者の社会的・個人的QOLに大きな影響を与える疾患を診療しているかと思います。楽な科と世間で思われている皮膚科で扱う疾患は膠原病からメラノーマまで実に多様であり、対症療法に甘んじざるを得ない難治性、重症の疾患が数多く存在します。主治医の熱意により診断や予後が決定され、また、他科との連携により全身の病態を理解して、はじめて治療が可能になる病態、疾患も多いのは皆さんご存じのとおりです。その意味で、皮膚科は常に時代の先端の医学を理解する努力が要求される診療科です。臓器別診療の時代となり、初期研修二年間の間に全身を診るトレーニングを受けた新しい世代の医師が皮膚科の分野にどんどん参入してくれることで、皮膚科医が皮膚という臓器のスペシャリストとして、他科の医者と対等に討論し、医療の中で大きな役割を担い、医療経済の改善に貢献していける、そして先に述べたような基礎研究を志す若い医師のモチベーションが高まると考えるのは私に限らないと思います。ただそのような楽観的な考え方の対極として、いくつかの現実的な問題が出てきているのも事実かと思います。それはスーパーローテートシステムの開始時から予測されたことですが、医師としてあるいは社会人としての初期教育が十分に行えないという現状があることです。すでに崩壊したとされる医局制度が再び見直され始めているのは、医療・医学が師匠と弟子という人間関係に裏付けられた徒弟制度により継承され、その中で新たな技術を身につけ、新しい研究を創り出していくという、ドイツ式の医学教育をある部分で肯定する指導医が増えてきたせいかと考えます。実際二年間何を勉強していたのかと思う新人を迎えた経験をもつ先生も多いと思います。批判はあるかと思いますが、医局という組織のなかで同じ釜の飯を食うことにより、生涯に亘る良き師弟関係、同僚としての強い繋がりを構築でき、結果として、良質な医療を提供できたと考える我々の世代から見ると、今後医局に属さず、後期研修を終える医師の中には、医師としての根幹部分を十分身につけることが出来ず、本来の医師としての矜恃を理解しないまま、無為な日々を送る人が出てくるのではないかと危惧します。
もう一つは、女性医師の増加と出産・育児による休職ないし、離職の問題があり、同世代の教授達の間で、いつも話題になります。医師の離職や引き上げの問題は日々マスコミに取り上げられますが、女性医師の離職の現状、実働医師数の実態や復職支援、託児所の整備など全く取り上げられないのが不思議です。学会での動きはありますが、一個人、一学会の力ではどうにもならないのが現状です。ではどうするか?これは私見ですが、女性医師を含めた我々医師の矜恃をもう一度考えてみることかと思います。医師としての最大の喜び、モチベーション維持の原動力はどのような疾患であれ、病気が治り、患者さんに感謝されることは論をまたないと思います。個々の医師の価値観の多様性が重視される時代ですが、医師としての矜恃を次の時代の医療を担う若い人に伝えていくのが我々世代の役割かと夢想する次第です。
2008年
私見:進化論的皮膚学
私見:進化論的皮膚学
大阪大学大学院医学系研究科分子病態医学
皮膚科教授 片山一朗
先日、敬愛する先輩の先生から「最近のアトピー性皮膚炎の食事指導は欧米型の食生活からの脱却や食物アレルギーの観点からの取り組みが主体であり、もう少し別のアプローチがありそうだ」との手紙を頂いた。皮膚病では疾患特有の気質や体型があるということはよく耳にすることである。一昨年からわれわれの教室でも生活習慣とアレルギーというテーマで疫学的な研究を開始している。その中で対象として乾癬とアトピー性皮膚炎を取り上げ、さまざまな観点からの解析をしている。よく知られているように乾癬では表皮細胞のターンオーバーが正常より10倍以上亢進しており、不全角化細胞として脱落していく。この細胞回転はアトピー性皮膚炎の慢性病巣部では対照的に遅延しているようで、角層も厚くなる。最近の研究では皮膚のケラチノサイトが産生する抗菌ペプチドは乾癬で産生が亢進しており、アトピー性皮膚炎で減少していることが明らかにされ、そのことが乾癬で皮膚感染症の少ない一つの要因とされている。皮膚の炎症を規定する遺伝子はどうも乾癬とアトピー性皮膚炎で同じ遺伝子座にあるらしいが、少なくともケラチノサイトのレベルではまったく正反対の挙動が観察される。このことは何を意味するのだろうか?皮膚のケラチノサイトを考えてみると乾癬ではアトピー性皮膚炎に比べ遙かに大量にエネルギーを消費しているのは容易に推測できる。豊かな栄養源に囲まれた、しかし病原微生物も活発な世界で生活していた祖先の中で抗菌ペプチドの産生と表皮ターンオーバー亢進による効率的な抗菌システムを備えた個体が生き残り、進化したと考えることも可能である。翻ってアトピー性皮膚炎を考えると乾癬とは全く逆の環境下で進化してきた我々の祖先がアトピー素因をもつ現代人のルーツなのかもしれない。エネルギー消費を低下させ、角層を厚くすることで外敵の侵入と寒さを防ぐ手段を得たことで氷河期を乗り越えてきたとの仮説が立てられる。実際に日常診療でBMIの高いアトピー性皮膚炎の患者さんや患児を見る機会は少ないし、我々の検討でも、脂質代謝に関与するある分子がアトピー性皮膚炎患者のケラチノサイトで発現低下していることを認めている。このような観点から表皮の細胞代謝を乾癬型の高回転型に変換することがアトピー性皮膚炎の治療に応用可能かもしれない。アトピー性皮膚炎の病因論の一つとして戦後の西欧化した食生活を指摘する論文は多いが所謂Metabolic syndromeに合致する患者がどれくらい存在するかは明らかではない。逆にアトピー性皮膚炎の患者さんはそういった西欧型食生活への急激な変化を拒否する形でさらにあらたな進化をしていると考えることも可能かもしれない。昨今の医療環境も劇的に変化しつつある。人類の進化に比べれば瞬きの時間にも足りないが、21世紀のこの時代に適応した皮膚科医はこれからどう進化していくのかと考えてもみた。
2007年
北京オリンピックと専門医教育
北京オリンピックと専門医教育
大阪大学大学院医学系研究科分子病態医学
皮膚科教授 片山一朗
チベットの弾圧、四川大地震、聖火のボイコットなど開催が危ぶまれた2008年第29回北京オリンピックですが、いざ蓋を開けてみますと陸上男子のウサイン・ボルト(ジャマイカ)の世界新記録や競泳男子の. マイケル・フェルプス (米国)の金メダル8個など、毎日夜更かしで、テレビに釘付けになられた先生も多いと思います。その中で中国、韓国の躍進がめざましく、地元開催国とはいえ、中国はスポーツ大国の米国のメダル数を抜く、素晴らしい成績でした。また女性球技選手の活躍が以前にもまして眼についた大会だったかと思います。
連日オリンピック中継を見ていると、選手の育て方やコーチングの哲学、
その競技の連盟や理事会のあり方などで、メダル組と一回戦敗退組に大きく分かれ、同じような現象が皮膚科や医学の世界にも起きつつあることが分かり、あれこれ考えてみました。
2015年の世界皮膚科学会が、ロンドン、ローマを押さえ、ソウルで開催されることが、昨年のベノスアイレスの総会で決まりました。韓国のユン教授が綿密な事前活動をされていたことに加え、韓国の基礎科学のレベルが急速に上がってきているのがその勝因かと思います。また韓国とならんでNatureやScienceをはじめとした一流雑誌に中国人の著者名を見ることが多くなって居ます。この理由としては、彼らが国の威信と自己の誇りをかけて、研究を行い、
切磋琢磨して、より良いポジションを目指し、国も強力な支援体制を整備していることが挙げられるかと思います。丁度オリンピックの長期の展望下での選手強化と同様のスタイルです。日本勢の中ではソフトボールの金メダルを筆頭にホッケーのサクラジャパンやサッカーのナデシコジャパンなど女子の活躍が目立ちました。彼女らには日本を代表して戦っているという気迫とゲーム楽しむ余裕があるように感じられました。それに比較して球技の男子チームや国技の柔道は全く情けない限りで、スポーツ選手としてのモチベーションが全く感じられませんでした。
話は突然変わりますが、スーパーローテート開始後、地域格差は存在しますが、元気でやる気のある女性医師の皮膚科への参入が顕著です。しかし結婚、出産、育児の過程で、復職が困難となる方も多く、結果として、少ない男性医師のモチベーション低下、基礎研究、難治性疾患に取り組む若い皮膚科医の減少に繋がり、皮膚科全体の活力を削ぎつつあります。現在スーパーローテート研修の短縮や卒前教育への前倒し、大学院生の奨学金の見直や医学部定員の見直しに加え、ようやく女性医師のサポート体制が論議の俎上に上がり始めていますが、産科、小児科、麻酔科などへの国を挙げての支援の裏返しとして、皮膚科バッシングが強まり、定員削減や後期研修終了後のポストの制限などデフレスパイラルに陥ることが予測されます。皮膚科の中堅層の開業や新規研究者の減少は近い将来の皮膚科の存在そのものを揺すぶる大きな要因になるかと危惧します。
このような現状に対し、皮膚科学会でも全国の大学レベルでの皮膚科医定員数の設定、大学間の人材派遣での連携、基礎研究の推進などが論議されていますし、大阪大学の皮膚科関連施設ではそのマイナー版がすでに始められています。是非後期研修をされている先生もオリンピックの女子選手を見習い、医療技術の修得はもちろん最優先されますが、それに加え、自分自身が
医師としての誇りを持ち、ワクワクするような時間が持てる診療、研究のテーマを見つけて欲しいと思います。私自身、指導医として10年後そして、さらに先の将来を見据え、しっかりした視点で皮膚科医を育てて行きたいと自戒するとともに、大学、関連病院、同門の先生方にもにもあらためて協力をお願いする次第です。
2007年
研究のすすめ
研究のすすめ
大阪大学大学院医学系研究科分子病態医学
皮膚科教授 片山一朗
11月となり年報作成の時期となりました。 さて今年2007年は昨年の寄付講座開設引き続き、4月に佐野榮紀先生が高知大学、5月に浅田秀夫先生が奈良医大の教授に就任されました。お二人の先生は長年阪大ですばらしい業績を挙げられ、あらたな環境で素晴らしい教室を作り、次の世代の優秀な皮膚科医を育ててくれるものと期待しております。同門の先生方もご支援宜しくお願いいたします。また5月には樽谷勝仁先生が兵庫医大、7月には山口祐二先生が名古屋市大にそれぞれ栄転されました。それぞれ阪大とも縁のある大学であり、お二人の先生にも是非ご自身の研究をさら発展させ、皮膚科医としてのフィールドを大きくして、また阪大戻って来ていただきたいと願います。これらの先生とは入れ替わりになりますが、5月に種村君が悪性黒色腫の基礎研究をテーマに米国から、10月には小豆沢宏明君が調節性T細胞の研究をテーマにドイツから無事留学を終えて帰国されました。是非留学の成果を阪大で発展させていただきたいと思います。
今年の9月号の日本皮膚科学会雑誌に京都大学の宮地良樹教授が「病院勤務医の危機・燃え尽きないために」という時宜を得た論文を発表されました。
勤務医の問題と共に臨床教室での基礎研究者も全国の大学レベルで減少しており、発表される論文も減少傾向にあることが報道されております。皮膚科学が臨床医学である以上、その中心が患者によりよい医療を提供することであることは言うまでもありませんが、それを支えるのは臨床研究でありまた臨床に基づいた基礎研究です。今、国際皮膚科学会が開催されているベノスアイレでこの小文を書いていますが、学会場は化粧品関連のブースに人だかりが目立つ反面、膠原病、腫瘍、再生医学などの分野にアジア系や中南米の若い先生方がたくさん参加しており、素晴らしい発表をされています。逆にアメリカや韓国などでは大学自体が美容皮膚科など診療報酬が比較的高く、医療保険に影響を受けにくい診療分野にシフトしつつあるようで、重症、難治性の皮膚疾患を診ない傾向に移行しており、結果として大学や医療全体の中での皮膚科の存在価値の低下、臨床医の基礎研究への参入減少、研究費獲得の低下による大学内での皮膚科への予算削減などが大きな問題となっていることを聞きました。わが国でも今後専門医としての診療、研究を行って行くためには基本診療科の専門医修得に加え、さらにサブスペシャリテイとしての専門医と博士号の修得が科せられることが喧伝されております。是非目先の損得で将来を決めるのでなく、自分自身の皮膚科学を創って行くためにも、大学や基幹病院で多くの重症、難治性の患者さんを診療し、その病態を理解する中で、新しい治療法の開発や創薬を目指して、一時期研究に没頭する時間を作って頂きたいと思います。
2006年
「声欄」皮膚病診療
声欄(皮膚病診療)
大阪大学大学院医学系研究科分子病態医学
皮膚科教授 片山一朗
スギ花粉飛散時に見られる眼瞼の皮膚炎
2006年2月号の「とくにスギ花粉飛散時に見られる眼瞼の皮膚炎について」を興味深く拝読させていただきました。忙しい日常診療の中で多数の症例を纏められたことに心より敬意を表します。
眼瞼部皮膚炎に関しては以前から小生も興味を持っており、今回の季節的な患者数の変動の結果は大変有用な情報かと思います。
小生は以前に勤務していた病院でシェーグレン症候群の患者さんを診察させて頂く機会がありましたが、その時、眼の乾燥感の強い人に眼瞼部の皮膚炎がある程度認められ、臨床的には3型に分けられることを報告しました1)。その時はシェーグレン症候群が女性に多いことより、化粧品の接触皮膚炎の鑑別が重要と考え、検討しましたがスギのIgE-RASTや花粉症に関しては有意な結果は得られなかったと記憶しております。その際このような皮膚症状が欧米ではUpper eyelid dermatitis syndromeとして記載されており、その背景には多様な因子が存在することを知りました2)。点眼薬の接触皮膚炎では下眼瞼、脂漏性皮膚炎などでは上眼瞼に病変が多いかと思いますが、シェーグレン症候群ではどちらかというと両者が混在してみられました。今回の浅井先生の症例をみますと、圧倒的に女性が多く、臨床像も多様で、季節的な要因があるかとは思いますが、接触皮膚炎、シェーグレン症候群などの背景因子も解析対象に加えて頂き、今後スギ皮膚炎との臨床像の差を明らかにして頂ければと思います。本来このような長期間に亘る多数例の臨床研究こそ大変重要なものであり、症例の多い開業の先生と大学が共同研究出来れば、巻頭言に栗原先生が書かれている新しい連携の構築にもつながるかと思います。あらためて大学勤務医も頑張らなければと思い、自戒の念を込めて筆をとらせて頂きました。。
1) Katayama I. Int.J. Dermatol. 33:421-,1994
2) Rietschel RL & Fowler Jr. JF Fisher’s contact dermatitis 4th ed. pp 307 1995
吹田市 片山一朗
2006年
皮膚科のレッドデータブックリスト
皮膚科のレッドデータブックリスト
大阪大学大学院医学系研究科分子病態医学
皮膚科教授 片山一朗
スーパーローテート制度が開始されて3年が経過し、多くの医療を取り巻く問題が噴出している今日この頃です。昨年は2年間の新規入局者零の厳しい時代を経験した後の久しぶりの新人を迎え、新たな医師教育が動き出した年でした。しかしマスコミ報道に見られるように、都市部と地方、診療科間で医師の偏在の見られることが国民にもはっきり分かるようになり、結果として国民、医師、行政担当者それぞれが不利益を被る時代に入ったようです。またマスコミの偏向した報道はその傾向に拍車をかけ、医療行政への批判も日に日に強まってきております。我々の大学でも大学での勤務より市内の関連病院を希望される方が多く、また大学自体の後期専攻医枠も定員があるため病棟担当医も含め、一人の医師にかかる負担が目に見える形で増加しています。特に我々の診療圏では重症患者や色々な意味で対応の難しい患者が紹介されてくる関係でどの診療科も勤務医師の疲弊が目につきます。医学界全体を眺めてみても、近年の医学界流行語大賞にもなりそうな小松先生の名付けられた「立ち去り方サボタージュ」により勤務医を辞めていく医師が増える一方のようです。この背景には法人化にともなう国からの経営効率の改善の標的として勤務医が直撃を受けたことと、一部のマスコミによる過剰な医師へのバッシングによる、医師としての尊厳の喪失感によるところが大きいかと思います。先日ある人から地域基幹病院の指導医クラスの勤務医は絶滅の危機に瀕しており、レッドデータブックのリストに載るかもしれないとの冗談を聞きました。しかし現実にはその冗談が本当になるかもしれないとの危惧が日増しに強くなっているのは私だけではないと思います。医師としての基本は患者さんの病気を癒すことであり、そのためには絶え間ない自己研鑽が要求され、より良い医療を提供するために、より高度な医療技術の修得に励み、またその過程で基礎研究の道を選択することで、医学が発展してきたと思います。このような本来医師としてスキルアップしていく環境が無くなりつつある現況を打破し、それぞれの診療科の伝統を次の世代に引き継いでいくためには、情報を広く共有し、勤務形態による役割分担をより明確にし、基礎研究の面白さを一人でも多くの若い人に伝えて行くことが最も重要と思います。私の周りを見渡してみると、泊まり込みで重症の患者さんを診る研修医、臨床の視点を大事にする大学院生、創造的な研究者、多忙な中で自分の経験を論文化し、患者さんの視点で診療の出来る医者、子供を背負って試験管を振るママさん医師など近い将来レッドデータブックリストに乗りそうな絶滅危惧種が目白押しです。もう一度皆さんの力でこれらの貴重な危惧種を再生し、臨床に根ざした研究を推進し、マニュアル医療、マニュアル研究から脱却して夢のある臨床医学への路を拓いて行きたいと夢見る今日この頃です。
2005年
就任のご挨拶
就任のご挨拶
大阪大学大学院医学系研究科分子病態医学
皮膚科教授 片山一朗
私は平成16年3月1日付けにて吉川邦彦名誉教授の後任として、伝統ある大阪大学医学部皮膚科学講座を担当させて頂くことになりました。
私は北海道大学を昭和52年に卒業後、皮膚免疫学を学びたく、佐野栄春教授の主宰されておられた大阪大学皮膚科学教室に入局させて頂きました。大学院では西岡清東京医科歯科大学名誉教授(現横浜赤十字病院院長)のご指導でアレルギー性接触皮膚炎の制御に関する基礎研究を開始し、現在も私の大きなテーマとして継続して研究に取り組んでおります。昭和60年より国立大阪病院膠原病科、北里大学、東京医科歯科大学にて臨床、研究に携わらせて頂き、平成8年からは長崎大学の教授として赴任し、アトピー性皮膚炎と膠原病患者の治療を継続して行うとともに、長崎で多くの患者さんの存在する成人T細胞白血病、皮膚悪性腫瘍、光線過敏症の治療、病態研究も開始し、現在にいたっております。大阪大学の皮膚科学教室には昭和61年迄在籍させて頂きました。当時福島にあった医学部と付属病院は今千里の丘に移転いたしましたが、大阪大学皮膚科に戻り、あらためてその歴史と伝統を噛みしめております。
大阪は18年振りですが、この間外から大阪大学の皮膚科の発展を見て参りました。吉川教授の指導の下,分子生物学、再生医学と大阪大学の皮膚科は正に日本の皮膚科学をリードして来ました。このような優れた基礎研究をさらに推進してくれる人材を育成し、その成果を臨床にそして患者さんにフィードバックさせて行くのが私に課せられた大きな使命と考えております。
21世紀も4年目に入り、日本の医学そして大学は大きく変貌を遂げようとしております。卒後研修制度や大学の独立行政法人化は特に皮膚科に取って大きな試練ですが、逆に全身管理を勉強する機会も増え、収入を上げる武器も手に入れることが可能となり、皮膚科がさらに発展できる大きなチャンスでもあります。若い先生方には是非大きな夢を持ってOnly oneの皮膚科医を目指し、一年でも上の先生は責任を持って後輩の指導をして頂きたいと思います。このような考え方に立ち教室員共々大阪発の皮膚科学を世界に発して行きたいと考えておりますがそのためにも大学、関連病院の連携はもとより、同窓会諸先生方のご協力は必要不可欠であり、是非ご指導、御鞭撻のほど改めてお願いする次第です。

2004年
長崎大学年報序文
皮膚科白書
元:長崎大学大学院医歯薬総合研究科
皮膚科教授 片山一朗
現:大阪大学皮膚科教授
片山 一朗
今年も年の瀬を迎え一年を振り返る時期になりました。昨年4月から長崎大学も大学院大学となり、昨年は「放射線医療科学国際コンソーシアム」、今年は「熱帯病・新興感染症地球規模制御戦略拠点」のテーマで文部科学省21世紀COE(Center of Excellence)プロジェクトに採択されました。今年の医学分野では他大学では九州大学と久留米大学プロジェクトのみが採択され、いよいよ長崎大学が日本の西の拠点としてオンリーワンの大学を目指す体制が始動し始めました。しかしそのような研究機関としての整備と同時に来年度から導入される「独立行政法人化」を控え、今年の7月から包括医療制度の導入、10月には医学部附属病院と歯学部附属病院が統合され、澄川耕二病院長の強力なリーダーシップのもと長崎大学医学部・歯学部附属病院としてあらたなスタートが切られました。またこれも来年度から導入されるスーパーローテートの開始を控え、関連病院を含めた長崎大病院群での研修プログラムが提示され、初年度は65名が長崎大学病院群で研修することとなりました。しかし全国的には大都市圏の有名病院への志望者が圧倒的に多く、いよいよ医学教育が大学から離れる時代が来たのかと感じられます。ただスーパーローテーターの身分、兼業の可否、指導体制、研修終了後の専門医教育の受け皿など、先行き不透明な点も多く残され、大学を離れた医学教育は不可能ではないかと考えております。このような研究機関、教育機関としての大学の役割が大きく変貌しつつある中で、我々大学関係者にとって最も大きな法人化の波が直ぐ近くに迫っております。先日の斉藤寛学長の法人化に対する学内説明会でも病院の増収、受験者数の増加など具体的な数値が示され、達成出来なければ組織再編などのの可能性も示されました。これは大学教員の任期制や身分保障と関わる大きな問題で、我々臨床科の人間にとっては研究か診療かを選択せざるをえなくなり、目先の増収を諮るため、地域医療の切り捨てや関連病院からの引き揚げなど、さらに極論を言えば大学病院対非大学病院での患者の奪いあいなどの事態が生じる可能性も冗談ではなくなるような気がします。国の目指すところが何かは分かりませんが、ゆとり教育の指導指針がたった10年で元に戻ったように、研究者や専門医の大学離れによる日本の医学レベルの低下や地域医療、老人医療へのしわ寄せが国民にいかに不利になるかが認識されるまでは、本当に適切で国民の要求に応える医療、医学教育を提供できなくなるかもしれないと危惧します。このような現実の中で若い先生達に言えるのは、臨床医である限り、真摯に医学を学び、その成果を患者さんに還元していくことしかないと思います。逆説的に考えると今回の医療、医学教育改革は本来の医師のあるべき姿を再認識し、次の世代に必要な医師を選別するための必要悪なのかもしれません。
このような状況の中、皮膚科学会からも「皮膚科白書」という冊子が発刊
された。名前からも想像出来るように、この冊子は患者さんへの啓蒙書ではなく、医療行政関係者への働きかけを目的として作成されたもので「皮膚科医療の現状と社会貢献度の実態、皮膚科の将来性をアピールするための内容」などが網羅された構成になっている。この白書の発刊の背景には想像するに大きく3つの要因があるかと思われます。その一つはHMOなどの民間の保険会社の参入により、多くのアメリカの大学皮膚科や専門医のActivityが低下し、自由診療への移行や(結果的に本来診療すべき皮膚疾患からの逃避が大きな問題となっている)、一般医への転向などが増加しているいること、似た現象がヨーロッパやお隣の韓国でも生じていることが挙げられるかと思います。小生を含め、本来このような問題に疎かった大学関係者から白書発刊の気運が高まったのも当然かと思われる次第です。2つめとしては皮膚科の診療報酬が他科に比較して非常に低く押さえられいること(結果として先ず一般病院で皮膚科など見かけの診療報酬が低い診療科が定員削減などのあおりを受ける)、さらに度重なる保険の改正により、その影響が加速されている現状への対応策として、医療行政への働きかけへの資料作成を目的としていることです。特に後者の問題は皮膚科に限らず多くの診療科にも当てはまるかと思われ、最近あちこちでそういった話を聞くことが多いのは筆者に限ったことではないと思います。3つめとして来年度より導入されるスーパーローテートへの対応が挙げられます。ご承知のようにこの制度は行き過ぎた専門医制度を是正し、全身疾患が診療できる医師の育成を目指すことを建前とし、かつ、全国レベルでの医師の均等な分布と診療報酬の引き下げを視野に入れた制度と理解しています。その是非と今後の動向はさておいて、導入後は2年間どの診療科にも入局者は来なくなる筈です。当然従来研修医に診療を頼らざるを得ない皮膚科などの小診療科は大幅な戦力ダウンとなり、日常診療や地域医療の貢献などへの大きな障害が生じることが懸念されています。また皮膚科が主として卒後教育に重点を置いた診療科であることより、教育機会も減り、またスーパーローテート終了後の専門医教育や入局の動機付けにも影響がでることが多くの大学教員より危惧されています。そのような意味からこのような白書を積極的に学生に配布し、実際に臨床現場での皮膚科学の実態を知って貰いたいという意味も白書刊行の重要な目的と考えられかと思います。長崎大学でも包括医療の導入に引き続き、医学部附属病院・歯学部附属病院の統合がなり長崎大学病院として10月1日より新しい組織運営が始まったのは先生方も既にご承知かと思います。今後臓器別診療の導入が示され、診療科を細分し、より患者さんのニーズに応える診療システムを構築していく体制も整いつつありますが、来年からは卒後研修の義務化に加え、独立行政法人化などさらに皮膚科などの小さい診療科にとっては厳しい制度が導入されてまいります。このような医療環境の大きな変化の中で皮膚疾患を持つ患者さんにどのような医療を提供出来るのかを勤務医、開業医を問わず個々の皮膚科の医師が考えざるを得ない状況がきていると考えるのは筆者のみではないと思います。皮膚科医が治療することにより医療コストの削減に貢献できるような疾患が数多くあり、また他科との境界領域でよりよい医療を希望される患者さんがたくさんおられるのも事実です。皮膚科白書はこのような変革の時代の中でこそ皮膚科の特徴を生かした新しい治療学を創り、皮膚科の存在価値を他科にアピールしていく必要があるという皮膚科の立場を主張していく上で今後非常に重要な役割を果たしていくと考えられます。
2003年
阪大100周年記念「皮膚科医見習い時代」
皮膚科学教室開講100周記念誌
「皮膚科医見習い時代」
元:長崎大学大学院医歯薬学総合研究科
皮膚病態学分野教授 片山一朗
現:大阪大学医学部
皮膚科教授 片山一朗


2003年
阪大皮膚科開講75周年記事
阪大皮膚科開講75周年記事
大阪大学大学院医学系研究科分子病態医学
皮膚科教授 片山一朗
片山 一朗(S・52)
今,研修医誰しもが身にしみて感じている事と思うがこの1年間の時の流れは実に速かった。歌の文句ではないけど,時の過ぎゆくままに,この身を任かせて,1年を過ごしてしまった様な気がする。
北海道の,のんびりした風土の中で6年間を送った私にとって大阪での新生活は,毎日が緊張の連続で,自分の中の何か大切なものが日々失しなわれていく様な不安にとらわれ何度となく,この息のつまる様な都会から,逃げだそうと思った。反面,毎日の平凡な生活の申で,新しい多くの人に会い,新しい発見に驚き,それが心の支えにもなってきた。
今何故私が数ある医学分野の中で,皮膚科という,特殊な科を専攻したかと,新ためて考えて見るに,学生時代,病棟実習で皮膚科をローテートした時,T先生の言われた言葉が大きな比重を占めていた様に思う。それは次の様なものである。
≠皮膚科というのは,他科に比べ,割と暇な時間が持てやすい,医学以外の分野に首を,つっ込む事も可能である。事実背はそういう人物が皮膚科には多かった。しかし一万で,皮膚科程未知の部分が多く残されている科は他にない諸君にやる気きえあれば,こんな奥行の深いおもしろい分野は少ない。〃
1年間という短い期間ではあるが,種々の疾患を持った人々が,原因も分らないまま,対症療法に甘んじている姿を見るにつけ,この言葉が思い出きれ,何かやらなければという気にさせられる。又まだ臨床経験が零に等しい私ではあるが,生体が,皮膚というキャンバスの上に,かくも多彩な表現をし得るという事も大きな驚きであった。今,皮膚科医としてスタート地点に立ったばかりの私であるが,この生体の作り出す神秘な現象の1つでも解明出来ればと考えている。そして多くの先生運に一歩でも近づく様努力したいと思う。
1977年