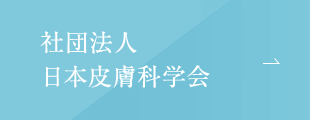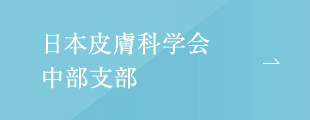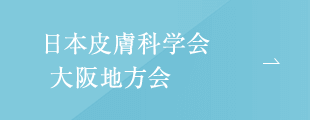9th World Congress on Itch
Wroclaw, Poland
平成29年10月15日-17日
大阪大学医学部皮膚科学教室
室田浩之
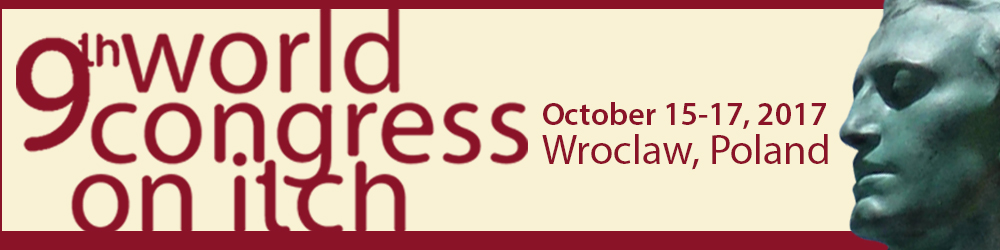
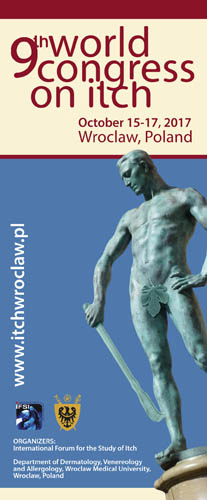
▷真性多血症の一症状として知られるaquagenic pruritusは水に皮膚が浸漬したのち1?10分で激しい痒みの生じる疾患である。これまでハイドロキシウレアや光線治療が適用されてきたが、逆に痒みを増強することも少なくないという。患者のなかにJAK2の変異が見つかっており、JAK2の治験が始まっているとのことたった。このほか、JAKを標的とした治療は様々な疾患に適用されつつあるようで学会内で異様な盛り上がりを見せていた。私が2日目午後のconcurrent1の座長をしている間、concurrentIIでは最近CellにIL-4が痒み(JAKを含む)に関わるとする論文を出したキム ブライアンが飛び入りで発表を行い、会場が盛り上がっていたようだ。午前のセッションではバウチスタらのグループがCXCL1/IL-8と痒みの関連を報告していたのだが、双方の研究グループの研究手法で共通していたのがVitD3によって皮疹を誘発した”アトピー(?)”モデル動物を用いていることであった。会場からはビタミンD3がアトピーのどういった側面を表現しているのが明らかにしなければならないという意見が多く出され、私も同感であった。▷これらのことからマウスモデルがヒトの痒みを真の意味で表現しているのかについて改めて「懐疑的」に考えさせられた。そう思ったVitD3モデル以外の理由として、いくつかの演題が「痒み」をsomatosensory sensationの一つとして扱っていたことである。気持ちは分からないでもない。アロネシスは触(圧)覚や熱痛覚は痒みを増強する現象を指すため、痒みは体性感覚と密接な関係がある。しかし教科書の体性感覚の記載には「痒み」は含まれていない。体性感覚をマウスの有毛部で検討した場合、その結果を直接ヒトに落とし込むことができるだろうか?全身毛で覆われる動物の毛で受容する触覚は種ごとに特徴的な発達を示しているだろう。▷この疑問は私たちの行っている研究にも示唆を与える。本学会では研究生の松本さんと1年半検討してきたアロネシスに関する研究結果を報告した。表皮は体外からの様々な刺激を感受し、グルココルチコイドを産生し恒常性を維持しようとする。表皮特異的にグルココルチコイド産生経路を欠損させた(表皮がグルココルチコイドを産生できない)マウスは触(圧)覚を加えると掻破行動を示す。これは表皮由来の神経栄養因子やケモカインによる神経の感受性亢進によって生じていた。触覚と痒みの関係を考える上で毛による感覚感受を常に念頭におくべきであろう。片山先生はこのグルココルチコイド変換酵素であるHSD11b1の発見の経緯、アトピー性皮膚炎の病態への関与と臨床上問題となっているsteroid withdrawalを取り上げ、皮膚ホメオスタシスが損なわれることが慢性アレルギー炎症と痒みに関わることを発表された。▷順天堂大学の富永先生は風によるアロネシス誘発モデルを提唱された。このアイデアには感服する。風を感受するのが毛であるならば、本研究は触覚受容と痒み発生における毛の重要性を間接的に立証している。

写真説明:ブロツワフの名物の一つが街のいたるところにある小人の像である。初日の記念講演は歴史的建造物であるブロツワフ大学の教室で行われた。大学に掲げられたWCIの旗のもと、本を読むのは小人の教授だ。風貌から垣間見れる知性、暖かさ、吸い込まれそうな懐の深さに圧倒される。
痒みとは何か?教科書的には痒みは体性感覚に含まれないため、その実態を説明しにくい感覚である。。痒みと痛みは同じかといえば”Yes and No”である。痒みよと痛みは上向性の伝達シグナルと下降抑制系を部分的に共有しているようだが、outputは異なる。痒みをイメージする映像を見ると、体性感覚にも異常が出る”下降賦活(?)”の経路も存在するとのことだ。さらに痒み感覚は多様である。”くすぐったい””ちくちくする”、”ヒリヒリする’など様々な痒みがある。この多様性はなぜ生じるのだろうか?痒みは未解決の問題が多いものの、見方を変えると科学的好奇心を「掻き」立てる研究テーマである。皮膚科医の臨床的な視点はその解釈により深みを与えるはずだ。
室田 浩之
平成29(2017)年10月20日掲載