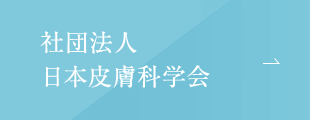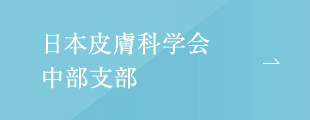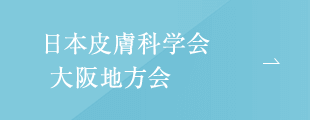第31回日本臨床皮膚科医会総会・臨床学術大会
2015年6月20日〜21日
会頭 川嶋利端
会場 オホーツク文化交流センター
大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学皮膚科学
教授 片山一朗

(写真:網走湖の遠景)


大会は旭川医大名誉教授の飯塚一先生の教育講演1「飯塚一コレクション」から始まり、土曜日朝早くから多くの先生が出席された。 シンポジウム5:「学校保健〜学校現場に役立つ皮膚科をアピールするために。興味深いアナフィラキシー症例小ネタ集」は原田晋先生がタコ焼に使う小麦粉中で増殖したstorage mite (実際にはホコリダニなども)によるアナフィラキシーを紹介された。南米からの報告が多いようでpancake syndromeと呼ばれており、アスビリン不耐症の合併が多いそうである。アスビリン不耐症例に関しては感受性HLA遺伝子の解析が進んでおり、花粉症と食物アレルギーが関連する口腔アレルギー症候群やFDEIAなど特定のHLAハプロタイプを持つ人が発症しやすいのかもしれない。この他、ハムスター咬傷での抗原が上皮由来とlipocalinとよばれる唾液由来たんばくの二種あること、何れも検査可能なとのお話であった。原田先生の発表はいつ聞いても勉強になる。 教育講演3 熊切正信 「ホクロ(色素系母斑)を診断する。」は当初,良性の色素性母斑が切除8年後に色素斑として再発、最終的にメラノーマを発症した例を紹介された。結局、最終的にはブレパラートからガンと感じられる感性が重要との話が印象的であった。 シンポジウム8 膠原病の診断と最新治療 川口鎮司 東京女子医大リウマチ科教授「全身性強皮症の早期診断と治療」はエンドキサンバルスが肺線維症に有効だか、内服の長期使用は発ガンのリスクを高めること、RNA polymelase I/III抗体陽性例では強皮症腎の発症リスクが高く、ステロイドの使用は禁忌などの有益なお話をいただいた。MDA5抗体、TIF1γ抗体など皮膚筋炎などでの重要な新規抗体はもうすぐ、保険収載とのことである。ただ最近の診断基準ではレイノー現象、capillaroscopy所見を満たせば皮膚硬化がなくても診断可能と言われたことには抗セントロメア抗体陽性のシェーグレン症候群が入る可能性を質問した。

(写真:原生花園から望む斜里岳)
関係者の皆さんありがとうございました。

熊切先生と能取岬にて
大阪大学大学院医学系研究科教授 片山一朗
平成27(2015)年6月22日